���ɋL�ڂ��Ȃ�����A�d�q�}�K�W��15���i2004�N3�����s�j�Ɍf�� |
| ���M�҈ꗗ | ||
|---|---|---|
| ��U | �薼 | ���� |
| ���ۏ�� | �I���W�i���e�B�[�ŋ�Y����2�N�� | �����@�x�v |
| ���ۏ�� | �킪�g�̔�͂��v���m�� | �����@���� |
| ���ۏ�� | �u�R����i�H�j�w���v�|�_���E���|�[�g���� �L- | �]���@�W�V |
| ���ۏ�� | �]�ɋؓ������� | ����@�斞 |
| ���ۏ�� | �C�_�͂��Ȃ��̎��ȕ\���̏�ł� | �e�r�@�ʕv |
| ���ۏ�� | ���w���Ɋ��ӂ��Ă��܂� | ���J�@�쏹�� |
| ���ۏ�� | �C���^�[�l�b�g�ŗ��j�����@ | �ےJ�@���� |
| ���ۏ�� | ���R�̐� | �r�c�@���O |
| ���ۏ�� | ���J��[�~4�����C�m�_������L | �_�_�@�K�u |
| ������� | �����N�����ƏC�_�쐬 | ��@�����q |
| ������� | �C�m�_���쐬�ɂ������̓I�ȎQ�l���� | ����@�_ |
| ������� | �Ō�܂ł�����߂Ȃ����� | �����@�b |
| �l�ԉȊw | ���������̃X�X�� | �Ίځ@����q |
| �l�ԉȊw | �u�I���v�ł͂Ȃ��u�n�܂�v�̂��߂̏��x�~ | ���c�@������ |
| �l�ԉȊw | �ʋΓd�ԂƐ}���ق�L�����p���Ăǂ��ɂ����� | �����@�h�i |
| �l�ԉȊw | ��S�̗F������ | ���@�F�q |
| �l�ԉȊw | ���s��ƂɑO�i�� | ���@�Ύq |
| �l�ԉȊw | �킪�q�ɕ�����C�m�_�� | �Љ��@���� |
| �l�ԉȊw | �C�_�����ւ̓��̂� | �c���@�� |
| �l�ԉȊw | �S�͑O�i�̂P�N | �㓡�@�a�F |
| �l�ԉȊw | �Q�N�Ԃ�U��Ԃ��� | ���c�@���q |
| �l�ԉȊw | �������̂��Ƃ� | ��d�@�M�Y |
|
�u�I���W�i���e�B�[�ŋ�Y����2�N�ԁv�@�@ ���ۏ���U�@�@�����@�x�v �_����� :�@���[�S�X�����B�A�����̔w�i�ƌ��� �|�����I�A�v�z�I�A�S���I�v���𒆐S�Ƃ��ā| �@���N���搶�̃[�~�ɉ�������Ƃ��A�C�m�_���ɂ��Đ搶���猾��ꂽ���Ƃ̓I���W�i���e�B�[�̕K�v���ł����B�w�p�_���ɃI���W�i���e�B�[���K�v�Ȃ͓̂�����O�̂��Ƃł����A���w�����͂��������F������Ȃ��A�u�w�p�_���Ƃ͂����������̂��v�Ǝv��������ł��B�v���̂قق�Ƃ����w���ł����B �@�Ȍ�[�~�ł́A�e�[�~���̌����v�悪���\����邽�тɁA�u�I���W�i���e�B�[�͂ǂ��ɂ���̂��v�Ō��_�����킳��邱�ƂƂȂ�܂��B�l�����łɌ����Ă��邱�Ƃ������Ă����傤���Ȃ��B�V���������͂ǂ��ɂ���̂��B�V�������_�A����͂ǂ��ɂ���̂��B�܂��A�I���W�i���e�B�[������Ƃ��Ă��A���ꂪ���ՓI�ȉ��l�̂�����̂łȂ���Ȃ�܂���B �@��X�����܂ł���Ă����u���v�́A��l�̋Ɛт��w�сA�����̒m���Ƃ��邱�Ƃ����S�ł����B���ȏ���ǂ�ŁA�������A���̓��e�����|�[�g��e�X�g�̓��ėp���ɂ܂Ƃ߂�悩�����킯�ł��B��w�@�ɓ����ď��߂āA�u���v����u�����v�ɃX�e�b�v�E�A�b�v���邱�Ƃ̍�����v���m��܂����B �@�V������ے肵�Ēn������ł����Ă��R�y���j�N�X�̂悤�ȓV�˂͂Ƃ������A��ʐl���V���Ȕ������邱�Ƃ͗e�Ղł͂���܂���B��X�����������悤�Ȃ��Ƃɂ��ẮA�����Ă��N���Ɍ�������Ă��܂��B�����̐l���S�����d�v�Ȃ��ƂقǁA�����̐��Ƃɂ���Č������s������Ă��܂��B���̏̂Ȃ��ŐV�������Ƃ����o���Ă����ɂ́A�����̂��ׂĂ̒m���A�o���A�����A���������A�w�͂��Ȃ���Ȃ�܂���B�Ǝ��̊����������Ă���l�A�l�ɂ͐^���ł��Ȃ��قǔS�苭��������Nj����Ă����l�͔����̉\�����߂Ă���̂��Ǝv���܂��B �@���̏ꍇ�́A�����V���v���ȓ��@���猤�����X�^�[�g���܂����B�u���[�S�X�����B�A�����ŁA�Ȃ��l�X�͗אl���E�����̂��B�l�ԂƂ͂��������낵���������Ȃ̂��v�ł��B���̓_�ɂ��ẮA��s�����̂Ȃ��ɔ[���̂䂭���͌�����܂���ł����B�����Nj�����I���W�i���e�B�[���o����Ƃ����̂����̊��ł����B���������̓���m�肽���Ƃ����~���������������̂ŁA�e�[�}�ɂ��Ă͂��܂�������Ƃ͂���܂���ł����B �@���͂��̓��������邽�߂̕��@�ł����B�����������Ȃ��Ă����Ȃ��āA�Ƃ������͂����ł͂��߂��Ƃ������Ƃ͕������Ă��܂����B�������Ⴄ�Ƃ��������ŁA�c�Ȃ��݂���E���Ă��܂��悤�ȏB������������ɂ́A�l�Ԃ́u�S�v�ɗ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗ����܂����B �@�l�̍s����������̂͐S���ł��B�����ĕ����̂悤�Ȑ����I���ۂ͐l�X�̍s���̐ςݏd�˂ɂ���Đ�������̂ł��B���������ĐS���Ɛ����Ƃ͕���������т��Ă���͂��Ȃ̂ł����A��ʓI�ɐ����w�͐S���ɐ[����������܂��A�S���w����������j�ɗ������邱�Ƃ��p�ɂł͂���܂���B�����w�҂��猩��A�S���͖ڂɌ������A�����܂��ł���A���l�ł���A�ڂ낢�₷�����̂Ȃ̂ŁA���͂̑ΏۂƂ͂Ȃ�ɂ����̂ł��傤�B�����S���w�͉Ȋw����ۂƂ��Ƃ��܂�����A������ώ@�Ȃǂ��d�����A���j�I�ߋ��ɂ�����s���葽���̐l�X�̐S���͑ΏۂƂ��邱�Ƃ͂��܂��ʓI�ł͂Ȃ��̂ł��傤�B �@�����ƐS���������ɋ��n�����邩�B���ꂪ���̂����Ƃ��Y�Ƃ���ł��B�S���Ɛ�������j�̊W�ɂ��ăX�P�[���̑傫�����͂������̂��S���w�҂̃G�[���b�q��t�����ł��B�t�����͂��̒����w���R����̓����x�̂Ȃ��ŁA�ߑ�Љ�ɐ�����l�X�̐��i�\���ƃi�`�Y���̗����̊W�𖾂炩�ɂ��܂����B���̃t�����̗��_�����[�S�����ɓK�p���邱�����̌����̃|�C���g�ƂȂ�܂����B���ʂƂ��āA�S���Ɛ������邢�̓C�f�I���M�[�̊W�����Ƃ��������邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B �@��̓I�Ȏ��M���@�Ƃ��ẮA�Ƃɂ�����x�Ō�܂ŏ����Ă݂邱�Ƃ�ڎw���܂����B���̌���10���ɂ͍ŏ��̑��e���d�グ�邱�Ƃ��ł��܂����B�Ƃ��낪�A���炭�Q�����Ă���ǂݒ����Ă݂�ƁA�Ȃ�Ƃ܂��e�G�Ȃ��ƁB�_�_���͂����肵�Ȃ����A���ʂȋL�q���₽�瑽���B�����Ő��Ȃ��n�߂܂��̂ł����A�啝�ȏ���������]�V�Ȃ�����A���ʂ�������3����2�ɂ܂Ō����Ă��܂��܂����B�������������ōŏI�I�ɂ͂��Ȃ肷�����肵���_���ɂ��邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B �@���ꂩ��C�m�_�������M�������ɃA�h�o�C�X����Ƃ���A�Ȃ�ׂ����������ɁA�Ƃɂ�����x�Ō�܂ŏ����Ă݂Ă��������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���e���ł���A�]�v�Ȃ��ƁA����Ȃ����ƁA�����Č����������Ƃ������Ă���Ǝv���܂��B�搶���瑁�߂̎w�����邱�Ƃ��ł��܂��B�ꔭ�Ŋ����x�̍������̂�������l�͂��Ȃ��̂ł�����A��x�����Ă݂Đ��Ȃ���̂������Ǝv���܂��B�������������A�ǂ����������ƔY��ł��邤���ɏH���[�܂��Ă��܂��ƁA�ƂĂ���J���܂�����B �@���낢���J���܂������A�C�m�_�����������Ƃ͎����ɂƂ��Ă���߂ċM�d�Ȍo���ƂȂ�܂����B���̉ߒ��ŁA���搶���͂��߁A���搶���A�[�~�̊F����ɂ��܂��܂Ȏw�����܂������������܂����B���̏����܂��āA���߂Č��\���グ�܂��B
�u�킪�g�̔�͂��v���m��v�@�@ ���ۏ���U�@�@�����@���� �@�����C�m�_���������n�߂��̂͂P�N���̂P�����������B���a�����̐��{�ƌR�̊W���e�[�}�ł���B�R���ɂ͑�P�́A�S���ɂ͑�Q�͂̔����܂ŏ����グ������Ȋ���o���������̂ŁA�����ȂƂ��낱�̒��q�Ȃ�]�T���Ǝv�����B�������Ƃ�ł��Ȃ����Ⴂ�ł������B �@�T�����߁A���悢��{��ƂȂ��R�͂Ɏ��|�����Ă����B�r���o�߂��[�~�Ŕ��\����Ɓu����͘_������Ȃ��ȁB�ǂݕ����v�ƁA���搶����̌��������w�E�B�[�~�݂̂�Ȃɂ���ꂽ�B���͓���~���~���Ƃ��������q�ŁA�܂��܂���@���̂�������Ȃ��������A���ꂪ�킪�g�̔�͂��v���m�炳��邱�ƂɂȂ�]�@�������B �@���ꂶ�Ⴀ�ǂݕ�����_���ɋO���C�����悤����Ȃ����A�Ǝv������A�Ȃ��Ȃ��ȒP�ɂ͂����Ȃ��B��U�����Ă��܂������͂���̂ǂ��C������������B�Ȃ�Ƃ��_���炵�����悤�Ɛ�\����J��Ԃ����A�v���悤�ɂ����Ȃ��B�����͑�̑������Ƃ����̂ɁA���݂͎~�܂����B�ʖڂ��A���{�I�Ȏ蒼�����K�v���B �@�܂��A�C�����܂Ŏ��Ԃ������������A���͐����O����a�ɖ`����Ă����B���ł͂Ȃ��B�p�\�R���ł���B���͂�ł��Ă���ƓˑR�d���������A�܊p�̋�J���S�Đ��A�ɋA���Ƃ������Ƃ��A���J��Ԃ���A����̂Ȃ��{�肪���B�w���v�f�X�N�̔��コ��ɑ��k����ƁA���҂��ɉ��u���삳��Ă���Ƃ����B����a�@�Ŏ��Â��čďo���B �@�����āu�ǂݕ��v���e��j�����ď��߂��珑���������ǂ������������A���s�˔j�����ӁB�S���ł��オ���Ă��琄�Ȃ��������A�ƊJ�������ĂV���A�����ɑ�R�͂������B �@�����A��S�͂��B���̏ꍇ�A���������E�����Ɠ��������Ɩ��̂Q�̎��������Ƃ������߁A�ڂ�ʂ��Ă����ׂ���s������Q�l�}���͑������������Ǝv���B�Q�l�}���͌Â��Ċ��ɐ�łɂȂ������̂������A�n���̑�w������}���فA�����ē���}���قɑ݂��o���╡�ʂ����肢���đ����Ă��炤�Ȃǂ��ďW�߂��B��������������ǂނ̂����J�B���̍�Ƃő�S�͂̓��������Ƃɓ��鍠�ɂ͑��ꂪ�n�܂��Ă����B �@���̎����W���B���炩�ɐi�s���x�������Ă���B���͂S�͂܂ŏ����Ă܂Ƃ߂�\��ł������̂ŁA�܂��ł邱�Ƃ��Ȃ������Ȃ��̂����A�܂����ꂩ��W�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�����������B �@�d���̋x�݂𗘗p���ď㋞���A����}���ق̌����������֍s�����B�Ƃ���R�l�̓��L���J���Ăт�����B���܂Ŗw�NJ��������ɂ��藊���Ă������B���܂�Ɍ��I�Ȏ��Ŕ��Ǖs�\�B���L�Ȃ���A�l�Ɍ����邱�ƂȂ�čl���Ă���Ȃ��B�������{�l��������������瓖�R�Ƃ����Γ��R�B������ڂ̑O�ɂ��Ȃ���ׂ��p���Ȃ��B �@����Ȃ�ƁA�����͐����Ƃ̏��ȂɊ��H�����߂��B �u�������B�M�E�E�E�����ĉ��ď����Ă���̂������ς蕪�����v �@���s�ł���B���̐��ʂ��Ȃ��s�c���̂悤�ȎS�߂ȐS�����œ�������ɂ��A�������߂čēx�㋞�B���x�͖h�q�������̎j���{�����ł���B�ڂ�ʂ��������̂͂������邪�A�ق�̐����Ԃł͂ƂĂ�����������Ȃ��B���x���ʂ����Ƃ��ł��Ȃ��̂ōŒ���̗v�_�����������āA���Ƃ͑S�ĕ��ʂ��˗������B����Ɏ���֗X���ł���B �@�Ƃ��낪�����͑҂ĂǕ�点�Ǔ͂��Ȃ��B�d�b�Ŗ₢���킹��ƁA�P�J���قǂ�����̂����ʂƂ����B��������Ɠ��𐂂ꂽ�B �@����ɕa�C�����ȃp�\�R�����嗬�s�̕a�C�Ɋ������A�Ăѓ��a�����B�C���ł����ŁA���e�͈�s���i�܂Ȃ��B���ɏ����グ�Ă��镔�������܂Ɏ蒼�����āA�S�̏ł�����܂������X�B����ȏ�Ԃ��P�J���ȏ㑱���A�{���Ɋ����������̂��ƕs�����点�Ă����B �u�����悤�B�܂����搶���ǂ������Ă͗��Ȃ����낤�B����҂͒ǂ킸���Č����Ă����B�ʐM���Ȃ��瓦����̂��ȒP���v�B�C���I�ɂ�������ǂ��l�߂��Ă����B�@ �@�X�ɉ�Ђ���͓]�Ζ��߁B�����_���ǂ��낶��Ȃ��B�h���T���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�Ƃ��낪�s���Y���肪�ӊO�ɂ������C���]���ɂȂ�A���q�����߂����߂��B�W�߂�������n���ɋᖡ���Ȃ���A�������Ƃł͂��邪�悤�₭�O���ɏ��n�߂��B �@10�����{�A���Ԕ��\�ɒ���B����ɗ����������Ȃ����S�z�ł��������A�Ȃ�Ƃ��������B�݂̂Ȃ炸�A���������ƂɁA�����ŐV���Ȓ���_��搶�����������A���������C�Ɉꉞ�̊����ւƌ��������Ƃ��ł����B���ӊ����ł���B �@12�����{�A�Ђƒʂ菑���I�����Ȃɓ������B�Ƃ��낪�Ȃ�Ƃ����e���B���Əq��̕s��v��r�������͎����̓ǂ݈Ⴆ��l���̌�肳������B���X�������̂��߁A�Ƃɂ����v���悤�ɂ����Ȃ��B�ꐶ��������Ă���悤�ŁA���͖w�ǂ��P�Ȃ�Z����Ƃł���B�Ō�ɐ��Ȃ�����͓̂��R�Ƃ��āA��͂菉�߂��犮�S���e��S�|���Ă����悩�����B �@�܂��A�����̍Ċm�F���K�v�ɂȂ�ƁA���̓x�ɕ��������������Ă����B���ʎ����͋ɗ͐������Ă������肾�������A�Â������B�����̍Ĕ��@�ɂƂ�ꂽ���Ԃ͑傫���B���Ȃ��Ă���A�Ƒ�{�����Ă��������Ȃ��قǂł���B �@�Ƃɂ����ł��邾�������ĐX�������ɂȂ�Ȃ��悤�S�|���Ȃ��牽�x�����Ȃ��A12�����{�ɍŏI�e�Ƃ��Ċ��搶�ɑS���𑗂����B����ň�i���B���炭�͖w�Ǖ��C�ɓ���]�T���Ȃ������̂ŁA�g�̒����y���B�C�𗎂Ƃ��ċv���Ԃ�ɓ��D�ɐZ�������B �@������A��̓��������e���搶���瑗��Ԃ���Ă����B�\���ɂ́u���ʂ͂��邪�A�悭����Ƒe�G�B�����Ő��Ȃ���悤�Ɂv�ƋL����Ă����B���ȂȂǂ��Ă��Ȃ������R�Ƃ����]���ł���B�u�������A�����ɂ��v�B�ł��œ����Ă���ɂ͂Ȃ��B�N���N�n���W�Ȃ��B�u�U��o���ɖ߂�v���B������������āA�o�Z�݂����Ȃ��Ƃ��Ă�ꍇ����Ȃ��B �@���߂Ď����̕��͂�ǂݒ����ƁA�ԈႢ�����낼��B����Ȃ��̂��o������肾�����̂��ƁA�����Ƃ����B���Փǂݒ����Ă��뎚��Ӗ��s���ȕ��͂��o�Ă���B�܂�ŊԈႢ�T���N�C�Y���B�i�X�Ǝ����̕��͂�ǂݒ����̂��|���Ȃ��Ă����B �@����ł�������J��Ԃ������ɉ��Ƃ��A���܂ɂȂ����悤�ȋC������B�ēx�搶�Ɍ��e�𑗂�A�w����������ɂ܂����ȁB���ς�炸�ԈႢ��������B �u�܂��A���̒��x�Ȃ狖���Ă��炦���Ȃ����v�Ƃ悤�₭��������A������đ�z�ւő������̂͒��ߐ�O���A����̒��ł������B�����\��͒��؍ŏI���B�Ԉꔯ�ł���B���߂̍��̗]�T�͐Ռ`���Ȃ��Ȃ��Ă����B����Ȕ�����Ȃ������B �@���e������đ�z��Ђ̉c�Ə����o��Ɛ���̐��Ⴊ�R�̂悤�Ȑ�Bῂ��������ɐQ�s���̊���ׂ߂��B���搶���͂��߂Ƃ���搶�e�ʁA�����ă[�~�݂̂Ȃ���A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�����l�łȂ�Ƃ����������邱�Ƃ��ł��܂����B �@����A�I����ĂȂ������B���|�[�g���E�E�E�E�E�E�B
�u�u�R����i�H�j�w���v�|�_���E���|�[�g����L-�v�@�@ ���ۏ���U�@�@�]���@�W�V �@�C�O�o���P�S��A�����o���i�������A��j�S�W��B�@�C�O�o������A�����i�܂ލ��`�j�X��A���O���Q��A���B�P��A�����Q��B�@�C�O�o���P����̕��ϓ����P�O���B�@�����o���P����̕��ϓ����P�D�T���B�@���@���o�������v�Q�P�Q���B�@ �@����1�N10�����i���Q�O�O�Q�N�S���̓��w�ȍ~�A�Q�O�O�S�N�P���̘_����o�܂Łj�̊ԂɁA���ꂾ���̏o��������܂����B�@ �@���̐������݂���ƁA���炭�A�N�����u�Z����������ł��ˁ`�B�悭���|�[�g��_���������܂����ˁ`�B�v�ƌ����Ă������邱�ƂƎv���܂��B �@�������ɖZ�������X�ł������A�t�ɖZ�������炱���A�Ȃ�Ƃ����Ɓi���w�ʎ擾�j�܂ł�������ꂽ�Ǝv���܂��B�Ȃɂ��A�{���͂Ȃ܂����́A�؉H�܂�Ȃ����获�M�ɓ���Ȃ��Ƃ������ȁi�����ȁH�j�́A�u�ċx�݂̗F�v�N8��30��/31����2���Ԃ� �Еt���Ă������w���̍�����̂��̂ŁA�����炭���Ԃ������Ղ肠������A�p���ď����グ���Ȃ��������Ƃł��傤�B �@�Ƃ͂����A����ł́A�����L�ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�ȉ��A���ۂɂ́A�ǂ̂悤�Ȏv�l�@���邢�͎菇�̂��ƂŁA���̂P�N�P�O�����̊Ԃ��߂����A�_�������܂ő��������������s���ŋL���Ă݂����Ǝv���܂��B ���@ ���Ԕ��\�̂���A�u���i���Ȃ����Ƃɂ͘b���ɂȂ�Ȃ����A���\�Z�����d���̓����������Ă���̂ŁA�Ƃɂ������i�_���Ƃ��Œ�C���̂��̂������グ�邱�Ƃ�ڎw���܂��v�ƌ������A�i�����炭�A���搶�ɂ͕s�]�I�H�j����ɂ��A�u�Ƃɂ��������グ��B���g�̕]���͐R���̏��搶�ɗa����B �s���i�Ȃ炵�傤���Ȃ��B�v�Ǝ���ɈÎ��������A�ޘH��f�����B�g���ǂ����̂��h�Ȃǂƍl���n�߂���A�g���Ԃ�����Ȃ��I�����ߐ艄�����h�Ȃǂƈ��Ղɗ��ꂩ�˂Ȃ����Ƃ��o������A���o���Ă�������ł���B ���@�C�O�o���ɍۂ��ẮA�ڈ�t�̘_���쐬�p�Q�l�������g�����N�ɋl�߂ďo�������B�Ƃɂ����茳�ɂȂ��{�͓ǂ߂Ȃ��I�@�i�������ŁA�Z�ʂ̂����Ȃ��q���Ђ� �́A�ĎO��ו����ߗ������Ƃ�ꂽ�B�j�@�������A�����Ă��������������ׂēǔj���邱�ƂȂǂ́A�n�i��������B�@�u���Зނ͋�������܂œǂޕK�v�͂Ȃ��B�K�v�ȂƂ��낾���ǂ߂����B�v�Ƃ̋ߓ��搶�̋����i�H�j��n�炵�A�o�����ɔ�₷�K�v�̂Ȃ��ʋΎ��ԑ����̂P���Q���Ԃ��܂������Ǐ����ԂƂ��āA�ȂȂߓǂ݁A����ǂ݂ɂ��Ă��B�@�������A���̑��̎��Ԃ��C������œǏ��ɂ��Ă��B���̂��̑��̎��Ԃ��m�ۂ��� ���߂ɂ́A�C�O�o�����̌��n�ł̗[�H�̂����҂͎Г��Ɋւ��Ă͑؍ݒ��P��݂̂Ɍ��肷�邱�ƂƂ����s�����B�i�u�]������͎�Ԃ�������Ȃ��v�ƒ��݈��ɂ͍D�]�������͗l�B�j ���@�����o���ɍۂ��ẮA�e�Ȗڂ̃��|�[�g�쐬�̂��߂̎Q�l�����𐔍��A�펞�g�s�B�������A������ȂȂߓǂ݁A����ǂ݂ŁA�Ƃ�������Â��݂ɓ��e��c�����邱�Ƃɐ�O�����B�i��Â��݂ł��A�������ɖڂ�ʂ��ƁA����Ȃ�ɘ_�_�͕����яオ����̂ł��B�j ���@���Ȗڂ́A������̔N���ɂ����Ă��A�܂� ��ԋ����������ꂽ�T�Ȗږڈ�t��o�^�B���ȏ����͂����Ƃ���ŁA�ڎ����n���B�@���ʁA�������������A�Ȃ����y�X�ɂ͎�ɕ����Ȃ��Ǝ��o�����Ȗڂɂ��Ă͑��X��Give Up���AGive�@Up�f�����˂��Ȗڂɂ��ẮA�D�揇�ʂ�ݒ肵���B����́A���Ԃ�����Ȃ��Ȃ����Ƃ��ɂ́A�ǂ̏��Ԃ�Give Up���邩�Ƃ������Ƃ�\�ߌ��߂Ă����Ƃ����A����Ӗ��A���X�N�E�}�l�[�W�����g�̎�@�̉��p�ł���B�@���ʂƂ��Ĉ�N���͂S�ȖڂP�U�P�ʂ��m�ۏo�����B�܂��A��N���ɂ����Ă����l�ɁA�T�Ȗږڈ�t��o�^�B���ʂ͂Q�Ȗڂ�Give�@U�����A�R�Ȗڂɂ��ă��|�[�g���o�����B �i���ƂɕK�v�ȉȖڐ��͂U�ȖڂQ�S�P�ʁ{�C�m�_���U�P�ʂ̂R�O�P�ʂȂ̂ŁA�]�_�͂Ƃ������Ƃ��āA���̕��@�ő��ƒP�ʂ��m�ہB���m�ɂ́g�m�ۂ����͂��h�ł���B�{�e���M�̌����_�ɂ����ẮA���|�[�g�̕]�_�͖��m�ł���B�j ���@�C�����Ă������Ƃ́A�_���ɂ���A���|�[�g�ɂ���A�Ƃɂ����v���������Ƃ́A�����Ƀ����B�i������Ȃ��ƁA�����ɖY�p�̂��Ȃ��I�̃��X�N�L��j�B�����������Ƃ́A�����ȓ��ɕK���o�b��́u�����v�ɑł������B�iOutlook���p�F����́A���ƂɂȂ�Ɨʂ����܂��Đ��������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����邪�A������������̈��M�ŁA���Ԃ����ƁA�����ŏ����Ă��Ă������������������Ǖs�\�ɂȂ�̂ł��B�j ���@���̍쐬���������E�t�@�C���iOutlook�t�@�C���j�͕K���A�o�boff����Internet Disk�ɂt������Ƌ��ɁA�b�c�|�q�v�� ���������݁i�܂ޏ㏑���j�A����̃f�[�^�j���ɔ������B�i����́A��y���Z�̃A�h�o�C�X�ɂ����̂ł���B�j �܂��A�C�O�o�����ɂ͑�w����ݗ^���ꂽ�o�b�Ɖ�Ўx���̂o�b�̂Q����펞�g�s���A���ӁA��Ўx���̂o�b���o�b�N�A�b�v�p�ƈʒu�Â��āAInternet Disk�̑�p�Ƃ����B�i��x���������A�t�@�C���j������C�؍ݎ��ɔ����������Ɏ��ۂɖ��ɂ������B�j ���@�_���쐬�ɂ������ẮA�O�L�̂Ƃ��胁�����Ă������̂��A�܂��͓K���Ƀt�@�C�������A���邢�̓R�s�[�@�\�𑽗p���āA�p�b�`���[�N�I�Ș_������U�쐬���A�l�X�ȗv�f�i���́A�ڍדxetc.�j�ŁA���̃p�b�`���[�N�I�_���ꊴ�Ȃ�����C�ʊѓx����ɐ����E���Ȃ���Ƃ�����@���Ƃ�Ȃ���A���e�A��e�c.�ŏI�e�Ƃ�������Ŋ����ɂ��������B���̂��߁A���w���̔��Α啗�C�~�I�_�����e�\��́A��ڒ�o�A���Ԕ��\�̂��тɃX���������i�ꉞ�A�����̃C�x���g�����牼���ߐ�Ɛݒ肵�č�Ƃ��Ă������� �j�A�]���A�\���ڂ����ꃌ�[���̐���ɂ͂�����̂́A��]�O�]���A���ǁA�ŏI�e�������グ���̂��ɁA���e�ɉ����āA�薼���čl�E�������邱�Ƃł��܂����킹���B ���@�K���������͎̂����������悤�Ǝv������������i�u�@���v�Ɓu�L��v�̋����W�j�Ɋւ��āA����ɊY�������s�����炵���������Ȃ������Ƃ����_�ł���B�i���ꂼ��̕���Ŏv���ɖ𗧂����͂Ȃ����Ƃ��Ȃ��������A���p�ΏۂƂȂ�悤�ȕ����͌�������Ȃ������B�j�@���Ȃ킿�A��s�������Ȃ������p�����s�������Ȃ������p�������X�g�A�b�v�Ȃ�����������Ƃ̏ȗ����o����A�Ƃ����A�{���ł���A����Ȏ��Ԃ��₷�ł��낤��Ǝ��Ԃ������Ȃ��������Ƃ��A�Ȃ�Ƃ��_�����M���Ԃɍ������傫�ȗv�f�ł��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B�i�����Ƃ��A��s�������Ȃ������̂ŁA�����ōl���Ă݂邵���Ȃ����A�Ǝv�����̂���w�@���w�̓��@�ł��邪�B �j �@�ȏ�A���ꂪ�_�������L�ƌ����邩�ǂ����A���Ȃ���^��ł��邪�A�Ƃ�����A�ŏI��o���̑O���ɒ������A�����A�ŏI��o���̌ߑO���Ƀv�����g�A�E�g������ȂǂƂ����A���ς�炸�̍j�n����o�āA�Ȃ�Ƃ���o�����A�Ƃ����̂����Ԃł���B�K���ɂ��āA�ʐڐR�������i�����Ē����A���́A�����̑�\�z����A�ʓI��3���̂P�ʂɂȂ��Ă��܂������̘_�����X�^�[�g�ɁA���ꂩ������̕�����������Ă������Ƃ��l���Ă���B�i���̈Ӗ��������āA�ŏI��o���ɘ_����ڂ�ύX���A�Ō�Ɂu���_�v�Ƃ������t���������B�@�ꉞ�A�����ɏh����o��������ł���B�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ� �@���Ƃ����F��X�A�������̌��e�����Ă��킭�A�u����A�����i�D�lj߂��B�w�ǃt�B�N�V��������Ȃ��́B�w���R�肽���� (by �Ȗ�肳�H)�v�܂����� ���̂Q�N�Ԃ��ے����邪���Ƃ��A�Ō�̍Ō�ł��̕����L�̑薼���܂��ύX��]�V�Ȃ�����܂����i��j�B
�u�]�ɋؓ��������v�@�@ ���ۏ���U�@�@����@�斞 �@���w���āA�ŏ��Ɋw���ɂȂ����ȂƊ�����̂��A5���ʂɑ����Ă���e�L�X�g�̎R��������Ƃ��ł��B�����āA�[�~�ɂ���Ă͂��̑O�A5���̘A�x�ʂɈꔑ������x�̃[�~���h�ɎQ���������ł��B���h�[�~�ł͐�y�̌o���A���m�ρX�̕��X�Ƃ̋������Ȃ���b�ł����Ƃ����Ԃɍ��h�͂����܂��B�A��̓d�Ԃ̒��ł������ꂩ��2�N�Ԃő��Ƃ��邼�I�ƈӋC�ɔR���ĉƂɂ��ǂ���܂��B����ł����������ŏo������O�̋C�����A��x�ʂ͌o���������Ƃ���Ǝv���܂��B �@���w�̋��������߂����ɁA�����Ă����e�L�X�g�̎R�߂Ȃ���A�Ȃ��o�C���ɑ��ݍ���ł��܂����̂ł͂Ȃ����E�E�E�E�Ǝ����̔O�������Ȃ���e�L�X�g���J���A�u���|�[�g�ۑ�v�����������Ă���Ӗ����l���n�߂�̂�6�����ł��傤���B���N�x��5�ȖځA4�{/�Ȗڂ̃��|�[�g�v������܂�����A��N�Ԃ�20�{�A��N�Ԃ�52�T�Ԃ���܂����畽�ς����2�|3�T�Ԃ�1�{���|�[�g���d�グ�邱�ƂɂȂ�܂��B����2�|3�T�ԂƂ����̂͐搶�Ƃ̃l�b�g�o�R�̃R�~���j�P�[�V�������鎞�Ԃ��܂݂܂��B���Ƃɂ���ăe�L�X�g�͌����i�p���j�̏ꍇ������A�����Ȃ�Ǝ������łĂ��܂��B�������āA�����̕��X�^�C����͍����Ă���ԂɁA�����Ƃ����Ԃ�7���̃X�N�[�����O�̎������Ă��܂��܂��B �@�X�N�[�����O���ɁA�C�_�̘b�肪�ł܂��B�C�m�_���̍��i��Łu�Ƒn���v�ɏd����������Ă���Ƃ̘b����������܂��B���|�[�g�œ�����t�������̂ɁA����ɏC�m�_�����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B������ρA�u�Ƒn���v���K�v���I�@�����ɂ́u�Ƒn���v�ȂL��̂����B�����Ɂu�Ƒn���v������A��w�@�Ȃ�ē���Ȃ��ŁA�X�C�X�C���̒��j���ł����A�u�c�N�T�v���Ȃ���9���̃��|�[�g���ߐ�ɒǂ��Ă��邤���ɉĂ��I���܂��B �@�ł��A�F����S�z���Ȃ��ł��������B���̒��A��L��Ίy����B���߂�A����Ε����ƒN���̌��t�ɂ���悤�ɁA���Ǝ�������|�[�g�͂Ȃ�Ƃ��Ȃ�܂��B���|�[�g�쐬��搶�Ƃ̃Q�[���A���̑̑��ƈʒu�Â��Ă��܂����Ƃł��B���|�[�g�͉ۑ茈�܂��Ă���A�e�L�X�g������܂��B�l����͈͂����߂��Ă��܂��B�ޗ��͗^�����Ă���̂ł��B���Ƃ͍ޗ��Ɏ����̖��t�������邾���ł��B�d�����Ȃ���̕��ł�����A�d���ƕ��̎��Ԃ����ɐU�蕪�����邩�ǂ�����������ڂɂȂ�܂��B���͘A�x�A�T���ɐ}���ق��Ă���A�W�����ă��|�[�g�쐬���܂����B �@���āA�C�m�_���ƂȂ�ƃ��|�[�g�Ƃ͏��肪�������܂��B���̏ꍇ�́A�܂��u�Ƒn���v�ł��B8���ʂ���C�m�_���̃e�[�}��I�Ȃ��ẮE�E�E�Ɠ��̂Ȃ��Ń`���c�L�n�߂܂��B�u�Ƒn���v�Ƃ͂Ȃ�H�Ȃ�čl������A�u�Ƒn���v�E�u�C�m�_���v�Ƃ������t�����ŖA�̂悤�ɕ�����ł͏������肷��悤�Ȋ��o�ɂȂ��Ă��܂��B�������Ă��邤���ɑO���̃��|�[�g���o���A����10��������|�[�g�Ɏ��|���邱�ƂɂȂ�܂��B �@���������|�[�g�������A�搶�̍u�]�Ȃǂ��������āA����Ƀ��|�[�g�̓��e��L�x�ɂ��Ă����ߒ��ŁA�����̒��Ő������ĕ��͂ɂ��Ă����g���[�j���O��m�炸�m�炸�̊Ԃɐi�߂Ă���̂ɋC���t���܂��B�Љ�ɂł�ƁA�Ȃ��Ȃ���̃e�[�}����������l������������̌��t�ŕ��͂Ƃ��ĕ\������@�����܂���B��w�@�ɓ���A���|�[�g�������Ă����ߒ��ŁA������Z�߂āA�����l�ɔ���悤�ȕ��͂ŕ\������Z���g�ɂ��Ă����܂��B���̉�������Ɂu�C�m�_���v������̂ɋC���t���܂����B �@���Ƃ̓e�[�}�������邱�Ƃł��B�e�[�}�͂��ꂼ��̋����̂��镪�삩��T�����ƂɂȂ�܂��B���͎����̎d���ƊW���肻���ȃe�[�}����i�荞�݂܂����B�傫�ȃe�[�}�͂����v�������ׂ鎖�͂ł��܂����A�傫���L���e�[�}��_���Ƃ���50�|100�y�[�W�̐��E�ɓZ�߂�Ɉׂɂ̓e�[�}�̒��g����̓I�ɍi�肱�ޕK�v������܂��B���̍i���݂̍�Ƃ���ςł��B�_���͓��e�Ɣ��ɖ��l�ɗ������Ă��炤���߂ɁA������ł̌`���I�ȃ��[��������܂��B��{�͈��p�����m�ɋr���ȂǂŎQ�Ƃł���悤�ɂ��܂��B��̓I�ɂ͐搶����r���̕t�����̎w���E�}�j���A���ɉ����ď������ɂȂ�܂��B���������p�ł���悤�ɐ������Ă�����Ƃ͎�Ԍ���������܂����B �@�e�[�}�̑�g�����܂�ƁA�������W�߂�Z�i��͍����邱�ƂɂȂ�܂��B���̏ꍇ�͎d���Ɗ֘A����e�[�}��I�̂ŁA�����ɂ����Ύ��������邩�����Ă����̂Ŏ����W�߂ɂ͂������J���܂���ł����B������܂��ł����A���������ł͘_���͏����܂���B�������E�����������́u�Ƒn���v���������������ŁA�N���]���̗���ɂ����Ę_�|��W�J���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B��g�̃e�[�}�ł͘_���̒��n�_�������܂���B�_���͒̂��錋�_���K�v�Ȃ̂ł��B���̗���ł͂���܂���B�������璊�o�������ɑ��Ď����́u�Ƒn���v���������ċc�_���s���A�����_�Â���̂��_���ł��B �@���̏ꍇ�͌��ݐi�s���̎��ۂ�_���̃e�[�}�ɑI�т܂����B���������ɏ��ω�����̂ŁA�_���̌��_���_���̑�ڂ����߂�̂ɋ�J���܂����B���肬��12���ɂȂ��Ă���_���̑�ڂ����߂܂����B�����W��1�N���̖�1�|2���ʂ���W�߂āA�ǂݎn�߂܂����B1�N���̃��|�[�g��o����1������V�w��4���܂ł͉ɂł��B1������4���܂�3�����Ԃ��_���̑��i�K�̎d���ݎ��@�ł��B���̊ԂɎ������W�߁A��g�̃e�[�}�Ɏ����̓��Â����o����A�C�m�_���̌`�������Ă��܂��B��́A�_�����`���ɏ]�����`�ɗ��Ƃ�����ł����͎d���̐��E�ƂȂ�܂��B�܂��Z�܂������Ԃ̂��鎞���ɒ��g���C�ɂ��Ȃ��ŁA�Ȃ�ł��ǂ����珑���ĕ��͂ɂ��Ă��܂����Ƃł��B�����Ă��邤���Ɏ����̘_���̌��_�A��_�������Ă��܂��B���͂��̑f�e�������^�C�~���O��5���̘A�x�ɐݒ肵�A�������L���Ă������Ă��A�Ȃ������ƌ��߂܂����B�܂�1�|4���܂Ŏ����W�߁A�o���s�o���͕ʂƂ���5���ɂȂ�炩�̌`�œZ�߂Ă݂�悤�ɂ��܂����B�d���ƕ����鎞�Ԃ̔z���A�i��肪��ςł������A�K����5���̘A�x�͔N�x������10���ʑ����ċx�݂��Ƃ�܂����B �@�������A���グ����ڂ����������Ă���z�b�g�ȃe�[�}�Ȃ̂ŁA5���ȍ~���V�������o�����A�_���Ƃ��ēZ�ߏグ��͔̂N���ɂȂ�܂����B�����͂��邪�A�_���́u������_����ځv�̐ݒ�ɂ͍Ō�܂ŔY�܂���܂����B10���ɘ_���̔��\�\�s���K�������قōs���܂����B10�����̗\�s���K���̘_����ڂƍŏI��o�����_����ڂ͈Ⴂ�܂��B12�����{�ɑ�ڂ�ς��悤�ƌ��S���܂����B�����Ŕ[���ł��Ȃ��ƁA���l�ɂ͐����͂ł��܂���B�����Ŕ[������܂Ř_���̐������グ��̂��d�v�ł��B �@�_���̓��e�Ƃ͕ʂɘ_���̌`���𐮂����Ƃ����Ԃ�������܂��B1�T�Ԉʌ��Ă����K�v������ł��傤�B���p�A�r���̐����A�ڎ��ƃy�[�W�̈�v�A�v�����^�[�̕s��̔����A�Ƃ��ɂ̓p�\�R�����_�E�����Ď�����������ȂǕs���̎��Ԃ��N���܂��B3������A�ȈՐ��{�̎�Ԍ����n���ɂȂ�܂���B���N�̔N���N�n�ɂ̓p�\�R���̃E�B���X����X�I�ɗ��s�������̃p�\�R�����E�B���X�Ɋ������܂����B�f�[�^�̃o�b�N�A�b�v���d�v�ł��B����̃T�[�o�[�������̎����A�[�J�C�u��Ƃ��ė��p���܂����B���͏o���̑����d�������Ă���̂ŁA�����ɂ��Ă������̃t�@�C����down and up load���ĕۑ��ł������T�[�o�[�E�A�[�J�C�u�@�\�͏d��ł����B �@�ȂA�_���쐬�}�j���A���݂����ɂȂ��Ă��܂��܂����B�����g�͊y�V�I�Ȑ��i�Ȃ̂��A�_���쐬���y���݂Ȃ���i�߂܂����B�q�����H��ŕ�������Ă����̂��y����ł���悤�Ȋ����ł��傤���B���̒��ɏo��ƁA�����̎d���ɗ�����ēZ�܂�����̎��Ɏ��g�ދ@��ɂȂ��Ȃ��߂��荇���܂���B�_���쐬�̉ߒ��ŕ��Â���̊y�����ƁA�����̍D��S�������܂����B�����A���ɘ_���������@�����A���Ԃɒǂ��Ȃ����ŏ��������ȂƎv���Ă��܂��i�ł��A���Ԃɒǂ��Ȃ����ł̘_���쐬�͎�̐��E�ɂȂ��Ă��܂��A���ǂȂɂ������Ȃ��Ȃ肻���ł��j�B �@�ȒP�Ɏ���2�N�Ԃ̗���������܂����B����ʐM����w�@�͕����鎞�Ԃ������̎d���̍��Ԃɂ͂ߍ��ݕ����邱�Ƃ��ł��܂��B���[���ɂ��搶�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����������Ƃ�܂��B�搶�̎���ɂ܂œd�b�Ŏ��₵�����Ƃ�����܂��B����ʐM����w�@�͎d���������Ă���l�̕��̏�Ƃ��Čb�܂ꂽ���ł��B�����A�قƂ�ǑS�ẴR�~���j�P�[�V�����̓p�\�R����ʂ��Ă����Ȃ��̂Ńp�\�R���Ɋ����K�v�͂���܂��B �@�Z����2�N�Ԃł������A2�N�Ԃ̕��Ŏ����̍D��S�̕��Ƃ��t����������l�̗ւ��L�������̂���Ԃ̍��Y�ł��B���܂Ő��l�a�\�h�̂��߃W���ŋg�����Ă��܂������A�u�]�g���v���K�v�Ȏ����v���o�����Ă��ꂽ2�N�Ԃł����B�u�]�ɋؓ��������v�Ƃ����̂��A����feeling�ł��B
�u�C�_�͂��Ȃ��̎��ȕ\���̏�ł��B�����͂���܂���v�@�@ ���ۏ���U�@�@�e�r�@�ʕv ��Ⴂ���̋�J�͔����Ăł����Ȃ����B��Ƃ������t������܂��B���̑�w�@�ł�2�N�Ԃ́A�����l���Ă����ȏ�Ɍ��������̂������ɗ^���Ă���܂����B��������J���瓾�����̂͑z���ȏ�ɑ傫���A�����ċM�d�Ȃ��̂ł��B�^���ɍl���A�Y���Ƃ́A�{�l���C�t���Ȃ������ɐV���ȉ\���ݏo���A�M�d�ȍ��Y��^���Ă���܂��B����͌����ĎႢ�킯�ł͂Ȃ��R�O��㔼�̎�����w�@�œ����ő�̋��P�ł��B���́A������^��̒��ɂ����i���̈Ӗ�������̂��Ɗm�M���Ă��܂��B �@�F����������̕����A�E��ł͐ӔC����|�X�g�ɏA���ĖZ�����d��������A�ƂɋA��Έ����ׂ��Ƒ������邱�Ƃł��傤�B�����ł͂Ȃ��Ă������Ƒ����̑厖�Ȃ��Ƃ�����Đ����Ă���������Ǝv���܂��B�ł��A�����ɂ����đ�w�@�Ō�������Ƃ����ЂƂ̎�����I������܂����B���̌��f���Ō�܂ő��d���A�ւ�Ɏv���Ă��������B�܂����ꂪ�C�m�_�������ւ̏o���_�ɂȂ�܂��B�ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ���������܂��A�����ĕs�\�Ȃ��Ƃł͂���܂���B ���w�̓��@ �@�����Ĉ����͂Ȃ����Ɨ���[�߂�킯�ł����炻��Ȃ�̓��w���@�͕K�v�ł��B���̏ꍇ�A��w�@�Ŋw�т����ƍl�����̂͂����炭2���R������������ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B���ƂȂ��Ă�3�N�ȏ���O�̂��ƂɂȂ�܂��̂ŁA���m�Ɏv���o�����Ƃ͑����̍�����܂����B����ł���͂茤���ɍs���l�܂������́A���S���v���o�����Ƃ����ʓI�ł��B �@���̗��R�̂ЂƂ́A��Ђł̐l���ٓ��ɂ��A���Ȃ�Z���������������瑽�����Ԃɗ]�T�̂��镔���Ɉڂ������Ƃɂ���܂��B���ԓI�]�T���ł���Ɠ��X�̐������莝���������ɂȂ��Ă�����̂ł��B���R�]�v�Ȃ��Ƃ��l���܂��B���������ߒ�����������܂��B��������قǎ�������Ȃ����́A����܂ł��c���Ă������Ƃ�������x����Ă݂悤�ƍl����悤�ɂȂ�܂����B��w����ɒ��r���[�Ɋw��ł������Ƃ������ōĂѐ^���Ɏ��g�����Ɩ{�C�Ŏv���悤�ɂȂ����̂ł��傤�B����Ɠ����ɁA���ݎ������g��u���Ă���r�W�l�X�̐��E���w�p�I���n����T���Ă݂����Ƃ��l����悤�ɂ��Ȃ�܂����B����͎����ɂƂ��đf�p�ŏ����ȒT���S�ł������Ǝv���܂��B �@�����ЂƂ̗��R�͔N��ɊW���Ă��܂��B30����O�����I���A�㔼�ɓ˓����悤�Ƃ��Ă������́A�ӂƢ40�͐l���̕���_�ł���B� �Ƃ������t�������悬��܂����B�����̖{�ő���t��������Ă������t�������Ǝv���܂��B�l�Ԃɂ́A����ЂƂ̕���_����܂łɕK������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����A���̃|�C���g���Ă��܂��ƌ����Č�߂肵�Ă�����x��蒼���Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ������e�̂��̂ł����B���傤�ǂ��̍��A�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂��m���ɂ���Ɗ����Ă��܂����B����Ŏ����݂�����������w�@�Ōo�c�w���w�ԂƂ������Ƃł������킯�ł��B����t���̏ꍇ�͢�m���E�G�[�̐X��̎��M�ł����B���������̂Q�ɂ͔��ɑ傫�ȈႢ�����݂��Ă��܂����B �C�m�_���������Ƃ������� �@�C�m�_�������������邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ͂����ЂƂł��B����قǓ�����Ƃł͂���܂���B�������g���C�_�̃e�[�}�Ƃ��đI�肵���ۑ肪�����Ă���^�̖��_�m�ɂ��邱�Ƃł��B����������P���Ȍ��t�ŕ\���ł������ɉz�������Ƃ͂���܂���B����ƊE�̌��������Ă��������T�����Ă��̂͢���R�X�g�̎��̉��P��Ƃ������t�ł����B���ꂪ�݂���A�قڊԈႢ�Ȃ��C�m�_�������������邱�Ƃ��ł��܂��B���̏ꍇ�A�ŏ��̈�N�͑I���Ȗڂ̒�o�ȊO�͂��̍�Ƃɔ�₵�܂����B���ӎ�����Ɏ����Ă���ΕK����ɓ�����̂ł��B �@���̂��߂ɂ͂܂��A�����e�[�}�Ɋւ���{�𐔑����T���A�ǂݍ��ނ��Ƃł��B�������������ׂĂ��ŏ��̃y�[�W����Ō�y�[�W�܂ł�ǂޕK�v�͂���܂���B�������C���������Ƃ��낾�����E���ǂ݂��Ă��������ł悢�̂ł��B�܂���厏��G���ނɂ��ڂ�ʂ��܂������A�V���̐ؔ������W�߃t�@�C�����O�����܂����B�����ŋC�t�������Ƃ������Ȃ�ɏ������߂Ă����܂��B���͂̌`�Ԃɂ͂Ƃ��ꂸ�ǂ�ǂ��Ă����܂��B�������Ƃɂ�莩���̓�����������A���_�����m�ɂȂ��Ă������Ƃ��킩��܂��B�ǂނ��ƂƏ������Ƃ����Ԃ̋�������s���Ă��������B���̏��������̂��X�g�b�N���Ă����Ă��������B���̐ςݏd�˂��d�v�ɂȂ��Ă����܂��B�����Ă�����x�ł��Ă����Ȃ�A���ɂ���𑼐l�ɓ`���邽�߂ɂ́i���邢�͐������邽�߂ɂ́j�ǂ̓�����ǂ̂悤�ȕ��@�Ŏg���Ă������Ƃ����ʓI�ł���̂����l���Ă��������B�Q�N�̏��߂܂łɂ��̒i�K�܂ł���A���Ȃ菇���ł���Ƃ����܂��B �@���Ƃ͒S�������̎w�������܂߂Ɏ邱�Ƃ��̐S�ł��B���v���A���̏ꍇ���̂��Ƃ����Ȃ������l�Ɋ����܂��B�������g�ōl��������X�����������悤�ȋC�����܂��B���ʂȉ�蓹�����Ȃ����߂ɂ��A���ɂ͗E�C�������āA�܂����鎞�͒p��E��Ŏw�������ɂԂ����Ă������Ƃł��B���������邱�Ƃ͂���܂���B�Ȃ��Ȃ炱���͊w�Z�ł���A���Ȃ��͊w��������ł��BJR�̊w�����������g���闧��ɂ���̂ł��B�����͂ЂƂu���ꂽ���y���݂܂��傤�B���Ă̎Ⴉ�肵�����v���o���Ȃ���B �}�X�^�[���擾����Ƃ������� �@����2�N�Ԃ͊ԈႢ�Ȃ������Ƃ����Ԃɉ߂��Ă����܂��B�ł��ǂ�Ȃɒ��q�������Ă������~�܂�Ȃ����Ƃ���ł��B�C�����̂�Ȃ���p�\�R���̓d��������đ�w�@�̃z�[���[�W�𗧂��グ�邾���ł��悢�Ǝv���܂��B�}�X�^�[�̎��i�����Ƃ������Ƃ͎��ɑ̗͂������܂��B���Ƃ��Ēm�͂����̗͂��~�����Ǝv���͂��ł��B�܂��X�|�[�c�Ɠ����ł����D�����ێ�����ق�������ł��B���̃C�`���[�ł���V�[�Y�����ɃX�����v������܂��B�킽���̏ꍇ�A�����X�����v�̂Ȃ��ɑ������q�̂悢�����������B�ꂷ��Ƃ����\���̕����K���ł������Ƃ�����ł��傤�B���ɂ͋C�y�Ɏ��g�ނƂ������Ƃ��K�v�ł��B�����̂��Ƃ킴�ɢ�l���ꐆ�̖��̂��Ƃ���Ƃ������̂�����܂��B�킽���̍��E�̖��ł��邱�̌��t�́A�����ȐS������^���Ă����̂Ɠ����Ɍ����ӗ~�����߂Ă��ꂽ������܂��B �@�ȏ�Ƃ�Ƃ߂��Ȃ����Ƃ������Ă����̂łƂĂ��F����̎Q�l�ɂȂ����Ƃ͎v���܂��A�Ō�Ɋm���Ɍ����邱�Ƃ͏C�m�_�����{��o�̂��Ƃɂ͐S�n�悢��J���ƊJ�������҂��Ă���Ƃ������Ƃł��B�����Ƃɂ��ꂼ��̌�����簐i���Ă��������B�����Ă킽���ɂ͂R�ɂȂ邩�킢�����q�Ƒ����ɗV�ׂ�Ƃ��������̎��Ԃ������ɂ͂���܂����B �@�F����̂����������F�肵�܂��B
�u�C���^�[�l�b�g�ŗ��j�����@�v�@�@ ���ۏ���U�@�@�ےJ�@���� �@ �@���͎l���̂��錧�̎i���E�Ƃ��āA�����w�Z�̐}���قɋΖ����Ă��܂��B�l���ƌ����A��͂�u�n���v�ł����A�Ζ���͂��́u�n���v�̌������ݒn���牓�����ꂽ�R�ԕ��Ɉʒu���܂��B�n���I�ɂ��C��I�ɂ���ςȕƒn�ŁA�K���Ȍ�y�{�݂��Ȃ��A�u����Ɏ��c�����v�Ƃ����ő����ɂ����Ȃ܂�܂��B �@���̂悤�ȕs�ɂ܂�Ȃ��y�n�ŋΖ����Ȃ���A��w�@�Ŋw�т��Ƃ��ł����̂́A�C���^�[�l�b�g�����p�����T�C�o�[��w�@�ł���{�����Ȃ����݂����������ł��B�܂��A�C�m�_����|�[�g�����M�����ŁA�C���^�[�l�b�g��p��������͌������Ȃ����̂ł����B �@���̏C�m�_���̑�ڂ́u���S�}���قƑ卲�O�l�܁v�Ƃ������j�����i�ߑ�j�j�ł���A�Q�Ƃ��ׂ������̑����͓�������̐}���ٓ��ɏ�������Ă��܂��B���j�����Ƃ���������A���炩�̐V�����̔��@�͕K�{�ł����A�����ɒ��ڃA�N�Z�X���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ����Ƃ��傫�ȔY�݂ł����B �@�������A��������}���ق�����}���قł́A�C���^�[�l�b�g��ő����ژ^�����J����Ă��܂��B�����ژ^���������A�X�����ʂ�\������A���h�߂��̌����}���قʼn{���ł���悤�Ɏ葱���i�}���يԂ̋��͑ݏo�j����A�������W�͂��قǍ���Ȃ��Ƃł͂���܂���ł����B�������p������Ȑ}���ٓ��̃z�[���y�[�W���ȉ��ɋ����܂��B �P�A�u��������}���ّ��������E�\���V�X�e���iNDL�@OPAC�j�vhttp://opac.ndl.go.jp/index.html �@�@ �u��������}���كA�W�A����OPAC�vhttp://asiaopac.ndl.go.jp/�@�@ �@�@��������}���ق̑����ژ^�ƁA�G���L�����������p�ł��܂��B�G���L�������͐�s�����̒����ɗp���܂����B���p�ғo�^���Ă����ƁA�I�����C���ォ�畡�ʕ��̐\�����݂��s���܂��B �@�Q�A�u���{���}���ّ��������vhttp://opac.library.pref.osaka.jp/cweb/jsp/search1.jsp �@�@���ق͐�O���{�ɂ�����L���̐}���قł���A����Ђɑ����ĂȂ��̂ŁA��O�̏o�ŕ����悭�������Ă��܂��B �@�R�A�uNACSIS Webcat�vhttp://webcat.nii.ac.jp/ �@�@ �uWebcat Plus�vhttp://webcatplus.nii.ac.jp/ �@�@ �������w�����������鍑���̑�w�}���ق𒆐S�Ƃ��������ژ^�ł��B �@�S�A�u��������}���ف@�����ژ^�l�b�g���[�N�V�X�e���v �@�@�����}���فi�s���{�����}���فA���ߎw��s�s�s���}���ٓ��j�̑����ژ^�i�a�}���̂݁j�B�@��ϗL�p�ȃV�X�e���ł����A��ʂɂ͌��J����Ă��܂���B���̂��߁A�߂��̌����}���قő�s���������肢���邵���Ȃ��̂��c�O�ł��B �@�T�A�u�����������ف@�A�W�A���j�����Z���^�[�v http://www.jacar.go.jp/ �@�@�@�����������فA�O���ȊO���j���فA�h�q���h�q�������̏����������I�����C����ʼn{���A�v�����g�A�E�g�A�_�E�����[�h���邱�Ƃ��ł��܂��B�����V�X�e�����[�����Ă��āA�������牓�����ꂽ�l�ԂɂƂ��Ă͑�ςȕ����ł��B �@�U�A�u���m���Ɂ@�}���̃I�����C�������v�@http://www.toyo-bunko.or.jp/library/SearchMenu.html �@ ���E�L���̓��m�w���}���فB�M�d�ȗ��j�����@���邱�Ƃ��ł��܂����B �@�V�A�uᩐ��Ѓf�[�^�x�[�X�v�@http://www.libro-koseisha.co.jp/top01/top01.html �@�@�w���{�l������n�x��w�G���L�������W���x���o�ł��Ă���ᩐ��Ђ̃z�[���y�[�W�B���́A�l�����̃f�[�^�x�[�X�ɃA�N�Z�X���܂����B��O���̐l�������̉����ׂɂ͂����Ă����Ǝv���܂��B �@�����̃z�[���y�[�W����g���邱�ƂŁA���Ȃ�̗��j�������N�W���邱�Ƃ��ł��܂����B�������A�����⒘�Җ��̕������Ă���悤�ȓ���̎�����T���̂ɂ͕֗��ł����A���m�̎����Q�̒�������ɗ�������T���o�����߂ɂ́A���͂���L�[���[�h�����s���낷��Ȃǂ̎�Ԃ��|���銄��ɂ́A�u�C�~�y�̊����@���܂���ł����B�����A���ڗ��ق��ď��˂̊Ԃ�����A��������ɂƂ��Ă݂�ƁA�ӊO�Ȕ��������邱�Ƃ����X����܂����B�C���^�[�l�b�g�����B���Ă��A�����z�����Ȃ����̂�����Ɗ����܂����B�܂��A�f�[�^�x�[�X������Ă��Ȃ�����������܂��B�C���^�[�l�b�g�͖��ɗ����܂����A����ɂ��ׂė���̂ł͂Ȃ��A�����ɂł���x���x�͎��ۂɑ����^��ł݂邱�Ƃ��K�v�ł���ƒɊ����܂����B
�u���R�̐v�@�@ ���ۏ���U�@�@�r�c�@���O �@ �P�D�̘b �@���w���Ă���̂Q�N�́A�Z���Ȃ���ƂĂ��}�s�Ō��������̂�ł������B���́A�����̊�Ƃɏ�������J���Z�p�҂ł���B���̋ƊE�ł́A����v�E�������锼���̐��i���A���������߂āu�v�Ƃ����B���{�́u�v�̋����͂͂P�X�W�O�N��ɐ��E�ɓG�����ł��������A�P�X�X�O�N��㔼�ɂ͋����͂����������g�ƂȂ��Ă��܂����B�ł͂��́u�v�Ŗׂ���ɂ͂ǂ���������̂��B���傤�ǂR�N�O�̂��ƁA�����Ȃ�ɂ��̕ǂ���������ړI�ŁA���w���悤�Ǝv���������̂ł���B �Q�D�̏�ɂ��R�N �@�e�[�}�͔����̂̐��i�J���헪�Ɩ��킸���߂Ă������Ƃ́A��ōK���ƕs�K���ɂ����炵�Ă��ꂽ�B���w�O�̈�N�Ԃ́A�Z�p�I���_���痣��āu�v���l����悤�S�����A�����v��ɐ��荞�ݓ����ɗՂ̂ł���B �@�C�m��N�ځA�قڊu���ōs����\���[�~�ł́A�e�[�~�����A�����e�[�}�̐i�������B���́A�����ō쐬���������v�揑�ɏ]���A�S�̘̂_���\���A�͍\������������Ȃ��甭�\���Ă����B���ɑ傫�Ȗ��_���w�E���ꂸ�A�[�~�̒��Ԃ���͏����Ǝv���Ă����B���S�ł́A�w�E�������̂͐i�W���������߂ł͂Ȃ����ƕs���������Ă������A�������W�ȊO�͂قƂ�ǂł��Ȃ��ł����B�C�m��N�̓��|�[�g���o�������Ŏ��t�ł������B�d���Ŗ�肪���o���A�Q�R���O�ɉ�Ђ��o�邱�Ƃ��s�\�ł������B�A��Ă�������J�n�ł���̂͂Q�T���A�y���������ꂩ����͏o�ЂƂ������X�������Ă����B���|�[�g��o��́A�C�́E�̗͂Ƃ��Ɋ��S���D�����Ă��܂��Ă����B �@��_�����S�����Ă����̂́A�\�������̑I���Ȗڂ͎����̏C�m�_�������ƌ��т��čl����Ƃ̌��t�ł������B�C�m�_���ƑI���Ȗڂ����ѕt���ă��|�[�g�쐬�������Ƃ́A�m�炸�Ɏ���̌����ۑ�̏��ɖ𗧂��Ă����B�����āA�v�������ĂR�N�ځA�܂��Ɂu�v�̏�ɂ��R�N�ƂȂ�C�m�̂Q�N���ƂȂ����B �R�D����@���ēn�� �@���́A�p�\�R����Q�O�N�̑�x�e�����ł���B�w������̎�̓v���O���~���O�A�Љ�l�ɂȂ��Ă���̓p�\�R��������y���݁A�p�\�R���͐����̈ꕔ�ł���B�������A���S�̂��ɁA���Ƃ����͂���̂ł���B �@�C�m�Q�N�ɓ���A���v�f�[�^�̉��H���n�߂��B���́A���̏C�m�_���̍ő�̔���͔����̋ƊE���V�~�����[�V�����ɂ������邱�Ƃƌ��߂Ă����B���̂��߂ɕK�v�Ǝv���鐔�l�i�������\��Y���j���g�o�ⓝ�v�N�ӂ�V������Ƃ�̂́A��ςȍ�ƂŐ��l���W�����łP�O���ɂȂ��Ă��܂����B�]���āA�P�O���Q�T���ɍs��ꂽ�C�m�_�����ԕ�́A�S���̎��_�̃[�~���\�ƂقƂ�Ǔ������e�ł������B �@�������A�P�P���̐��������Ƃ������ɃV�~�����[�V��������Ƃ������Ȃ��Ȃ�A�����̂̊J����P�[�X�X�^�f�B�Ȃǂ������n�߂��B�P�Q�����I�ՂɂȂ�A��̕s�K������Ă����B�܂��A�ŏ��̕s�K�̓m�[�g�p�\�R�����A�܂����������オ�炸�A�n�[�h�f�B�X�N�͈ى������͂��߂��B���̂Ƃ��A�������Q�O�y�[�W�̏C�m�_���ł��������A�����̎��ɂ͑S���Y�ł���B���Ƃ��C�m�_�����~��˂ƁA�S���͂��p�\�R�������Ɍ������B�p�\�R���̉�̂�������A�V�K�̂n�r�������OS�C���X�g�[�����J��Ԃ����B��������܂ŁA�P�O���Ԃ��g�p�����B���������A�R���ł����Ƃ��l����ƁA�p�\�R�������͐��������f�łȂ��B���̎��_�łȂ�ƂP�Q���Q�W���ł���B �@�����āA��ڂ̕s�K������Ă���B���P�Q���Q�X���ɏC�m�_����o���ߐ肪�P���P�T���ł������ƋC�Â����̂ł���B�u�����A�Q���P�T�����ߐ肶��Ȃ��̂��v�A�Ƃ�ł��Ȃ����Ⴂ�����Ă����B��������A�c��S���̂R�̂U�O�y�[�W���T�Ԃŏ��������A�V�~�����[�V�������I�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������́A��������ɓO��ŁA�Q������\�t�@�ʼn����ł������B���Ԃ̐������I���A�܂��A�V�~�����[�V�����͌��ʂ��������A�\�������ɘ_�������Ă��炢�{����\���Ɏ�����Ă�������B���̌�A�R�O�O�s�̃V�~�����[�V�����v���O�������P���ŏ����グ�A�e������̌v�Z�ɂQ���g�p�����B�����ĂP���P�R���A�̍ق𐮂��ăv�����g�A�E�g�����A���Ƃ����ߐ�ɒ�o�ł����̂ł���B �@������O�����A�o�b�N�A�b�v����邱�ƂƁA���ߐ�����͊m�F���邱�ƁA�ł���B�O�ɂ͔O�����āA����@���ēn�邮�炢�̐T�d������������A����Ȏ��̂ɂׂ͊�Ȃ������ł��낤�B �S�D�Γ� �@�F�X���������A�C�m�_���̌����́A�\�������̎w���̉��A�قړ����̖ړI�ǂ���ɏ����グ�邱�Ƃ��ł����B�����Γ�����������ɂ킪�܂܂��Ă����������_����������A��ϊ��ӂ��Ă���B����ł��A�Ɩ��𗣂ꂽ�q�ϓI�ȖڂŁA�����̋ƊE�����邱�Ƃ��ł��A�l�ԓI�ɂ������ł����Ǝv���B�ȏ�A�u�v�̂��Ƃ���q�ׂĂ������A�C�m�_������萋����̂Ɉ�ԏd�v�Ȃ̂́A��͂莩���̈ӎv�ł���B
�u���J��[�~4�����C�m�_������L�v�@�@ ���ۏ���U�@�@�_�_�@�K�u �@ ���J��[�~�R�������A�w4�����̊F����ցx�Ŏn�܂钷���̓d�q���[�����͂����Ƃ��납��A���S�����̏C�m�_���Ƃ̊i����͎n�܂�܂����B �y���J��[�~�R�������S�����ւ�2003�N�P���Q�S���t���d�q���[���@�|�����|�z �w4�����̊F����� ���āA���̕���L�͂R�����������P�N�Ԃ̐S�\��������ꂽ���S�������A���̌�P�N�Ԃɓn���Č����肵���d�q���[���̒�����A�g����h�g�ߖh�g��s�h�Ȃǖ{���̉�b���L�^���A���S�����̐킢�̋L�O��ɂ���Ƃ��鎎�݂ł��B���������܂��āA�ҏW�҂̗]�v�ȃR�����g�͋ɗ͔����A���Ԏ��ɉ����ēZ�߂Ă݂܂����B���A�o��l���̓v���C�o�V�[�ی�̊ϓ_��艺�L�ʏ̂ɂ���ĕ\�L�����Ē����܂����B4���̊F����A�������炸�I
�@�[�~���Љ�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʏ� �ł́A��璷�J��[�~4�����́g�{���h�̏C�m�_������L����������肨�y���݉������B ------------------------------------------------------------------�\----------- �y�g�D�����h���g���������m�l�h�ւ�2003�N�P���Q�T���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�g���������m�l�h�l�B ���[���ǂ����B�c�O�����c �y�g�ΘJ�w���h���g�[�~���h�ւ�2003�N�Q���X���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�g�[�~���h���� ������肪�Ƃ��������܂��B �g�[�~���h�������撣���Ă�����̂ŁA�������N���Ȃ���Ƃ����v���Ă��܂��B�Ƃ���ŁA���A�g�[�~���h�͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ă��܂����H���́A���_�̃e�[�}�╶���\�������l���Ă��܂��B�܂����J�싳���֘A�����Ă��܂��A�������߂đ��_�֎��|�������ł��B���̂�͑�ό����������Ă��܂��B�{���ɂ����������肪�Ƃ��������܂��B�c�c�ȉ����x �y�g�[�~���h���g�ΘJ�w���h�ւ�2003�N�Q���X���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�g�ΘJ�w���h���� ���v���Ԃ�A�]��A�����Ȃ��̂ŐS�z���Ă܂����B�����C�̂悤�ʼn����ł��B���͉����撣���Ă��܂���B���������ƈВ���悤�ł����ƂĂ��ƂĂ����Ă����̂��炢�̂ł��B�ƌ����Ă��܂����܂ł͎���Ȃ�����ƁA�������Ă��邾���ł��B���ďC�_�̊W�ł����AODA���班�������]�����ăJ���{�W�A�ɂ��Ċw�сA���̒��̉����̈�[�Ƃ���ODA������Ƃ��悤�Ǝv���搶�ɘA�������Ƃ���u�J�������w�v���w�ї������Ȃ����ƌ����ꌾ�Ń`�����ł����B�c�����c�@�@���J��搶�́A�D���������搶�ł�����{���Ă��A���𖧂ɂ��������ǂ��Ǝv���܂��B�܂��S��������ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�c�c�ȉ����x �y�R�������g���������m�l�h�ւ�2003�N�Q���P�V���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�g���������m�l�h���� �c�O�����c ����ƁA���_�̂��ƁA�����Ă��邤���ɂǂ�ǂ�ς���Ă����܂��B���������Ӗ��Łu���߂ɏ����n�߂�v�Ƃ����l�̈ӌ��������Ƃ��ł��B���͂��܂Ƃ߂�X�s�[�h�ɂ���������̂ŁA�F�ɓ��Ă͂܂���@�_�͂Ȃ��̂ł��傤�B�����A���e���ς��̂́A��͂肢�낢��ƕʂ̃A�C�f�A�������邽�߂ŁA�Ƃɂ����ʼn_�ɍl������ł����傤���Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB�c�c�ȉ����x �y�g�|�b�|���h���g���������m�l�h�ւ�2003�N�R���R�O���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�c�O�����c �y�g�[�~���g���S�����ւ�2003�N�S���Q�R���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�S���̊F����� �y�g�ΘJ�w���h���4�����ւ�2003�N�S���Q�R���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�F����@����ɂ��́A�����Ă����l�ł��B���Ď��́A�X�N�[�����O�̌�A�搶�̐����������R���T���ēǂ݂܂����B�m���Ɂg���������m�l�h�������ʂ�P���Q��ǂ����ł͗����ł��܂��o���Ă����܂���B�c�����c�@����̖{���P�T�Ԃœǂ݁A�����čŒ�R��͌J��Ԃ��ǂ�ł��܂��B���ꂪ�ǂ��̂������̂��͕�����܂��A�_���������ɂ������Ă͋ꂵ�܂Ȃ�������Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B�Ƃ���ŁA���̏C�m�_���\�z�ɂ��āA����A���J��搶���h���̃R�����g���܂����̂œ����ׂ̈ɏ����V�F�A-�����Ē����܂��B -�@�s�搶�̃R�����g�t��芸�����͂���ł����Ƃ��āA�Ƃ����������Ă݂�Ƃ����ł��傤�B�������A���܂�ɂ��ǂ�ł����发�����Ȃ����܂��ˁB���ɂǂ�Ȗ{��ǂ̂ł����B���Ƃ��A�u�k�Њw�p���ɂ̗ьꓰ�w�����������Ǝv�z�x�A�X�O�؎O�Y�w�V�q�E���q�x�A�݂������[�̓��c���w�����̓`���v�z�x�A�l�����@�w�V�q�Ɠ����x�A�����o�Łw���������j�E�ߑ㉻�Ɠ`���x�A��Εہw�����l�̉��l�ρx�i�T�C�}���o�ʼn�j�A�|�����w�����̎v�z�x�iNHK�u�b�N�X�j�A�Ȃǂ͏��Ȃ��Ƃ��ǂ܂Ȃ���Β�����m�蓾�Ȃ��ł��傤�B�����Ɗ�{�I�Ȃ��̂̌����A���m����g�ɂ��Ȃ��ƂƂĂ��C�m�_���ɂ͂Ȃ�܂���B�c�c�ȉ����x �y�g�D�����h���g���������m�l�h�ւ�2003�N�T���R���t���d�q���[���@�|�����|�z �w���ɂ́A���N�̘A�x�̓J�����_�[�̊W�Łu�����̂R�A�x�v�Ƃ������ƂŕʂɈӖ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�����w�Z��4���ɐV�w�����}���āA���̎����́A��肪�������₷���A�s����Ȏ����ł��B���k�̖��s���A����A�\�͎�����O���́u���₵���n�̕��v�̓o��ȂǁA�P��s����������܂��B�c�����c�@��T���J��搶��范��̃��[��������܂������A�w��ɂ́A���R���B�̈Ӗ��̂ق����傫���Ƃ݂Ȃ���A�Ǝv���Ă��܂��B���_�ɂ��ẮA�͕����A�Ɛߕ��������Ē��J��搶�֑������Ƃ���A�_���鏇���Ƙ_�|�ɂ��āA�M�d�Ȏw�������炢�܂����B3�����̕��ɔ�ׂāA���ɂ́A���J��搶�́A������e�ՂɌ����Ă�������C�����܂��B�Ƃ������Ƃ́u�����ɂ́A�����ōl����\�͂��Ȃ��v�Ɣ��f����Ă���̂�������܂���B�c�����c�܂��A�g���������m�l�h����́A8���ɂ͏����グ��Ƃ���������Ă��܂������A�i��͂ǂ��ł����B3���ɂ��f�������_���̂h�s�֘A���ɂ��āA�����ڂ������₵�����Ƃ��˂��ˎv���Ă��܂����A��������Ƃ��ɂł������Ă��������B�c�c�ȉ����x �y�g�|�b�|���h���g���������m�l�h�ւ�2003�N�W���X���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�g�[�~���h���u�������荘�v�Ƃ����̂��W���̎���[�~�ŕ����܂����B���厖�ɁB�W���͂V�l�̏��K�͂̃[�~�ƂȂ�܂����B�l�Q�͘_���̓r�������Ă���ɑ��ăR�����g���ĖႢ�܂������g�D�����h����͑����i��ł���悤�ł����B�����͂܂����ɂ�������ŏł�������܂����B���|�[�g���܂��W�����Ɏd�グ�Ȃ��ƂX����o�Ȃ̂ŁE�E�E�E�B���̎�̃[�~���A�搶�͂��Ȃ����ǁA���\�L�Ӌ`�ȃ[�~�ł����B����ł́B�x �y�g���������m�l�h���g�|�b�|���ւ�2003�N�X���P�O���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�������育���������Ă��܂��܂����B���莆����A�撣���Ă���������l�q���݂���悤�ł��B���́A�O��̃[�~�̌�A�߂��Ⴍ����ɖZ�����Ȃ��Ă��܂��܂����B������3���ԑO�ɁA���`����߂��Ă����Ƃ���ł��B�C�m�_���Ɏ��g�����Ǝv���Ă���̂ł����A����Ɖ����ł��܂���B�Q�����I�Ƃ������ƂŁA��������̂悤�ɁA�ŋ߁A�搶������Ȃ��l�́A���Ƃł��܂����ƌ����Ă���̂́A���́A���ł��B�Ƃ�����A�v�X�ɁA��M�ł��܂����̂ŁA�C��������܂����B�L��������܂��B�x �y�g�|�b�|���h���g���������m�l�h�ւ�2003�N�X���Q�V���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�_���������쐬���ł��B�S���Ɋւ���f�[�^���W�߂Ȃ��瓝�v�I�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B���̌��ʂ��A�搶�ɑ��M���Ă��u����ł̓R�����g�ł��Ȃ��v�ƌ�������w���ł��B���̃p�^�[�����������Ă��āA�C���ł�܂��B���낻�댈�����Ȃ��Ǝ��Ԃ��Ȃ����B�d�������ꂩ�痈�N�Q���܂ŖZ�������B�Ƃ���ŁA�g�[�~���h�͌��C�ł����ˁB���[�����Ă��Ԏ����Ȃ��̂ŐS�z�ł��B�����Ă܂����ˁB�c�c�ȉ����x �y�g�ΘJ�w���h���4�����ւ�2003�N�P�O���P�O���t���d�q���[���@�|�����|�z �w���d���ƏC�m�_���̍쐬��ς����l�ł��B�ǂ��ł����H�@�C�m�_���͐i��ł��܂����B���́A�������O�ł��B�Ȃ��Ȃ���P�͂��I�炸�ɂ��܂��B�܂����A�F����A���������I�������Č�����Ȃ��ł��傤�ˁI����Ȓ��q�ʼnʂ����āA�_�����o���オ��̂��H���A���ɏł��Ă��܂��B�c�c�ȉ����x �y�g���������m�l�h���g�ΘJ�w���h�ց@2003�N�P�O���P�O���t���d�q���[���@�|�����|�z �w���S�z�Ȃ��I �y�g�[�~���h���4�����ւ�2003�N�P�Q���R���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�S�����e�� �g���������m�l�h����P�Q����ς̂悤�ł��ˁB�M���̃o�C�^���e�B�Ȃ���v�ł��傤�B�I�b�g�g�A����Ȃ��Ǝ��������闧��ł͂���܂���B���́g�D�����h����ƈႢ�A�����Q���ڂ�o���Ă���̂�����B�Ƃ���Łg�ΘJ�w���h�����Ă܂����H�g�|�b�|���h����͓S���}���炵���A���[���ɏ���Ĉ꒼���ɑ����Ă���悤�ł��ˁB
�y �g���������m�l�h���g�[�~���h�ւ�2003�N�P�Q���U���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�o���O�ɒ�o���Ă������e�Ɋւ���R�����g��搶���璸���}���蒼�������Ă���Ƃ���ł��B���łɁA�\�[�V�����L���s�^�����_�̎Q�ƕ����Ƃ��āu�t�N���}���p�b�g�i���v�𐄏����ꂽ�̂ł������܂ŃV���K�|�[����ۂR�K�̋I�ɍ������X�ŒT���Ă��܂����B�i�ƂĂ������œǂދC�����܂���̂Łj�ł��A��Ȃ����ȓc�ɂ̖{���̔߂����Łu�o�b�g�}���̖���v�͒u���Ă���܂������A�ړI�̕����͌�����܂���ł����B�����Ȃ�����A�C���^�[�l�b�g�ŏ����ł��B�Ƃ��낪�A���̃C���^�[�l�b�g�����ȃo�C���X�i�H�j�Ɋ������Ă��܂��A����ꓬ���Ă��܂��B���̃o�C���X�i�H�j�́AIE���N�����邽�тɁAUSA�̃A�_���g�T�C�g�Ɏ����I�ɐڑ����Ă���āA���X�Ə���ɒ��ߌ��Ȃ������ʐ^����ʂɕ\�����Ă���̂ł��B���̋������������\�������ƁA�w��̂��C�����킹�A�ςȂ��C���N�������Ă���܂��B�ł��A�ɂȂƂ��Ȃ�A���ĉ�ʂ������Ă�����̂ł����A���̖Z�����Ƃ��ɂ���ł͏��X焈Ղ��Ă��܂��B�@�F������A�����������o�C���X�i�H�j�ɂ͋C�����܂��傤�B���̌��́A���コ��ɂ͎��₵�ɂ����̂ŁA���n�̃C���^�[�l�b�g�v���o�C�_�[�ł���ANTT�ɏ��������߂Ă���Ƃ���ł��B�܂������A���������̂ł��B���̐؉H�l���������ɁA�����������o�C���X�i�H�j�Ɗi�����Ă���@�g���������m�l�h����̋ߋ��ł����B�x �y�g�ΘJ�w���h���4�����ւ�2003�N�P�Q���P�S���t���d�q���[���@�|�����|�z �w���́A�C�m�_���������I���܂����B �y�g�[�~���h���4�����ւ�2003�N�P�Q���P�V���t���d�q���[���@�|�����|�z �w4���̊F����� �y�g���������m�l�h��� 4�����ւ�200�S�N�P���Q���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B �Ƃ���ŁA�g�[�~���h�̃��b�Z�[�W���Ɏ����[�����������߂������܂����B����́F�u��b�̖������͈������ǂ݂Ȃ��痝�����A���߂ďo����ƂɊ������Ă���ƁA�ƂĂ��c�t�Ȏ��₵���ł��Ȃ��悤�ȋC�����āA�����₪���̂��Ă��܂��܂��B�v���̉ӏ��Ȃ̂ł����A�g�[�~���h��遂��}�����T���߂ȕ\���͕ʂɂ��āA���ɂƂ��ẮA�C�m�ے��́A�������u���₪�ł��Ȃ��v���́A�ł��Ȃ��̂����l��������2�N�Ԃł����B���ǁA�����Ȃ�ɖ���������ڂ���邱�Ƃ������s�ׂ̊�b�Ȃ̂��ƍ��g�ɟ��݂ĕ��������̂ł��B�@����́A�l���Ă݂�A�搶���ŏ����玄�����ɐF�X�ȕ\���ŌJ��Ԃ��b���Ă��ꂽ���ƂȂ̂ł����A���̈Ӗ�������Ɩ{���ɗ����ł����Ƃ���ł��B�����A�����w���Ƃ́A���ꂾ���������悤�ȋC�����Ă���̂ł����A�Ƃ��������N���ǂ��N�ɂȂ�܂��悤�ɁA�ł́A���ꂩ���Ђɍs���܂��B�x �y�g�[�~���h���4�����ւ�200�S�N�P���P�S���t���d�q���[���@�|�����|�z �w���J��[�~4���̊F����� �C�_�̒�o�́A���Ԃ��Ō�̂悤�ł��l�B�i�����ł�����j�F����I����ăz�b�g���ċ�����ł��傤�ˁB�Ō�̍Ō�܂ŁA�e�s�F�Ȃ炸�A�搶�s�K�����܂����B�����ł��A���e�ɂ��Ĕ����������ł��Ă��܂���B�������A�^�C�����~�b�g�̂��߁A�ꉞ�H�`���͉ʂ��܂����B�������]���ƍ���͐搶���ɂ��邽�߁A�����ǂ��������Ă��d������܂���B25���ɁA������n����邱�Ƃ��o��Ŗʐڂɖ]�݂܂��B���ƃ��|�[�g��4�{�c���Ă��܂����A2�{�ɂ��Ă͗]��N���[���������͂��ȏC���Œ�o���Ă悢�Ƃ̂��Ƃň��S���Ă��܂����A�����P�{�̊����́A�M���̃I���W�i���e�B�̍l���ŏ����悤�w������Ă��āA���ꂪ�Ȃ��Ȃ����ȂƂ���ł��B�ǂ���̐搶���A�ߋ��Ɉ�x�ق߂��Ă��܂������߁A���X�M�u�A�b�v�₻�̂܂܂̒�o��(�����o��������i�ł��傤���j�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�l�̐S���̋��낵���������܂��B��ԕp�x�悭�A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���J��搶�ɂ͂����Ԃ��Ă��܂��A���ł����̂ɁB������ăg���E�}�ł��傤���H
�y�g�ΘJ�w���h���4�����ւ�200�S�N�P���P�T���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�F����A�����C�ł����B ����̂P���P�S����AM11:30���ɁA���}�g�ɂĎ����C�m�_�������܂����B�����M���M���܂ŁA����Ă��܂����B�ꉝ��ォ���ʏ���܂ŗ����ɂ͒����Ɗm�F���Ă̔����ł����A�V�C���ƂĂ��S�z�ł��B���{�C�͑��A���܂��ɋ��s����A���É��Ƒ��̂��߂ɁA�P�T���ɒ������ǂ����@�@�c�����c�@������A�R���̐�y�ɋ����Ă�������ʐڎ���̎����Z�߂Ă��܂��B���|�[�g���������e���o���܂����B������P�X���܂ł̍ŏI��o�܂Ŏ�����ɂ�萋�������Ǝv���܂��B���ƁA�A�E�������撣��܂��B�ł́A�Q�T���ɂ���ł��邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă��܂��B�x �y�g�D�����h���4�����ւ�200�S�N�P���Q�O���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�h���������m�l�h����ցACC:�S�����̊F���� ���̎������͂P���Q�T���i���j�P�R�F�S�O����ł����A�ׂ����킸�ɁA�T�����ւ̐\������͂��������܂��B�Տꊴ�̂��߁A�������O���ɑ��t���邱�Ƃɂ��܂��傤�B �y�g���������m�l�h���g�D�����h�ւ�200�S�N�P���Q�P���t���d�q���[���@�|�����|�z �w�悸�A�����g�D�����h����̈ӌ��Ɏ^���ł��邱�Ƃ�\�����܂��B���̑�w�@�́A�l�Ԃ�U�藎�Ƃ��̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ𐬒������邽�߂̋@�ւ��Ɗ����Ă��܂��B�]���܂��āA���Ə؏����d�v�ł����A����g�ɂ����̂������d�v���Ɗ����Ă��܂��B���̊ϓ_�ł����܂��ƁA�������ɁA�_����Z�߂鑬�x�ƁA���[����łĂ�ʂ͑����܂��������w�O�Ɣ�ׂĂ̈Ⴂ�ɋC�����Ȃ��ĔY��ł��܂����B �������A�ŋߋC�������̂ł����A���́A�搶�̒�����R�������ǂ߂�悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B���ł��A�o���Ă��܂����A�搶�̒���͎��ɂ͓���ŁA2�N�O�ɂ͓��e�𗝉�����̂ɑ����Ȏ��Ԃ��������Ă��܂����B�ł��A���́A����x�͂Ƃ������A�搶�̘_�_�������ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�{�ǂ݂̑��x����A����������₩�Ȑi���̂ЂƂł��傤�B�ł��������A���̒��ɂ���قǑ����̎v�z�Ɨ��_���������Ă��āA�����̋^��_��Y�݂Ȃǂ́A��l���قƂ�ǂ̏ꍇ�A�������Ă��邱�ƂŒm�������Ƃ��d�v�ł����B�܂�A�w��Ƃ́A�����ʂ�A�₢���āA��������w�Ԃ��̂Ȃ̂ł���A�₢����͂������Ƃ��S�Ă̎n�܂�ł���A�͐�l�̋Ɛтׂ�������w�Ԃ��̂Ȃ̂��Ɨ������܂����B ���ǁA�w��Ƃ͐l�ނ����グ������Ȓm���x�[�X�̐�����ɂȂ�A�h��������Ă��������Ȃ�ł��ˁB�����ŁA������ɂȂ�鎑�i�͎���͂Ɨ���͂ł�����A����2�N�Ԃł��ꂪ���サ�Ă���Ό�����������ƂɂȂ�܂��H�F����́A�ǂ����l���ł��傤���H���̃e�[�}�Ő���25���͈��݂܂��傤�I�I�x ------------------------------------------------------------------�\----------- �@�ȏ�AM2��1�N�ԂɁA�������Ō����肵�����[���̂����A�ق�̈ꕔ���Љ���Ē����܂����B�����ǂ�Œ����������ŁA���́A�C�m�_��������ڎw���ďW�܂��������̃����o�[���AM2�I�����ɂ͐[���J�Ō����̂����������������������Ǝv���܂��B �@����قǕp�ɂɉ��ł��Ȃ��̂ɁA���̂����m�̊ԕ��ł������悤�ȍ��o�����o�������Ă���钇�Ԃł��B�C�m�_�������i��o���������H�j������������ǁA����ȏ�ɤ���Ƃ������݂Ȍ��t���Ə��Ă��A��͂�Ō�ɂ͌��������Ȃ�܂��B �Ƃ���ŁA���J��搶�͂���Ȃɕ|���l���ł����āH�@�ܘ_��Ⴂ�܂��B���ۂ̐搶�ͤ�w��ւ̎p���͋ɂ߂Č���������ǁi�����甽�_�ł��Ȃ��̂ŕ|���B�j�w���v���̗D�������ł��B��w�@���̊F����ł�����A���S���Ē��J��[�~�ɒ��킵�Ă݂ĉ������B
�u�����N�����ƏC�_�쐬�v�@�@ ��������U�@�@��@�����q �@ �@ �@�����������̒��Ő����˂Ȃ�Ȃ������N�̏��������A�ł����̒��ŏC�_���o�ł������ƂɐS���犴�ӂ����Ă��܂��B���g�̌��N�A�V�e�̌��N�A�����ւ̔��R�Ƃ����s���͑S�Ă̒����N�̏����̋��ʂȔY�݂ł�����܂��B�����̔Y�݂͖{�w��w�@�ł̏C�_���܂߂��w�K�ɂ��A�������\�͂�{�������ƂŎ��̏ꍇ�͂悢�����ɐi��ł���܂����B�C�_�쐬�Ől�ԂƂ��Ă������ł������Ƃ�����Ȃ���n�ł���A�܂����ꂩ��̐l����w�K�̏o���_�ł��邱�Ƃ�S�ɍ��ޖ����ł��B ���N�̊Ǘ� �@���̓I�A���_�I�Ȍ��N���p���I�Ȋw�K�̏o���_�ł����A�ǂ����Ă������s���Ƃ�����肪�O�ʂɏo�Ă��Ă��܂��܂��B���͑�̖��11�������܂Ŋw�K�����Ē���5���ɂ͋N���Ƃ��������ł����B�w�Z�}���قɋΖ����Ă��܂��̂ŁA5��50���ɂ͐�t�s���̉Ƃ��o�ēs���̐E��Ɍ������܂��B�Ċ��x�ɂ͂���܂������A�̒��������Ă��N�x���Ƃ�킯�ɂ������Ȃ��̂ŁA�����̒ʋΎ��Ԃ������ɂ��ĂĐ����s����₢�܂����B�����s����������ƋL���͂����ނ��āA��I�ɂ��s����ȏ�ԂƂȂ�܂��B�܂��p�\�R���ɂ��ڂ̔�J�������ł����炷�ɂ́A�p�\�R���p�̒��ߗ��p�̃��K�l���K�{�ƂȂ�܂��B����ɓ��ɓ��j���Ȃǂ͉Ƃ̒����Ă��肫��ɂȂ�܂��̂ŁA���̉^�����K�v�ƂȂ�A�߂��̃R���r�j�ɃR�s�[���Ƃ�ɍs�����肵�܂����B�ꐡ�����x�e������Ȃ��Ƃ������Ĕ\�����������Ă��܂��܂��B�W�����鎞�ƁA�x�����鎞�̃o�����X���l���邱�Ƃ�����ƋC�Â��܂����B���ꂩ�璩�̖�W���[�X�͖����������܂���ł����B�r�^�~���s�����S�g�̔�J�ɔ��Ԃ�������悤�ł��B �@���_�ʂ̃��t���b�V���ɂ����ӂ��܂����B����͎��̏ꍇ������������܂��A���{�f����`�����l�����s�u�Ō�����悤�ɂ��āA�s�C��{���܂����B���̍��̌��C��������x�Ƃ������ɂ́A�Ⴂ��������i�ɐڂ��ĉߋ�����z���邱�Ƃ��Ⴓ �̉Ɍq����悤�ł��B�������A���Ƃ�������̓����␢�E��ɂ��ڂ������āA�ߋ��Ə����ւ̓W�]�̃o�����X���S�����邱�Ƃ��őP�ł����B �V�e�̂��� �@�����������N�ł��鎞���ɁA�e�͂܂��ɐl���̍ŔӔN�ł��B�����ł��悢�ŔӔN���߂������Ă�肽���Ƃ����C�����͂���܂����A������Ƃ����Ă��܂�J��肷����̂��V�e���������ĘV��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���A���\�Ή߂��̕��̉Ǝ��ւ̋��͂����}���Ă���܂����B���̔N��̒j���͐펞���ɌR���Őj�d���܂Ŏd���܂�Ă���A��̎��㕃�͎G�Ђ�D���悤�Ȃ��Ƃ����Ă���܂����B������ ����ɂ�鐊�������X�Ɏn�܂�A�u���O�͎Ⴍ�Ă����v�Ƃ����悤�Ȍ��t�����̖��ł��鎄�Ɍ�����悤�ɂȂ�܂����B��������̐l�Ԃւ̃W�F���V�[�̂悤�Ȃ��̂��V�l�ɂ��邱�ƂɋC�Â��A�ǂ����ɕ��̂悢���F�B�����Ȃ����̂��Ǝv���Ă���܂����Ƃ���A�ˑR��������P�A�E�n�E�X�����錾���܂����B���͕���14�N�̉Ăɂ��̎{�݂����w���A���N�セ���̐ӔC�҂̕��Ƌ��R�ɐ�t�s���ōĉ�����Ƃ��������S�������̂ł����B���̐S�z���_���̉���ŕ��ɓ`������Ƃ����l�����܂���B�����ɂ͖S��̌Z�v�w���������Ă��Ĉ��S�Ȃ̂ŁA�����̂��邤���ɂƘb��i�߂܂����B�~�G�̏��g�[������̂ŁA������������悭�Ȃ邱�Ƃ͕��ɂƂ��Ă��悢���Ƃ��Ǝv���܂����B �@�V�e�̉��ɂ͎���Ƃ�������������Ǝv���܂��B����͂���Ȃ�ɂ��炵�����Ƃł����A�ǂ����Ă����ꂪ�ł��Ȃ��ꍇ�̓P�A�E�n�E�X�ɓ����Ă��炤�̂��{�l�̂��߂ł�����悤�ł��B���̖{�w��w�@�ł̊w�K�����Ɏh����^���āA�C�_�̒�o���ƂĂ����ł���܂����B ���������� �@���������łȂ��j���ɂ������ւ̔��R�Ƃ����s�������邱�ƂƎv���܂��B����̓��{�̏͌\���߂����l�Ԃɉߍ��ȉ^����W�J�����Ă���ꍇ������܂��B��������̐l�Ԃ��W�܂�Ƃ܂��A���N�̂��ƁA�V�e�̂��ƁA�����ւ̕s�����b��ƂȂ�܂��B���̏ꍇ�A�C�_�̃e�[�}�ƂȂ����u�w�����V���x�����\�����Y��ɂ�鎩�Ȏ����v�ł́A����̕ϑJ�����Ȃ̉\�����L���邱�Ƃŏ������������k�������A�����Ɍ���̐l�ԂƋ��ʂȔY�݂����o�������Ƃ��s���ւ̎��_��ς����̂ł����B�u�s���v�Ƃ�����Ԃ́A��������Y�݂ł�����A���̎���ɂ��l�X�̐S�̒��ɒu����Ă����Y�݂̍����̂悤�Ȃ��̂��������Ƃ��w�K��ʂ��ė����ł��܂����B �@�Y�݂�����Đ����Ă����l�Ԃ̕��݁A���̕��݂����������ɏ����ł������Â����邱�ƁA�����ɐ������k�̈Ӌ`�����������Ƃ��c���ł��A���́u���v�̔Y�݂�����č���̐l�����l���邱�ƂƂ������܂����B �@�Ō�ɍs���͂������w�������������c�ؕ��m�搶�A�܂����̊w�K�Ȗڂł����b�ɂȂ����搶���Ɍ�������\���グ�܂��B����ɏ��c�[�~�̈�N���̕��X�A���N�̕K�C�X�N�[�����O�ł��ꏏ�������������̕��X�A����̎����ǂ�A�s���J�̃O���[�o�������Ȃ̐}�����̕��X�̂��e���Y��邱�Ƃ��ł��܂���B
�i���j�f�B�X�J�b�V�����E���[���i�W�҂̂݉{���j�ɂāA�u���搶�v���u�w�K�̃|�C���g�v��I���B
�@ �P�A���ׂƂ���������̃e�[�}���� �@���w������4���A�C�m�_���̌����e�[�}���i�肫�邱�Ƃ��ł����ɁA�w�������̌������Ŏ��~�߂̂Ȃ��b�����鎄�ɐ搶�͍��C�悭�����X���ĉ������Ă����B�b�E�r�E���C�X�����ł��邱�Ƃ����͌��߂Ă������̂́A���C�X�̉����������邩�͌��ߎ肪�Ȃ������B���̉āA�g�߂ȏo��������u�i���v�Ƃ������Ƃ����̂Ȃ��ŃN���[�Y�A�b�v����Ă����B���͂��̂��Ƃ̈Ӗ���{���ɒm���Ă���̂��낤���Ƃ����^�₪�N�����B�����āA11���ɏC�m�_���̃e�[�}�Ƃ��āu�i���ɂ��Ă̍l�@��C.S.Lewis�ɂ�����i���̃��B�W�����v�����肵���B���ׂ̐��E����A�L��Ȑ��E�֔�э��킯�ł���B �@�������Ȃ���A�������Ɂu�i���v�̐��E�͍L���A����L����ɂ͎������Ȃ������B�����̘g���A���ԁA��Ԃz���A����������̐��E�A�V���Ƃ��������E�܂ŁA�ʂĂ��Ȃ��ڂɌ����Ȃ����E�������ƍL����̂ł���B�ĂсA���ׂ̐��E�ɖ��������X�������A�ӂƋC���t���Ă݂��2�N���̏H���ƂȂ��Ă����B�C�����������C�_�쐬�v��́A�v��𗧂Ă�ォ�炱�Ƃ��Ƃ�����čs���A12���̃[�~�ɑ��e���o����Ƃ����搶��[�~�̐l�B�Ƃ̖��S����ꂸ�A12���̒��{���]�I�ȋC�����Ō}���Ă����B�C�_�̃e�[�}�ƃ��C�X�����ł���Ƃ������Ƃɗ����Ԃ�A1���̒�o�܂ł̎��Ԃ��l�������e�̍i�荞�݂����A�{�i�I�ɖ{���쐬�Ɏ��g�̂̓N���X�}�X�߂��̍��������B �Q�A�[�~���\�Ǝ����̎��W �@�P�N������s���J�ł̃[�~�Ȃǂɂ����āA�ŏI�I�ɂ͎g�p���Ȃ��������̂����邪�A���낢��ƎQ�l������ǂ�Ŕ��\���A����������Ƃ��Ďc���Ă������B������A4�T�C�Y��Word�œ��͂��A���p���͕����̕Ő��ƍs����K������A�Q�l�����̋L�ڂ̕��@�Ȃǂ����킹�ďC�_�ɂ��̂܂ܗ��p���邱�Ƃ�O���ɒu���č쐬�����B�܂��A�ǂ����ɂ́A�͗��ĂƓ��e���قƂ�nj��܂����i�K����A���_�E�_�_�ƂȂ���e�ɂ��S�F�̕tⳂ�F�������ē\���Ă������B�ꌩ���Ăǂ̂悤�ȓ��e�������̂ǂ��ɏ�����Ă��邩���킩��̂ł���B���Ƀe�[�}���肩��̖��N�ԁA���̂悤�ɗ��ߍ��܂ꂽ�����͍Ō�̒i�K�ő����ɖ𗧂����B �R�A���̋��n �@�����������Ƃł͂����Ă��A�Ō�͂�͂�̗͂ƋC�͂̏����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɨ\�����A1�N�̂Ƃ����璩�̃W���M���O��E�H�[�L���O�����H�����N�Ǘ��ɓw�߂Ă����B�ǂ����ݎ��ɂ́A�ڂ̂��߂Ƀu���[�x���[�Z�k�G�L�X��H���A�X�g���b�`�̑��Ȃǂ����Ĕ�J�����ɘa�����B12���͓������d��������ł��邪�A�Љ�l�Ƃ��Ă̋߂���������Ɖʂ����ĔN���N�n�̋x�݂ɓ���A�悤�₭�W���ł�����X���K�ꂽ�B1��13���Ԉȏ���Ɍ��������X�A�s���Ƃ����������|�S�ɋ߂��C�����Ɏ����Ȃ��悤�ɁA�Ƃɂ����]�v�Ȃ��Ƃ͈�؍l�����ɂЂ����當���ƃp�\�R���Ɍ��������B �@�����͂ق�̌`����̂��߂��ЂƂ�ŏj���A�N���N�n�̖�10���Ԃ̊ʋl��Ԃ��߂����A�C�_�������̂܂ܐV�N�̎d�����߂̂��ߏo�����B�قƂ�ǒN�Ƃ���b�����킷���Ƃ��Ȃ��C�_�쐬�ɋ���ł������߁A�E��ł̎d���̓��t���b�V�����ʂ�����A�����Ƃ̉�b���s�v�c�ƐS������Ă��ꂽ�B�������Ȃ���A�d���͐V�N���X�����Ȃ�̎c�Ƃ��������B�T���ɂȂ�̂�҂��čŌ�̊�����ڎw�����B �S�A�З͂�����Word�̋@�\ �@�C�_�{���̓��e�����邱�ƂȂ���A�ŏI�i�K�̘_���Ƃ��Ē�o���邽�߂ɁA�̍ق𐮂��邱�Ƃɑ����̘J�͂Ǝ��Ԃ��K�v�ł��邱�Ƃɓ���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�AWord�̋@�\�̂Ȃ��ł��u�}���v�́u�r���v�@�\�ƁA�u�����v�́u�A�E�g���C���v�Ŗ{�����쐬���A�Ō�Ɂu�}���v�́u�����Ɩڎ��v�ɂ���ďu���ɖڎ����쐬����Ƃ����@�\�𗘗p�������Ƃ���������t�����B���̑��A���p�����A�p���v�|�A�_���v�|�̍쐬�A�Ō��50�ňȏ�̖{���̃v�����g�A�E�g�ƕ��{3���̃R�s�[�A�p���`�ł̌������ƃt�@�C�����O���X�A�d�グ�̒i�K�ł̕��i�̏����Ȃǂ��܂ߗ\�z�ȏ�̘J�͂Ǝ��ԁA�����ďW���͂�v�����B�Z�p�ƕ����I�Ȗ�肪�Ō�ɍT���Ă������Ƃ����߂Ēm�����B��͂�]�T�������āA���߂ɏC�_�����������邱�Ƃ�Ƃ������߂������B �T�A���ʂƂ��Ă̏C�m�_�� �@�����������Ă��Ȃ��Ȃ��{���������n�߂��A�����̕��݂𑱂��鎄������������A�������ė�܂������A�Ō�̒�o���肬��܂ł��w�����������|��搶�ɂ͉��Ɗ��ӂ����`��������悢�̂��킩��Ȃ��B�܂��A�Ō�ɂ͎������肩�A�S�Ȃ炸�����͂���������ł��܂����Ƃ�Ɋ����A���̂��߂ɂ����Ƃ��Ԃɍ����Ē�o���Ȃ��Ă͂Ǝv���A���̂ǂ��ɂ��̂悤�ȃG�l���M�[������ł����̂��Ǝ����ł��s�v�c�Ȃقǂɒǂ����ݎ������Ђ����肵���B�����ĂЂƂ�ŏC�_���������̂ł͂Ȃ��B �@���̏C�_�쐬��ʂ��Ċw���Ƃ͔��ɑ傫�������B�������e����̐V�����������������������A�����̗͂̂Ȃ���コ���B�����ɁA�������g�Ŏ���邱�Ƃ��ł����B�����āA������S�ł͂Ȃ����A���̌��i�K�̐���t���ЂƂ̌`�ɂ��邱�Ƃ��ł����B���̏C�m�_���́A�������������̂ł͂Ȃ��A���ʂƂ��ď����ꂽ���̂ł���ƌ����̂����̎����ł���B
�@ �@�C�m�_���쐬�܂ł̒����悤�ŒZ�������Q�N�Ԃ�U��Ԃ�ƁA�ƂĂ����S�[���B���A�^糃[�~�ʼn߂������l�X�Ȏv���o�����̓����삯����B�T�C�o�[�[�~�ł̔��\�A�����Ȉӌ��������͂��߁A�ʐڃ[�~�Ń����̂悤�ɔ��ł���M�d�ȏ����̐��X�Aetc�B�����́A���w�O�ɕ����Ă�����w�@�̃C���[�W�i�����܂ł����l�́j�Ƃ͂�����ƈႤ���́B�Ƃɂ����A�^糃[�~�̂Ȃ��ɂ���Ɓw�S�ƉȊw�x�����R�ɐ[�܂�A�������邱�ƊԈႢ�Ȃ��B�y���������̂́A�ʐڃ[�~�I����̂Q����B�s���J�E�G�Ŕt���X���Ȃ���A�鎞�Ԃ��R�����ƖY��A�A��V���f�����^�C���ɂȂ������Ƃ��B�悭���݁A�悭�H�ׁA�悭�b�����B���������̂Ȃ������̎��Ԃ��[�~�̒��Ԃ����ƈꏏ�ɉ߂������B�ʐM����w�@�ł̐V�����w�K�X�^�C�������ɗ^���Ă��ꂽ���X�̑��蕨�Ɋ��ӂ��A�{�e�ł́A�C�m�_���ɕK�v�ȕ��������̑�����F���܂ɂ��`���������Ǝv���B�^�C�g���́w���������̃X�X���x�́A����Ȏ��̎������������Ă���B����ł́A���Ȃ�ɂ܂Ƃ߂��g ���������ɕK�v�ȂTW�PH �h�����͂����悤�B WHAT�i�����j�H �@�܂��A�����̌����e�[�}������������Akey words�𗊂�Ƀf�[�^�x�[�X�Ŋ֘A������������������B���̍ۂ͂ł��邾���ŐV�̘_���ɂ����邱�ƁB�����āA���̗̈�̌����̗�������ނ��Ƃ���ł���B����܂ł̌����ł͉����킩���Ă��āA�����܂��킩���Ă��Ȃ��̂��𖾂炩�ɂ��A���̒��Ŏ����̘_�����ʒu�Â���K�v������B�������A���܂�ɏ����W����ɋC���Ƃ��Ă���ƁA�c��ȗʂ̏��Ɉ��|����Ă��܂����Ƃ�����B������ �ł炸�����ɐi�߂Ă����ƁBabstracts��ǂ�ŁA����������Ă���Afull text ��ǂށB���̘_���̈��p�����̂Ƃ��납��A�֘A�_�������Â鎮�Ŏ�ɓ����B���肵���_����ǂ݃X�X���Ȃ���A�����Ȃ�Ɍ����j������Ă����Ƃ悢�B�����Ɍ����ƁA���͍��܂ʼnp��̘_����ǂ��Ƃ��Ȃ������B�C�m�_�����Ȃ���A���炭�p��̕����͈�ؓǂ܂Ȃ������Ǝv���B����A�����_�����܂Ƃ߂�ߒ��ł킩�����̂́A�p��̕����̑���B���{�ɂ�����_�������ł͌��E������̂��Ƃ킩�����B����́A���ɂƂ��đ傫�Ȏ��n�������B WHO�i�N���j�H �@�����ł���B��͂莩���ȊO�ɂȂ��B�����̐ӔC�Ő�J���Ă����̂��B�������A����Ȋi�D�������Ƃ��茾���Ă����Ȃ����Ƃ�����B�����������ČǓƂȍ�Ƃ��Ɗ����邱�Ƃ������B�����̂Ȃ��ɂ͂P��ǂ����ł͗����ł��Ȃ����e������B����ǂ��납�A���x�ǂ�ł����ɓ���Ȃ����̂�����B����Ȏ��A�d�q������Ў�Ɏ�C�Ȏ��������܊��������B�������Ԃ����钆�Ƀp�\�R���Ɍ������Ă���ƈÂ��C�����ɂȂ邱�Ƃ����Ă���B���͂��������������A���������������D�̃`�����X�B���N�Ŏd���͏����B�Ƒ����������Ă����B�q�ǂ������͉����B�������܂��܂����邼�B�S�������Ęb����F�l�����邵�B����ς莄�͍K���ҁB���Ⴀ�A������i�߂Ă������B�����A�P���Ȏ����ƌ��������āA�����͂�Ⴄ�̂��B WHY�i�Ȃ��j�H �@�Ȃ�Ƃ����Ă��A����������̌����ʼn�����舵���A�����ĂȂ��������s�������A�������@�m�Ɏ������߂ɂ����������͕K�{�Ȃ̂ł���B��������������ɃX�^�[�g���Ă��܂��ƁA���Ƃ���ρB���������{������ɁA�����̍s���������͂��łɒN�������\���Ă����������Ƃ�����E�E�E�l���������ł����낵���B�����Ȃ�ƁA���ۂɌ����ɒ��肵�Ă悩�����̂��ǂ�����������邱�ƂɂȂ�B�����̌����̃I���W�i���e�B�͂ǂ��ɂ���̂��i������������牽�x�w�E���ꂽ���Ƃ��j�A��������o�����߂ɂ��������������낻���ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B WHEN�i���j�H �@�������������A���������ɐ^���Ɏ��g�̂͂Q�N���ɓ����Ă���ł���B�v���悤�ɏW�܂�Ȃ��֘A�_���ɏł�������Ȃ���A��Ȗ�ȃC���^�[�l�b�g�Ō����ɗ�B�P�N���́A���������̕K�v�������Ȃ�����A�Ȗڂ̉ۑ背�|�[�g�Œǂ������̐����𑗂��Ă����B�P�N���̌���ɂ͎����̎����������n�܂������A�Z�����Đ�s�����͒��ׂĂ��Ȃ����i������v���Ɩ��d�ȍl���������j�Ƃ����킯�ŁA�摗���Ԃ̂܂܂Q�N���ɓ˓������B��ς������̂́A�i�݂䂭���������ƕ��s���Ē��ׂȂ���Ȃ�Ȃ��c��ȁi�Ǝv�����j��s�����̐��X�B�����A�����Ƒ����n�߂Ă����悩�����B���ɂQ�N���̏t����Ăɂ����Ă̎��́A���{�����������ʂ�]�����Ȃ���A���̌v������Ƃ����ߍ��ȃX�P�W���[���B����ǂ��A���̎������Ȃ�Ƃ����邱�Ƃ��ł����̂��A��J���Ē��ׂĂ������������̂������B���s���Ď��W������s�������炽������̃q���g��Ⴆ���B�������@�̏C������葱����̍ו��Ɏ���܂ŁA��s�������Q�l�Ɏ��s���낵�Ȃ��猩���������Ƃ��悩�����B������A�I������������琺���ɂ��Č����邱�ƁB�Ƃɂ����A�ł��邾�����ߑ��߂ɐi�߂悤�B�ł���A�P�N���̂����Ƀ������[���܂Ƃ߂��邭�炢��best�I WHERE�i�ǂ��ŁH�j�AHOW�i�ǂ�����āj�H �@����ŁA��ɓ��ꂽ���قƂ�ǂ̕������W���\�B����͋����������B�d���ƉƎ��Ɗw���̂R���̂�炶�𗚂����ɂƂ��ĉ����L������̂́A�����C���^�[�l�b�g���g����access�ł��镶���f�[�^�x�[�X�A�}�������V�X�e���A�G����}���̏������ȂǁB�����āA���肵�������͓������炱�܂߂ɐ������Ă������Ƃ���B���ł��ǂ߂�悤�ɕ������X�g���쐬���Ă����ƁA���ƂŖ��ɗ��B����ł͍���A����access�p�x�̍��������T�C�g�����s���ł��Љ�����B ������MEDLINE�̃f�[�^�x�[�X�B���E�I�Ȉ�w�̃f�[�^�x�[�XMEDLINE�𒆐S�Ɋ֘A���邳�܂��܂ȃf�[�^�𑊌݂Ƀ����N�ł���B���X�X���̃T�C�g�B ��������}���ق̃z�[���y�[�W��NDL-OPAC�̂Ȃ��Ō����ł���B�̘^�͈͕̔͂��L���A�l���E�Љ�/�Ȋw�E�Z�p/��w�E��w�Ƃ��������̂��J�o�[���Ă���B�������������̕��ʂɂ��ẮA���p�o�^����C���^�[�l�b�g�ɂ��X�֕��ʐ\���ő����Ă��炦��̂ŕ֗��B �i���j�_�C������Љ�����c���쐬���A�����Œ��Ă���Љ�V�N�w�̓��{�ꕶ���f�[�^�x�[�X�B�������ʂ̏��������Ƙ_�����^���_�E�����[�h�ł���B ���{��w��w�@�̃z�[���y�[�W�̐}���ٓ��ɂ�����B�w����̔��s����w�p�G���̃y�[�W�����̂܂܉摜�f�[�^�Ƃ��Ē~�ς��C�������ƂƂ��Ɍ����ł���悤�ɂ������T�[�r�X�B�_���E�G���̃��X�g�̌����͎��R�ɂł��邪�A�_���̃y�[�W�̕\������������ɂ͗��p�o�^���K�v�B���p�����͖����Ȃ̂œo�^�͂��X�X���B�������w�����߂钘�쌠�g�p�����A�y�[�W����ʕ\������ш�������ꍇ�ɏ���������B�x�����́A�����Ă���U�荞�ݗp���ŁB ��������Ă��Ȃ����m�_�����w���������Ƃ��͂�����ցB�������炢���������M�d�ȏ��B���̏ꍇ�A������express�Œ������Ă�60�y�[�W�Ł�55�i�������݁j�B�_���͂P�T�Ԉȓ��ɗX�ւœ����B����1������ʂ�Bank��check������A��55�͓����̃��[�g�ŗ����Ă����B ���{��w��w�@�̃z�[���y�[�W�̐}���ٓ��ɂ���̂�������B�č�PQIL(PROQUEST INFORMATION & LEARNING)�Ђ��C���^�[�l�b�g�Œ���S���f�[�^�x�[�X�B�����ݍZ���ɑ�����T�𗘗p���Ȃ���͂Ȃ��BKey words������hit����_���́Afull text���_�E�����[�h�ł���B��ς����b�ɂȂ����T�C�g�ł����B ��������A���{��w��w�@�̃z�[���y�[�W�̐}���ٓ��ɂ���̂ŕ֗��B���������p���l�͍����B
�@ �@�{���Ȃ�Q�N�Ԃ̂Ƃ�����R�N�������ďC���������̏C�m�_�����M�^���L�c���Q�l�ɂȂ�̂ł��傤���B �@���̑�w�@�����́A�w�������Ƃ̑����A�w�F�Ƃ̌𗬂Ƃ����_�łƂĂ��b�܂�Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���Ɋw�F�ɂ��Ă͓��w�O����̒m�l������A���ɗ�܂������Ȃ���̎����߂����܂����B�k��[�~�ł͓������̊�������点�Ă����������ƂɂȂ�A���͂Ȃ�����w�F���m�̌𗬂������߂邱�Ƃ��ł��A�����[�~�̏C�����Ƃ��Ē������t�������������Ȃ��ƌ����C�������A�_�������������邽�߂̏����ɂȂ����悤�ȋC�����܂��B �@�C�����邽�߂ɂ́A�C�m�ے��Q�N�Ԃ̊ԂɁA���C�P�ʂ��N���A���Ȃ���Ȃ�܂���B�P�N���ɂ�20�P�ʂ𗚏C�A�Q�N�ڂ͎c��1�ȖڂƘ_���Ƃ����悤�Ɍv��ǂ���ɐi���ɂ݂��܂������A�Q�N�ڂɑ̒�������A�_�������̖ڕW���������Ƃɂ��܂����B �@���Ƃ��ƁA���鎑�i�����̂��߂̕������������ƂȂ�A�w�ւ̏�M���ĔR�������Ƃ���w�@�ɓ��w���邫�������ł����̂ŁA�C���܂ł̊��Ԃ����т邱�Ƃɑ��Ă̖��͂���܂���ł����B���U�ɂ킽��w�Ԃ��Ƃ𑱂��邽�߂̈�̌`���u��w�@���v�ł����̂ŁA�������g�̃y�[�X�Ői�߂邱�Ƃ��\�ł����B�����Ƃ�����͉Ƒ��̗����������Ă����̂��Ƃ��Ǝv���܂��B �@���Ċ̐S�̘_�����M�́c �@�R�N�ڂ̓��|�[�g�̒�o���Ȃ���H�_�����M�i�߂悢�����Ȃ̂ł����A�Ȃ��Ȃ������������܂���ł����B�S�g�̕s���͂Ȃ��Ȃ������A��蕨�ňړ����邱�Ƃ���ɂł����B�������A�r���ύX�������̃e�[�}�ł͎��Ԕc�����s���ł����̂ŁA�g�̂����˂Ȃ�܂���B���Ɛ��ւ̃C���^�r���[�͉Ă̒Z�����ԂɈ�C�ɐi�߂܂����B�}���ًΖ��̂��ߕ������W�͊���Ă��܂������A����ł���ɓ���Ȃ������A������u�D�F�����v�Ȃǂ͒��ڌ����Ȃ��������ɂ��肢���ē��肵����A�z�z���ꂽ�ł��낤�W�@�ւփ��[�����Ĕq������A�܂��A�����Ȋw�Ȃ֏��J�����������ē��肵����ƁA�悤�₭�H�ɂ͍ޗ������낢�܂����B���ۂɋ�̓I�ȕ��͂����M���n�߂��̂�10���ȍ~�ł����B�����グ���������w�������ɂ����肵�āA�`�F�b�N���Ă��������܂����B�Ƃ肠����12���̃[�~�ɂ����Ă̍ŏI���\��܂łɒ�o�ł���`�Ɏd�グ�邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��܂����B���ǁA�ŏI���\��ł́A�ŏI�͂̌㔼�������Ԃɍ����܂���ł������A�N���ɂ͂Ȃ�Ƃ��`�ɂȂ�A�N�����͒��̓��ꍞ�݂ƁA�뎚�E���̃`�F�b�N�ɔ�₷���Ƃ��ł��܂����B �@���p�E�Q�l�����̐����͈ӊO�Ɏ�Ԏ��܂��B���̏ꍇ�́A100�_�قǂ̂Ȃ��ŎG���_�������������̂ŁA�g���E�g��Ȃ��͊W�Ȃ��A�R�s�[����肵���炷���ɁA�ԍ���t���ē����̑ܕt���̃t�@�C���ɓ���Ă����܂����B�������A�������Ƃ̏����f�[�^���p�\�R���ɓ��͂��Ă����܂��B�}���̏ꍇ�́A���p�E�Q�l�ɂ����y�[�W��K���f�[�^���͂��Ă����܂��B�������邱�ƂōŌ�̒���������Ƃ��ƂĂ��y�ɂȂ�܂����B �@�p�\�R���Ɍ������Ȃ��畷�����x�ڂ��̏���̏��c����Ȃ��Ƃ͂����Ȃ����낤�Ȃ��Ǝv������A���������炠���������c�ƁA�Ō�̒ǂ����݂ɂ��͂�����܂����B���ۂɊ���������̎����ւ̂��J���́A�_���Ƃ͊W�̂Ȃ��{���v�������ǂނ��ƁI�ł����B �@�Ō�ɁA�u�Q�l�ɂȂ�̂ł��傤���c�v�Ƃ����`���̋^��ɖ߂�܂��ƁA�Q�l�ɂȂ���̂Ƃ�������͂�͂�A�������u�S�g�̌��N�̈ێ�����������Ƃˁv�A�Ƃ���������O�̃A�h�o�C�X�ɂȂ�Ǝv���܂��B�Љ�l��w�@�Ƃ��Ȃ�܂��Ɗw�F�����̐g�̏�ɂ��A���낢��Ȃ��Ƃ��A�{���ɂ��낢��Ȃ��Ƃ��N����܂����B���̂悤�ȂȂ��ŁA�������g�̐��_�Ɠ��̂����ǂ���Ԃɕۂ��Â��邱�Ƃ��ƂĂ���Ȃ��Ƃ����݂��݊����Ă��܂��B �@��w�@�ɓ��w���ꂽ���R�͊F����A���낢��Ⴄ�Ǝv���܂����A�C�m�_�����o�������Ƃ��u�I���v�ɂȂ炸�u�n�܂�v�ɂȂ�悤�Ȍo���ɂȂ�܂��悤�Ɋ���Ă��܂��B �@�C���������I�����������ɁA����搶���瑗���Ă����������u�����͎����ł���ˁB�����}�C�y�[�X�������Ȃ��悤�Ɂv�Ƃ������t���A��w�@�����𑱂�����F����ɂ����肽���Ǝv���܂��B
�@ �@�P���͐l�ԒN�ɂ�������24���Ԃ���B�������A���Ԃ̊��o�Ƃ����̂͂��̎��X�ő傫���Ⴄ�Ƃ����̂�����������ꂽ�Q�N�Ԃ̑�w�@�����ł������B �@���ɁA�u���{�v��o���ؓ��O�̏j���P��12���́A���U������N�����A�R���r�j�ő�}�ւ𗊂̂��[��O��30�����������B���̊ԁA�H���ƃg�C���ȊO�͍ŏI�Z�������A���{�ɒǂ��Ă��āA�Ƃ��������Ԃ��ǂ�ǂ�߂��Ă����A�u�Ȃ�Ƃ����Ă���v�Ƃ������_��Ԃ̈���������B���ߐ蒼�O�ɂ����ӂ������̂́A�ǂ���玄�����ł͂Ȃ��āA�����[�~�̂j�����A�r��������l�̂��ƂƁA�ʐڎ���̂Ƃ��ҋ@���Řb�肪����オ�����B �@�ȏオ���{��o�O��̏ł���B�����ȏ����͐��_�q����A�ߑ�ȃX�g���X�͑̂Ɉ�������A��o�O���͗]�T�������Ė]�ނ��Ƃ��d�v�ł���B�������A��������͏\�����ӂ���悤�A���Ȃ�������ł���(�����A�Ⴍ�͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�A�A)�B �@���āA���̘_����A4�Ŗ�120P����B�_���ƍu�`���|�[�g�̌o������A4�A1�����쐬����̂ɂU���Ԓ��x�A���̏ꍇ�͂��������B�������A�����Ă��鎞�Ȃǂ̍l���Ă��鎞�Ԃ͏����B����āA������ςQ���Ԓ��x�A���̈�N�ԁA�_���ɔ�₵�����ƂƂȂ�B �@���̎��Ԃ��ǂ�����P�o�����ł��邪�A���̏ꍇ�͈�錧��̂s�s���瓌���܂Œʋɉ�����R����30�����x������B����āA�Q�l�}����ǂނ��Ƃ⌴�e�A�����Ȃǂ͒ʋΎ��Ԃ�傢�Ɋ��p�����B �@����ɁA�ǂ��v�Z���Ă����ԓI�Ɍ��e�쐬�͂��̂܂܂ł͓���Ɣ��f���A��N�T���̂f�D�v�ɃV���[�v�̃��o�C���R���s���[�^�[(PC-MM1-H3S�G970g�G�����o�b�e���[2H�ғ�)���w�������B�����āA�ʋΓd�Ԃ̒��Ō��e���^�C�s���O������X���������B�������̂́A�s�w�߂��ɂȂ�ƁA���낢��ȃA�C�f�B�A���o�Ă��āA���q������Ă��邱�Ƃł������B���o�C���R���s���[�^�[�͓d�Ԃ̒������ł͂Ȃ��A�ǂ��ł����e���^�C�s���O�ł���̂ő�ϖ𗧂����B �@�Q�l�}���ɂ��Ă͎����ōw������̂���ԗǂ��B�������A�\�Z�Ƃ̊W������A�}���ق𗘗p�����B���Ɏ���t�߂̂e�}���ق͋ߔN�A���������Y��ŁA�w�K�R�[�i�[�����R�ŁA�d���R���Z���g�����ɔ����t�����Ă���A���o�C���p�\�R�����g�p����̂ɂ͑�ϕ֗��ł������B�������_���̃f�[�}�ɊW������̂���r�I�����������B���A��Еt�߂ɂ��`�旧�}���ق̎O�c������20��30���܂ŊJ�ق��Ă��āA���X���p�����B��w�̐}���ق��s�J�X�K�̃O���[�o���r�W�l�X�X�N�[���ɑݏo����������A�{�w�̑S�Ă̐}���ق̑������C���^�[�l�b�g�\��Ŏ���A��ϕ֗��ł���B �@�ȏ�̂悤�ɁA�ʋΎ��ԂƐ}���فA�����ă��o�C���R���s���[�^�[���t�����p���ẮA���̈�N�Ԃ̘_���쐬�ł������B�Ƃ������A���̂Q�N�Ԃ́A���24���Ԃ��ϗL�Ӌ`�ɉ߂������Ƃ��������ł���B
�@ �@���̂��낤�B�ŏ��́A���ꂩ��n�܂����B���퐶���̒��łӂƊ������^��B��������Ă݂�ƁA��͂蓯���悤�Ȃ��Ƃ����Ă���l�������B���̂��낤�B�В[����֘A����Ǝv���鏑�Ђ�ǂ������B�ǂ��ɂ�������Ȃ��B�T�����������Ȃ��̂��낤���A����Ƃ��N�������Ă��Ȃ��̂��낤���B����Ȃ�A�����Ŋm���߂Ă݂悤���ȁB����Ȃ��Ƃ����������ŁA���{��w��w�@�����Љ����Ȃ����邱�Ƃɂ����B �@�������Ďn�܂����C�m�ے������B�ƒ�Ǝd���̗����̏�ɁA����Ɍ�����������������B�����ł������Ԃ��Ȃ����A�S���w�̊�b�I�m�����Ȃ����́A���|�[�g���������߂̕������Ȃ���A�����̌����e�[�}�̂��߂̕��A����ɂ����̓y��ƂȂ�S���w�̕��ƁA���Ԃ������炠���Ă�����Ȃ��B����Ȃ��Ȃ�������~���Ȃ���T�̎��������A�܂Ƃ߂ɓ���Ƃ������̍Ō�̑�l�߂ɗ����Ƃ���ő�ςȂ��ƂɂȂ����B �@�C�_���܂Ƃߎn�߂��P�Q�����{�A�ꂪ���Ɛf�f���ꂷ���ɓ��@�B�ł��邾��������p���K�v�Ƃ̂��ƂŁA�P�Q���Q�T���A�N���X�}�X�̓��Ɏ�p�ƂȂ����B�{���́A�N���E�N�n�̋x�݂̊ԂɁA�W���I�ɏC�_���܂Ƃ߂悤�ƍl���Ă����̂����A����ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ����B �@�����̒��X�F�R�O�Ɏ�p���ɓ�������̎�p�I���́A�ߌ�R�������܂���Ă����B���̊ԁA���Ǝ��͓�l�ŕa�@�̈֎q�ɂ������܂܁A��p�̐������F�����ł������B�ꂪ���Ɛf�f���ꂽ���ƁA��p�I����̌o�߁A�������茨�𗎂Ƃ��S�z�������镃�B�S�z���肪�旧���ŁA�������g�̏C�_�͊Ԃɍ������낤���A�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����A����Ȏv�������������̒������邮�����Ă����B �@��p�I����A�\�z�ȏ�Ɋ����i�s���Ă����Ƃ��������ォ��̐������A����͒�����ɂȂ�ȂƊo������߁A�ǂ�����ďC�_���������߂̎��Ԃ��m�ۂ��邩�l���Ă����B�a�@�ւ͖����ʂ��A��ɂ͏C�_�̂܂Ƃ߁B����܂ł́A�W�����悤�Ƃ���A���Ȃ�W���ł���Ǝv���Ă������A���̂Ƃ�����̓R���s���[�^�Ɍ������Ă��A�Ȃ��Ȃ��l�����܂Ƃ܂�Ȃ��B�����Ƃ������i�߂��Ȃ��܂܁A�C�������肪�ł�A���������߂��Ă����B�a�@�ŕ��ƕ�̊���݂�A�u���낻��A��v�Ƃ͌����Ȃ��Ȃ�A�������ɂ��邾���ł����Ȃ��̂ɁA�a�@�ʼn߂������Ԃ������Ȃ�B�Ƃɖ߂�ƁA�ȒP�ɂ͋C�������ւ���ꂸ�ɁA�����R���s���[�^�𗧂��グ��B �@����ȂƂ��A�[�~�̐^糐搶���͂��߁A���Ԃ�������̉�������܂����������B���܂��܃T�C�o�[�[�~�����薳�f���ȂƂ����킯�ɂ��������A�ȒP�Ɍ��ȗ��R���������B���������ꂾ�������m�点�Ȃ������̂ɁA���l���̒��Ԃ������l�k�ʼn��������t���������Ă��ꂽ�B�݂�Ȏ����g�̌��N���C�����Ȃ���A�u���Ȃ炫���Ƒ��v�v�Ɨ�܂��Ă���Ă����B��̊��ɑ��āA��ÂɑΉ����悤�Ƃ�����Ă������ɂƂ��āA���̒��Ԃ�������̐S�������A�{���ɂ��肪���������B�݂�ȖZ�������A�Ƃ��Ɍ����ɂ�����Ă������Ԃ������A��������������L�ׂČ��C�Â��Ă���Ă���A�{���ɂ������Ԃ����Ɍb�܂ꂽ�ƐS���犴�ӂ����B �@��y��������u�C�_�͑��߂ɗp�ӂ������������v�A���x�������������Ƃ��B���̂���ŁA����Ȃ�̏��������Ă����̂����A�Ō�̒i�K�Ŏv���������Ȃ����ƂɂȂ�A����Ɏ��Ԃ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����������Ԃ��Ƃ�Ă��A���x�͓��������Ȃ��B����ȋ������������Ă݂Ă��A�C�_�Ɍ������������킯�ł��Ȃ��A�Ƃɂ����A���Ƃ��܂Ƃ߂Ȃ���B �@�C�_�́A���ߐ�ɂ͊Ԃɍ����悤�ɒ�o�ł����B�������A�ŏI�I�ɂ܂Ƃ߂悤�ƍēǂ����Ƃ��A��̎�p�O��ɏ����Ă��������͎x���ŗ�ł��邱�ƂɋC�Â����B���̂���ȂƂ���ŁA����ȓ��v��͂������낤�A�����ł͂������������������������낤�A���X�B���ǁA���̏͂͒��ߐ�M���M���ŁA�S�ʓI�ɏ����������ƂɂȂ����B��ÂɂȂ��Ă������ł��A����ς肠��ĂĂ��Ďv�l���܂Ƃ܂�Ȃ������A�Ƃ������ƂɌ�ŋC�Â����B �@����A���Ƃ��C�_���o���鎖���ł����̂́A�{���ɐ搶�⒇�Ԃ����̗�܂��̂������Ǝv���B�܂��Ƒ����A�C�_���������Ԃ��Ƃ��悤�ɁA�S�ʓI�ɋ��͂��Ă��ꂽ���Ƃ����肪���������B�m���ɂ��̂Q�N�ԁA�������邽�߂Ɏ������g���ł������̓w�͂����Ă�����Ă����B�C�_�͎��ɂƂ��āA�Q�N�Ԃ̏W�听�ł���B����ǂ��A�����Ɏ�����l�ł͏����Ȃ��������̂ł�����B �@��܂������A�x�������A���������Ă������̎���̂�������̐l�����̂������ŁA�����܂ł���ꂽ���ƂɐS���犴�ӂ������B
�@ �@���̌����e�[�}�́A�ŏI�I�Ɂu�X�ܖ�ǂɂ����邿�炵�̔�����ʁv�ƂȂ�܂����B�����_����ڂ̒�o��6��30���ŁA���̃e�[�}�Ɍ��߂��̂�5���ɓ����Ă���ł����̂ŁA��Q�����ԁA�{���ɂ��̃e�[�}�ő��v���낤���H�����ł́A�����ƗL���Ȍ��ʂ��ł�̂��낤���H���s������A����ɂ����P�N���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��낤���H�ƕs�������ς��́A�\���������s���]�T�̂Ȃ��A�قƂ�Ljꔭ�����̌����ɂȂ��Ă��܂��܂����B �@����Ƃ����̂��A���w�O�ɖڕW�Ƃ����e�[�}�͐E��̈ٓ��Ō�����f�O��������A�C�m�P�N�ڂ́A�����e�[�}�T����菉�߂ĐG���S���w�Ƃ����w��ɂĂ�����ŁA�܂��N�ɂQ�郌�|�[�g�ۑ�Ɉ���ꓬ���閈���ł����B���l����ƁA���̎��X�Ɏ��Ԃ��S�����������킯�ł͂Ȃ��A���Ԃ̎g������������I�ŁA���g�̗v�̂̈������������������Ă��������̂悤�ȋC�����܂����B �@����Ȃ��ƂŁA���̏C�m�Q�N�ڂ͂ق�Ƃ��Ƀv���b�V���[�Ƃ̐킢�ƁA�����Ď����ΏۂƂȂ��ǂ̐搶�ւ̍��A�R�~���j�P�[�V�����ɒǂ�ꂽ�P�N�ł����B�������ʂ́A���炵�ɂ�锄����ʂ��������Ɩ��m�ɒf���ł���f�[�^�𑵂����Ȃ��������߁A�܂�A���炵�ȊO�̊֗^�ϐ���r���ł��Ȃ��������߂Ɏ��s�ɏI���܂����B���ȓ_�́A�ߋ��̎��ጤ�������낻���ɂȂ������߂ɁA�\���ł������s������ł��Ȃ��������Ƃɂ���Ǝv���܂��B�܂��A�{�����̑O�ɁA���_�̏C���������邽�߂̗\���������K�v�ł���A���̂��߂̒i���⎞�Ԃɗ]�T���Ȃ��������Ƃ���ɂ����s�v���ł����B �@�����A���g�̐E���ɂ�����^�����P��ɂ��Ă̌������s�����߂̎��g�݂��Љ�l��w�@�ɂ����錤����|�ł���Ƃ���A���̍���̎����͕s�����ɏI��������̂́A������ʂ��A�E���̒��ł̐V���Ȕ����ƍ���̉ۑ肪�����Ă������Ƃ͑傫�Ȏ��n�ł������Ǝv���܂��B�����č���̎��s��ƂɁA���͂����Ɣ��W�������ʂ�������悤�������ɂ����肽���Ǝv���Ă��܂��B �@�Ō�ɁA�����y�яC�m�_���A���|�[�g��o�ł́A�����ĉ��x��������߂����܂����B�h���������t�����������܂����搶���ɁA�����ă[�~�̒��ԂɊ��ӂł����ς��ł��B �@�܂��A�V���Ɏ��g�̌����e�[�}�ɒ��킷����B�ɂ��̎��̎��s�Ⴊ�Q�l�ɂȂ�K���ł��B
�u�킪�q�ɕ�����C�m�_���v�@�@
�l�ԉȊw��U�@�@�Љ��@����
�u�Ȃ��A�Ō�ɂQ�O�O�Q�N�P�Q���R���ɐ��������C���C�`�Ɉ����̈ӂ�\����ƂƂ��ɁA�{�e���M���A����U�������o�ĂQ�O�O�R�N�P�Q���Q�T���ɐg������킪�q�P�l(�Ă�Ђ�)�ɂ��̘_�l����������B�v
�@ �@����A����Ƃ̎v���ŏC�m�_�����o�������܂����B�C�m�_�������ɂ�����܂ł̂��̂Q�N�Ԃ́A�l�ɂƂ��Ĕ��Ɍ��������̂ł����B���̒����ĒZ���������̂�̊T�����������������Ǝv���܂��B�����o�߂��݉B�����ɁA�����ɋL���܂��B �y�P�N���z �T�� �@���̃[�~���J����A���̏�Ŏ��̓����̃e�[�}�ł������w���f�B�J���G���W�j�A�̐E���������̌����x�i���Ȃ݂Ɏ��͕��i�A�a�@�Ń����g�Q���Z�t�����Ă��܂��j�ɂ��Ĕ��\����B�[�~�̏���y������u���̌����̈Ӌ`�͂ǂ��ɂ���́H�v�Ƃ�����������A���S�Ƀt���[�Y���Ă��܂��B �U���`�X�� �@�C�m�_���̂��Ƃ͂������̕Ћ��ɂ͂��������̂́A���߂Ẵ��|�[�g��o���T���A�l�ꔪ��̓��X���߂����B���̂��ߏC�m�_���̍�Ƃ͒u������ƂȂ��Ă������A���|�[�g��o�̂��߂̊w�K��i�߂邤���ɁA�S���w�̗l�X�Ȏ��_�ɂ��Ăڂ���Ɨ������͂��߁A�C�m�_���̃e�[�}�ɂ��Ă��V���Ȋϓ_����l�������悤�ɂȂ�B �P�O���`�P�� �@�w�w���t�B�����ɂ�����a�ς̌����Ƃ��ɂ��āx�Ƃ����e�[�}�ɑ傫���ύX�����ӁB�͂肫���Ď��Ȃ�̉����̂��ƁA�\���������s�����A�I�͂���Ȍ��ʂ��o�Ă����Ȃ����s�B�������Ȃ���A��������A�u�������������Ƃ͂悭���邱�Ƃł���A�S�z���Ȃ��ł��������B�v�Ƃ��������t�����������A����Ɍ�����i�߂悤�ƕ��N����B �Q���`�R�� �@�[�~�̐�y�����C�m�_������o���ꂽ���Ƃ��A���ƈ�N�����Ȃ����Ƃɕs��������������B�܂������̊F����̕��������ł܂��Ă������Ƃɏł���o����B �y�Q�N�ځz �S���`�W�� �@�����̎�������w���̂��ƁA����Ȃ�\�������Ə��Ȃ��Ȃ������s�����̘_����ǂݐi�߂钆�ŁA�悤�₭�{�����Ɉڂꂻ���Ȍ��ʂ������B �X���`�P�O���@ �@���ɖ{�������s���B���Ɏ�Ԃ̂������ςȍ�Ƃł��������A���X�Ƀf�[�^���W�܂�ɂ�āA���ʂɊ��҂����܂�A�������s���̂��y�����Ȃ��Ă���B �P�P���`�P�� �@���ʂ��o��������̂ŕ��͂Ɏ�肩����B�����A���ꂪ�\�z�ȏ�Ɏ��Ԃ��������Ă��܂��A���Ԃ�����Ȃ����Ƃɂ���Ȃ�ł��������B���ǁA�������Ȃ��ɒǂ����܂�Ă��܂����A���Ƃ���o�����܂łɏC�m�_�����o����B �@�Ƃ����킯�ŁA���������̂�ł͂���܂������C�m�_�����o���邱�Ƃ��ł��܂����B��o���I�������A���͌������邱�Ƃ̖ʔ��������������Ă��܂��B�m���ɘ_�����������Ƃ͋ꂵ����Ƃł͂���܂������A�����Ɋy�����ʔ�����Ƃł�����܂����B���ɂƂ��Ă͂��̏C�m�_�����܂��Ƀf�r���[�_���B����A����ɕ������Č�����i�߁A�����ł��[�����䂫�N�̖ڂ��猩�Ă��ǂ��_�������������Ǝv���Ă��܂��B���ꂩ��C�m�_�����������F�l�A�Ō�ɂ͌������s�����Ƃ��ʔ����Ɗ�����Ǝv���܂��̂ł�����Ă��������B
�@ �u����J���܂ł���.�v�Ɩʐڎ���̐搶���̌��t��,���̏C�m�_���Ƃ̐킢��,�����_�����C�����邾�����c��,2004�N1��31���i�y�j�ɏI����}���܂�����,���傤�ǂ��̓��̂P�N�O,����,�����w���̎R�c��������K�₵,�C�_�̃e�[�}�ɂ��ĎR�c�搶�Ƒ��k���Ă���܂���.���܂����e�[�}��,�ƒ�p�̔�����p�������Ƃ�,�ǂ̂悤�ɋC�������ω����邩�H�ɂ��Ăł���.�ł�,�����Ō��߂����̂�,�����ȂƂ��날�܂�C���̂�Ȃ��e�[�}�ł���.�܂�,����,�����Ŕ������g���Ă݂�ƋC�������悭�Ȃ�,�������g��Ȃ��l�Ɣ�r���ē��v�I�ɗL�Ӎ����o��͂��Ɨ\�z����,����ȊȒP�ȃe�[�}�ŏC�_�Ƃ��Ă����̂��Ȃ��Ǝv���Ă���܂���.������,���܂����ȏ�,�s���Ɉڂ��Ȃ��Ă͂Ȃ炸,�܂��������̂�,�팱�ҕ�W�ł���.�Œ�ł�20���W�߂˂Ȃ�Ȃ��̂ł���,�����ȒP�ɂ͎w�肵��������,�����ꏊ�ɏW�܂��Ă����l�͏��Ȃ������Ă���܂���.������,�Ō�̐�D�ł���F�l�̓�l�̑�w�����ɗ��݂Ȃ�Ƃ������Ă��炢�܂���.�ł�,���ꂾ���ł��g�[�^���P�P���ȏォ����܂���.���̏ꍇ,�K�����̂悤�ȑ�w�����������̂ŏ�����܂�����,�팱�ҏW�߂Ǝ����ꏊ���ǂ����邩���|�C���g���ȂƎv���܂�.�e�[�}�����߂�܂łɎ��O�ɔ팱�҂��W�܂邱�Ƃ��m�F���ׂ����ȂƂ��v���܂�. �@2��̎������I����,�Ȃ�Ƃ��L�Ӎ����o��,����,�G���W�������Ę_���������n�߂悤�Ƃ����̂�,�����H���̐���9�����ł���. �ł�,�Ȃ��Ȃ��ŏ��̏����o�������܂������Ȃ��I�ŏ��̂P�y�[�W�́C�Y�݂̋ꂵ�݂Ɠ�������ƑO�q�̗F�l���猾���܂�����,���̒ʂ��,�F�X�Ș_���̏����o���̐^�������Ȃ������ƂP�P���߂�������,�Ȃ�Ƃ�1000�������܂���.�ł��ŏ��̏����o�����d�v�Ǝv���܂�.���Ȃ킿,�ǂޑ��ɂ����ɂ���͂������낻����,�I���W�i���e�B�[�����錤�����Ƃ�����ۂ�^���鏑���o���ɂ���K�v������Ǝv���܂�.�����Ė�,�����̘_����ǂ�ł����ׂ��ł�.�C���^�[�l�b�g�ł̐}�������V�X�e���⍑��}���ق̌����V�X�e���𗘗p���Ę_������肵,������������_���𑽂��ǂނׂ��Ǝv���܂�.�ǂނ��Ƃɂ��C�m�����[�܂�͓̂��R�̂���,�����菇,�_���̍\��,������,�����Ȃǂ��g�ɂ��Ǝv���܂�. �@�܂�,���̂P�N,�������ɋ}�����܂蕢�ʃp�g�ɂ��܂�����,�o���r���̐V�����̒���,��i�Ƀf�[�^�[��������`���Ă��������,�팱�҂ւ̎ӗ�����ɂȂ炸,�Г��a�������Ȃ�g������,�q���̉^����ʼn������Ă��Ă����̒��͘_�����炯�ȂǏ��������Ȃ��قǂ̃h���h���������̂�����܂���.�܂�,�R�c�搶��,����1�N�n�Ă���Ă���ꂽ�W��,���[���ł̂��w���ƂȂ�,�����̊W�Ŗ钆�Ƀp�\�R������̃��[�����M���Ŗڂ��o��,�R�����g�����Ă�,�l���Ă��邤���ɖ邪���������Ƃ����x������܂���.�ł�,���͉��������v���o�ł�. �@�ŏ���,�O�q�̔@��,����܂肨�����낭�Ȃ��Ǝv�����e�[�}�ł���,������U��Ԃ��,�������ׂ��������Ƃ�,�����������������ʂ��ł���������Ȃ��ȂǐF�X�Ɖۑ肪������,����,�����Ɛ[���������Ă݂����Ƃ����C�ɂȂ�܂���.�e�[�}�����߂鎞��,�s��ȃe�[�}���l�������ł���,�����ȃe�[�}�ł��ǂ�ǂ�@�艺���Ă����Ƃ������낢���̂ł�. �@��w�Q�l�ȗ�,���\�N�Ԃ�ɑ�A�������Ɍ������Ȃ�,���N�̔N���N�n��, 1���������ɂ�����p�\�R���Ɍ��������Ē��Ɍ�������!?�̖����ł�����,�Ȃ�Ƃ��_���������グ,���͂ق��Ƃ��Ă��܂�.���ꂩ��C�_���n�߂���F�l,���x�����܂������ɂȂ肪���ł���,�I��������Ƃ̏[�����͍ō��ł�!������Ă��������I �@
�@ �@2�N�O��4���A��]�ƕs��������Ȃ����w�@�ɓ��w���܂����B �@5���ɖʐڃ[�~�ɏ��߂ĎQ�����A�����̌����e�[�}�ɂ��Ĕ��\���܂����B�[�~���E��������l�X�Ȏ���A���ӌ������������A�����Ȃ�ɂ͖������Ă��������v������{�I�Ɍ������K�v���������܂����B�ł��A��̓I�ɉ�������悢�̂��킩��܂���ł����B���̌�A���|�[�g�쐬��T�C�o�[�֓lj�ɎQ������̂�����t�ŁA�d���A�ƒ�����邩��ƏC�m�_�����瓦���Ă��܂����B �@1�N�ڂ̔N�������A2���̖ʐڃ[�~�ɎQ���B���̎����ɂȂ��Ă悤�₭���Ƃ����Ȃ���ƍl����悤�ɂȂ�܂����B��y���͂��łɏC�m�_�����o����A1�N�̔��\�����S�ƂȂ�܂����B���́A����̕������\���܂������A�܂��f�[�^���W����ɂ͖����c���Ă��܂����B �@4���ɂȂ��Ă悤�₭�n���B�f�[�^���W�����܂����A�v���悤�Ȍ��ʂ��ł܂���B���ǁA11���܂Ńf�[�^���W���s���܂����B���w���̌v��ł́A���e���ł��������Ă���͂��̎����ł����B�f�[�^�̕��́A�C�m�_���̍쐬�A�ł�͕�����ł����B �@12��23���̃[�~�ɎQ���B�C�m�_����o�����܂Ŏc���Ƃ���3�T�Ԃł��B��������Ĕ��\���܂������A�����ł����ʁA�l�@�ɖ����ł����A�������炽������A�h�o�C�X�����������܂����B�����܂ł́A�܂��܂��������Ƃ��������܂����B �@�N���N�n�̓p�\�R���ƌ������������X�B�_���쐬�Ŏ������ӂ������Ƃ́A�����̖ړI�A���@�A���ʁA�l�@�Ɉ�ѐ������邩�A�Ƃ������Ƃł����B���𖾂炩�ɂ����������̂��H�@�ǂ����{�����̂��H�@�����킩�����̂��H�@�������牽��������̂��H�@���⎩�����Ȃ��當�͂��쐬���Ă����܂����B�Ƃɂ�����������������S�ł����B �@����Ȏ����A�ʐڎ�����I���A���{���o�������A�ق��ƈꑧ���Ă��܂��B �@���ꂩ��C�m�_���Ɏ��g�ފF����A��w�@��2�N�Ԃ́A�{���ɂ����Ƃ����Ԃɉ߂��čs���܂��B���ꂼ��̎������Ǝv���܂��̂ŁA�����ɍ������v��𗧂āA���̂悤�ɏł邱�ƂȂ������ł���_������������邱�Ƃ����F�肵�Ă��܂��B �@�Ō�ɁA�ʐM���̑�w�@�Ƃ������ƂŁA�ǓƂȃC���[�W������ē��w���܂������A���ۂ͑S������Ă��܂����B�^糋����A�[�~�̊F����ɗ�܂���A�������A�o�ȗ��͈��������ł����A�[�~���y���݂ł�����܂����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�܂��A���ꂩ�����낵�����肢���܂��B
�@ �@���̂Q���A���Ȃ�ɂȂ�Ƃ��C�_���܂Ƃ߁A���n�Ȃ������o���邱�Ƃ��ł��܂����B�����������̂Q�N�Ԃ�U��Ԃ��Ă݂�ƁA�e�[�}�̏o�߂�A�_���\���̑g�ݒ����A���ߐ蒼�O�̒����̊J�n�ȂǁA�܂������]�Ȑ܂̘A���ł����B���������������̂��Ƃ��ӂ�ӂ�ƕY�����Q�N�Ԃƌ����邩���m��܂���B�w�������̖k��搶�̂��w����������A�ƂĂ���o�͂ł��Ȃ��������ƂƎv���܂��B���̏C�m�_������L�͂��̂悤�ȈӖ��ŁA���̔��ȋL�Ƃ��ēǂ�Œ�����K���ł��B �u�e�[�}�̏o�߂�v �@�ŏ��̈�N�Ԃ͗��C���Ȃ̃��|�[�g��o�ɒǂ��A�C�_�ɂ͂قƂ�ǎ�����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B12���̃[�~�ŁA�k��搶���_���e�[�}�������ƍi��悤�Ɏw������܂����B�����̃e�[�}�́A�����̕���ɂ܂����邽�߂ɘ_�_���͂����肵�Ȃ����̂ł����B���������̎��A�����̍\�z�̊Â��Ȃ���]��A�v���]���č��{�I�ɑ��̃e�[�}�ɕς��悤�ƍl���Ă��܂��܂����B���̌��ʍl�����e�[�}�́A���̑�w�@�Ŋw��ł�����e���痣�ꂽ���̂ŁA����ɏœ_�̂ڂ₯�����̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B���̃[�~�Ő搶���A�u�e�[�}��ς���̂͂��܂�Ȃ����A���܂ł̊w�K�����������ǂ��v�Ǝw������A�[�~���Ԃ���̏���������A���ǂ܂����̑�ڂɖ߂�A���̘_�_������ɍi��悤�ɓw�߂܂����B �u�_���\���̑g�ݒ����v �@�Q�N�����n�܂������A�悤�₭��ڂ����܂�܂����B�������������e�Ɏ��|����ƂȂ�ƁA��{�I�Ș_���\���̗������s�\���ŁA���x���ڎ��̑g�ݒ������K�v�ł����B1�N������A�_���ɕs���ȍ��ڂɂ��Đ搶���[�~���Ƃɂ��w�����Ă��܂������A����K���A�J��Ԃ��S�̂̍\����g�ݒ����܂����B���ǂ��̍�Ƃ͒�o�ԍۂ܂ő����܂����B�����炽�߂Ĉ����̃[�~�̑����Ɋ����܂��B���̎��_�ł́A�܂�����ƑS�̂̍\���������Ă����i�K�ŁA���e�̎��M�͎�t�����̏�Ԃł����B �u���߂Ă̍���}���فv �@�Q�N���̂T���A����ł̓_�����Ǝv���A��s�����̒����ɍ�������}���قɍs���܂����B�p�������Ȃ��珉�߂Ă̍���}���قł����B�Ȃ�ׂ������R�s�[�����悤�ƈӋC����ŗ��ق��܂������A�P���̉{�������ƃR�s�[�����ɐ�����̂�m�炸�ɁA���lj��x�������^�ԉH�ڂɂȂ�܂����B�����ɋx�݂�����āA������A����}���قŔ�₷�������x������܂������A���v�����̍�Ƃ��玄�̏C�_�̍쐬���n�܂����悤�Ȃ��̂ł��B�W���܂ł͂��̃R�s�[��ǂޖ����������܂����B �u���ʼn҂��v �@�k��搶�̂��̂����t�͎��̍��E�̖��ł��B���͑�w�����قɊւ��錤�����s�����̂ł����A�ŏI��o�܂ł��Ɣ��N�Ɣ������Q�N���̂W���̍��h�ŁA�����̑Ώۂ����Ȃ����邱�Ƃ��w�E����܂����B�u�_���͓����g�����A���ʼn҂����̂ǂ��炩�v����ł���Ȃ�A���͑��ʼn҂������Ȃ��ȂƎv���܂����B���ꂩ��͋x�����ƂɁA�s���̑�w�����ق�K��A�������n�߂܂����B�����Ƃ����Ă������ٌ��w�ł�����A�y�����ЂƎ��ł�����܂����B���ɂ͐E���̍D�ӂɂ��G��܂����B�����C�m��w�̎����قł́A�x�ْ��ɂ�������炸���J�Ȉē����A���߂Ď��ۂɍs�����Ȃ���Ύ��Ȃ��o��������Ǝ������܂����B������w�⑁��c��w�A������w�̃L�����p�X�ɓ���̂����߂ĂŁA�Z�n���̊w��������̂��y���݂ł����B �u�Ōオ��ρv �@10���̏C�_���Ԕ��\�ł́A�v�|���܂Ƃ߂�����̌����A�����̕��̖͗͂�����Ɋ��������܂����B���̒��Ԕ��\�Ő搶�����璸�����A�h�o�C�X�����ɁA�_���ɂ������̒lj����ڂ�ݒ肵�A����Ƃł����Ǝv�����̂��V�N�J���̍��ł��B���������ꂩ�炪��ςł����B�ǂݒ����Β����قǁA�뎚�E���A�Ӗ��s���̌�����������A���x�������������K�v�ł����B�����Ă��鎞�͗ǂ��Ǝv���Ă��A�����ǂނƒp���������Ȃ�悤�ȕ��͂������Ƃ������Ƃ��p�ɂł����B��͂葁�������ɕ��͂������I���A�������Ɛ��Ȃ��鎞�Ԃ��m�ۂ��ׂ��Ȃ̂��Ǝ������܂����B �@���̂悤�Ȍo�߂ł��A���Ƃ��C�_���o�ł����̂́A�Ȃɂ����搶�̂��w���̂������ł��B�搶�ɂ͊��ӂ�����܂���B�܂��K�ȃA�h�o�C�X�����Ă��ꂽ�[�~�̒��Ԃւ̊��ӂ��Y����܂���B���v���A��ςł������A�L�Ӌ`�Ŋy�����A�l���ʼn��x�����키���Ƃ̂ł��Ȃ��M�d�Ȏ��Ԃ��߂������Ǝv���܂��B |
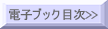
|
 |