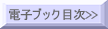「全ては学位授与式のために」
国際情報専攻 田中 肇
書き終わったのは郵送締め切りも迫る、1月中旬の市ヶ谷集合ゼミのあった朝。「プリンターよ壊れてくれるな!」と願いつつ印刷し、それとばかりに家を出て、電車に飛び乗り一路市ヶ谷へと向かったのでした。そして階戸教授に提出しホッとしてゼミの最中眠りそうになること暫し。人生最長の不眠記録(48時間)でゼミ後の楽しい飲み会、酒もうまい筈もなく、早々と切り上げ家に帰ったと記憶しています。
元々切羽詰まらないとエンジンがかからない気質故、レポートでも先生方々にご迷惑を掛け、修士論文ももうだめかと思う事数回。机に座っては何時間もキーボードを打つことができず、「ああ、今日も書けなかった」と寝床に入る毎日でした。そんな私でも修了することができたこと、一重に階戸先生の温かいお力添えと、ゼミの仲間の励ましによるものだと感謝しております。今まで払った授業料も!さすがに無駄にはできません。階戸先生はじめとするゼミの仲間の励ましがガソリンなら、この授業料!!!への執着がロケット燃料だったかもしれません。何とかぎりぎりセーフで滑り込んだのでした。
思い起こせば楽しくもあり苦しくもあった2年間でしたが、何といっても最後の最後の論文執筆がやはり一番苦しい時期でした。初年度上期下期合わせて20本のレポートも論文執筆に比べるとウォーミングアップだったなぁと感じる次第です。ただ今になって思えば、ただのウォーミングアップで終わっちゃった感があり、レポートも論文執筆の一環として、論文を見据えた履修科目の選択や論文の一部となり得るレポートの執筆を行えばよかったなどと悔やんでもいます。また、大好きな小説を読むことができなかったのもつらかったですね。本屋へ行っても買う事が出来ない!そもそも課題図書や論文用の本も読み終わってなかったし。おかげさまで今は読書三昧です。
思いだします。
課題図書、参考図書を読んでいた電車の中
所沢でのスクーリング
夏合宿@軽井沢
市ヶ谷集合ゼミ
緊張した初めてのサイバーゼミ
一文字も書けずに唸っていた自室の机
論文執筆の気分転換に毎晩のように行ったサイゼリアのあの席
眼を皿のようにして読んだWAL-MARTのアニュアルレポート
全ては学位授与式のためにあったんだという事が後になって分かりました。学位を頂いた時、涙が出るほどうれしかったです。やっと終わった修士課程ですが、なんとなくやり足りない感じがしてしまい、今年は科目履修生で大学院に残していただくこととなりました。また、この過程を通じ、自分の興味の新たな部分に気付き、別な資格にもチャレンジです。修士は終了致しましたが、またまた学習の開始です。このような気持ちにさせてくれた学校と先生方に感謝!

「学位記伝達式を終えて」
国際情報専攻 樋口 壽男
桜の花が満開の今、あらためて2年前の開講式のことを思い出します。希望と不安を感じながら、これからご指導いただく諸先生方の講義概要を緊張して聞いておりました。特に通信制大学院であるため、孤独な学習、研究生活になりはしないかと、とても不安に思いましたが、指導教授である階戸先生の励ましの言葉に助けられ、お蔭様で2年後には、なんとか、自分でも納得のいく修士論文を完成することができ、学位を取得することができました。振り返れば、大変な日々ではありましたが、短くも感じる思い出深い2年間となりました。
入学後は、パソコンを使ったサイバーゼミのほか、軽井沢合宿、所沢でのスクーリングなど、想像していた以上に、指導教授となる先生、そして、同期生や先輩と直接、顔を合わせる機会も多く、定期的な集合ゼミや懇親会を通して、互いに、情報交換など、親しく交流を重ねることができました。一方、学業が始まると「仕事」と「研究」を両立させながら、目前のいくつもの山を越えなければなりませんでした。正直言って、かなり辛い道程になりました。リポート作成は、自分で選択した科目に対して、担当の先生から与えられた課題について学習するものでした。1年次には、5科目に対して20本、2年次には、ミニマム4本のリポートと修士論文を書き上げなければなりません。忙しい仕事を抱えている方には、かなりハードな課題となることは間違いありません。リポートを書き上げるには、仕事をこなしながら、基本教材をはじめ、参考図書、文献など多くの書籍を読まなければなりませでした。主に、図書館を利用して、関連図書を、早め、早めに、探しましたが、すぐに、揃うものばかりではありません。必要なものは、書店やインターネットで買い求め、手元に置き学習をはじめました。そして、日々読書を続けることで、分かっているように思えた事柄でも「なるほどなあ」「そういうことだったのか」と、新たに感じ入ることも多々あり、辛いながらも、密かに楽しく思えたことも、度々ありました。しかし、いざ、書き始めると、筆が進まず、気が付くと、夜が白々と明けてきたこともしばしばありました。課題リポートを完成させるためには、担当の先生との間で何度となく、やり取りを重ね、できる限り納得のいく、内容に厚みのあるリポートに仕上げることが大切だと思います。修士論文は、実質、2年目から取り掛かることになりましたが、当初、決めていた「研究テーマ」があまりにも、幅広になりすぎていたために、整理がつかず、悩んでいたところ、先輩からのアドバイスが「ヒント」になり、その後、明確な問題に絞り込んで、研究することで論文を書き上げることができました。後輩の皆様も、壁にぶつかり悩むことになるかも知れませんが、階戸先生をはじめ、諸先生方、先輩の「ひとこと」が、問題解決の糸口になります。そのためにも、サイバーゼミはもとより、市ヶ谷集合ゼミ、夏季・冬季スクーリング、特に、軽井沢合宿を通して、さらなる交流を深めてください。日々の仕事に追われながらも参加意識を高めることで、さらに充実した2年間を過ごすことができると思います。
今、修士論文奮戦記を書きながら2年間にわたりお世話になりました指導教授の階戸先生をはじめ、教職員の皆様、そして個性あふれるゼミ仲間の皆様を思い浮かべ、感謝の気持ちでいっぱいです。誠にありがとうございました。

「―悪魔の誘惑疑似体験―」
文化情報専攻 櫻井 直美
私はC・S・ルイスの『悪魔の手紙』を修士論文の題材にした。『悪魔の手紙』(The Screwtape Letters,1942)は1941年にイギリスの宗教新聞に連載された31通の書簡であり、翌年一冊の本にまとめられて出版された作品である。構成はスクルーテイプ(地獄の高官である老獪な悪魔)からワームウッド(スクルーテイプの甥で一人の青年を誘惑するために地上に遣わされた若い悪魔)への31通の手紙よりなっている。手紙はすべてスクルーテイプからワームウッドへ一方通行であるが、その手紙によりワームウッドや被誘惑者である青年の行動や魂の変化が語られる。何度も悪魔の手中に落ちかける被誘惑者の青年は、最後に死を迎えた瞬間、悪魔が〈敵〉と呼ぶ神のもとへ向かう。悪魔の視点による手紙なので善と悪の倒置が起こっている。
その作品を修士課程在学中のほぼ二年間研究するうちに、非常に巧妙な悪魔の人間に対する誘惑方法を熟知するに至った。これは悪徳商法の手口を調べるうちに、巧妙な商法を見破ることができるようになったというようなものかもしれない。
私は論文執筆を進める過程でいくつものスクルーテイプの誘惑手口を疑似体験することとなった。たとえば、キリスト教の理解を深める為に、ある教会の主宰する「聖書勉強会」に参加したときのことである。勉強会の最後に祈りの時間が設けられていた。その祈りの内容を注意深く聞いていると、ふと胸が熱くなり神のイメージが心に沁みこんで来る瞬間を何度も体験した。祈りが終わり教会を後にして、外の空気にふれたとたんに現実的な思考となり、夕食の準備や雑用のことで頭が一杯になる。そして、祈りの後に感じた胸の熱さが払拭されるのであった。このことは、まさしく『悪魔の手紙』の第一信でスクルーテイプが助言している誘惑方法なのである。スクルーテイプが担当していた被誘惑者が、読書中に神の側へ思考作用が向かったとき、「そろそろ昼食の時間だ」と提案して危機を切り抜けた。「実生活という一服の清涼剤」の効果はてきめんで神の存在を深く考えることから簡単に遠ざかってしまうという誘惑方である。
また、日曜日の過ごし方をめぐり「疲れているが家族の為にどこかへ出かけよう」と私は考える。「無私の精神」からせっかく出かけたのに家族がつまらなそうな顔をしているとがっかりする。一方、家族もそれほど出かけたいわけではなかったが、私が提案したのでそうしたと考える。このことは第二十六信でスクルーテイプが「えせ譲り合いゲーム」と称し、人間に憎悪を生じさせる手法としてワームウッドに薦めている。皆の為に「お茶の時間を庭で過ごそう」というような些細な提案から、「あなたさえよければ」、「君がそうしたいというのなら」という会話になり、双方とも激昂する。安っぽい自意識過剰な「無私の精神」の萌芽が「えせ譲り合いゲーム」としていたるところで展開され憎悪を引き起こすというものだ。
日常生活の様々な場面で「あっ、悪魔の誘惑に陥りそうになっている!」と思うことが少なからずあるのだ。このことは修士論文執筆を通しての大きな収穫であったかもしれない。
いや、もしかしたらこのように「悪魔の誘惑方法を熟知した」と勘違いさせる私の傲慢さが悪魔にとってなにより都合のよいものである可能性もある。いまごろスクルーテイプは私が悪魔の手中に陥るのは時間の問題であるとほくそ笑んでいるかも知れない・・・・・

「Change!!!」
文化情報専攻 刀祢 智恵子
大学院に入学したきっかけは、およそ二年前のこと。何か、自分の遣り残したことがあるような気分にとらわれ、同時に10年に及ぶアメリカ生活でたまらなく日本が恋しくなった時期でもあり、たまたまインターネットで通信制の大学院があることを知り、あわてて願書を送った。すったもんだの末、やはりかなりのカルチャーショックを経験し、やっと入学。
英語が90%以上の生活から日本語のテクストブックを読まねばならない過酷な状況に突入! 文章を目で追っても意味がついてこず、かなりの苦戦。T先生にはテクストブックのチェンジを願い出るも空しく却下。不安を胸に抱きつつ課題に取り組む日々。そんな課題消化不良状態と同時に一年生の段階から修士論文の準備にとりかかる。入学時、論文に書きたいことがはっきりしていたはずなのに、迷う迷う。あれも、これも、またあれもこれも。結局は元の木阿弥に落ち着くも、書き始めると気になること、書きたいことが増える増える・・・。よって内容は支離滅裂。かつてprocrastinationをしたことはありませんでした。これは自慢です。ところがどっこい。論文締め切り期日を前に年末から年始にかけて担当のM先生には多大な迷惑と、睡眠不足を強い、自分のことは棚に上げ、添削の催促をする始末。あああ、あの長い夏休みはいったいなんだったのだろうか、と反省するも時すでにおそし。涙。しかしこんな私でも、何とか、ようやく、論文を仕上げることが出来ました。つまり、こんな私でも、“Efforts will always pay off.” と言って良いのでしょうか。もしくは書き上げたこと自体が “Once in a Blue Moon.” なのでしょうか。
アメリカ大統領Obama氏のキャンペーン・スローガンは図らずも “Change!”、 “Yes, We Can!” でした。この気持ちが修士論文への取り組みにも大切と学びました。私も含め、社会人にとって学びのモチベーションは様々、またゴールも同じく様々。それこそがこの大学院の醍醐味。しかし、諸先輩が述べられているように、計画性はやはり大事です。どうぞ、これから論文に取り掛かられる皆さん、“There is no royal road to learning.”という言葉を胸に日夜邁進されますように。そうです、“Yes, You Can!”です。

“The Question Is the Story Itself.”「問題は物語それ自体」
文化情報専攻 宮澤 由江
“The Question Is the Story Itself.” 「問題は物語それ自体」―これは私が修士論文で取り上げたポール・オースターの『ニューヨーク三部作』からの引用です。オースターはこれを言葉と現実の物事の関係を表わすために使っていますが、この言葉は私の論文後記にも相応しいように思います。なぜなら今、論文に関わっていた時期を振り返ってみると、私にとっての論文の執筆とは結論を論じること以上に、その過程に某かの意味があったと感じられるからです。
修士論文のテーマとして文学と絵画を同じ系譜として扱ってみようと考えた時、実は学術的な根拠は何もありませんでした。それは私の「第六感」だけで決定したと言えます。取り上げようとした小説と絵画に違う角度から刺激された私は、双方を同時に考えるといっそう明快に理解できるのではと思ったのです。
このように書くと、スムーズにリサーチや執筆がスタートしたように見えますが、実際はとんでもありません。そもそものスタートが「勘」なのですから、足元のぬかるんだ泥道に幅木を渡してその上を歩いているようなものです。さらには、私がその「勘」を動員したのは2年次になる直前ですから、アイドリング運転の長すぎるゼミ生で、担当の松岡先生にはずいぶんご心配をおかけしたと思います。
とにかく自分の第六感を確信に変えるため、また執筆に梃子を入れるために是が非でもその絵を見なければと、ニューヨークに赴きました。おりしも、松岡先生が研究のため3ヶ月間のニューヨーク滞在中だったのはとてもラッキーでした。美術館通いはもちろんのこと、様々なニューヨーク事情をご一緒に体験させていただき、苦しかった論文執筆中での一番楽しい思い出です。
しかし現地では「本物を見たらきっと書くべきことがすっきり見える」と思っていたのは実に単純すぎる考えだったことに気付かされました。当の絵画を目の前にすると、そこには「自分の考えを確固とする」には不可能なほど、多くの思考があふれていたのですから。帰国後、膨大な量の断片的なメモが部屋中、PC中に溢れている状態になってしまいました。文章の散漫さを何度も指摘され、引き締めてゆく作業は私にとって本当にたいへんでした。書いて、消して、入れ替えて、また書いては消す… 秋口には原稿は混乱の度を増し、中間発表のための資料や発表原稿を用意する作業の中で、やっと自分の書いているものの向かう先が見えてきたような次第でした。
時間内にベストは尽くしたつもりですが、正本を提出した今でも、まだ手を入れたい衝動に駆られます。しかしそう思う度に感じるのは、この論文はある時点での私の思考であり、私の思考はあれからまた少しずつ先に進んでいるのだということです。
この原稿は書き上げた修士論文が保存されているPCで書いています。私の書いた論文はこの小さなハードディスク上に存在しており、またそのコピーが大学院に1部あります。でもこの論文の真の意味とは、その書かれたものだけではなく、私がそれを書くために得た知識であり、引き伸ばされた感性であり、また深められた探究心にあると思います。

「私にもできた!」
人間科学専攻 石川 由美
人に勧められ、行動分析学が学べるというので先のことは何も考えず,眞邉ゼミに飛び込んだ2年前。毎月ある面接ゼミに加えてサイバーゼミもあり,そんなに発表することがあるのかと不安でならなかった。
あれから早2年が経ち,私でもリポート提出をこなし,どうにか修士論文も書き上げることができたのは,大して発表できなくても面接ゼミに出席していたからだと思う。
「発表しなくてはならない!」この思いが,研究を進める原動力であったのだ。仕事中に高速をとばし文献がある図書館へ行ったり,朝でも夜でも実験協力者の都合に合わせて出かけて行ったり・・・。普段の私だったらあり得ない行動である。
さらに,リポート提出期限が迫ってきたりデータの集計で時間が必要な時に限って,子どもが体調を崩し病院に連れて行かなければならなくなったり,猫の手も借りたいくらい仕事が忙しい時期なのに社員が辞めたため,面接したり仕事を教えるという余計な仕事が増える。それでなくたって,仕事と家事と学生の3本立ては私にとって大変であったに,これ以上時間をどうとるの?何も考えずに入学したのが間違いだったのかとマイナーモードになってくる。
「何でこうなるの?ぜんぜん計画通りいかないじゃない!」
そう。人生は計画通りにはいかない。でもどんな状況でも人生にイエスということができるって言っていた人がいたな。フランクルだっけ。「そうだ。この状況は,私に乗り越えることができる状況であるのだ。」と自分自身に言い聞かせた。
明日の事は心配せず今日なすべき事をすればいいのだ。もともと,大してできる人間ではないのだから,その日にやるべき事を忠実にやればいいのだ。もし,まったく手付かずの日があったとしても,計画通り進まなくても,提出期限迄にリポートも論文も提出すればいい。それだったら,私にもきっとできる。
そう考えると,楽になってきた。
そうこうしているうちに2年経って,「私にもきっとできる」が「私にもできた!」にかわっていったのだった。

「魚はやっぱり天然物!」
人間科学専攻 櫻井 庄二
2年前、通信制という未知の学習スタイルに不安を感じながら、新たなる学問の世界への期待と冒険心を抱いてこの大学院の門を開きました。今まで多分野にまたがって勉学し、その暁には資格を得るという、今で言う所の好子を糧に努力してきました。しかし、その学習スタイルは、一般的なもので、そこでは専門分野における教師・指導者による学問への導き(授業)があり、その流れの中に乗って現在まで来ました。それが当たり前に思い、学習することも出来ていました。今回この通信制の大学院にて一番感じたことは、この学習方法の違いでした。今までの私は与えられて学習をしてきましたが、ここでは自分から学習する、即ち、自ら勉強する時間を生活の中から作り出し、自ら知識を探し求め、理解し、解らない事や間違った知識も自ら解決して正しい知識を吸収してゆくと言う事でした。これを魚に例えてみると、養殖物と天然物でしょうか。養殖は外敵から保護されて、餌を不自由なく与えられてぶくぶく育ちます。一方天然物は外敵から身を守りながら、自ら行動して餌を探し、獲得してゆかなければなりません。待っていては餌にいっこうにありつけなく、必要なものを必要な分だけ摂取するため身は引き締まっています。私の好きな、釣りの世界でも、やはり釣堀の魚や、養殖魚の放流物を釣るよりも、天然物、いわゆるネイティブを釣りあげた時のほうが、釣り師の冥利に尽きません。なぜなら、ネイティブは警戒心が強いため偽物(餌)を直ぐに見極めてしまい、なかなか釣れません。運良く針がかりしても、力と体力で最後まで抵抗し、すんなりと釣りあげさせてくれません。だから面白いのです。魚で言う養殖が今までの学習スタイルであり、後者の天然物がこの通信制の大学院であると私は思います。当然、私は今まで養殖されてきました。時々網から抜け出しては天然
もどきをしてきましたが、やはり気が付くと網の中に戻り、のんびり餌を待っているタイプでした(自分では天然ぶっている)。それが、はっきりと思い知らされたこの2年間でした。とにかく、行動しければ餌(知識)を得ることが出来ないのです。しかし、分かっていても出来るとは限りません。天然物で言う外敵にあたる、仕事、家庭、疲労、お酒などの誘惑に打ち勝ち、更には初めて耳にする用語や内容を理解していくのは、こんなにも大変であるとは思いもよりませんでした。正直言って、ゼミ仲間や先輩の支えや、決して見放さない指導教授の言葉無しには終了にまで行き着くことは出来なかったと痛感します。
この大学院の眞邉ゼミを選び、ゼミを通してすばらしい人々に巡り会えたことは、私の人生の幾つもの選択の中において、最高の選択をしたと自負しています。
以前は早く終わらないかと待ち望んだこの2年間も、今になってみると寂しさを覚え、この環境と繋がりを切りたくないという思いに寄せられます。そんな思いをするのは久しぶりのことです。皆さん本当にありがとうございました。

「2年間の物語」
人間科学専攻 藤原 誉久
修士論文の提出を終え、憑き物がおちたような感覚を味わった私は、研究と全くかけ離れた、長編の小説が無性に読みたくなり、塩野七生さんの「ローマ人の物語」をよみ始めました。ローマ人は他の民族に比べ体格では劣り、戦いにおいて優れた民族ではなかったのに、なぜ千年も繁栄を築くができたのか。読み進めると、何かを成し遂げるときの普遍的なあり方がローマ人を通して描いているように思いました。
私の2年間は微々たる時間でローマ人の千年とは比べようがないかもしれません。
仕事を研究の素材としてとりかかったものの、どこから手をつけていいか分からず、暗中模索するばかりでした。しかし、暗中模索の中で泥沼に入り込まなかったのは、行動分析という道しるべがあって、またそこを出発点にできたからということです。すべての道はローマに通ず、私の場合はこの2年で、仕事や研究について、拙いながら行動分析に立ち返って説明する作業をしたような気がします。今後立ち返る道もできました。
ローマがアテネの民主政ではなく独自の共和制を築けたのは、保守性を大事にしつつ、ローマ人に合った政治体制をコツコツ積み重ねていった結果でした。翻って研究も、保守性を持ちつつ、色々な手法の中から自分の研究にあったものを取り込んでいって、堅実に進むことが大事だと分かりました。
大学院に入学するまでは自分の分野しか知らず、職種によって考え方は違うものだと思っていました。しかし面接ゼミで、様々な職種のゼミ生でも同じようなところに悩んでいることを知り、行動分析の言葉を使ってお互いの問題を考えていくことで、自分の考えをまとめていく作業になったように思います。
この2年間は長い物語の序章を書き終えたくらいですが、これから自分なりに目指していくところの物語を紡いでいけたらと思います。

「自分のやりたいことやってみました。。。」
人間科学専攻 三浦 ひとみ
およそ20数年前、病院で新人検査技師をしていた私は、血液細胞を顕微鏡で覗きながら「異常細胞を見逃したらどうしよう」と思いながら、何回も細胞をみ返したり迷ったりしていました。そのとき、ものすごいスピードで細胞をカウントしている先輩に「そんなに早く見て、異常細胞を見逃しませんか?」と聞いたことがありました。先輩は「大丈夫、異常細胞があれば向こうからこっちの目に飛び込んでくるから」と笑っていました。それから約1年も経つと、先輩と同じように確かに異常細胞があれば私の目に飛び込んできました。さらに、標本を一目見たときに「あっ異常細胞が出ているかも」となぜかわかるようになりました。その感覚が忘れられず、「熟練者とは、口で説明できない力を持っているんだなあ」と思いつづけていました。
それから、細胞を見る仕事からはなれたとき、血液細胞を見ていた自分を思い起こし、「やはり熟練者は必要であろう。理屈ではなく、細胞を見る目や、波形を見る目、画像を見る目はおそらく熟練の域があるのだろう。」と考え、はやく熟練者になる方法はないかと考えていました。
眞邉ゼミは自分のやりたいことを話せ、先生と一緒にみんなが考えていくスタイルで、いろいろな業種の方との交流で、視野が開けました。そこで、やはり気になっていた「熟練者」にこだわってみました。そしてこのゼミで、熟練者は初心者と違うのだと納得することが出来ました。もちろん、この2年は大変でした。子どものことも、職場のことも、父親の他界もなぜ今・・・と言うタイミングで、さまざまのことがあり、大学院をあきらめようと本当に思ったことも何度かありました。しかし、今言えるのは、「やりたいことやってみました。やってよかった」のみです。
眞邉先生、ゼミの皆様本当にありがとうございました。