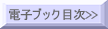�u�����݂̂Ȃ���w�@�v�@�@ ���ۏ���U�@���� ���i
�@���z�ɂ��čl����ƁA�����ł��\�������܂�Ȃ��Ɖ����n�܂�܂���B�C�m�_�������l�ŁA���̊�{�\�������߂邱�Ƃ���Ԃ̔Y�݂̎�ƂȂ�܂��B��x�\�������܂�A���ׂĂ��X�^�[�g�\�ɂȂ���̂́A�����ǂ��āA����I�����ׂ������߂��Ȃ��܂܁A�����k�Ɍ���������Ă����A���̊ԁA�C���ł����Ŋ����ɒǂ�ꂱ�ƂɂȂ�܂��B�����āA�Ō�͓ˊэH���ƂȂ�A�����z�A�����e���Ș_���ƂȂ�̂ł��B
�@�ܘ_�A�����Ȃ�Ȃ��悤�w�͂��邱�Ƃ��A�ǎ��Ȍ��z�����̂Ɠ����ŁA�_���ɂ��K�v�ł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B
�@�܂��A���ނ���W�߂Ă�������Ă�Z�p���Ȃ��ƁA�����z�Ɋׂ邱�ƂƓ����悤�ɘ_�����������肪�R�ς��āA�{�����g�ݗ��Ă��Ȃ��Ƃ����ɂȂ肪���ł��B
�@�����āA���̎��͓ˊэH���Ȃ�ʁA�������肬��̘_����o�Ƃ�������ꓬ�̖����ł����B
�@�������A��w�@�����͋ꂵ�����Ƃ���ł͂���܂���ł����B����̋����ƋC���u���Ȃ����ԂƉ߂������S���ւ̃[�~���s�A�ΉA�ƍg�t�̃[�~���h�ł̌�炢�ȂǁA�v���o�͐s���܂���B
�@�܂��A�T�C�o�[�̗��_�������A�ǂ��ł��w�������錤���`�Ԃ��A���̓����{���ʂ��ƃp�\�R���Ƃ̑Θb�Ƃ��������K���Ɉ�ς��Ă���܂����B����́A������肪��������C��������Ƃ͂Ȃ��A�_�̐��Ȃ�ʁA��y���̃T�|�[�g��������̏�����^���Ă���邱�Ƃ��A�Ӗ����Ă��܂����B
�@���v���N�����Ă݂�ƁA���̂悤�Ɏ�����w�@�����𑗂邱�Ƃ��o�����̂́A�����̋��������y�A�����̒��ԕ��̂��A�ł���ƒɊ����Ă���܂��B

�u�_���G�S�C�Y���v�@�@
���ۏ���U�@����@�M�q
�u���{��͓���E�E�E�v
�@���ꂪ�C�m�_���������I�������̗����Ȋ��z�ł���B
�@�������Ȃ���A�����u���{��̓���v�ɋC�t�����̂́A�C�m�_���������グ�A�_���v�|�̉p��ɒ��肵���Ƃ��ł������B�����̏��������{����p��ɂ������āA�Ȃ��Ȃ��s���I�h�ŕ��͂����Ȃ��̂ł���B�������W�㖼���≼��@�I�\�����Ȃ�Ƃ��������ƁE�E�E�B
�@�����炭���͂Ƃ������̂ɂ́A������̃G�S�C�Y�����@���ɔ��f�������̂Ƃ�������B
�@���̏ꍇ�́A���Ǐ����w�O���R�I�v�S�W�x�Ƃ������Ƃ������Ă��A����ł���Ȃ�����I�݂ɐv���ꂽ�A�������k�ł��ė���ؔ��Ȕނ̕��͕\���ɓł���Ă���A���ӎ��̓��ɁA����������I�i�����I�H�j�ȕ\�����D��Ŏg���悤���B
�@�m���ɁA�����镶�͂̃v������������������I�ȕ��͕\���ł���A�����ɑn������a�V�Ȕ��I�\���Ȃǂ����݂�����ł��낤����A�S�n�悭�ǂ߂邩������Ȃ����A���ꂪ�f�l�̕��͂ƂȂ�Ɓu���킸�����ȁv�ł��鎖�́A�����g���悭�悭���m���Ă���E�E�E�B
�@���������������͕\�����D��Ŏg���̂͂��̍ۂق��Ƃ��Ƃ��āA��ʓI�ɏ��X�ɏo����Ă����发��w�p�_���ɂ����Ă��A���̏ꍇ�Ƃ͎�j���A���X�͈Ⴆ�ǂ��A���l�̌X����������̂ł͂Ȃ����B
�@�܂�u�ǂݎ�ɂƂ��ėD�����Ȃ��A���镶�́v�Ƃ������Ƃł���B
�@�����C�m�_�������M����ɂ������āA�����ς��̌����ҋC���ŁA��发��W����w�p�_���Ȃǂ�ǂ����Ă������A�����͂�͂�u���������邩�炱���ǂނ��Ƃ��ł���I�I�v�Ƃ����ނ̂��̂ŁA�u�ǂݎ�ɗD�����A�ǂ�ł��Ĕ��Ȃ��v�Ƃ������̂���͐r���������ꂽ�A�J���ɂ����̂ł������E�E�E�B
�@����������发�Ƃ��w�p�_���Ȃǂ́A�ǂݎ�Ƃ��Đ��Ƃ⌤���҂�ΏۂƂ��Ă��邩��d�����Ȃ��̂�������Ȃ����A����ɂ��Ă��w���ɂ��ɂ��I�I�x�i���P�j�I�Ȋ��o����������̂ł���B
�@�܂�A�������������������Ƃ����ƁA�C�m�_���Ɍ��炸�A���͂������ɂ������Ă̋��P�Ƃ��āA�u�ǂݎ�ɗD�����A���Ȃ����͂������܂��傤�v�Ƃ������Ƃł���B
�@�����A����ʋ��t�Ƃ��l����_���쐬�̃|�C���g�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
�P�D�Z���e���X�͒Z�߂ɍ\�����邱�ƁB
�@�@��̃Z���e���X�ɂ��낢��l�ߍ��݂�����ƁA�����ߑ��Ɋׂ��āA�������ē`���������Ƃ��s���ĂɂȂ�B���̌��ʁA�ǂݎ肪�������ĉ����`���Ȃ��Ȃ�B
�Q�D�u���v��L�����p���邱�ƁB
�@�@�_���Ƃ���������A�ǂ����Ă����p���������s���Ȍ��t���g��Ȃ���Ȃ�Ȃ���ʂɑ������邪�A������{���ɐ��荞�ނƁu�P�D�Z���e���X�͒Z�߂ɍ\�����邱�Ɓv�������ł��Ȃ��B���̏ꍇ�́u���v��L�����p���邱�ƁB
�����́A�㔭�̌����҂ɂƂ��Ă���ϗL�Ӌ`�Ȃ��Ƃł���Ƃ�������B
�E�E�E�Ƃ����̂͌��O�ŁA�����́u�����̘_�����p��ꍇ�Ƀ��N�`���������v�Ƃ������h�ȃG�S�C�Y���Ȃ킯�����B
���P�j
�����ł͊����ĉ��ȕ\�����g���Ă���A�O�̂��߁B
����Ɍ����ƁA���̕��̂�����ɂ��āA��发��w�p�_���Ɂw���ɂ��ɂ��x�I�Ȍ�����\�������p����Ă����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���̓��e�����ɕ��G�ŁA�Ƃ����ɂ��������Ƃ�����ۂ�`���邽�߂Ɏg���Ă���A�������炸�B

�u�����w�` ��V�抮���ł��I�v�@�@
���ۏ���U�@����@�m�V
�@
�@���́A��\���N�O�̑�w���w�ȗ��A�����ɂ́A����甠���w�`�̃e���r���p�����āA��Z�̑I����������Ă��܂��B
�@�������A���N�̐����́A��D���Ȕ����w�`�����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B���܁A�r���o�߂��Ƒ��ɕ����Ȃ���A�C�m�_���̍ŏI�����Ɏ��g��ł�������ł��B
�@�d���Łu�q�ǂ��̍K���v�Ƃ����e�[�}�Ɋi�����Ă���������A���X�ň���̖{���ڂɗ��܂�܂����B��Z�A������Љ���{�ł����B���̊w�����̊w�ȕҐ��͂����Ȃ��Ă���A�Ɠǂݐi�߂Ă���Ƒ�w�@�����Љ����Ȃ̂��Ƃ��L�ڂ���Ă��܂����B��w�@�Ō������Ă݂����A�Ƃڂ���ƍl���Ă������̂������ɕς��]���_�ł����B
�@�[�~�́A���f�B�A�ɂ��Ă��w������������ߓ��唎�����ɂ��肢���A�Q�N�Ԃ̑�w�@�������n�܂邱�ƂɂȂ�܂����B
�@�Q�N�O�̓��{��w�̓��w���͓�\���N�O�Ɠ����A���{�����قł���܂����B
�@�n���A����̍��͔������ł����A���w�������̓����̍��́A�i�ʂ̎����܂����B
�@���́A���{�����قő�w�@�̓��w���B
�@���̒��j���������ɏ��w�Z�̓��w��������܂����B
�@�u�q�ǂ��̍K���v�����̌����e�[�}�̍����ƂȂ镔���ł��B�d���Ǝq��Ă̗�����}��Ȃ���q�ǂ��̍K�����������B����́A�����g�����H��ڎw���e�[�}�ł�����܂��B���j�̓��w���ɏo�Ȃł��Ȃ��������Ƃ��A�d���Ɖƒ�Ƒ�w�@�́u�O���v��S�ɐ����_�@�ƂȂ�܂����B
�@���āA��w�@�ɂ����錤���ɂ��āA�O�̂��ƂɐG�ꂽ���Ǝv���܂��B
�@��߂͗��C�Ȗڂ̃��|�[�g�ł��B��w�@���C�����邽�߂ɂ́A�C�m�_���쐬�̑��ɉȖڂ̗��C���s��Ȃ���Ȃ�܂���B�P�N�ڂ́A��y�̊��߂�����A�T�Ȗڗ��C���܂����B�O���ƌ���A���v20�{���w�肳�ꂽ�����̃��|�[�g�ɂ܂Ƃ߂Ē�o�ł���̂��ƕs���ł����ς��ł����B�������A��y�́u�ŏ��͒�o�ł���̂��s�����������ǁA���ꂾ���̎����Ɩ{���̃��|�[�g�͏����Ă��܂���B�v�Ƃ�����܂��̌��t��M���A�Ђ����烊�|�[�g�쐬�Ɏ��g�݂܂����B
�@�P�N���ł����R�A�C�m�_���̘_���\���̗��Ăƕ��L���������W�ɂ͓w�߂܂������A���ۂ́A���C�Ȗڂ̃��|�[�g�쐬�ɑ唼�̃G�l���M�[���g���Ă����悤�Ɏv���܂��B�������A���C�Ȗڂ̃��|�[�g�쐬�́A����ɒP�ʂ��擾����ړI�����ł͂���܂���B�Q�N���ɂȂ��ďC�m�_�������M���n�߂āA���ꂪ����܂����B����ꂽ���ԂŃe�[�}�ɍ�����������T���A�e�[�}��_�q�ł���u��b�̗́v��g�ɂ���������ʂ��������̂ł��B
�@�܂��A���́A�P�N���ƂQ�N���ŗ��C�����Ȗڂō쐬�������|�[�g�̓��e���C�m�_���ł����p���܂����B���Ȃ킿�A�C�m�_���̓��e�ɊW����Ȗڂ𗚏C���Ă������߁A���|�[�g�ŐG�ꂽ���_�����p���A���������p���邱�Ƃ��ł��܂����B���C�Ȗڂ��C�m�_���Ɏ�荞�ނ��Ƃ��ł������v���傫�����̂�����܂����B
�@��ڂ́u�͗��āv�̏d�v���ł��B���̏ꍇ�́A�P�N���Łu�q�ǂ��ƃ��f�B�A�v�Ƃ̊W�ɂ��ĕ��L���������W�߁A���̌�A�e�[�}�̍i���݂��s���A�͗��Ă����߂��̂͂Q�N���̏t�ł����B
�@�_���������i�߂Ă����ƁA��{�I�ɂ͏͗��Ă��A���̌�̎��M��automatical�ɐi�߂Ă���܂����B���̏ꍇ�͂S�́~�S�߁B���Ȃ킿�A�C�m�_����16�߂ō\�����܂����B�����Ȃ�ł����A�͗��Ă�������̂ɂł��܂����̂ŁA���Ƃ͏͗��Ă������I�ɘ_���������Ă��ꂽ�悤�ȋC�����܂��B�i�ƁA�����܂������A���ۂɂ́A���������~�܂�����A�X�����v�Ɋׂ������Ƃ͉�����܂����B�j
�@�������A�͗��Ă��_���������Ă����Ƃ����̂́A�傰���ȕ\���ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B���̏ꍇ�A�C�m�_���쐬�ɂ������ẮA�͗��Ă̍쐬���U�����̍�ƂƂ������������܂����B
�@�O�ڂ͐}���ق̃��t�@�����X�E�T�[�r�X�ɂ��Ăł��B
�@�C�m�_���������i�߂Ă����H�A�_�|��⋭���镶�����K�v�ƂȂ�܂����B����܂ł́A�_���A�Q�l�}���A�z�[���y�[�W�Ȃǎ��͂ŒT���Ă��܂������A�Y��ł���������A�E��ɋ߂������}���قɍs���āA���t�@�����X�E�T�[�r�X���Ă݂܂����B
�@�u����Ȏ������ق����ł����E�E�E�B�v�ƈ�ʂ�������ĂQ���҂��܂����B
�@�Q����A�}���ق̃J�E���^�[�ɍs���ƁA�����ɂ͕�̎R������܂����B�u���T���̕������ǂ����E�E�E�B�v�Ǝi���̕��B���ǁA���̂قƂ�ǂ̕��������p�܂��͎Q�l�����Ƃ��ė��p���܂����B������v���A�������������i�K�Ń��t�@�����X�E�T�[�r�X���Ă��悩�������ȁA�Ƃ������������܂��B
�@���{��w�́A���N�̔����w�`�ŁA�������D���ƌ������Ă���܂����B
�@�������͂Q�N�O�ɁA���{��w��w�@�����Љ����Ȃɑ�V�����Ƃ��ē��w���܂����B�����w�`�ɗႦ��ƁA�������V�����́A��V���C���ꂽ�Ƃ�����̂�������܂���B�������V�����́A�Q�N�ԂƂ����ڕW�̊��ԓ��ŁA��W��𑖂�F����ɕ�Z�́u�s���N���F�v��n�����Ƃ��ł����Ǝv���܂��B��W��̊F����́A�����Љ����Ȃ̂悫�`�������̑I��ɂȂ��Ă����Ăق����Ǝv���܂��B
�@�����A��V��𑖂�ɂ������ĂQ�N�ԁA���w���⎶�B����������������ߓ������A�������牞�����Ă�����������w�@�̏���y�A�E��A�}���َi���̊F����A�����ĉƑ��̎x���������Ė����A�Q�N�ԂŊ������邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�����ɉ��߂ĊF�l�Ɋ��Ӑ\���グ�܂��B
�@���N�͒g�~�ł����B���̊J�Ԃ������̂ł��傤���B
�@�t�ɂ́A���̂R�����肪���������Ƒ��T�[�r�X�����āA�����g�����t���b�V�����܂��B
�@�����āA�V���ȃe�[�}�Ƀ`�������W���悤�Ǝv���܂��I

�u�C�m�_����3�x�̖�������^���Ă����v�@�@
���ۏ���U�@���ہ@����
�@�C�m�_���̒�o���I���āA�悤�₭�ق��Ƃ��Ă���A�������̍������A�C�m�ے���2�N�Ԃ͐F�X�Ȃ��Ƃ��������B
�ȉ��A���ꂩ��C�_���o�������ɎQ�l�ɂȂ�Ǝv���A�G���������Ă݂�B��w�@�����̗���́A4���ɕ�������̂ŁA�e���̃|�C���g���Q�l�̂��߂Ɏw�E�����Ă����B
�P�D�@1�N�O���i4���`9���j
�@�E���������Ȃ���A���|�[�g�����ƁA�y��h�A�X�N�[�����O�Ȃǒǂ���B�d�������Ȃ���A5���Ȃ̃��|�[�g�����͑z���ȏ�ɁA���Ԃ�������B���̂��߁A�[�~�ł͏C�_�́u�^�C�g���v�Ɓu�˂炢�v�i�`�S��1�����x�j���l������Ηǂ����낤�B
�Q�D�@1�N����i10���`3���j
�@�悤�₭��w�@�����ɂȂ�鎞���ł���B���|�[�g�쐬�́A�O���ł̊w�v�̂����ď����Ă����Ηǂ����낤�B
�@�X�N�[�����O�́A7�����{�ɍs����ċG�X�N�[�����O��11�����{�ɍs����~�G�X�N�[�����O�̂����ꂩ����u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���e�͂قړ����ł���̂ŁA���Ƃ��Ă͉Ă̍Œ������C��̗ǂ��~�G�X�N�[�����O��E�߂����B
�@�C�_�Ɋւ��ẮA�u�e�[�}�v�E�u�_���v�E�u�͗��āv�܂Ői��ł���Ώ\���ł���B�����āA�_����Q�l��������W�́A���߂ɍs���Ă����ׂ��ł���B�g��Ȃ��Ǝv���Ă��A�֘A�������Ȃ��͉̂������Ă����ׂ��ł���B
�R�D�@2�N�O���i4���`9���j
�@�C�_��o�́A1����{�Ȃ̂Ŏc���Ƃ����10�������Ȃ��B�������A�w�������ɐ��Ș_�����o���A�Y��Ȃǂ̂��w��������Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A�l���Ă���ȏ�Ɏ��Ԃ͂Ȃ��B���������āA4������{�i�I�ȏC�_�Ɏ��g�ނׂ��ł���B
�@�C�_�������n�߂�R�c�́A���܂肠�ꂱ��Y�܂��ɁA�Ƃɂ����S�̂Ɋւ��ĕŐ��͏��Ȃ��Ă������グ�Ă݂邱�Ƃł���B�������邱�ƂŁA�s�����Ă�����e��Q�l�����Ȃǂ������ł���̂ł���B
�@2�N���̃��|�[�g��1�ȖڂȂ̂ŁA���߂ɒ�o����ׂ��ł���B���̎��ɁA�O���̉ۑ肾���ł͂Ȃ�����̉ۑ�������Ă������Ɨǂ��Ǝv���B���߂ɏ����ĐQ�����Ă����A����̒�o���Ԃ��n�܂�Ɠ����ɒ�o����A�c��̎��Ԃ͏C�_�ɏW���ł���B
�@9���ȍ~�́A�C�_�����ɏW������Ƃ����X�P�W���[���ɂ��Ă����A�o���ォ��������邪�A�s���̎��Ԃ��N���Ă��Ώ��ł��邩��ł���B
�@�����g�A�E��ł̃X�g���X�����܂�A�Ăɓ��������������B���̌��ʁA�z���|���[�v�̋^��������̂ŁA��p�����������ǂ��Ƃ����b�������ɂȂ����B�d���̓s��������A�H�Ɏ�p���邱�Ƃɂ����B
�S�D�@2�N����i10���`3���j
�@�C�_�������ẮA�C������Ƃ�����Ƃ������B���e�ɂ���ẮA�^�C�g�������ύX���Ȃ���A����ꓬ���������X�ł���B
11����{�Ƀ|���[�v��p���A���̌�A���T�Ԃ͑̒��s���̂��߁A�C�_�̓X�g�b�v��Ԃł������B�C�m�ے��̂Q�N�Ԃ͗\�z�ȏ�ɐF�X�ȏo����������B���߂ɏC�_��i�߂Ă����A���̂悤�ȕs���̎��Ԃ��N���Ă��]��y�[�X������Ȃ��čςނ̂ŁA�C�_�̎��M�ɂ������Ă͑��ߑ��߂ɐi�߂Ă����ׂ��ł���B
�@��p��A�C�_�ւ̃��X�g�X�p�[�g���s���B12���ɓ���A���������C�_���͂��ƂɎw�������ɑ���A�w�����Ȃ���C�_���C�����Ă�����Ƃ��������X�B�����A���̍�Ƃ���ԁA�ꂵ���h���������Ǝv����B
�@�N�����ɉ��Ƃ���o���A�ق��Ƃ���B���̌�́A�ʐڎ���i�w�������ł������卸�̊���F�����A�����̋ߓ��唎�����A�֍���O�v�����̌v3���j���āA�_���ɑ��Č������w�E���邪�A2�N�Ԃ͎����I�ɂ���ŏI��B�����ł̎���́A�v���o�ł����邵�A����̐l���̗ƂɂȂ���̂ł������B3���̐搶���ɂ́A���̏����Č���\���グ��B
�@�C�_�͏����I���Ĉ�x�ڂ̖������������A�ʐڎ�����ē�x�ڂ̖��������������B�O�x�ڂ̖������͊w�ʎ��^���̓��ł��낤���B���{��w����3���ڂ̏؏������炦����́A���������œ�������B
�@�Ō�ɁA���{��w�ɓ��w���Ă��瑁20�N���߂����B��Z�ł�3�x�ڂ̑��Ƃ��}���邪�A����A��Z�̑f���炵���Ɋ������Ă���B

�u�݂Ȃ��܂̂������ł�!!�v�@�@
���ۏ���U�@���@�L�j
�@�C�m�ے��ɓ��w�����̂́A28�ł����B��А����ɑ���s�����Ȃ��A���R�Ǝ��Ԃ������߂��������B�����̎���30��O�ɏ����̑I�������L���邽�߂ɁA��w�@�Ő��m����g�ɂ������Ǝv���A��w�@�I�т̏��w�Z������ȂǐϋɓI�ɎQ�����Ă��܂����B���̑�w�@�I�т̏����́A��А��������Ȃ���w�Ԃ��Ƃł����B�����Q�������w�Z������̂Ƃ��A�{��w�@�ł̓l�b�g��Ń[�~�ɎQ�����Ȃ���������⊈���ȋc�_���ł���Ǝf���܂����B���͓��{��w�����w���N�w�Ȃ𑲋Ƃ��A���w�E���Z�����{��w�̕t���Z�o�g�ł����̂Ŗ��킸��Z���{��w�̑�w�@�ƌ��߂܂����B
�@���̏C�m�_���쐬���Q�l�ɂȂ邩�킩��܂��A�C�m�_�����쐬���邽�߂ɑ�Ȃ��Ƃ́A�@�e�[�}�̑I��A�A�����W�߁A�B���e�\���ł��B�ł��邾�������i�K�ł����̍�Ƃ����Ȃ���Ɨǂ��ł��B
�@�e�[�}�̑I��Ɋւ��āA���搶����L�͈͂ɋy�ԃe�[�}�łȂ��A���e�m�ɍi�荞�ނ悤��w�����܂����B���w�����̑����i�K�Ńe�[�}�����߂�ꂽ���Ƃ��A�w�Z�����̂����Ńv���X�ɂȂ�܂����B
�@�����W�߂Ɋւ��āA����J�}���قɕp�ɂɒʂ��܂����B����A�e�[�}�ɑ������^�C�����[�ȓ��e�𐏎��c�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���A���{�o�ϐV���̕K�v�ӏ�����Ђ̂����x�݂𗘗p���Ȃ��玑�����������܂����B�����T���͐}���فE�V���Ȃǂ����łȂ��A�C���^�[�l�b�g�̊��p�������߂ł��B�C�_�������͂��߂Ă�����������K�v�ƂȂ�܂����A��ɑË������������W�߂邱�Ƃ��̐S�ł��B
�@���e�\���Ɋւ��āA�ߓ��搶���璅��_�����邽�߁A�u�p���[�|�C���g�v���쐬����悤��w�����܂����B�p���[�|�C���g���쐬�������ʁA�C�_���쐬���邤���ŃX�����v�Ɋׂ炸�A�����ɍ쐬�ł��܂����B�܂��A1�N�ڂ̃��|�[�g�쐬�ŋߓ��搶�ɓO��I�ɕ��͂̏�������b����ꂽ���Ƃ����ɖ𗧂��܂����B
�@�C�_���쐬����Ƃ��S�|�������Ƃ́A�u�C���]���v�Ɓu�W���v�ł��B�d�����I���A���Ɗ��Ɍ������C�͂��Ȃ��Ȃ�܂��B����ȂƂ����́A��Ђ̓Ɛg���̎�����U�����܂����B���́A�����������Ԃ���͂��߂�悤�S�|���܂����B�̐S�Ȃ��Ƃ́A�u�����������鎞�Ԃ��Ȃ��v�Ǝv���A�W���͂����߂邱�Ƃł����B
�@�C�m�_���������I���A�F�X�ȈӖ��ŋ]���ɂ������Ƃ�����܂����B�w��P�o�̂��߂ɁA�^�o�R����߁AY�V���c�͎��&�A�C�����|�������܂����B�T���͂قƂ�ǐ}���قɒʂ��A���������ƏC�_�쐬�����܂����B���̗B��̊y���݂ƌ����A�z�e���̋i���X�ł��������邱�Ƃł����B�T���̓V�C�̗ǂ������N��̐l�Ԃ��A�f�[�g���Ă�����i���A�܂����v���܂����B
�@�Y��ĂȂ�Ȃ����Ƃ́A�C�m�_���͂ЂƂ�̗͂Ŋ������Ȃ����Ƃł��B�N���ɂǂ����Ŏx�����Ă���Ƃ������Ƃ������ĖY��Ă͂Ȃ�܂���B���́A�C�m�ۉߒ�2�N�ڂɕ����̈ٓ��ɂȂ�A���_�I�ɗ������݂܂����B��ЂƊw�Z�̃_�u���������ꂵ���Ďd�����������߂�������������܂����B����Ȏ��A�Z���ԂœI�m�ȃA�h�o�C�X�����Ă��ꂽ��Ђ̗F�B�Ɋ��ӂ��Ă���܂��B�F�B���g���d���Őh�����ɂ��A���̑��k�ɏ���Ă��ꂽ���Ƃ��{���ɂ��ꂵ�������ł��B
�@���́A���N���[�g�Ђ��甭�����ꂽ�u�Љ�l&�w���̂��߂̑�w�E��w�@�I�сv�Ƃ����G���̒��Ŗ{��w�@���Љ��Ƃ���������܂����B�����g�A��ނ������ƂȂǂȂ��ƂĂ��ْ����܂������A�M�d�Ȍo���������Ē������w�Z�W�҂̕��X�Ɋ��Ӑ\���グ�܂��B���͎G���̔������̒��A�w�̖{���Ɍ������G�����w�����Ă���o�Ђ��܂����B�����ɗF�B�̂Ƃ���ɍs���A�G����ǂ�ł��炢�܂����B�F�B�Ɋ��ł��炦�����Ƃ��A���ł��Y����܂���B�{���ɂ��肪�Ƃ�!!

�u�y���������@�_(�OO�O)�^�@��w�@�����v�@�@
���ۏ���U�@�c�K�@�M�G
�P �͂��߂�
�@
�@�v���Ύ��̑�w�@�����́A�S�Ắu�C�m�_������L�v��������ăt�@�C���������Ƃ���n�܂�܂����B�����̐i�ߕ��A�d���ƌ����̗������@���A��y���̋M�d�ȃA�h�o�C�X���Q�l�ɂQ�N�Ԃ��y�����L�Ӌ`�ɉ߂������Ƃ��ł����Ǝv���܂��B
�@���A���̕��͂�ǂ܂�Ă���F�l�ɂ́A�ł���ΑS�Ă̕���L�ɖڂ�ʂ����Ƃ������߂��܂��B�����ɂ������m�E�n�E�ɏo���͂��ł���B
�@�ł́A���̂Q�N�Ԃ��Љ�܂��B
�y���|�[�g�쐬�z
�@�P�N����20�{�A�Q�N����4�{�A�s��24�{�̃��|�[�g���쐬���܂����B
�@�w��̋��ސ}���A�Q�l�}���S�Ă�ǂނ��Ƃ͍Œ���̊�{�ł��B���̏�ŁA�����őI�Q�l���Ђ��P���|�[�g�ɕt��2�`12�����x�ǂ݂܂����B�ǂ�ł��邤���ɘ_�_���������ꎩ�R�ƕM���i�悤�Ɏv���܂��B���̉Ȗڂł����ɗ����Ђ������A�C�m�_���ɂ����ځE�Ԑڂɖ𗧂��܂��B�Ƃɂ����{��ǂނ��Ƃ������߂��܂��B����2�N�Ԃ�170���ȏ�͓ǂƎv���܂��B
�@���A�Q�l�}���ɂ��Ă͏��X�Ŏ�ɓ���ɂ������Ђ�����܂������A�C���^�[�l�b�g�iAmazon�EeBOOK-OFF���j��}���قőS�ē���ł��܂����B
�@�܂��A100�~�V���b�v�ŏ��ޗ��Ă��R�����ė��āA���|�[�g��C�m�_�����́A�Q�l�ƂȂ肻���ȐV���E�G���̐蔲���╶���̃R�s�[�ނ��ē����悤�ɂ��Ă��܂����B�Q�N���ɗ��C����\��̉Ȗڕ����܂߂āA�蓖���莟��Ɏ��W�������̂ł����A���ۃ��|�[�g�������Ƃ��ɂ͑�ϖ��ɗ����܂����B
�@�����āA�C���^�[�l�b�g�Ō����������͑N�x������A���|�[�g�Ɍ��݂��������邱�Ƃɖ𗧂����Ǝv���܂��B�������A�l�b�g��̏��͋ʐ����ł��̂ŁA������Ƃ������̂��������ė��p���ĉ������B
�@���|�[�g�͗^����ꂽ�ۑ�ɂ���Ċw�K������̂ł��B�C�m�_���̂悤�Ɏ����̖��ӎ���Njy������̂ƈقȂ�A�Ȃ��݂̔�������ɂ�����̌n�I�Ȓm���̏K����ڎw�����̂��Ǝv���܂��B����܂ōl�������Ƃ����������悤�Ȏ����ɂ��ďn������悢�@��ƂȂ�܂����B���߂͂Ƃ܂ǂ�������܂������A����Ă���Ɗy����Ŏ��M���邱�Ƃ��ł��܂����B
�y�C�m�_���z
�@���́A�E�Ə㎝���Ă������ӎ����C�m�_���̃e�[�}�Ƃ��ē��w���u���܂����̂ŁA���w�̂����ԈȑO���炠����x�̎Q�l�����͎��W���Ă��܂����B�_���̃e�[�}���n���i���������j�̎Y�ƐU����ڎw�������،����ł����̂ŁA���ɒn�����𒆐S�ɐV���Q���i�n�����E���{�o�ϐV���j��O�O�ɓǂ݁A�֘A�L�������W�������܂����B
�@�܂��A���Ђ̓C���^�[�l�b�g��}���قŌ������ē��肵�A�����_��������w�@�̐}���كf�[�^�x�[�X�T�[�r�X��ACiNii(�_���f�[�^�x�[�X�A�L��)�A�n���̑�w�}���ٓ������p���ďW�߂܂����B
�@�����Ȑ��̎������W�߂����Ƃɂ��A�_���̕����������R�ƒ�܂��Ă������A���ؐ������߂邱�Ƃ��ł����̂ł͎v���Ă��܂��B
�@���A�����W�ɂ��Ă̓C���^�[�l�b�g���֗��Ŏ����葁�����̂ł͂���܂����A�n�����e�[�}�ɂ��Ă��邾���ɁA�����e�n�Ɏ��ۂɏo���������Œ��ڎ��W�������́i�ʐ^�E�C���^�r���[�����܂ށj���_�����\�������ő�Ϗd�v�ɂȂ����Ƃ������Ƃ�t�����������Ǝv���܂��B
�@
�@�_�����M�̃X�P�W���[���͎����Ŏ��Ԕz�����čs�Ȃ������Ǝv���܂��B�������A�Q�N����10���Ɏ��{�����u�C�m�_�����Ԕ��\��v�͐���Q�����ĉ������B�����Ă����ڕW�ɂ�����x�܂Ƃߏグ�邱�Ƃ�ڎw���ĉ������B�����̕�����M�d�Ȃ��ӌ��A���w�E�������������Ƃ̂ł���f���炵���@��ƂȂ�܂��B���͂����Ř_���̕��������ŏI�I�Ɍł܂�܂����B�����āA�ŏI��������̃��n�[�T���Ƃ��Ă����_�I�Ȏ��M�ɂȂ���܂��B
�y�[�~�z
�@���͒n���ݏZ�Ƃ������Ƃ�����A�W���[�~�ɂ͂P����Q���ł��܂���ł����B�������A�搶�ɏo���n���[�~����s�Ȃ��Ă��������A�e�g�̂��w���������������Ƃ��ł��܂����B���K�I�ɂ����ԓI�ɂ���Ϗ�����܂����B�܂��A�d���ŏo�������@��Ɍ������ɂ��ז����Ă��w���������������Ƃ�����܂����B
�@���A�T�C�o�[�[�~�͊e�n�ɎU����Ă���w�������Ȃ���ɂ��ă[�~�ɎQ���ł���d�g�݂ł���A���炵�����̂��Ǝ������Ă��܂��B�Q���ł��Ȃ��Ă���ŋL�^�����邱�Ƃ͂ł��܂����ALive�ɏ���y���݂͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�y�̑��܁z
�@����w�@�Ŋw�ڂ��Ǝu�������͂قƂ�ǂ��d���������ē̑��܂𗚂������ł��傤�B���́A�C�m���擾�Ƃ������u���ѓO���邽�ߖ��������Ԃ����悤�ɐS�����܂����B���ǁA�c�Ƃ̂�������A���݉�̂�������A�o�������A�x�����A���������A�P�����������������邱�Ƃ��ł��܂����B�u�p���͗́v�Ȃ���������Ă��܂��B
�y�Ō�Ɂz
�@���Ƃł�����A����w�@�̋I�v�ɘ_�����f�ڂ��鎑�i��������Ƃ̂��Ƃł��B�Q�N�ԂŊ�b�I�Ȉ���ݏo�����Ƃ͂ł����Ǝv���܂��̂ŁA����͌������p�����Ď��т�ςݏd�˂čs�������Ǝv���Ă��܂��B
�@�Ō�ɁA�F�l���y������w�@�����𑗂��悤���F�肢�����܂��BOB�Ƃ��ă[�~�ł������@�����܂������낵�����肢�������܂��B

�u�C�m�_�����I���āv�@�@
���ۏ���U�@�Γ��@�S��
�@�Q�O�O�V�N�P���A�C�m�_���ŏI�C���ł�X�����I���A���̑��̊w���������I�������B�h��������܂��y����������̂Q�N�Ԃ������B���Ƃ��ƋZ�p�u���̊w���Ƃ��āA��R�O�N�O�ɑ�w�@�H�w�����ȋ@�B�H�w��U�̏C�m�̍����擾���A�J���Z�p�҂Ƃ��đ���ƂɏA�E���A��̑�^�v���W�F�N�g�I���㋽���ɋA�茻�݂̋@�B�H��֓��ЁB���Ђ���͓����w�@�ւ͊��ɂQ���̏C�m�C���҂��o�Ă���B�H�w�C�m�������Ƃ��ẮA����ȏ�C�m�̍��͗v��Ȃ��ƍl���Ă������A����@�o�c�������Â̕����Z�~�i�[�ɎQ�����邽�тɁA�o�c�C�m�擾�̕��ɑ���ӗ~���ނ�ނ�Ƃ킢�Ă����B�\�������A�ߓ������̎Љ�l�o���̐搶������b���f���A�̌��S�������w�������B
�@�����̌����e�[�}�́A�������g�̋Z�p�ғI���z�ƌo�c���o���~�b�N�X�����AMOT�iManagement of Technology�j�Ɋւ���_���Ɏ��g�ޗ\�肾�����B��N�ڂ͉ۑ�ɑ��郌�|�[�g��o�ƁA����̎d���̒�����AMOT�Ɋւ�������W�߂悤�Ƃ����B�d�����A���[�U�[�K��ɂ��A�o�c�҂̕��X����o�c�Ɋւ������O��I�ɏW�߂����A����������̃e�[�}�Ƃ��Ă܂Ƃ߂悤�Ƃ��Ă��A�����ς�܂Ƃ܂�Ȃ��B���܂��ɁA�ł�����Ƃ����V�K�J�[�U�[���^�[�Q�b�g�Ƃ��ċ��������߁A����̊��������̒��܂ň�t�ƂȂ�A�ۑ�������܂܂Ȃ�Ȃ���ԂɊׂ肩�����B�����̐��i�Ƃ��ĕ����������̂Ƃ��낪����A�܂��A���l�ɂ��ꂱ��Ǝw�}�����̂������Ȑ�������A�D���ȃS���t�͐�ɋ]���ɂ��Ȃ��ƐS�ɐ����A���ׂĂ���������v��𗧂Ă��B�Ӕь�͂�������ƂȂ�A�Ǐ��ǂ���ł͂Ȃ����߁A�Q�����Ƃ��ɐQ�āA�ڂ��o�߂��Ƃ��ɉۑ�����ƐS�Ɍ��߁A����Ƃ��͌ߑO�P���N���A���邢�͂R���N���̓��X���������B�i�������ŏC�m�_�����I��������݂ł��ߑO�R���O��̋N���̏K���͕ς��Ȃ��I���̌��x�Q���j
�@�����ĂQ�N�̌㔼���C�m�_���̂܂Ƃ߂̒i�K�ɓ��������A�S���܂Ƃ܂�Ȃ��B�e�[�}��MOT����g�߂Ȓ����E������Ƃ̐����ƂɊւ���e�[�}�֕ύX�����A�܂Ƃ߂ɓ������B�V�K�J�[�U�[�������ɓ���l�߂̒i�K�Əd�Ȃ������A���֊W���o�Ă����ʔ����悤�ɕ��͂��i�݂������B���������Ď��̏C�m�_���͌����Ċw��𒆐S�ɏ����o�������̂ł͂Ȃ��A���̌��Ƒn���̐��E�̒�����g�ݗ��Ă�ꂽ���̂ƂȂ����B���������ꂩ��̎����̃o�C�u���I�����̂��̂ƂȂ����Ǝv���Ă���B�Ō�͎w�������̊K�ː搶��肢�낢��ƃA�h�o�C�X���A���Ƃ��_���Ƃ��Ē�o���邱�Ƃ��ł����B
�@���̓�N�Ԃ�ʂ��A�ő�̎��n�͌\���搶�E�ߓ��搶�E�K�ː搶�Ƃ߂��荇���A���Љ�̖L�x�Ȍo���ƁA�w��Ƃ������ɗZ�����A���̂���l�����G���W���C����Ă���l�Əo��������Ƃł���B�����g�l���ɂ͏�Ƀx�X�g�ŗՂގ�`�ł���B�V�тł���A�X�|�[�c�ł���A�m�{�Z���ł���B�i�����Ƃ��A���������_���ɂ̂ڂ����ق����ǂ������̂����E�E�E�j
�T�T�ő��̊w���ɂȂ�A���N�͂T�V�B�w��ɔN��͕s�v�B��y�ɂ��`�������A���̑�w�@�ł͕K�������鎖���ł���B��x�����Ȃ��l���A�S�͂łԂ��邱�Ƃ������߂������B�������ΐl�����Ɋy�������̂ł���B

�uMeet the deadline�Ɠ\�����āv�@�@
���ۏ���U�@�@���J�Y�@�z��
�@1�N���̏I��荠�̃T�C�o�[�[�~�ŋߓ��唎�搶���u2�N�ɂȂ����猈�߂�ꂽ�����ɂ������ƕ����ɑΉ�����悤�ɂ��Ȃ����v�ƌ���ꂽ�̂��悭�o���Ă��܂��B�u���ԊǗ��v�u�X�P�W���[���Ǘ��v�uMeet the deadline�v�ł��ˁB���ł͂킩���Ă͂���̂ł����A���ꂪ����B����قǓ�����Ƃ����ɂ���ł��傤���B�Ƃ肠�����ӑĂȎ����́A�p�\�R���ɁuMeet the deadline�v�Ɠ\�������܂����B���ł�����͏a���P��������Ȃ���c���Ă��܂��B����͊w�����������łȂ���А����ł��厖������قǑ厖�Ȃ��Ƃňꐶ�������Ȃ��ł��悤�Ɣ邩�Ɏv���Ă��܂��B
�@���āA1�N���ł����A5�Ȗڂ͂������Ɗ��������A���|�[�g��o���������悢�Ǝv���܂��B�����̏ꍇ�A���e�ɂ͖ڂ��ނ���������͎�����̂łȂ�Ƃ��Z�[�t�ł����B�����悹�����̂Ɂu�p�������w�ǁv�Ƃ������ɃA�J�f�~�b�N�ȉȖڂ��Ƃ��Ă��܂��A�������p��̖{�������ė������͂߂܂��������̂��o���Ă��܂��B
�@2�N���͂��������1�Ȗڂ����ł悢�킯�ł����A�����ł��悹�����̂�3�Ȗڂ��͂��Ă��܂��܂����B�Ȃ��Ȃ玩���́A�d�����悭��s�@�ɏ��̂ł����A�ς�ł�G���W����2�Ƃ̂��ƁB2�Ƃ��s���������^���t���܂ł��B�����͗\���I��3�Ƃ��Ă������ȂǂƖ��d�ȋ��ɏo�Ă��܂��܂����B�����ł��uMeet the deadline�v�łȂ�Ƃ���o���܂������A2�Ł@�����̂��ȂƎv���܂��B�]�T�̂�����͕����ꂽ�ق��������̂ł����B
�@��s�@�̘b���o�����łɁA���Ƃ����낤�ɏC�_�������N��12����C�O�o�����d�Ȃ��Ă��܂��܂����B�s���͂���Ȃ�̎g��������܂��̂Ŏd���W�A�A��̔�s�@�ŕ��W�̖{��ǂނ悤�ɂ��܂������A�ӂ�ӂ�ȓǏ��������悤�Ɏv���܂��B
�@�Ō�ɂ܂��߂Șb�ł��B���͓��[�~�̂��N�z�̏����̕����A�݊w���ɑ�ώc�O�Ȃ��Ƃł������S���Ȃ�ɂȂ�܂����B���̕����T�C�o�[�[�~�̎��Ɂu���J�Y����̌������y���݂ɂ��Ă�v�ƌ����Ă���܂����B��������X�v���o���A�����Ȃ�Ɋ�������낤�Ƃ��܂����B���̏�����肵�A���߂Ă����\���グ�A�����������F�肷�鎟��ł��B

�u�Ê���߂��@�����Ȃ�l���̐����������߂āv�@�@
��������U�@�]���@����
�@Are thy wings plumed indeed for such far flight? �u���̗��͂��̉������Ăɂ܂��Ƒς������H�v�c�c ���͘_���̍Ō��1�s��ł��I�����Ƃ��A����Ŏ����̐l���ɂЂƂ̋��������̂��A�Ƃ����v���ɂƂ���A�������̊O�A����̊D�F��w�ɁA�����}���������ƐL���Ă���V�̂������ɖڂ�������B100�N�ȏ�͊ԈႢ�Ȃ��B�䂪�Ƃ̖v���̈ꕔ�n�I�������ق��Č��ߑ����Ă�����(�ނ�)�̖ł���B
�@
�@���͌����v�揑���o����Ƃ��e�[�}�����ɂ��悤���A�Ǝv���Y�B�����̐t����̓T���g�������Ă͂₳��Ă����B�s���Ȃ����w�ȂǑ������ׂ����́A�����̐����Ɩ��W�ȕ��w�͕��w�ɂ��炸�A�u�A���K�W���}���v�����m���l�̎��ׂ��������A�Ƃ��������ł������B���v���Ύ����Ⴉ�����B�ł�����Ȃ�ɐ^���ł������B20���I�����̎Љ�̒��Ŏv��������Ƃ����̈�l�A�W���[�W�E�I�[�E�F���ɋ������������B���͗��ꎄ�͌Ê���߂����B�ʐM����w�Œm�邱�ƂɂȂ����d�D�l�D�t�H�[�X�^�[�̐��E�Ɏ䂫���܂ꂽ�̂̓y���M���ł́w�n���[�Y�E�G���h�x�̕\���ɕ`���ꂽ���̖��䂪�Ƃ̖��̖�f�i����������ł������B�����ĂȂɂ����������̐l�ԓ��m�̌��э��� �gOnly connect�c�h �Ɏ䂩�ꂽ�̂ł������B�����ɂ��߂�ꂽ�v���A�肢�͉��ł��邩�B���̎v���͈ꐶ��ʂ��Ăǂ̂悤�Ɍ`������Ă������̂��낤���B���ǔނ́u���E�ρv��Nj�����Ƃ����e�[�}�Ɏ��g�ނ��Ƃɂ����B���쎛�����Ƃ̍ĉ�傫���������g�ɂ��Ȃ����B
�@�t�H�[�X�^�[��������ƒ���A�t����A�����ăG�b�Z�C�A�Z�ҁA�����ւƂقڑS���ɖڂ�ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂������ǂ͌����̎��ԓI����̒��ŕs�\�ł������B�ނ̃P���u���b�W����̃G�b�Z�C�ɂ��Ă͌�������肵�Ȃ��܂܂ɏI��������A�Z�҂̈ꕔ�ɂ��Ă͒�o������1�����O�ɂ���Ɠ���ł������̂�����A�͂�͂炵�Ă��܂����B�j�n��ł���B��i��ǂޕ��@�͐l���ꂼ��̍H�v������Ǝv���B�ŏ��̂����͂߂ڂ����ӏ��ɏo��ƁA�m�[�g�ɏo�T�L���ă��������A���͂�������ł�����������͗��s�Ƃ��Ő����̎��Ԃ𗘗p����Ƃ��̂����ŁA���Ɍ������Ƃ��͂��̏�ő��A�p�\�R���ɓ��͂��Ă��܂������������I���Ƃ������Ƃ��A���|�[�g�̖{���������Ă���Ǝ���ɂ킩���Ă����B���̍ۂɘ_�|�W�J�ɏd�v�ȕ����Ǝv����ӏ��͐ԐF�ŁA�����I�ȁA����h�����ꂽ�ӏ��͐F�ŁA�Ƃ����F���������݂��B���ۂɘ_����g�ݗ��Ďn�߂�ƁA���̐F�����͗����Ƃ��ɘ_���̂Ȃ��ɓ��邱�ƂɂȂ邩��i�����Ȃ�Ȃ��ꍇ�����邪�j��������Ȃ����A�Ƃ����l�����낤���A���ƂœǂݕԂ��Ƃ������̊������킩��̂��ʔ������̂ł���B���ЂƂG��Ă��������͓̂��w�̎u�����l�X�Ƃ̂ӂꂠ�����G�l���M�[�̎����ɂ͐�ΕK�v�ł���B��B�ɏZ��ł���̂Ŗ����̃[�~�ɏo�邱�Ƃ͂܂������ł������B����ł���N���ɂ�6��㋞�����B������2�N���ɂ͎���ς���ď㋞�����̂͘_���e�e���ł��Ă���̈�x�����ł���B���̈Ӗ��ʼn������ɂ��Ă��u�T�C�o�[�[�~�v�ɎQ���ł����̂���Ԃ悩�����B2�N���ɂ�9����Â��Ă�������B������Ɣ��\���Ȃ��Ă������A�ߋ����������邱�Ƃŕ��������T��ꂽ�̂ł���B�V��������������ł����̂��T�C�o�[�ł̏o�������������ł���B
�@�����͎��i�u�[���ƂȂ��Ă����B�w�ʎ擾�ŕ����I�ȃv���X�悤�Ƃ�����̂ł���B����͂���ŎႢ�l�����ɂ��×~�ɐ����ė~�����B���͐�ɐG�ꂽ�悤�ɁA�L�����A�����ĉ�����̓I�ȍs�����N�����v��Ȃǂ͍ŏ�����Ȃ������B��N��Ŕ��f�����u�p�ꋳ���v���r�W�l�X�Ƃ������͎�̐��E�ƂȂ����B������̎l���̈�͂��̐��ɓn�����B���Ǝ��ɂ��Ăǂ̂悤�Ɏ~�߂Đ����Ă䂭���́A���̐��ɂ���ҋ��ʂ̉ۑ�ł���B�N�w�ł���A�@���ł���A�����Ȃ�ɓ������o���Ă���l������B�ł����̓��������ՓI�ɑ��҂ɒʂ���Ƃ͌���Ȃ��B�����Ȃ�ɓ����̎��������݂��������̂ł���B���ǁu���A���v�͈����R�̂悤�ɓ���g����̒��ɂ܂��ꂱ��ł���B����������ق����u���Ƃv��{��2�N�Ԃł������B���̈Ӗ��ŕЎR�����́u�R�~���j�P�[�V�����_�v��ǂ݉������͖̂]�O�̎��n�ł������B���x������𓊂������Ȃ���A�������Ȃ��w���Ɨ�܂��������������搶�Ɋ��ӂ���B��c�����̕K�{�Ȗڂł͓`���|�\�́u�\�v�ƃV�F�C�N�X�s�A�̗Z���Ƃ������݂ɋ����S��ł��ꂽ�B�ߌ��͐��E���̃e�[�}��������B����͖����\�̐��E�Ɍ��т��B�w��ɔ��\�̋@����̂��搶�̂��w���ɂ��B�|�싳���́u���w�Ƃ��Ă̐����v���܂������V�������_�ł������B�ۉ��Ȃ��Ƀt�@���^�W�[�̐��E�֗U�����̂ł���B����Ő_�Ƃ͉����A�l�Ƃ͉������l���������B�V�F�C�N�X�s�A�Ɛ����ɂ��̂悤�Ȍ`�Őڂ��������Ƃ́A�c���e�Y�́u��g�p�a�v�Ɏ䂩��Ă������Ắu�p�w�k�v�ɂƂ��ẮA�܂��ɖ����ɂ���o��ł������B
�@���A���͒n��̍s���撷�ɑI��Ă���B�l��2���̓c�ɒ��̗X�ǒ��Œ�N���}�������́A�قƂ�ǂ̐l�������o�����Ă���B����́A10�N�قǑO�Ɂu�����ي����v�̃��[�_�[�𗊂܂�Ƃ��A�n��̊������ɑ������Ă����o�����Ă̑I�o�ł���B�Ƃ��낪���̎d�����Ŗ@�Z�����B�s���̈ӎv�`�B�͖ܘ_�����A����͐l�ԓ��m�̐S�̌��э���������ɂ��Ă��܂��Ă���B�ǂ��`���Ƃ��Ắu�Q�}�C���V���t�g�v�͕������̂Ƃ��ẴR�~���j�e�C�̍Đ��E���W�͋i�ق̉ۑ�ł���B�����̂��ƂŌ�肩���邱�ƁA�l�X�ɖ����������Â��邱�ƁA��������H�ɂނ��т��邱�ƁB���A���͂����S����y����ł���B�q�|�N���e�X�̂��Ƃ� �gArt is long. Life is short.�h�@�����邪�A���Ɏc���ꂽ�l���͂܂������ɂ���A�Ƃ����S���ł���B���̂悤�ȏ[������^���Ă��ꂽ�䂪���{��w��w�@�A�����ɂ��ꂼ��̏�M�����W����Ă��鏔�搶�����ɐS����̌h�ӂƊ��ӂ��������A����ɏo����w�F���Z�o�Ƃ́u�l�ԓ��m�̌��т����v���ł���Ύ��̏C�m�_���͖����Ƃ��Ɋ�������̂ł���B

�u���{��̕ǂ����z���āv�@�@
��������U�@���@�t��
�@�C�m�_���������I������I�I�܂��o���B�������Ȃ������B�v������X�ɗ����B���̓�N�Ԃ͎��̐l���̒��̈�u�̂��Ƃł��邪�A�ł������ɂƂ��Ē��������B�h�������B�ł��悩�����I
�@��Ԑh�������̂���͂���{�ꂾ�����B����̓��{��ɂ͊���Ă����̂ŁA���܂�s���R���邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ������A��w�@�ɓ����Ă���A����Ȃ����{���w�̐�������ɂ��āA���ɂ��킩��Ȃ������B�u�����H���̂��ƁH�v�u�C�_�H���̂��ƁH�v�u���j�R�[�h�H���̂��ƁH�v�p�\�R���̎g�����������炸�A���ׂĂ̌��t�����܂�ď��߂ĕ������̂悤�������B���{��̓�����������B�ꎚ�̈Ӗ����������߂ɉ����Ԃ�������A�������̓��{�ꎫ�T�⒆���ꎫ�T�����ׂ��B���̓��{��͂���Ȃɉ���ŁA���v���ȂƋC�����������Ƃ��������B���Ԃ͎��Ƃ����邵�A����s���u���̎��Ƃ�����B�y���������W�̌𗬂�|��̎d��������A���̏�Ǝ��������āA�L�̎���肽�����炢�A�����قǎd�����I���Ȃ��B�_���͖�����10���ȍ~���珑���͂��߁A�P����2���܂ł̐h�����X�ł������B�ł���܂��Ă���A�܂���Ԋ��ӂ������̂��w�������̏��c�ؐ搶�ł��B�搶�͎������̂Ă��ɐe�ؒ��J�Ȏw���ŁA���{��������Ȃ���A���{�����������Ă��ꂽ�B�ʓ|�������炸�ɁA��������̎��������������A�搶�ɂ͑�ς����b�ɂȂ����B�搶�I�{���Ɂ@�ӎӁI�ӎӁI
�@��ԗǂ��������Ƃ���w�@�ł̕��ł������B���{�ɗ��Ĉ�Ԃ悩�����Ǝv�����B�h�����������ē������̂������������B��̌��t�̗R�����������߁A��ʂ̎��������Ȃ���Ȃ炸�A�����ɏ�����Ă����ʂ̓��{��𗝉����Ȃ��Ƙ_�����������Ƃ��ł��Ȃ��B�ꎚ�̈Ӗ����������߁A�K���������T�ƒ������T�A�����Ē�����厫�T�ׂ�B���̂悤�ȕ��͎��Ԃ������邯��ǁA���{��ƒ�����̗����̌����ɂȂ�B���x�̘_���́u�������ꕶ���̑Δ�Ɣ�r�����\�]�ˎ���𒆐S�Ƃ��āv�Ƃ����e�[�}�ł��邪�A�����̎������Q�l�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���Ȃ��Ă��Q�O�O���ȏ�̎�����ǂB���{�̍]�ˎ���̕����͒����Ƃǂ������W������̂��A�����̔��b�����͓��{�łǂ������ӂ��Ɏ�e����Ă������̂��A�����������ƂɊS���������B�F�X�Ȗ{��ǂ߂Γǂނقǒm�I�D��S�������A��Ɋ������A���̊y�������g�ɕt�����B���X�Q�鎞�Ԃ��Y�ꂽ���Ƃ��������B���̓�N�Ԃ̑�w�@�ł̊w�K�������A���{�ɗ��Ă����ԑ�ςł��������A�ł���Ԋy���������Ǝv���B������o���_�ɂ��āA���������𗬂̌����𑱂��A�����̗����Ɛe�P�̂��߂ɔ��͂�s�����Ă��������B�܂��A���{�ł̒������w�̌����ɂ��Ē����ɓ`���邱�Ƃ�����̉ۑ�ł���B
�@��N�Ԃ̊Ԃɏ��c�ؐ搶�A�ߓ��搶�A���V�搶�A�|�ѐ搶�A�����ă[�~�̐�y�����A�܂������ۂƃw���v�f�X�N�̔���l�ɑ�ς����b�ɂȂ�܂����B����Ȃ����f�����|���������Ƃ����l�т���ƂƂ��ɁA�S���炨���\�������܂��B�܂��x���Ă��ꂽ�Ƒ��Ɋ��ӂ��܂��B
�@�Ō�ɁA���c�ؐ搶�A�ӎӁI�ӎӁI�I�I

�u���N�̖��������Ⴂ���̖��������v�@�@
��������U�@�r���@�֎q
�P�@�ʐڎ���\�ْ�
�@�P���Q�V���A�ʐڎ���������邽�ߎs���J�̓��{��w�{���A�Q�O�P�����ɑҋ@���Ă����B
�\�莞�����x��Ė��O���Ă�A�w���ʂ�X�K�̕����ɓ������u�ԁA�����ɒ|��搶�A���Ɏ���搶�A�E��ɏ����搶���ڂɂ͂������B
�@�ȑO�ɂ����������搶�����ł���ɂ�������炸�A�ْ������`����Ă����B�u�悭�撣��܂����ˁv�ƒ|��搶�̗D�������ɂق��Ƃ������̂́A���T�C�h�̐搶�̎���Ɍ˘f���Ă��܂������A�A�����J���w�������ƕ����ė~�������Ƃ��ƌ�ŗ����ł����B
�@�A�����J���w���D�������A��w����Ɋw�����ŁA�t�����X���w�A�h�C�c���w�ȂǂȂǁA���w�̗̈�̍L���ƕ��s����ɐɊ����Ă��܂����B
�Q�@�C�m�_���\���ƍ�
�@���̓��[�}�E�J�g���b�N�ɉ��@�����C�M���X��ƃO���A���E�O���[���̃J�g���b�N�I�F�ʂ̔Z���S��i�i�w�u���C�g���E���b�N�x(Brighton Rock 1938)�A�w�͂Ɖh���x�iThe Power and the Glory ,1940�j�A�w�����̊j�S�x�iThe Heart of the Matter,1948 �j�A�w��̏I���x�iThe End of the Affair,1951�j�̍���ɗ���Ă��鈤�ƍ߂�`���Ă݂��B�����̍�i��ǂ�ŃJ�g���V�Y���������Ă��鈤�̖{���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�ȂǁA�ǂ̏@�h�ɂ����ʂ��鍢��Ȗ��ł���ƌ�����B�t�H�[�X�^�[�����ՂɁu���Ȃǂƌ����ȁv�ƌ���ꂽ�悤�Ɉ��Ƃ͉i���̖��ł���A���s���邱�Ƃ̍����Ɋ������B�߂͐l�Ԃł���ȏ�N�ł��Ƃ����ƁA���̂��߂ɃL���X�g�����̐��ɐl�Ԃ̎p�Ƃ��Ă�����A栂���p���ĉ�X�ɗ��������悤�Ƃ��āA�l�Ԑ��Ɛ_��������ĂQ�O�O�O�N�O�ɂ��̐��ɐ��܂ꂽ���Ƃ��m�M���邱�Ƃ��o�����B
�@�ʐڎ�����I���A�͗ʂ̂ӂ����Ȃ��Ɍ�����c��B������������U�A�|��[�~�ɏ����ł������Ƃ͂킪�l���ɐV���Ȉ�y�[�W���lj����ꂽ���ƂɂȂ�B���̂悤�ȓ�N�Ԃ��߂��������Ƃ͌��������̂��Ƃ������Ă���B�N��̈Ⴂ�z���āA���Ɋw�Ԏp�����������l�B���҂��Ă��Ă��ꂽ���炱���A�[�~�ւ̎Q�����\�ł������Ǝ������Ă���B
�R�@�|��[�~�\�y�����ЂƎ�
�@�|��[�~�͌ߌ�P���R�O������x�e���ԂP�T��������łT���A�U���܂ōs����B���̂��ƐH�������Ȃ���M�d�Șb�����Ƃ��ł��鍧�e��҂��Ă���B����[�~�ɎQ�����邽�тɐV���ȏC�m�_���̍\�z�����܂�邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������B���ʓI�ɂ��������̂������̂ƂȂ��Ă����B�W���̌y���[�~�͕w�{��������A�y���݂��ō��ł������B��Ȃ���N�������Ȃ���X�����������͉̂��\�N���̂��Ƃł������B���̂悤�Ȍo������w�@�Ȃ�ł́A�Ə�����Ԃ����悤�ȋC���ɂ�����ꂽ�B
�@���ł��Y����Ȃ����ك[�~��2006�N3���ɍs��ꂽ�B�ٍ�����Y���C�M���X�̎��قł̃[�~�͗[���܂ł��������B3�����{�Ƃ����̂ɐ�Ɗ����ɐk���Ȃ�����[�H�ƍ��e��͐▭�ȉ����������������Ă��ꂽ�B
�@�����͎Ԃœ��ʌ����V�g�[���̐���g���s�X�g�j�q�C���@�����w�����B�C���@�̓����͒j���̂݁A�����͋q���ŊG������Ă����B�g���s�X�g�N�b�L�[�Ƌ����̃T�[�r�X������A�S���牷�߂�ꂽ�B�A��͏C���@�����̓��ʃJ�g���b�N����ŁA�|��搶�̃I���K�����t�ɍ��킹�ă[�~���̊F����Ɖ̂������͖̂Y����Ȃ��B
�@�H�̃[�~�����肩��A�^���ɏC�m�_���������Ȃ��Ă͂Əł�������n�߂��B1�N�ڂ͂S���Ȃ̃��|�[�g�ɋꂵ�߂�ꂽ�B
�S�@���̎����\�l���͗�
�@���͐́A��w�i�w����߂ĉƒ�ɓ���A���N�̖��������Ⴂ���̖������������Ă���̂��B���w���Ɍ��S���������̃[�~�ɎQ�������]�͒��O�ɍ���ɂ߂āA�X�^�[�g���獢����Î����Ă��邩�̂悤�������B��҂̒������������A���ق�����}�X�[�p�[�����A�V�����ɏ��ւ��V���Ԃ����ē����Ɍ������B�������يԂ͔�s�@�̕��������A�Ȃ��H�Ǝv���邩������܂��A����-�����ԉ���������ؕ��̂ق����Q���U��~�ƈ����̂��B���w���Ɉ���搶�Əo������B�u�悭����������܂��ˁA�Ɠ��������Ă܂�����v�Ƃ����A���S�ǂ���Ƃ����B�u�����͂���܂����A�����͍��o�����̂ł���A�v�Ƒ吺�ł������������B
�@JR�̗��͌����Ċy�ł͂Ȃ��B�����ԁA�����p���ł���A�O���������Ă���B���̋�ɂ���ԓ��Ń��|�[�g�ۑ�̖{��ǂ݁A��Γł��邱�Ƃ��킩��A��ɂ��v���X�v�l�ɍl�����p���邱�Ƃɂ����B�܂��Ɂu�l���͗��ł���v�Ǝ�����������ł���B���������Ăǂ��Ȃ�̂��Ǝv���邪�A�Z���l���ʂɂ������Ȃ������B
�@�P�N���̕K�C�Ȗڂ̃X�N�[�����O�ŁA�u���ɏI���͂���܂����v�Ə�c�搶������ꂽ�B�������썰�͉i���ɐ���������̂��B���ł��낤�ƕ��͖��ʂɂȂ�Ȃ��̂��B�D���Ȃ��Ƃ�����Ă���J�A���炢�Ȃ��Ƃ�����Ă���J�A��������Ȃ������̂���Ă��邱�Ƃ͐����邱�Ƃ̈ꕔ�Ȃ̂��B�����݂Ȍ��t��������ł���B
�@���������͎q��ɂ߂��܂�A�������������Ă��邨������Ȃ̂��B���ɂ́A�����̂悤�ɑ��̐��b�𗊂܂�āA���|�[�g�̒�o�ƏC�_�̏������C�ɂȂ�A�����̉^�������߂����v�������������B�܂��������N���A���H�̑O�Ƀp�\�R���Ɍ������Ȃ���A���܂łɌo���������Ƃ��Ȃ��V�N�Ȋ��o���y����ł��邱�ƂɋC���������������B
�@�[�~�ɖ���Q�����邱�Ƃ́u�Ӗ����铦���ł���v�ƁA�|��搶�Ɍ���ꂽ�Ƃ��́u�^���ł���v�Ɠ��������Ȃ�B��������̓����A�D���Ȍ��t�ł���B�D���Ȃ��Ƃ����Ă��錻�݁A�킪�܂܂Ȑl�Ԃł������̂��A�ӂƂ��ꂪ�����Ă����тȂƏΊ�ɂȂ�B
�@JR�̗������Ɛ���ŏI���ɂȂ�̂��A�ꖕ�̋��������P���Ă��������B�������|��搶�́u�I���[�~�ɎQ���ł��܂���v�Ƃ���ꂽ�͂��A���ꂪ�{���Ȃ�s���̂����͓��}�X�[�p�[�����ɔ�я�艓���Ȃ��Q�������Ē������ƏC�m�_����o���I�������A�����ɐ����̂ł���B�@

�u���ӂ̓��X�\�\�C�m�_����o�ւ̓����v�@�@
��������U�@���{�@�h�q
�P�D�͂��߂�
�@���̂Q�N�Ԃ�U��Ԃ�A�܂��ŏ��ɁA�w�������ł���|��搶���͂��߂Ƃ���搶����A�[�~�̊F����A�A�Ȃ���x���Ă��������������̕��X�A�����ĉƑ��ȂǁA�����x���Ă��������������̕��X�֊��ӂ̌��t���q�ׂ����Ǝv���B������ł��A�����ЂƂ�łł����ȂǂƎv�������Ƃ͂Ȃ������B�p�������Ȃ���A�̂���v�ł͂Ȃ����́A�l���݂Ƀ[�~�ɂ��Q���ł����A�|��搶�̎w�������[���ł̂���肪�قƂ�ǂł������B�������ɂ��͔͓I�Ȋw���Ƃ͂����Ȃ������Ǝv���B������A���͂ւ̖��f�́A����Ȃ��̂ł������Ǝv���B�a�@�Ɛ}���فA���ɂ͑�w�@�܂ő���}�����Ă���������Ƃ��������B����ł��A�[�~��X�N�[�����O�ւ̎Q���͔��Ɋy���݂ł͂������B�������A��ɑ̉��v�̐������C�ɂ��Ȃ���A���ʂ̖�̕��p�ƕ���p�A���������̌����ڂ̒x���ɂ��ł�A��ɂ����炦�Ă̎��u�ł͂������B�p�\�R���Ɍ������Ă��Ă��A���̂Q�N�Ԓɂ݂��������ɂ������Ƃ͂Ȃ������B�����A���@���p���o�����Ȃ���A�_���������グ���@��������������Ƃ����̂�����A���̋�J�Ȃǂ͂܂��܂��債�����Ƃł͂Ȃ��B�������A�����̓n���f�B������Ă���悤�Ȏ����A�C�m�_�����ɏ����グ�邱�Ƃ��ł����̂́A�����ȊO�̑����̕��X�̂������Ƃ����v���Ȃ��B������A�܂��������͂��߂ɁA�ӈӂ��q�ׂ����̂ł���B
�Q�D���_�����߂�
�@���ꂩ��C�m�_���Ɏ��肩������̂��߂ɁA������ł����ɗ����Ƃ�\���グ����悢�̂����A�ˏo�����Ƃ�����Ȃ��̂ŁA�����̂��Ƃ��������Ă������������Ǝv���B��w�@�ɓ��w����O�ɁA����ӎ�����Ɏ����ƣ���A�h�o�C�X���ꂽ�B�Љ�l�w���Ȃ�A���Ɏ����̐g�߂ɂ��邱�Ƃ��悢�Ƃ����B�Љ�ɏo�čv�����Ă���l�����ɂƂ��ẮA�悭�l���Ă݂�A�ӊO�Ƃ��낢��C���t�����Ƃ����邾�낤�B�����������ӎ��́A�������g�̓��ʂ��炭����̂ł���悤�Ɏv����B�������������̌��_�̂悤�Ȃ��̂��A��ɔO���ɒu���Ȃ���_���쐬�����݂���ƁA�Ō�܂łԂꂸ�ɁA�_��W�J���邱�Ƃ��ł���Ǝv����B���̂悤�Ȃ��Ƃ͂��炽�߂Đ\���グ�邱�Ƃł��Ȃ��̂����A�����̏ꍇ�A�ӊO�ɂ���ȓ�����O�̂��Ƃ���������B����������������A�m����������Α�����قǁA�����������Ƃ⏑���˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���邱�Ƃ��ی��Ȃ������Ă����B�Ō�͌��ǁA���������Ȃ����A�Ƃ������Ƃ����ɂȂ��Ă��܂�������ł���B
�@�Љ�v�������Ă��Ȃ��A�n���f�B�L���b�v���炯�̎����Ɍ����������Ƃ���A���̌����͎n�܂����B���̖��ӎ��́A����Ӗ��A���̕��X��葽���āA�傫�����̂��Ƃ�����̂�������Ȃ��B���̂悤�Ȏ����I�����e�[�}�́A�@���̐��E�ł������B�̃{�����e�B�A�ł����b�ɂȂ����A�C�G�Y�X���t�����V�X�R��̐_�������́A�w�����x�̐����Ŏ��ɃX�g�C�b�N�ȁA�~���ɖ������������_���A�����ĉ��S�N�ɂ��킽�莩���̑̂ɗ����A�_���Ƃ����A�Ñォ��̓��{�l�̑f�p�Őg�߂ȁA�������_���ɑ���v���ł������B
�@�@���Ƃ����ƁA�Ƃ������{�l�ɂ͌h���A�ނ���A�����M�[�I�Ȕ����������l�������邪�A����͈ꕔ�̉ߌ��Ȍ�����`��@���܂����̃J���g�ɂ����̂Ǝv����B�{���̏@���́A��X�̐����̊�ՂƂȂ��Ă��镶�����`�����Ă�����̂ł���ƍl����B���ɁA�_���Ƃ͉�X���{�l�̐������̂��̂ł���A�����𗣂ꂽ�M�Ƃ������̂���{�l�͂����Ă��Ȃ��A�Ət����Ђ̗t���{�i�͌����Ă���B����́A�w�����x�ł��������Ƃ�������̂ł͂Ȃ����낤���B�w�����x�̌o�T�Ƃ���@���́A�L���X�g����������܂ł��Ȃ��A���E�@�����ӂ���ł���B�w�����x�̐��E�ς�_���Ƃ������̂́A�����M����l�X�̐����̈ꕔ�ƂȂ�A�����܂ł��̕��������ł����̂ł͂Ȃ����낤���Ǝv������ł���B
���̒��ł́A�����S���Ⴄ�M�`�Ԃ����@�����́A�����đ��������邱�ƂȂ��A�ނ��다�����������āA���݂̎������`�����Ă���Ǝv����̂ł���B���ɂƂ��āA�u���v�͓�����O�ł͂Ȃ��B�ނ���A���u��������Ă��邱�Ɓv�����������Ă���B�����̢����́A���肻�߂ɉ߂��Ȃ��B�����炱���A������Ă��邱�ƣ��X�����ۂ̖��Ȃ�������������邱�Ƃ��ł���̂�������Ȃ��B�����v�����Ƃ��A�������������邱�Ƃ��ł��邱�ƂقǁA�K���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��悤�Ɏv�����B���������l�ԂɂƂ��āA�܂�������飂Ƃ������Ƃɂ��āA������������ł���Ȃ��Ƃ�������Ȃ����E�ς�l���ς������Ă��ꂽ�@���Ƃ��������́A�L��Ő��炩�ȉF���ɐG�ꂽ���Ƃ����v�����A���̌����͂ł������B
�@
�R�D�Q�N�Ԃ�U��Ԃ���
�@������T����ł́A�ӊO�Ƃ������A�v���Ă����Ƃ���Ƃ����ׂ����A�_���Ɓw�����x���r�������Ă��镶���⌤���҂͌����đ����͂Ȃ��悤�ŁA��s������T���̂͗e�Ղł͂Ȃ������B�������A���͍̂l���悤�ł���B��s�������C�ɂ����A���R�Ɏ����̍l���Ŕ�r���A�_��W�J���邱�Ƃ��ł���A�Ƃ��l���邱�Ƃ͉\������ł���B�����l����A���肪�������Ƃł�����B
�@�|��搶���A�C�̂��̂Ƃ��R�̂��̂Ƃ��m��ʁA��藯�߂̂Ȃ����̌����e�[�}���A�E�ϋ��������Ă�������A���Ƃ��`�ɂȂ�悤�A�����ł��C�t���ʘ_�_�������o�����Ƃ��āA�I�m�Œ��J�ȃA�h�o�C�X��������A���̏�ŁA���Ɏ��R�Ɍ��������Ă����������Ǝv���B���̓_�ł��A���͔��Ɍb�܂�Ă����Ǝv���A�|��搶�ɂ͊��ӂ�����Ȃ��B
�Ȗڂ̗��C���A�ƂĂ��L�Ӌ`�Ȃ��̂ł������B���ɁA��@���N�w���u��Ƣ�N�w�j���u��́A���̐�U����̗��C�ɂ�������炸�A��U�Ⴂ�̎��ɂ��A�E�ϋ�����ϒ��J�Ɏw�����Ă������������Ƃ́A��ς��肪�������Ƃł������Ɗ����Ă���B�����̌������̂��܂߂āA�˂������ċq�ϓI�ɁA���ᔻ�I�Ɍ���Ƃ������_��������ꂽ�悤�Ɏv���邩��ł���B
�@
�@�G���A�[�f�́A�@���w�̕����I�w���Ƃ��āA���̂悤�Ɍ����Ă���B
�@�l���Ȋw�̒��ł��A�w��ł���Ɠ����ɁA���勳��I�����_�I�ȃe�N�j�b�N�ł����鏭���̒��ɑ����邾�낤�Ƃ��A�߂������ɑ�1���̕����I�������ʂ������낤�B
�܂��A���N�[���́A���̂悤�Ɍ����B
�@����̉�X�̗L�l�́A���Ȃ���̖̂Y�p�ƁA���̌��ʂƂ��Ă̐l�ԑS�̓I�ȑr���ł���B���ꂪ�A�l�ԂɂƂ��čł���{�I�ȏ�ł��錾��̏�Ő����Ă���̂��A���㐫�̓��F�ł���B
�@����́A�����S�̂ɂ������邱�ƂȂ̂�������Ȃ��B��X�l�ԂɂƂ��ĕ����Ƃ������̂́A�l�Ԃ̐������̂��̂ł���A����đ��݂��邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B����̉�X�́A�����Ƃ������̂̈Ӗ����Ȋw�Z�p�╨���I�Ȃ��̂Ƃ����悤�ȋ��`�ȈӖ��ɂƂ炦�����Ă���悤�Ɍ�����B�������A�����͖{���A�����I�Ȃ��̂������w���Ă���̂ł͂Ȃ��B���_�I�Ȃ��́A�S��L���ɂ�����̂����w���Ă���B���̖Y�p�́A�܂��Ƀ��N�[���̌����u�l�ԑS�̓I�ȑr���v�ɂȂ����Ă����̂�������Ȃ��B���������Ӗ��ŁA�����͑�Ȃ��̂ł���A���ɂƂ��Đl���ōł���ȑ�w�@�̂Q�N�Ԃ��A��������U�ɐȂ��������Ƃ��ł��A�����Ŋw�сA�����ł������Ƃ��A�S���炠�肪�����A�K���Ȃ��Ƃł������Ǝv���B
�@�Ō�ɂ�����x�A���̂悤�Ȃ��̂��x���ē����ĉ��������A�|��搶���͂��߂Ƃ���F�l���Ɋ��ӂ̈ӂ�\�������B�܂��A���ꂩ��_�������������X�ɂ��A���͂Ȃ���A�G�[���𑗂点�Ă������������Ǝv���B���Ԃ����͂ǂ�Ȑl�ɂ������ɗ^�����Ă��邪�A��������R�Ɏg�����Ƃ͓�����ƂƎv����B�����A�����Ă�����߂Ȃ��ł������������Ǝv���B�l�X�Ȏ�����������ŁA�w�ƂƂ̗����͑�ϓ�����ƂƂ����@�\���グ�邪�A�F�l�͌����Ĉ�l�ł͂Ȃ��A�܂����炵���\�������������Ǝv������ł���B

�u��p�ł̏C�m�_������L�v�@�@
��������U�@���c�@���
�@��w�𑲋Ƃ��Ă���10�N�B�܂�����������w�@�ɐi�w���悤�Ƃ͖��ɂ��v���܂���ł����B�������A�������ďC�m�_���������グ�āA�U��Ԃ��Ă݂�Ǝv���o���ꕶ������܂��B�u�w�ԏ������������Ƃ��Ɏt�������v(1)����́A��N���Ɏ�u�����u��r�����E��r���w���u�v�̉ۑ�}���̒��ŏo��������̂ł��B�����Ƃ͂܂��������̂Ȃ��Ƃ��낾�Ǝv���Ă�����w�@�Ɏ����i�w�����̂́A�܂��Ɏ��̒��ŏ��������������炱���A������ꂽ�@������悤�Ɏv����̂ł��B
�@�v���Ԃ�̊w���������n�܂�A���C�o�^�̂Ƃ��͖����L����܂����B�����Ă݂����Ǝv���悤�Ȗ��͓I�ȉȖڂ������������ł����̂ŁA�I�Ԃ̂ɍ����Ă��܂����̂ł��B�Ȃ�Ƃ������̌����e�[�}�ɊW������̂ɍi���āA���C�ł������܂ŗ~�����ēo�^���܂����B�������A�͂������ȏ����߂����Ă����Ɍ�����܂����B��w�@�̕��Ȃ̂ł����瓖����O�̂��Ƃł����A�ƂĂ�����̂ł��B�ʊw���ĕ�����̂Ȃ�A���ԂɂȂ�Ύ��Ƃɏo�Ȃ��ĕ�����킯�ł����A�ʐM���̏ꍇ�́A�����Ōv��𗧂Ăĕ����Ȃ���Ȃ�܂���B�����̂͊ȒP�ł����A���s����̂͂ƂĂ�����̂ł��B������ۑ肪�����Ȃ��̂��ƁA�d���̖Z�����𗝗R�ɕ����牓������A������ĕ����n�߂Ă��A���ȏ����߂��邽�тɎ����̒m�\�̌��E���v���m�炳��A���Ȃɂ́A��w�@�͖����������̂�������Ȃ��Ǝv�����Ƃ̌J��Ԃ��ł����B�������A����Ȏ����Ȃ�Ƃ����|�[�g���d�グ�邱�Ƃ��ł����̂́A���[���Ŏ��₷������ɂĂ��˂��ɂ��w����������搶���̃o�b�N�A�b�v������������ł��B�搶���̂��l�����\�ꂽ���[�������������̂́A�ƂĂ��҂����������̂ł����B�Y�킵�Ă������������|�[�g����A�V���Ȏ��_�����邱�Ƃ������A�܂��A�v�����������ق߂Ă��������ƁA�P���Ȏ��͎�������낤�Ƃ����C�ɂȂ邱�Ƃ��ł��܂����B�����̃A�N�Z�X�`�F�b�N�̎����A���w����X�N�[�����O�łł��������Ԃ̊���v���o���A��l�ŕ����Ă���̂ł͂Ȃ��̂��Ƃ����C�����ɂȂ邱�Ƃ��ł��܂����B
�@��w�@�i�w���甼�N���āA��p�ɏZ�ނ��ƂƂȂ�܂����B�ʐM���̑�w�@�łȂ���Ε��𑱂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ł��傤�B�p�\�R��������A�C���^�[�l�b�g�ɃA�N�Z�X���邱�Ƃ��ł���A���E�̂ǂ��ɂ��Ă����ł���Ƃ������Ƃɉ��߂Ċ��S���܂����B���۔�r���e�[�}���������߂ɁA��p�ɏZ�������ŁA�������Č��������[���@�艺���邱�Ƃ��ł��܂����B��w�w�Z�ɒʂ����̂ŁA�������͑����ЂŁA�����̃q���g�����炤���Ƃ��ł��܂������A�A���P�[�g�����ɋ��͂��Ă��炤���Ƃ��ł����̂ł��B�������A�������̂́A�Q�l�}���ł����B��s�����������邱�Ƃ�֘A����_���ׂ邱�ƂȂǂ́A�C���^�[�l�b�g�łł��܂������A�Q�l�}���Ɋւ��ẮA��ɓ���邱�Ƃ�����A���{�ɋA�邽�тɒ��ׂ���A���{�Ɉꎞ�A������F�l�ɗ���ʼn^��ł��������A�����Ă��炤�������@���Ȃ������̂ł��B���ɐh�������̂��A2�N��11������ł����B����̉ۑ背�|�[�g�̎Q�l�}���́A�Ȃ��Ȃ���ɓ���Ȃ��A�C�m�_���͂܂Ƃ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������ɁA��w�w�Z�ł̒�����̕����ǂ�ǂ����Ȃ�A�w�Z�̗\�K�A���K�A�ۑ背�|�[�g�A�_���Ƃ�邱�Ƃ������A�����܂łɎd�グ�邱�Ƃ��ł���̂��Ə�ɕs���ł����ς��ł����B12��31�����p�\�R����ł��Ȃ���̔N�z���ł����B�������A��p�́A2���̋����������j������̂ŁA1��1�������j���ł����A2�����畽���Ȃ̂ŐV�N�̃��[�h�͂ǂ��ɂ��Ȃ��A�������āA�������ԏサ�ĕ�����Ƃ����ߑs���ɋ���邱�ƂȂ�����i�߂邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A�N���ɂ͑�p�암�Ŕ��������n�k�ɂ��A�C��̃P�[�u�����j�����A�C���^�[�l�b�g������Ȃ���ɂ����Ȃ�Ƃ����n�v�j���O�ɂ��������܂����B���[�����Ȃ��Ȃ��͂����A�t�@�C����Y�t�����d�������[���Ȃǂ́A�����Ă���Œ��ɃC���^�[�l�b�g���Ւf����A����Ȃ��Ƃ������Ƃ������܂����B�ʏ�ʂ�ɖ߂�̂�1�����Ɣ��\����܂������A���|�[�g�Ƙ_���̊����͂�������O�B����������Ă���钆�ɋN���āA�C���^�[�l�b�g���Ȃ����肵�āA�Ȃ�Ƃ��������ɂ��ׂĂ��o���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@���w����Ƃ��́A��N�ԂƂ������Ԃ��ƂĂ��������̂Ɏv���܂������A�߂��Ă��܂������Ƃ����Ԃł����B�������A�搶���Ƃ̏o��A�ꐶ�J��Ԃ��ǂ݂����Ǝv���{�Ƃ̏o��ȂǁA�����̎����l�������傫���L���������Ƃ́A���ɂ��ς��������M�d�Ȍo���ŏ[���������Ԃł����B���x�������������ɂȂ�Ȃ�������Ƃ��C�����邱�Ƃ��ł����̂��A�w�ԏ������������Ƃ��ɍŗǂ̊w�юɂŕ����邱�Ƃ��ł������炾�Ǝv���܂��B���ꂩ��C�m�_���Ɏ��g�ޕ��ɂ́A���̒ʐM���̃����b�g��傢�Ɋ��p���ď[���������������Ă���������Ǝv���܂��B�܂��������g���C���^�[�l�b�g�̃g���u���ɏo������o������A��o���������]�T�������Ďd�グ�邱�Ƃ�����Ǝv���܂����B������|�[�g���i�܂��ꂵ���Ƃ������邩�Ƃ͎v���܂����A�h���͈̂ꎞ�����ŁA�I����Ă݂�A�ƂĂ��悢�o���ɕς��ƐM���đO�i���Ăق����Ǝv���܂��B
(1)E.�L���[�u������X(�ɓ���������)�A�w����̐^���x�A���{������

�u��e�̕����ԁv�@�@
��������U�@�ɓ��@���q
�@�v��������Q�N�O�A���q�����w�Z�֓��w����̂ɍ��킹�āA�����w�Z�ɖ߂肽���Ǝv�������Ƃ����Ƃ̎n�܂�ł����B�q���Ɏ肪������̂ŁA�����̒ʊw�͕s�\�ł����B�����ŒʐM����Ŋw�ׂ�Ƃ����T�����̂ł��B�K���ɂ��A���{��w��w�@�����Љ����Ȃ̕������ł́A�L������̌�����ʐM����Ŏ���ĉ�����A���R舒B�ȕ��͋C�̒��Ŋw�Ԃ��Ƃ��o���܂����B
�@���ɏ��N�x�́A�V�F�C�N�X�s�A�Ɣ\�Ƃ����v���������Ȃ��R���{���[�V��������{���ɑ����̂��Ƃ������Ē����܂����B���̂Ƃ��̔\�̎��̌����A���̏C�m�_���̓��@�ƂȂ����قǂł��B
�@��1�x�̃[�~�ł́A�����q�A��̎Q���ŁA�F�l�ɂ͑�ς����f�����������܂����B�搶�����͂��߃[�~�̊F�l�́A�����g�����}���ĉ�����S���犴�ӂ��Ă��܂��B����2�N�����㔼�ɂȂ��Ă���ƁA����ɂ�����Ԃ��o����悤�ɂȂ�A�q���̐����Ɋ�����������₵��������Ƃ������Ƃ���ł����B
�@�q���͊m���ɐ���������̂́A���͂���2�N�ԁA��̂ǂꂾ���w�K�o�����̂ł��傤���B�����U��Ԃ�O�ɁA�܂���e�̖����Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂������`���������Ǝv���܂��B
�@��7���Ɏq�����N�����A�����C�ɓ���܂��B
�@���̊ԂɁA�葁���x�b�h���C�N�����Ď�l�̗m���Ǝq���̗m����p�ӂ��܂��B
�@���̌㒩���т̎x�x�����A�H���������Ă���A�w�Z�܂ő���܂��B
�@�A���Ă���A�����̒����т����܂��A�����|���A�Ƃ̎G�����s���܂��B
�@�q���̂��}���̂��ƁA�T�b�J�[���̃s�A�m���̐��j���̂ƁA�j���ɂ���Ă̑���}����
�@���܂��B
�@�[���́A�����C�A�H���Ƃ߂܂��邵���A9���̏A�Q�܂Ńo�^�o�^���܂��B
�@�����Ďq���ƈꏏ�ɂ��₷�݂Ȃ����B
�@����炪���R�ƍs����킯���Ȃ��A�{������A����A������A�ӂ������肵�Ȃ���i��ł����̂ł��B���͂��A�_�����������̂ł��傤���B���ǁA�q���ƈꏏ�ɐQ�Ă���A��4���Ƃ��T���Ƃ��ɋN���ď����Ă��܂����B���A�v���Ԃ��Ă��悭�Ō�܂ł��ǂ蒅�������̂��Ǝv���܂��B�ЂƂ��ɁA�搶���̂��w���ƃ[�~�̊F�l�̂����ł��B���̏�����肵�āA�S���炨���\���グ�܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�܂��A�Ƒ��ɂ��������͂��Ă��炢�܂����B�[�~�̊ԁA�q����a�����Ă��ꂽ��l��`����ɂ́A�{���ɂ����b�ɂȂ�܂����B
�@�������ďI����Ă݂�ƁA�P�l�łȂ��������Ȃlj����Ȃ����ƂɋC�t���܂��B�K���ǂ��������ŁA�N���̏�������Ă���Ƃ������ƂɁB�P�̘_���������I���A�ł��w���Ƃ́A���ӂƂ������Ƃ�������܂���B

�u�K���Ȏ��ԁv�@�@
��������U�@�����@���q
�P�@�͂��߂Ɂ@�\�n�����N�N���Ă��܂����I�\
�@�u�n�����N�N���Ă��܂����I�v
2005�N4���A��w�@���ƂȂ��ď��߂āA�w�������ł���i���搶�̌�������K�˂��ۂɁA�������������t���B�\�n�����N�N��\�����̊o������Ă��̏�ɋ��܂��B�Ƃ������Ƃł���B
�@��w�@���w���炢�ʼn����傰���ȥ���Ƃ��v�������m��Ȃ��B�������A�J�Łu�c��W���j�A�v�ƌĂ�Ă��鎄�̐���́A�O�Y�W���̌��t����Č����u�����v�ł���B������̐l���̑����ƃo�u�������i�C�ɈЈ�����Ȃ���A��A�E�ȂǁA�l���̑�Ȑߖڂɂ́A��ɕK�v�ȏ�̊o���]�V�Ȃ�����Ă����̂ł���B�L���ȎЉ�ɐg��u���Ȃ�����ǂ������y�R�B���Ԃł̓W�F���_�[���ǂ��̂Ƙ_�c����Ă��邪�A����������W�F���_�[��u�t�F�~�j�Y���v�Ƃ��A����Ȃ̃��e�Ȃ����̕Ƃ݂ł���I�j���ٗp�@��ϓ��@�H�����牽�H����ȑO�ɁA�������ɂ͋��l�������I�����Ă䂭���߂ɂ́A�h�����낤���t���[�^�[���낤���A���ɂ́u���炵���v�蕨�ɂ������Ă�邵���Ȃ��B��������v���Ȃ��琶���Ă����̂��B����Ȏ�����w�@�ł̌����ΏۂɁu�����_�v��I�B�܂��ɕ�������̂ɑ��������u���̑I���v�������B
�Q�@�i���[�~�́u�i�K�I�J�}�W�b�N�v
�u���₨��A�|���Ȃ��B�v
�ӋC����ł���Ă��������A�i���搶�͏_�a�ȏΊ�ŏo�}���ĉ��������B��w���ォ��́A������݂̏Ί炾�B����������ނ��ďΊ�ɂȂ��Ă��܂��B���̏Ί�Ɍ��t�������A�w�������̌����ӗ~���ǂ�ǂ�����o����Ă䂭�̂ł���B���ꂼ�i�K�I�J�}�W�b�N�I���̑̌��܂��Ȃ��炢�����Љ�悤�B
�@�u�ʔ����ˁI�v�u��������Ȃ��I�v�Ƃ������@
�@�����̏����i�K�ł́A�搶�ƌ����ɂ��Ă̈Ă��A�������������ɂ��Ă̕������肷��B���̏ꍇ�́A�w�l����^���̏o���_��T��ׂ��A�ߑ�̐V����w�l�G����Ђ��[����ڂ�ʂ����B�T�ɂR��͑�w�̐}���ق⍑��}���قɒʂ��A�����ɏ������Ă��Ȃ��G���́A����w�֏o�������B������n������Ƃ͌���Ȃ����A�X�J�������B�C�������Ȃ邭�炢�n���ȍ�Ƃ��B����ł����Ƃ��������̂��i���搶�ɕ���ƁA�܂��͂��̒��ŗǂ��_�������āu�ʔ����ˁv�u������Ȃ��v�Ɗw���̓w�͂��Ί�Ŏ���ĉ�����B�J�߂��邱�ƂɂƂĂ��ア���́A���������ɂȂ�C�������N��Ԃ��Ȃ��A�搶�̃A�h�o�C�X������āA�ӋC�g�X�ƁA�X�Ȃ���n�����߂Č��������яo���Ă����̂ł������B
�A�u���₨��v�Ƃ������@
�@���ꂱ��Ǝ��n�����L�������āA�{���̌����ւƖ߂�Ȃ��Ȃ肻���Ȏ��Ɏg�p�����B�C�m�_����������ŁA�����̕����L���邱�Ƃ△�ʂ��Ǝv�����Ƃ����Ă݂邱�Ƃ���ł����B�������A���Ă��܂��Ă͑�ςȂ��ƂɂȂ�B���͕w�l�G���������Ă������A�]��ɂ��L�������ċC��������ߑ�̃G���{�⌻��̒j�������l�G���ɂ܂Ŏ��L���Ă����B�������A�i���搶�̌������ŏ��̎q�R�l�A�L���[�L���[�Ɓu�܂Ƃ��v���������Ă���p�Ɂu���₨��v�ƥ���B�������悤�ȏΊ���ׂĂ���搶�����āA���ȂЂƂ�����B���}�ɋO���C�����������̂ł������B
�B�u���v�B������A������I�v�Ƃ�������
�@�����玑�������W���Ă��_���Ƃ����������ɂ��Ȃ���Ή��ɂ��Ȃ�Ȃ��B���ɂQ�N�ڂ̉Ĉȍ~�́A���͂ɂ��邱�ƂɘJ�͂��₵�Ă䂭���Ƃ���ł���B�킩���Ă��邯��ǁA�ł������Ȃ��B���Ԃ�������������Ă������B�u���������v�Ƌ}������ē��R�̏��ŁA�i���搶�́u���v�B������A������I�v�Ɖ��x���J��Ԃ������ĉ��������B����������ƕs�v�c�Ȃ��Ƃɏ�����C�ɂȂ��Ă��܂��̂��B�����E�X�ł���B���͂Q�N���̂P�Q���ɂȂ�܂ňꕶ�����������Ƃ��ł����ɂ����B����ł����߂��Ɉׂ�������ꂽ���ƂɁA���X�Ȃ��炱�̏�Ȃ������������Ă���B
�R�@�n�b�s�[�A���[
�@��w�@�̍ŏI�ړI�́A�C�m�_���������邱�Ƃɂ��邪�A���ꂾ���Ɏ����Ă��Ăܑ͖̂Ȃ��B����������w�@�Ƃ����w�я�ɂ���̂�����A�����Ɋy�������ł͂Ȃ����I���������v���悤�ɂȂ����̂́A�Q�N���ɂȂ��Ă��炾�����B��w�@�P�N�ځA���܂��܉i���[�~�������ȊO�ɂ��Ȃ��������Ƃ�K�C�Ȗڂ𗚏C���Ȃ��������Ƃ�����A�w�����m�̐ړ_���Ȃ��܂܂P�N�Ԃ��߂������B�w��������Ƃ��ߏo����Ƃ����D�z���ɐZ��Ȃ�����A���ԂƂ̃R�~���j�P�[�V�������Ȃ����Ƃŕs�����߂����Ă����B
�u���̂܂ܑ�w�@�������I������Ⴄ�̂��Ȃ��B�₵���Ȃ�����v
����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��I�P�N�ڂɗ��C���Ȃ������K�C�Ȗڂ̃X�N�[�����O�ł́A��R�̒��ԂƉ���Ƃ��ł����̂��B
�@�R���ԂƂ����Z�����Ԃ̒��ŁA��������U�̕K�C�Ȗڂł����r�����E���w���u�̍u�`�ł́A�L���X�g���ɐG��邱�ƂŁA���Ă̕����ɂ��Ċw�B����́A�������ЂƂ�ЂƂ肪�A�����̐�����ׂ���������I�ю���Ă䂭���Ƃ���ł���Ƃ������Ƃ�Ɋ�������̂ł��������B�����āA�u�`�I����ɂ́A�u�n�b�s�[�A���[�v�Ɩ��Â���ꂽ���e�����A�����ł͑���U�̊w����搶���Ƃ��C�y�ɂ������ނ��킹��A�y�����ЂƂƂ����҂��Ă����B�u�n�b�s�[�A���[�v�͏u���Ԃɉ߂��Ă��������A���U��Ԃ��Ă݂�ƁA�X�N�[�����O�̂R���ԂƂ����S�Ă̎��Ԃ����ɂƂ��Ắu�n�b�s�[�A���[�v�������Ǝv���B
�S�@�����Ɂ\���ꂩ��C�m�_�����������A��w�@����]������ց\
�@�����͎���s�����A�͂ݎ���Ă䂭���̂��B������ƌ����āA�ЂƂ�悪��ɂȂ��Ă��܂��ẮA�����ėǂ������ւ͍s���Ȃ��B��w�@�Ŋw�Ԋw���Ƃ��āA���Ԃ�搶���i����͌����w�������݂̂Ȃ炸�j�Ƃ̌𗬂��ɂ��A�M���W���C�Â��Ă䂭���Ƃ��傫�Ȍ����͂ƂȂ�A�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���̑�w�@�́A�ʐM���̑�w�@�Ƃ������Ƃ������āA���ڃR�~���j�P�[�V��������邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ���������m��Ȃ����A���̕��A�X�N�[�����O���Ïk���ꂽ�R�~���j�P�[�V�����̏�ƂȂ��Ă���B�܂��A���[����T�C�o�[�[�~����肭���p���Ă䂭���ƂŁA�搶�⎖���X�^�b�t�A�����Ē��ԂƂ̐ϋɓI�Ȉӎv�a�ʂ��\�ł���A���[��������w�@���C�t���߂������Ƃ��ł���B
�@�����ĉ������A�w������̃��b�Z�[�W�����Ŏ���ĉ�����搶�������������Ă���B�������S�O�킸�ɂ��̑��M�{�^���������Ă��܂����I
�@�����ƁA�����ǂ��Ȃ�B�@�\�K���Ȏ��Ԃ��\

�u�{���̓�N�ԁv�@�@
�l�ԉȊw��U�@���@�J��
�@���ɂ��Ďv���o���ƁA��糃[�~�ł͋�������鎖���肾�����B���w���̓�����[�~�ւ̎Q���B���̒��Ŕ�ь��킳������Ȑ��p��B�u�ʂ����Ă��̒��Ŏ��͓�N�ԂŖ����ɏI�����鎖���o����̂��낤���H�v�u�Ƃ�ł��Ȃ��Ƃ���ɗ��Ă��܂����̂ł͂Ȃ����낤���H�v���ꂪ���̍ŏ��̖{���������B
�@���̗\���͂��镔���ł͓I�����A���镔���ł͑傫���O��Ă��܂����B
�������[�~�ł̂����𗣂��Ɠ������ԓ��m�̘a�C�\�X�Ƃ������͋C�����̃[�~�̖{���Ȃ̂��ƕ�����̂Ɏ��Ԃ͂�����Ȃ������B
�@���̃[�~�ɎQ�����邱�Ƃ͑�ςł������Ɠ����ɑ�ςȊy���݂ł��������B�Z�����d���̒��A���Ԃ��H�ʂ��A�����̃A�C�f�A���܂Ƃ߃X���C�h�ɂ��A����\����B���̍�ƂƓ����i�s�ő��̃��|�[�g�ۑ���o���A�Ƃ����悻����܂ł̐l���̒��ł��ė��Ȃ������������̓�N�Ԃł���Ă��܂��悤�Ȋ������������B�������A����͂������ċ�ɂ����ł͂Ȃ��A�ނ���w�Ԋy���݂��Ċm�F����悤�ȍ�Ƃł������B����܂Ŏ����̊w��ł������̂Ƃ͎����قɂ���w����w�Ԏ��́A���̏����ȊD�F�̔]�זE���ƂĂ��h��������̂ł������B����ɁA���ʂ̐l���𑗂��Ă��邾���ł͌����ďo����͂Ȃ������ł��낤���ԒB�Ƃ̏o��́A���́A�Ƃ�����Έ��y�ȕ����ɗ�����Ă��܂��ӑĂȐ��i�����X�ɏC�����A���|�[�g�ւ̌����͂Ƃ��Ȃ��Ă������B
�@���悢��C�m�_���������i�K�ɓ����āA�{���̂悤�ȓ��͉������Ă������B�f�[�^�̎��W�Ə����A�������瓱���o�����l�@�E�E�E�B�����x�݂͋x�݂ł����ċx�݂ɂȂ�Ȃ��قǍQ�����߂������Ă������B���̎������ԂƂ̂��Ƃ�ŋ~��ꂽ�B�����������ꂵ���킯�ł͂Ȃ��A�F�����Ȃ̂��ƁB���Ԃ̂��肪������Ɋ����鎞�Ԃł��������B
�@�_���̕��{�̒�o�A��������Ƃ����������킽���������Ԃ��߂��Ă����A�����Ɏ����Ă���B�I�Ղ̖Z�����́A�M��ɂ����������̂ł������Ƃ����ǂ��悤���Ȃ��B
�����A�������₪�I��������A�������l����ƁA���̖Z�����������Ԃ͂ƂĂ��f���炵�����Ԃ������̂��Ɗ����Ă���B
���ɂ��̓�N�͎������g�ɂ����Ă������A�D�P�Ƃ܂��ɐl���̃^�[�j���O�|�C���g���}�������ɒ��g�̔Z����N�ł������B
���X�ɁA�������ȑO�̂悤�ȕ��}�Ȃ��̂ɂȂ���鍡�A���̓�N�Ƃ����Z���A�������ƂĂ��[���������Ԃ����f���炵���P��������n�߂Ă���B
���̓�N�͎��ɂƂ��ĖY����Ȃ����Ԃł��������A���l�̂�����Ԃł������B�Ō�ɁA���C�悭�w�����Ă�����������糐搶�A���̑f���炵�����Ԃ����ɉ߂����Ă��ꂽ�������̊F����A��y�A��y�̊F����A�����Ďx���Ă��ꂽ�Ƒ��ɐS��芴�ӂ������B

�u�l���ő�̃J���`���[�X�N�[���v�@�@
�l�ԉȊw��U�@�@�_�R�@�b��
�@���傤��2�N�O�A�d���𑱂��Ȃ����w�@�ɂ��ʂ��铖��w�@�����������Ƃ��玄�̊w���������n�܂�܂����B��w����́A�i�w��]�ł������ƒ�̓s���ŏA�E���Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�A�E���ė����������炢���͑�w�@�ŕ��������Ɣ��R�ƍl���Ă��܂����B
�@���ꂩ��̎Q���ł��邽�߁A��ʖʂł̕s���͂���܂������A�ő��ɓ����ɍs�����Ƃ��Ȃ��̂ŗ��s�C���Ń[�~�ɎQ���ł��邩�ȂƂ��Ȃ�y���C�����������̂��o���Ă��܂��B
�@��w�@�����āA�F����ɂ͓�����O��������܂����̌�����������܂����B���X�����܂����A���������܂ʼn��Ƃ��d�Ԃɏ���悤�ɂȂ�܂����B�܂��A�t�̓n���n���ƎU����܂�ď��߂Č��Ċ������A�Ă̓[�~���s�œꕶ�������ɉ��v���ցA�H�͍g�t�ŊX���݂����F�ɕς��A�~�͕��̗₽����m��A����l�G�̒��Œ����悤�ŒZ���悤��2�N�Ԃ������Ǝv���܂��B
�@���|�[�g��o�����́A�d�����I�����[����T���͐}���قɈ����������āA���Ԃ��o�ƏW���͂��������A�����䂳�������邱�Ƃ������ł����B���[���̂��Ƃ蓙�A�[�~�����m�ŗ�܂����������Ƃ��A�����͈�l�ł͂Ȃ������悤�Ɋ撣���Ă����������Ƃ����N���܂ɂ��Ȃ�܂����B�݊w���ɓ]�A���z��������A�V�����E���V�����Z���Ɋ��ꂸ�̒���������������������ꂵ���������ǁA���v���ƃT�C�o�[�[�~�̔��\��|�[�g�쐬���C���]���̈�ɂȂ��Ă����̂�������܂���B
�@�J���`���[�X�N�[�����D���ŁA����܂ł��낢��ȏK�����Ɏ���o���Ă͒��f���Ă���ł����B�ł��A��w�@�͉��Ƃ������o�����ɏC���ł��܂����B��w�@���̂����ɂƂ��ẮA�l���ő�̃J���`���[�X�N�[���Ȃ̂ł��傤���B
�݊w���̏[���������ԂƓ��w���Ȃ���Ή���Ƃ̂Ȃ������搶�͂��߁A�[�~���Ƃ̏o��͉����ɂ��������Ȃ����̂ɂȂ�܂����B���ӂł��B
�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�u�����Ȃ���͂Ȃ��v�@�@
�l�ԉȊw��U�@���@��b�q
�@2�N�O��4���A���{��w�̑�w��قŊJ�u�����I�������́A��ׂ�̃x���`�ɍ����ăT���h�C�b�`��H�ׂĂ��܂����B���̉Ԃ����J�̂̂ǂ��ȓ��B�s�y�ɂ����Ƒ��A��̂Ȃ��ŁA�X�[�c�p�̎��͖��炩�ɕ����Ă����̂ł����A����Ȃ��Ƃ͂܂������C�ɂ��܂���B�����ɂ��邱�Ƃ̂ق����������������Ƃ��o���Ă��܂��B
�@�������I�@�[�~�ɎQ�����Ĝ��R�B��b�͊O����H�����A���{��ł����A�Ȃ������ς�킩��܂���B���߂�1�N�Ԃ̓e�L�X�g���Q�B�����Ɩق��ĂЂ����畷�������B���܂��ɁA�[�~�ɎQ����������ɂ͔��\�͕K�{�B���߂Ẵ[�~���\�͂T���̃T�C�o�[�[�~�ł������A���̂Ƃ��̃X���C�h�̓e�[�}�ƖړI�̂������Q���ۂ����ł��B
�@�Q�N�Ԃ̃[�~�Ŕ��\�����������������̂��ш��ɕ��ׂĂ݂܂����B�p���[�|�C���g�̃t�@�C������29�B���e���������Ă݂�ƁA����������T�C�Y�������܂������A����d�˂邲�Ƃɓ��e�����������܂Ƃ��ɂȂ��Ă��܂��B�ł��Q�N���ɂȂ�������̎����ł́A�e�[�}�ɓƗ��ϐ��Ə]���ϐ��������Ă��āA�Ȃ�ƂȂ����ʂ��Ă���悤�ɂ��݂��܂����ǁA���ۂɂ͂Ȃɂ�����������������Ȃ��A�Ƃ������قق��܂����i�H�j���_�̂܂܂�������B���X�g�X�p�[�g�̒��Ԕ��\�̂�����ł���Əœ_����܂��Ă���Ƃ��������ł��傤���B
�@���̂���̎��́A7���ɂ���Ɨ\���������I������i�K�ł��{�����̏]���ϐ������܂炸�A��ԑ��肵�������̂�����ł��Ȃ��Ƃ����W�����}�Ɋׂ��Ă��܂����B���̂���́A�u�Ō�E�ɕK�v�Ȕ\�͂��ĂȂɁH�v�u�ǂ�����Α���ł���́H�v�Ƃ������ɓ�������A�����Ȃ�����Ⴄ�����e�[�}���l�����Ⴈ�����E�E�B�Ƃ����l�����������������߂Ă��܂����B���ǁA�����͉�����肽���낤�A�Ǝ��⎩���̌J��Ԃ��ł������A���̋^��̓[�~�ɎQ�����邱�Ƃʼn������Ă����܂����B�[�~�̒��Ԃ���f�p�ŃV���[�v�Ȉӌ����A���Ƃ������甲���o���āA�܂����̃[�~�ł͂܂Â��B����ƏC���ł���̂����Ƃ�������E���グ�Ă��ꂽ��糐搶���͂��߁A���Ԃ��y�̂������ł��I���ӁI���ӁI
���̂Q�N��U��Ԃ��Ďv�����́B�Ƃɂ����[�~�ɎQ�����āA�ӌ������킷���Ƃ̑���B�͂��߂̂P�N�ԁA�u�����������̂��킩��Ȃ��v�Ƃ���ꑱ���A�r���Ŏ����ł�������������������Ȃ��Ȃ�B�������Ȃ�Ƃ��[�~�ɎQ���������܂����B�Q�������͂��悤�ƐS�Ɍ��߂Ă��܂����B���܂ɂȂ�A���ꂪ��Ԃ̋ߓ��������Ɗ����܂��B�����ĉ��������ԂƂ̏o��B��������ƃ��[�������Ȃ���A�g�у��[���̂��鎞��ł悩�����B�Ɣ邩�Ɏv�����Ƃ������B�����Ȃ���͂Ȃ��Ƃ������Ƃ���������2�N�Ԃł����B
�@�C�m�͌����̕��@���w�ԂƂ���B��糐搶��������������錾�t�ł��B���̑�w�@�ł̊w�т�����ɐςݏd�˂āA�����Ƃ����ƌ���ɊҌ��ł��錤���𑱂��Ă�����悤�ɁA���ꂩ����K���o���}�X�B

�u���|�[�g�̌����́v�@�@
�l�ԉȊw��U�@�@�����@�N��
�@�ʐM����w�@�Ƃ������t�ɗU���ċC�y�ȋC�����œ��w�B����1�炢���Ȍ��r�Ƃ��������̂��Ƃɓ����ɍs���āA���łɔ����������̐H�ׂĥ���Ȃ�Ďv���Ă��܂����B����ȊÂ��������ł��ӂ��ꂽ�̂��A�P�N���̑O�����|�[�g��o�P�����O�B�u���낻�냌�|�[�g�n�߂Ȃ��ƂȂ��v�Ǝv���āA���|�[�g��o�����܂ł̓��������|�[�g��o�{���Ŋ����Ă݂���A�d��ɂ͋C�����������Ȑ������\������Ă��܂����B�u���̃��|�[�g���I��点�邽�߂ɂ͑��ɃX�g���X�������Ă͂����Ȃ��v�Ƃ�������Ȕ��f�̂��ƁA�����R���r�j�ő�ʂ̂��َq���w�����A���َq��H�ׂȂ��烌�|�[�g�ɗ�ޓ��X�������܂����B�����ƁA�R���r�j�̓X������ɂ͑�Ƒ����Ǝv���Ă������Ƃł��傤�B���َq�̐��ʂ������Ă��A�����ɒ�o�����O�ɑS�Ă��o���I���邱�Ƃ��ł��܂������A�����ɑ̏d�����Ƃ������܂��܂ł��Ă��܂����B
�@�u��������̓R�c�R�c�Ɗ撣�邼�I�v�Ƃ��������𗧂Ă����̂́A�L����Q���Ǝv�����炢�ɂ���Ȑ����͂�������Y��Ă��܂��A�܂��P�����O�ɓd���e���ċC�����������ɁB��������َq�̗͂���Ė����ɏ���܂������A�̏d�v�ɏ������T�L���������Ă��邱�Ƃ��������A�܂��C�����������ɂȂ��Ă��܂��܂����i�Q�N���̏C�m�_���̍쐬�̂Ƃ��ɂ����x���C�����������܂������j�B
�@���َq�̗͂���ă��|�[�g�������グ���Ƃ������Ƃ͏�k�ɂ��Ă��A�d�������Ȃ���Ƃ����Ŗ����ɑ�w�@���C���ł����̂́A�[�~�̓��������m�ŘA���������Ă������Ƃ��傫�������̂��ȂƎv���܂��B�ʐM���Ƃ����V�X�e���ł́A����ɂ����Ĉ�l�Ŋ撣��Ȃ�������Ȃ��Ƃ������Ƃ����܂̗v���Ƃ��đ傫���悤�Ɏv���܂��B�[�~�̓��������m�ŘA������荇���ė�܂��������ƂŁA���Ƃ��Ō�܂ł���ꂽ�悤�ȋC�����Ă��܂��B�Ō�ɁA�ǂ����܂ꂽ�Ƃ��ɂ������X�g�X�p�[�g���Ȃ����B�����e�Ɏw�����Ă�����������糐搶�A�������̊F����A�[�~�̕��X�Ɋ��ӂ������܂��B
�@���x�͑������̏d��߂��ׂ��f�H����ɂł��s�������Ȃƌv�悵�Ă��܂��B
�@

�u�n�v�j���O���Ă�����̂ł��ˁI�v�@�@
�l�ԉȊw��U�@�����@����
�@���́A�������肬��ɂȂ��Ă���Q�ĂĂ��n�߂�X��������̂ŁA���߂ɂ��Ȃ��Ă͂ƁA�P�N�̂P�P���Ɍ����P�̒��������{���ĂQ�N�̂S���ɏW�v���A�T�����猤���Q�����{���ĂX���Ɍ��ʂ��܂Ƃ߂܂����B�������A�P�O���̒��Ԕ��\��Ɍ��Ȃ��Ă���P�Q���܂Ŏ�ɂ����A�P�Q���ɂȂ��Ă������Ė��ƍl�@�ɒ��肵�n�߂܂����B���߂āA���e��N���̋x�݂ɓ���܂łɁA�S���̐搶�ɒ�o�����������̂ł����A����l�@�Ɏ��Ԃ��������Ă��܂��܂����B���̂��߁A�N���N�n�͂��[���ƃp�\�R���ɂނ����đ��e����o�ł����̂����U�ł����B�{���Ɉɍ�搶�\����܂���ł����B
�@���́A���x���C�m�_���̊����͖������ȂƎv���āA�Q�N�ł̑��Ƃ�������߂邱�Ƃ�����܂����B����Ȏ��A�͂ɂȂ����̂��A�[�~�̓����̊F�l��ɍ�搶�ł����B�����ŁA���̕���L���L�O�Ɏc���܂��B
�������P�i���L�����⎆�@�j�ł̃G�s�\�[�h��
�@���L�����⎆�́A���e���Ƃ肠�����A�����̎�|�ɂ��������̎��⍀�ڂ��ڂ��Ă����s��������R�I�����āA���Ƃ́A���S�Ǝv���Ă��܂����B�������A���́g�Ƃ肠�����h���ߎS�Ȍ��ʂɁE�E�E�A���E�l�@���������_�̍�N�̂P�Q�����{�ɁA���̎Q�l�ɂ����������A���P�[�g�̈�Ă̐e�ł��邱�ƂɋC�Â����̂ł��B�ƂĂ�������܂����B���ꂩ��A�A���P�[�g�̎Y�݂̐e��T���̂���ςł����B�����ł��A�����Q�l�ɂ��Ă����̂́A��Ă̐e����ł����B���̎��A���⍀�ڂ̏o�T�𑁊��ɖ��m�ɂ��Ă��������A�ǂ������Ɣ��Ȃ��܂����B�i�����炢�ł����ˁj
�@�����@�Ŏ��{���悤���A���������@�Łu���S���X����h�~�̂��߂ɋ������ǂ��v�Ɗw�сASPSS�̍u�K��ł́A�u���v�I�Ɋ��p���邽�߂ɂ͂T���@�ȏオ�]�܂����v�A�Ƃ������Ƃ́A�U���@�ł����A���̑Ώێ҂́A���Z�ȕ��X�Ȃ̂łU���@���˗����邱�Ƃ��S�O���ĂT���@�Ŏ��{���܂����B���̌��ʁA�قƂ�ǁg�P�h�A�g�R�h�A�g�T�h�Ƃ����l���������܂����B�������ǂ��l���ĂP�A�R�A�T��������܂���ˁB�����āA���̌����łU���@�̃A���P�[�g�����{�����Ƃ���A�U���@�ł����v�ł����B���̍l�������ł����ˁB���S���X����h�����߂ɂ́A�U���@�ł��\�����v�ł����B
�@���⎆�̈���́A���̐ߖ�̂��߂ɗ��ʈ�������āA���{�������ʁA�Ō�̗��ʂ�Y��Ă��܂��l�����l�����āA�V���b�N�ł����ˁB�܂�A���⎆�̈���ŗ��ʂɈ������ꍇ�́A�Ō�̗��ʂ��g��Ȃ����������ł��ˁB
�������Q�i���������@�j�ł̃G�s�\�[�h��
�@���������ł́A���Ƃ��V������̉ċG�x�ɂɓ���O�ɂ��ׂĂ̒������I�����Ȃ��ƁA�X�̃C�x���g�₻�ꂼ��ċG�x�ɂ��Ƃ邽�߂ɁA�l�����ŏ����̐l���ł̋Ɩ��ƂȂ邽�߁A�������ʂɉe�����ł�B���̂��߁A�T���̏��{�ɒ����˗��������B���́A�X�Ɏ��ʂŎ������͎҂��W���邱�Ƃɂ��Ă����̂ł����A�����˗����ɏW����������J�����ƂƂȂ����B���̎��_����A������p�̃|�X�^�[���쐬���Đ�������Q�{�݂Q���{�����B���̌��ʁA������́A�T�������ƂU�����{�ɂ`�{�݂́A�P��ڂR���A�Q��ڂT���A�a�{�݂́A�P��ڂQ���A�Q��ڂO���ƍ��v�ł��P�O���ł����B����ł́A���������̓����Q�E�����`�E�����a�̂R�Q���v�悵�āA�Œ�ł��T�O�������҂��Ă����̂ŁA�S�O�����s�����Ă��܂��B���͂Ƃɂ���������܂����B�܂��������Q�����{�ł��Ȃ��B
�����ŁA�Ƃɂ����l�������Ȃ��B�������A�����Q�̒������Ԃ��A�����f�U�C���FABA�f�U�C����\�肵�Ă��邽�߂ɁA�Œ�ł��Q�T�Ԃ͂�����B����ɁA�����Ώێ҂���Ζ����Ȃ̂ŁA�˗������ɂ�������������B�Ƃɂ������̓�����A�x�ݎ��Ԃ�A�t�^�[�T�𗘗p���āA�e�������߂���A�X�l�Ɏ��������˗��������B�Q�{�݂P�P�������߂���A�܂�ŃZ�[���X�}���̂悤�ł������B���ɂ́A�~�[�e�B���O�̎��ԂƏd�Ȃ�A�I���̂�҂��Ă݂���A�e�����Œm���Ă���l�̋Ζ����čēx�K�₵����A����͎d�����Ȃ̂ŁA�����̐����ɂ͂V�`�W�������邽�߂ɁA����̃A�|���Ƃ�����A���x�{�ݓ������낤�낵�����Ƃ�����܂���B�@
���̌��ʁA�T�T���̋��͎҂�����ꂽ�B�������A���ɂ́A������]�Ŗ��O���Ȃ�������A�������@���A���}�e���s�[�ɑ}��������@�ƈ��̂ڂ��^�b�v����v�l��Ö@�̂Q���v�悵�Ă��邱�Ƃ�b���Ă����̂ŁA�u�A���}��������v�Ƃ��u�A���}�͊��k�n�������߂Ȃ́v�ȂǁA���܂��܂Ō��ʓI�ɂT�O���̋��͎҂ƂȂ����B
�@���Ă��āA���ꂩ�炪�܂���ςł����B�܂��O���[�v���������āA�T�O���ɌʂɎ��������˗������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�����Ώێ҂̋Ζ��т��m�F���Ȃ���A�Q�{�݂P�P�����������߂���A�����˗������łU���P�X������J�n���ĂP�T�Ԃ͂�����܂����B����ŁA����S�A�ŏI�����I���\��́A�V���P���ƂȂ�A�܂��܂��A����Ɏ��Ԃ�������܂����B�U���̈ꃖ���Ԃ́A�d�����������̕�����Ȗ����ł����B
�����Ԕ��\��̃G�s�\�[�h��
�@�P�O���̒��{�ɒ��Ԕ��\�����܂����B�������A���Ԕ��\��Ŕ��\����\��ł����B�������A���Ԕ��\��̑O���Ɏ�l���ꔑ���@���܂����B���̎��́A�܂��ǂ������̂ł����A�����̗[���ɒ��w�Q�N���̑��q���u�������ɂ��I�v�ƌ����n�߂܂����B���̎����́A�܂������̕��ɂ��ȂƎv���Ă��܂����B�������A���q�̕��ɂ́A��̂X���ɂȂ��Ă������܂炸�A���ɂ̕��ʂ���������E�������ֈړ����Ă��܂��B���́A�u���������āA�������A������a�@�ɍs���A�������p���Ă��炦�āA�����͔��\��ɍs���邼�I�v�Ƒ��q��A��āA��Ԃ̊O���Ɏ�f���܂����B�Ƃ��낪�A�f�@���Č������Đf�f����ē��@�����肵���̂��A���\����̂P���ŁA���@�����̂��R���A��p�����Αт̈�t�����Ă�����{���邱�ƂɂȂ�܂����B���ƂW�̖����ƂɋA�����̂́A���\����̒��̂R���������ł��傤���H���̎��A���Ԕ��\��̔��\��f�O���āA�ɍ�搶�Ǝ����ǂɒ��Ԕ��\��̌��Ȃ̃��[���𑗂�܂����B���ƈɍ�搶�́A����Ȏ��ԂȂ̂ɁA�����ɕԎ�������܂����B�����A�C�ɂ����Ă��������Ė{���ɂт����肵�܂����B
�@���̌�A���̃I�y���̏o���̂��߂ɖ����S�̐����𑱂��A�������d���͏�ł��B���̌��ʁA�C�m�_���́A�܂�����������ƂȂ�Q�������߂��A�P�Q���̃[�~�ŁA�ʐڎ���̗��K�E�E�E�E�B���́A�����̏C�m�_���̓��e�������Y��Ă��܂����悤�ŁA����Ղ�Ղ�̔��\���K�ƂȂ��Ď��Ȍ����Ɋׂ��Ă��܂��܂����B�����ŁA�C�m�_���́A�Q�T�ԂɈ�x�͖ڂ�ʂ��ׂ��������Ɣ��Ȃ��܂����B
�@�����ɁA�����ɁA�������N���邩�킩��Ȃ��ł��ˁB�������A�����ɉ������c��Ȃ��悤�ɁA�Ō�܂ł�����߂Ȃ��������厖�ł��ˁB�Ō�܂ŁA������ĉ��������ɍ�搶�A�{���ɗL��������܂����B

�u�C�_���M�ɋ�藧�Ă����́v�@�@
�l�ԉȊw��U�@���V�@�f��
�@���w�����̎��̌����e�[�}�́u���̌���Ɩ��_�ɂ��āv�Ƃ������x�̑�G�c�Ȃ��̂ł����B����������@�����R�Ƃ��Ă��܂����B���`�x�[�V���������͂������̂ł����A�ʐڃ[�~�E�T�C�o�[�[�~�Ō����e�[�}�ɂ��Ĕ��\���J��Ԃ������ɁA�l�I�Ȏv�����݂�A�t���Ă��n�̐m���ł͗ǂ������͂ł��Ȃ��Ƃ��������͂�����Ƃ킩���Ă��܂����B������������i�߂Ă����ɂ́A�����@�̊�{�I�ȍl������S���w�̊�b�m���A�����ĉ������Ȋw�I�Ȏv�l��{���K�v������܂����B�����̊�b�m���ƂȂ����̂́A��͂背�|�[�g�w�K�ł����B�͂��߂ĐS���w�⌤���@��{�i�I�Ɋw�Ԏ��ɂƂ��āA�w��Q�l�}���̓��e�̓X���[�Y�ɓ��ɓ��炸�A�˘f���Ă��肢�܂����B���ɂ́A�Ȃ�Ď����n�߂Ă��܂����̂��ƁA����̔O�������Ԏ����炠��܂����B�d�������Ȃ���̏C�w�ł��������߁A�w�K���Ԃ��m�ۂ��邽�߂ɁA��肽�����Ƃ��䖝���A�ǂ���������C���ێ��ł��邩�l���܂����B�Ⴆ�A�P�N�O���̓��|�[�g�������I�������A�������f������Ă������A�Ǝ����Ɋy���݂�^����������܂����B�������A�s�v�c�Ȃ��ƂɌ���ɂȂ�ƁA�w�K�Ɏ��g�݁A�ۑ�𗝉����鎖���̂��A�������ɕω����Ă��܂����B
�@�Q�N���ɂȂ�ƁA�e�[�}�����X�ɍi���Ă��āu�g�у��[���̉����������Ԃɂ���ۂ̕ω��v�ɂ��Č������悤�ƍl����悤�ɂȂ�܂����B�����ԐM�̕������[���̈�ۂ��ǂ��Ȃ�Ƃ�����ʓI�Ȋ��o���A�����Ƃ��Đ��������Ȃ̂��A���ؓI�ɖ��炩�ɂł��Ȃ����ƍl�����̂ł��B�������A�ǂ̂悤�Ȍ������@���K�Ȃ̂��S�����������Ȃ������̂ŁA��s�����ׂ���A�����Ȏ��O�������J��Ԃ����肵�܂����B����Ȓ�����A���ƂȂ��������@�̓��������Ă��āA�����ɑ���ӗ~�����ɓ��ɑ������Ă��܂����B�����āA�ŏI�I�ɂ͌����̗�����A���O�����E�\�������E�{�����E�����Ƃ��鎖�Ɍ��߂܂����B�����W�{���̖ڕW�́A���v�I�ɁA�������͂̂���1,000���Ƃ��A���̒������ʂ����ɍŏI�I�Ɏ������s���Ƃ����ؓ��ɂȂ�܂����B�������A���e����̓I�ɂȂ�ɂ�āA���X�ɋ��|�����N���Ă��܂����B����́A�菇���ԈႦ����A�����̃f�[�^�����ʂɂȂ��Ă��܂��A�܂��͓K�Ȍ��ʂ��o�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ����|���ł����B����Ȏ��A�����~���Ă��ꂽ�̂́A�[�~�̊F�����搶�̃A�h�o�C�X�ł����B�����ł��s���Ȏ�������ƁA�[�~��[�������p���ĊF����ɏ��������߁A����������Ă��������܂����B�������̂́A�����̃[�~�������łȂ��A�C�����E�������̕������܂ł��A�T�|�[�g���Ă����������Ƃ������ł����B�ʐM���̑�w�@�Ȃ̂ŁA�ǓƂȕ��������Ȃ�Ǝv���Ă����̂ł����A�{���ɗ\�z�O�ł����B���A�l�ŁA����Ȏ��ł������̔@���ł͂���܂����A������i�߂čs�����Ƃ��ł��܂����B�����ł́A�[�~���E�C�����E�������̕���F�l�A����ɂ͉͓��搶�E��糐搶�܂ł����͂��Ă�������A�ŏI�I��1,516�ʂ�������邱�Ƃ��ł��܂����B�f�[�^�͎��͂ł��ׂĂ���͂��邱�Ƃ́A�ǂ��l���Ă��s�\�ł��������߁A�E��̓�����w������̎����鎖�ɂ��܂����B�c�傩�ׂ����f�[�^�ł��邽�߁A��̉��l�̕�����`���Ă���邩�s���ł������A���肪�������Ƃɑ����̕��̏��͂�����A�\�z���Z���Ԃœ��͍�Ƃ��I�����܂����B�ŏI�i�K�ł�������Q���҂̊m�ۂ��A���͂��Ă����Ƃ����w�������l����������Ă��ꂽ�̂ŁA�����������܂����B�����ł́A�ԐM���Ԃ̓������K�v�ł��������߁A�F�l�̃v���O���}�[���A�V�X�e���J���ɋ��͂��Ă���܂����B�ꎞ�͂ǂ��Ȃ邩�Ǝv���܂������A���ʓI�Ƀf�[�^�͔�r�I���m�Ȃ��̂������܂����B
�@���̎��_�Œ�o����܂ł̊����͂P��������Ă��܂����B��{�I�ɃY�{���ł̂�т艮�Ȃ̂ł����A���̎��͕s�v�c�ƏW���͂����܂�܂����B����ȗ͂͂ǂ����痈��̂��A������l����ƕs�v�c�Ɏv���܂��B�������������M�ɋ�藧�ĂĂ����Ɗ����Ă��܂��B����́A�������g����O���N������I�ȓ��@�t���ł����B�����āA�����^���Ă��ꂽ�̂́A���͂̊F����̑��݂ł����B�����܂Ŏx���Ă�������̂�����A���Ƃ��_���ɂ܂Ƃ߂����Ǝv�����̂ł��B�������������@�ɑ���A�^���͉��Ȃ̂���T�����Ă䂭��������Ȃɂ��y�������̂��Ɗ�������悤�ɂȂ����̂��A�x���Ă��ꂽ�F����̂��A�ł��B�܂��A"evidence-based"�̍l�������͂��߂Ƃ��錤���̎葱���́A���q�ϓI�Ő��������ʂւƎ����Ă���܂����B
�@�C�m�_���̐��{���o����i�K�ɂȂ�A���̂Q�N�ԂŊw�����v���o���ƁA���ׂĂ�����̐l���ɖ𗧂��Ƃ��肾�Ɗ����Ă��܂��B���S�̒��́A�C���ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����₵��������܂����A���g����B�����A�����āA�����A�[�~�̊F�����搶�E�������Ă��ꂽ���ׂĂ̊F����ɑ��銴�ӂ̔O�ň��Ă��܂��B
�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
|