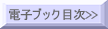�u�F����̋��͂Ŋ��������_���v �@�@
���ۏ���U�@�����@�R�O�@
�@���̓T�����[�}�����N�ɂȂ��Ă������̒ʐM����w�ŗ��j�w���w�сA���̉����Ƃ��ē���w�@�ŕ������Ă����������B�v���u�E���\�N�O�v�̍��Z����ɂ́A�u��w�@�v�Ŋw�ׂ�ȂǂƂ������Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ������B���ꂪ�C�m�_���������I�������A����ő�w�@���C���ł���̂��Ǝv���Ɓu���ł͂Ȃ����v�Ǝv����قNJ����������ݏグ�Ă���B
�@ �������A�_���������グ��܂ł̓��̂�͋��̘A���ł������B�܂����w�ł��邩�ǂ��������ł������B�p��͂܂������ʖځA�_�������Ȃō�邱�Ƃ�����A�_���e�[�}�����܂��ĂȂ��Ƃ����L�l�ł������B�����œ���ʐM���畔�Z�F��̎��������Ȃ����Ă���Α�O�Y�搶�i����w�@������j�ɑ��k�����Ƃ���u���w����Ȃ獑�ۏ����U���w�����[�~�x�ɏ������邱�ƂɂȂ邾�낤�v�Ƃ������Ƃł������B
�@ ����Ȃ�C�m�_���͒����W�̖����e�[�}�ɂ��悤�ƌ��߂��B�����Ē����W�Ȃ�A�q���̍�����^��Ɋ����Ă����u�푈���Ȃ��N�������̂��v�Ƃ����������̋@��ɍl���Ă݂悤�Ǝv�����B����Ŏ��͘_���e�[�}���u���B���ςɂ��Ă̈�l�@�v�Ƃ��ēo�^�����B�������A�ΐ搶����́u�e�[�}���傫������A�����ƍi�荞�߁v�Ƃ̃A�h�o�C�X������A���̌�A�e�[�}���u���B���ς̖��_�ɂ��Ă̈�l�@�v�ƕύX�����B���̎��_�ł́A�ߌ���j�̒m�����܂������Ȃ������̂ŁA���܂��_�q�ł��邩�ǂ������ɐS�z�ł������B�����떞�B�ɂ�����{�̌R�����Ȃ��u�֓��R�v�Ƃ����̂����m��Ȃ������̂����疳�����Ȃ������B
�@ ��N�ڂ͌܉Ȗڂ̃��|�[�g��o�ɂقƂ�ǂ̐��͂��X�������B�^����ꂽ���ނ͍u�`�T�v�����Ȃ��班�Ȃ��Ƃ��܉�͓ǂݕԂ����B�������̂ł͏\�炢�ǂB����ł��_�_�����߂Ȃ����̂��������B���X�u�w�p�_���͓ǂސl�ɕ�����Ȃ��悤�ɏ������̂Ȃ̂��v�ƍ��߂����C�����ɂȂ邱�Ƃ��������B����ł����Ƃ��܉Ȗڂ̃��|�[�g���o���邱�Ƃ��o�����B
�@ �C�m�_���̂��Ƃ��C�ɂȂ��Ă����̂ŁA��N�ڂ̓��|�[�g�̍쐬�ƕ��s���Ę_���e�[�}�ɊW�������ȕ����̎��W��Ƃ��s�����B���W��ƂƂ����Ă��ڂ����ǂޗ]�T�͂Ȃ������̂ŁA�}���قŘ_���e�[�}�ɊW�������ȎQ�l�����ɂ����Ɩڂ�ʂ��A�Y��Ȃ��悤�ɖ{�̑薼�Ɩڎ����R�s�[�����B�܂��A�[�~�Ȃǂœs�S�ɍs�����Ƃ��́A�W���Ђ��o���邾���w�����A��ʂ�ǂނ悤�ɂ����B�������ł��Ȃ�̎������茳�ɏW�܂����B
�@ ���|�[�g��o�ɖړr�������\������{�i�I�ɘ_���̍쐬�����Ɏ��|�������B�ŏ��ɍs�����͎̂Q�l�����̓ǂݍ��݂ł������B�}���قő薼�Ɩڎ����R�s�[���Ă������{��������x�}���ق֍s���ēǂ݁A�d�v�Ǝv����Ƃ���̓R�s�[������悤�ɂ����B�Ƃ��낪�A���ׂẲӏ����d�v�Ǝv���Ă��܂��A���ǂ��ׂĂ��R�s�[����j�ڂɂȂ邱�Ƃ������������B
�@ �������Ė��B���ς̑S�̑������߂��i�K�Ř_���̃X�g�[���[���Ɏ��|�������B�X�g�[���[�́A�u�܂������v�̂Ƃ���Ŗ���N�A���́A���͂Ŏ����W�A��O�́A��l�͂ōl�������q�ׂ�Ƃ����\�z�Ŗڎ�������A�́u�����[�~�v�ɒ�o�����B�����[�~�ł͑��������A�[�~������u�܂��A�������낤�v�Ƃ��������t�ƁA�u���ɑ�O�͂Ƒ�l�͂�������d�v�ȕ���������A�����Ŏ����̍l���m�ɏq�ׂ�悤�Ɂv�Ƃ̃A�h�o�C�X���A��悸�z�b�g�����Ȃł��낵���̂����ł��͂�����Ɣ]���ɏĂ����Ă���B
�@ ���͋ߓ��[�~�Ƒ����[�~�Ƃ�����̃[�~�ɏ��������Ă��������A��όb�܂ꂽ���Ř_���������i�߂邱�Ƃ��ł����B�ߓ��[�~�ł́A�����̃[�~���㖼�ɂ��p�\�R�����g�����u�T�C�o�[�[�~�v���������s��ꂽ�B���͂��̃[�~�œ����̐l��������s��������A����ɂ���Ď����ł͋C�Â��Ȃ��������_��_���ɔ��f���邱�Ƃ��ł����B�T�C�o�[�[�~�͊炪�����Ȃ��Ƃ������_�����邪�A������Ă��邤���ɂ���e���݂��킫�A�������������Ƃ��ċC�y�ɘb���o����悤�ɂȂ����B����͑傫�Ȏ��n�ł������B
�@ �܂������[�~�͐搶�w�Ɍb�܂�Ă����B�[�~������������l�i�ォ��O�l�ɂȂ����j�Ȃ̂ɐ搶���͋ߓ������A���������Ƃ�����l�̋����̂ق��ɁA�[�~���A������m�ے��̎R�{����A�܊������V������̌ܖ��̕��������̃[�~�ɎQ������A�_���̐i����������������Ă����������B���ɂ́u�H������Ȃ��v�u��������v�Ȃǂ̎w�E���A�����̃[�~�ɕύX�������̂��Ē�o���āA�܂��u�]����Ƃ�����Ƃ��J��Ԃ����B���ɑ�O�́A��l�͂ɂȂ�Ɨ��j�ς������ɗ���ł���̂ŁA���̎w�E�͈�i�Ɖs���Ȃ����B�ꎞ�͂ǂ������悢�̂��܂�����������Ȃ��Ȃ�A�p�\�R���̑O�ň�����Y���Ƃ��������B
�@ ����Ŏv�����̂́u�����̘_�_�͕ς��Ȃ��ق����ǂ��v�Ƃ������Ƃł������B�_�_�Ƃ����̂́A�u���̘_���łȂɂ�i���������v�Ƃ��������Ȃ�̍l�����E�咣�̒���_�ł���A���ꂪ�ς��ƑS�̂̍\�����̂��̂��ς���Ă��܂����ƂɂȂ�B���ꂾ���Ɂu�܂������v�͏d�v���Ɗ������B�_���𒅎肷��ɂ������ẮA�܂��u�܂������v�Ɓu�ڎ��v�Ɏ��Ԃ������A�\���ɂ��荇�킹�Ă���{�_�̏��q�ɓ���ׂ��������B���ꂪ���̔��ȓ_�ł���B
�@ ���l����ƁA���̓�N�Ԃ͎R�o��Ɠ����������B�d���ו���w�����ăq�[�q�[�����Ȃ���R��o���Ă���A����Ȋ����������B���͒���ɂ��ǂ蒅�����u�����𖡂���Ă���B�ǂ��������F����̂��A�Ɗ��ӂ��Ă���B���Ɏ��̂悤�Ȃ��̂�������w�@�Ɏ���Ă�������A���������w�������������ߓ������A���������ɐS��肨��\���グ�܂��B
�@ �܂������[�~�����Z�߂Ă����������ΐ搶�ɂ͂��Ƃ̂ق������b�ɂȂ����B�ΐ搶�͎������̃[�~�����▅��J���悤�Ɍ��Ă����������B�Ō�ɂ͌뎚�E�E���܂Ŋm�F���Ă����������B���͐ΐ搶�ɏo���Ȃ���A��w�@�ɓ��w���邱�Ƃ��A�C�����邱�Ƃ����炭�ł��Ȃ������ł��낤�Ǝv���B������v���Ǝ��͐ΐ搶�ɏo������Ƃ��A���̐l���ōō��̍K�^�������Ǝv���Ă���B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�@ ����ő�w�@�͈ꉞ�I���̂�������Ȃ��B�������A���͏C�m�_���Ɏ��g��ł��āA�܂��V���ȋ^�₪�N���Ă����B���͋ߌ���j�𗝉����悤�Ƃ��ďC�m�_���Ɏ��g����ł��������A�t�ɂ킩��Ȃ����Ƃ������Ȃ����Ƃ����̂�����ł���B�C�m�_���ł͈ꉞ���_�炵�����̂��o���Ă��������A���ׂĂɂ킽���Ĕ[�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�u�Ȃ������Ȃ����̂��v�Ƃ������_�Ō���ƁA�܂��܂�������Ȃ����Ƃ������B����̃e�[�}�ɂ��ẮA���ꂩ�������ɂ��낢��Ȏ��_���猤����[�߂悤�Ǝv���Ă���B

�u�[�������X�N�[�����C�t�v�@�@
���ۏ���U�@���������Y
�@�Q�O�O�U�N�Q���P�P���A�ۑ��̂��߂ɐ����ɐ��{���ׂ��C�m�_�����e��E�e���邱�Ƃ��ł����B�����A���B�ő�w�@�����ۂɗX���B���{��o�������P�R���B�j�n��̓����B�����ĖJ�߂���b�ł͂Ȃ����Ƃ͏��m���Ă���B
�@����ł��u�����̂��Ƃ͒I�ɏグ�āv�i���߂�Ȃ����j�{�w��������C�m�_���쐬�܂Ŋw�������ɉ����āA���n��ɏq�ׂ�B���ɖ{�w���u�肷����₱�ꂩ��C�m�_���Ɏ��g�܂����ɂƂ��ĎQ�l�ɂȂ�K���ł���B�������C�m�_���쐬��A�K�v�ƂȂ�Z�p�I�ȋL�q�͂��Ȃ��i�l�l�ɂ��b�ł���悤�ȑ�w�@�����͑����Ă��܂���j �B
�@ �{�w�����ɗՂލہu�����v�揑�v�̒�o�����߂��邪�A���̏ꍇ�́u�ߑ㐭���v���C�߂���肾�����̂Łu�ߑ㐭���Ɛ����I���S�w�v�ɂ��č쐬�����B
�@ �w�������́A�w������Ɋw�u�����w�v�̋��ȏ��i�w���㐭���̊�{�m���x�k���o�Łj�������ꂽ�֍���O�v�搶�i�w������̉��t�Ɛ�y��y�̊W�j�ɂ��肢�������ł������B
�@ �֍��搶�Ƃ͈�ʎ����Ȃ��������A�@�̈ē��ɐ搶�̂����O�������u�w�������ɂȂ��Ă���������v�ƈ���I�ɍl�����B
�@ �u�菑���o��A��w�@�����ۂ��d�b�������������B�u�֍��搶�͒ʐM����w���̋����ƌ��C����邽�߃[�~��S������Ȃ��v�Ƃ������e�ł������B
�@ ����Ɂu���A�w�����������߂ĉ������v
�@ ��l�Ɂu�ߓ��_�C�n�N�搶�̃[�~����]���܂��v
�u�ߓ��唎�i���ƂЂ�j�搶�ł����v
�u�����͂��v
�u�u�菑�ɂ��ẮA���ߐ肪�߂��̂Ō����v�揑�͂��̂܂܂Ō��\�ł��v
�@ �ߓ��搶�Ƃ͈���I�Ȃ��t���������������B���Z������w�������_�x�w���Y�t�H�x�w�\�̐^���x�i�Q�O�O�S�N�R���ō����x���j�ȂǁA���{���\���鑍���G�����u�ǂ��Ă������ɂƂ��āu�ߓ��_�C�n�N�ҏW���v�̂����O�͒m���Ă����B
�@ �搶���ҏW������ɐ��ɖ₤���w�]���x�i���C�^�[�͗��ԗ��j��ҏW�҂Ƃ��ĎQ�^�����w�����x�i�k���L��j�Ȃǂ̐V�����w�����Ă����B
�@ ���������B���_���͂Q��o��i�@�ł͓������͌��\���Ȃ����j�Ȃ̂œ��e�ɂ��Ă͐G��Ȃ��j���ꂽ�B��������ł́A�����v�揑�ɉ����Đ������Ȃ�������Ȃ����A�O�q��������ɂ��u�Ԃ����{�ԁv�ŗՂB
�@ ���������͐H���ׂ�B���H�͋߂��̎��i���Łu�V���v�o�ϊw���P�K�̋i�����Łu�^���R�p�X�^�Z�b�g�v�B
�@ �ߓ��搶�ƍ��j�����搶���������ł������B
�@ �ߓ��搶�́A�J����ԁu�N�A�Ȃ�Ŕw�L�łȂ��́B�w�L�𒅂Ă��Ȃ��̂͌N��������B�������Ō����Ă����Ȃ����ǁv
�@���̌�A���R���ɎQ�����邽�ߔw�L�𒅂Ă��Ȃ������B
�u������������Ƃ͂��l�т��܂��B�����Ĕw�L�𒅂܂���ł����B�w������̎�X�����C���Ō�������ɗՂނ��߂ł��v�ꂵ����̓��فB
�@ ����̓��e�ɂ��Ă͐G��Ȃ����A���Z������w���{�o�ϐV���x����G�������ǂ��Ă����|��b�����B���j�搶�́u���n�������̂ł��ˁv�Ƃ������t�����Ɏc�����B�@
�@ �����Ȏ��ł͂��������A�������ł͋ߓ��[�~�̓������ƂȂ鋴�{������n糍K�Y���i���[�~�j�Ɛe�����Ȃ邱�Ƃ��ł����B�J�u���͎��p�Ō��Ȃ����B
�@ �Q�O�O�S�N�S���Q�O���B�p�\�R�����C�P���ځB�p�\�R���̊�{���삩�狳���Ă��Ē����B�l���m��̌��������ł͂��������A�ߓ��[�~�̓������A���q�ێu���Ɛe�����Ȃ邱�Ƃ��ł����B�n糎��ƍĉ��B ���H��Y�ꂽ���߁A�P�l�ŋ߂��̘a�H�X�i�X���͖Y�ꂽ�j�ɂă����`�r�[���P�O�O�~�i�P�l�P�t�j�����݂Ȃ���u�b��ċ���H���C�X�吷��v�u���h�v�u���g�v��H�ׂāA�ߌ�̌��C�ɗՂB
�@ ��͏���s���̃z�e���ɏh���B���߂Ă̒n���������߁A�z�e�����̘a�H�X�ōς܂���B�S�l�˂��e�[�u���ɐw���B�u�₫�Ƃ�Z�b�g�v�u�V�Ղ琷�荇�킹�v�u���h�g���荇�킹�v�u����i�v�u���邻�v�r�[���E���ΏĒ��B���o�E�ǔ��E�����E�����̗[����ǂ݂Ȃ���P�l�ŏ����B�X���ɂ͒��ؗ����X�����������߁A�H��ɂ́u�ܖڃ`���[�n���v�𗊂ޗ\�肾�������u����݂͑�����v�Ƃ̂��ƁB
�@ �Q���ځB�q������w���̃R���r�j�Œ��H�Ɓw��ʐV���x�w�����V���x�w���{�o�ϐV���x�w�t�W�T���P�C�r�W�l�X�A�C�x���B�u���H�o�C�L���O�v��ɍς܂������ߌy�H�ɂ���B�u������T�v�Ɓu�����\�[�Z�[�W�v�u�����v�u�L���������v�B�ʃr�[�����w�����邩���������u����Ȃ��v�B�@
�@ �T���Q�P���y���[�~�B�u����y���Z�~�i�[�n�E�X�v�͌y���w����n�C���[�łR���B�y���[�~�͂Q���R���B�u��֏�ԁv�łP���W���Ԃ̃[�~���s���B���ɂ�����T�����̕��̊w���Ɉ��|���ꂽ�B����ɓn�錤���e�[�}�B�^���Ɍ��������Ɏ��g�܂��p���Ɏh������B�����e�[�}�̌��ߕ��A�_���̏������ȂǎQ�l�ɂȂ����B�T�����̊F�l�̑��݂��Ȃ���ΏC�m�_���͂P�s�������Ȃ��������낤�B
�@ ���͒n�����������e�[�}�ɂ��Ă��邽�߁A�ݏZ���镟�����̒n�����w��������x�w�������F�V���x���k�̃u���b�N���w�͖k�V��x�E�֓��b�M�z�̒n�����w��ʐV���x�w�M�Z�����V���x�w��ѐV���x�w�����V���x�Ȃǂ����Q����B
�@ �P���ڂ̗[�H�́u���t���g�`�[�Y�a���v�u�T���_�v�ȂǁB�H�����ł̓W���[�X�̗ނ͈��ݕ���B�[����[�~�͑����B�Q���ڂ̒��H�ŐH�ׂ������̑��k�B�u�ē��v�Ɠ����邪�Q�b�ŋp�������B
�@ �Q���ڂ̒��H�͘a�m�H�̃o�C�L���O�B���H�͊O�H�B�y�����U��B�Δȋ߂����n���ȃ��X�g�����ɓ���B�l�����������߁u�ł���Γ������j���[���v�Ƃ̂��ƁB�u�r�[�t�J���[�v�i���̓J���[�����j�𒍕��B
�@ �F���y��������U�Ă���ԁA���q���Ǝ��́A�������łP�t�B�[�H�̃��j���[�͎v���o���Ȃ��B�������l�I�ɂ͂P���ڂ��͏[�����Ă����ƋL�����Ă���B�[����[�~�͑����B�ߓ��搶����u�N�͂���ł�����ł��v�ƏĒ���n�����B�����́u�������v �B
�@�R���ڒ��H�B�a�m�H�o�C�L���O�B���H�͕��U������ˊٓ��Őۂ�B���i���|���B���h��ʂ��Đ搶���y���̐e�r��[�߂邱�Ƃ��ł��A�L�Ӌ`�Ȍo���ƂȂ����B
�@ �V���Q�R���Ċ��X�N�[�����O�B���یo�ρE�S���w�E�N�w�Ȃǂ̍u�`���[�����Ă����B���H�̓R���r�j�Ŕ������u������T�v�u�����\�[�Z�[�W�v�u�C���T���_�v�ȂǁB�ߓ��搶�́A�u��₵���v�u�����݂̖��X�`�v�u�C���T���_�v�������オ��B
�@ �I����̓n�b�s�[�A���[�B�[�H�͏���s���̈��݉��ő��q�E�����E���{�����Ɓu�ē��o�C�L���O�v�B�w�ɗ���ߐH���i�܂Ȃ��B��Ƀz�e���ɖ߂�B
�@�Q���ځB���H�o�C�L���O�B�������Ԃ̂��߂��A�q�͎��̂݁B�e�[�u���ɖ߂낤�Ƃ���Ɓu�������������܂��v�B�ߓ��搶�̐��B�搶�������z�e���ɏh�����Ă���Ƃ͒m��Ȃ������B
�u���͕w�̔�ꂩ��ꑫ�����z�e���ɖ߂�܂����v
�u�N�A����������낤�v
�@ �ߌ�́u�����G���͕K�v���ۂ��v���e�[�}�Ƀf�B�ׁ[�g�ɎQ������\��ł��������A�̒�������z�e���ŋx�{�B
�@ �R���ځB���͓I�ȋ����w�ɂ����Ƃ��I�������B
�@ �P�P���Q�O���~���X�N�[�����O�B�o�Ȃ̕K�v�͂Ȃ��������A���w�S���������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@ �R���Q�T���C�����B�T�����̕��̏I���j���ɏo�Ȃ����Ē����B�Q����͋߂��̋������A���̎h�g���������B�R����͒��ؗ����X�B�����������̂ŁA�r�[���Ɓu���[�����v�u�ܖڏă\�o�v�u�L�q�v�𒍕��B�Ȃ������Ȃ����������R�Ƃ����\��B
�@�Q�O�O�T�N�S���Q�R���B�V�N�x��P��̃[�~�B�V�����̊������A���i���Ɛe�����Ȃꂽ�B
�@ �V���Q�R���B�Ċ��X�N�[�����O�B�o�Ȃ̕K�v�͂Ȃ��������A���͓I�Ȏ��Ƃu���邽�ߏo�ȁB�f�B�x�[�g�ɏo�ȁB�ߓ��搶����V�����̊F����Ɂu����͗���҂ł��v�ƏЉ���B
�@ �X���Q�S���B�ߓ��[�~�C�������B�F����̂����͂Ő������ɏI��邱�Ƃ��ł����B
�@ �P�O���Q�Q���B�O���ے����Ԕ��\�B�u�͂��߂Ɂv���������Ă��Ȃ������\����B�ْ��̂��ߒ��H���A��ʂ�Ȃ��B����{�ْn���H���Łu�؊p�Ϙ��v�Ɓu���ւ���H�v�̂݁B���̊F����̏C�m�_���̓��e�A�v���[���͂Ɉ��|�����B
�@ �I����A�߂��̒��������X�Ŕ��ȉ�B�킳�E�Ē��E�����������B���������肷��B�����Ɍ������V�����Ŋʃr�[���Ɓu����������ٓ��v�B
�@ �{�i�I�ɏC�m�_���Ɏ��g�̂͂P�Q���ɓ����Ă���B��A���ƌ��U�ȊO�̓p�\�R���Ɍ��������B
�@ �Q�O�O�U�N�P���Q�W���B�C�m�ے���������B�C�m�_���̕��{����Ɏ���ɓ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@ ���߂ɒ��H�B�P�l�Ŏ��w��ٓ��̒��ؗ����X�Łu���ւ�胉���`�v�B���̌�A�ߑO���Ɍ���������I���������Y�i�E���q�E�g��B��Ɠ��ւ���H�B�F����̓r�[���������B���{���́u����̑O�Ƀr�[���͂܂����v�Ƃ��������ɏ]���āu�E�[�������v�𗊂ށB
�@ ��������ł́A�����̖ړI�E�Ǝ����Ȃǂ����ꂽ�i����̏ڍׂɂ��Ă͋L�q���Ȃ��j�B
�@ �����̊w���s���̍��ԂɁu�T�C�o�[�[�~�v�ɎQ�����A�ߓ��搶�⓯�����́E�C�����Ȃǂ̊F�l���琔�X�̏��������B
�@ ��������C�m�_���̌�������܂ł����n��őz�N���܂������A�ߓ��唎�搶���n�ߊe�搶���E�����X�^�b�t�E�����⏕�̊F�l�́A�^���Ɋw���̗ǂ������҂Ƃ��Ă��w�����Ē����܂����B�C����O�ɉ��߂Ċ��ӂ��Ă��܂��B���肪�Ƃ��������܂����B�F�l�̂������̐[���Ƃ����K��S��肨�F��\���グ�܂��B
�@ ���ꂩ��u�C�m�_���v��������邷�ׂĂ̊F�l�ցB�u�C�m�_���v���u�C�m�_������L�v�̕������{�A�y���������܂��B

�u��w�@�ł̏[������2�N�Ԃ�U��Ԃ��āv
�@�@���ۏ���U�@�����@����
�@�v�������Ƃ����Ԃ�2�N�Ԃł������B���x���̍������ɐg��u���Ď������A���̐��ʂƂ��āA�C�m�_���������グ��Ƃ����ڕW���f�������́A���{��w�̒ʐM����w�@�̖�����������B
�@���ɂ܂Ō�����w�@���Ƃ��Ă̐����́A�����Ċy�Ȃ��̂ł͂Ȃ������B�����A��ԑ�ς������̂̓p�\�R�����g�����Ȃ����Ƃ������B�ʐM���Ƃ������ƂŁA���ۂ̌��������Ƀp�\�R���͌������Ȃ����̂ł��������A����܂Ŏ��̓p�\�R�����܂������g�������Ƃ��Ȃ������̂ł���B�p�\�R���Ɗi��������X�����������A�������[�����o������A���|�[�g���������肵�Ă��������ɁA�p�\�R������ɑ���s���������X�ɕ��@����Ă������B����ƁA���������ߓ��唎�����̃[�~���T�C�o�[�[�~��p�ɂɍs�Ȃ��Ă����̂ŁA�T�C�o�[�[�~�֎Q�����邽�߂ɂ́A�K�R�I�Ƀp�\�R�����g�����Ȃ��Ȃ���Ȃ炸�A���ʓI�Ƀp�\�R���ɑ�������邱�Ƃ��ł����B
�@�܂����|�[�g�쐬���ƂĂ���ςȍ�Ƃ������B�Ƃ�킯���X�̎d�������Ȃ��Ȃ���A���|�[�g�쐬�̎��Ԃ���邱�Ƃ͎���̋Ƃ������B���������������Ԃ�����Ă̍�ƂƂȂ��Ă��܂��A���_�I�ɂ����̓I�ɂ���ς������̂������B�������A���l����ƁA���|�[�g�ɂ���������g���Ƃ��A��̏C�m�_���쐬�ɂ������ɖ𗧂������Ƃ͑���Ȃ��B�܂�A�������ʂ����������Ȃ����̈Ⴂ�����ŁA���������̂ɕς��͂Ȃ��̂ł���B���̈Ӗ��ŁA���|�[�g���C�m�_�����M�̗\�s���K�ƈʒu�t���Ď��g��ł������Ƃ͑�Ϗd�v�ł���B����ƖY��Ă͂����Ȃ��̂́A�K����N�ڂŌ܉Ȗڕ��̃��|�[�g���o���āA�P�ʂ��擾���Ă������Ƃł���B�����g�͖Z�����ɂ��܂��āA��N�ڂɎO�Ȗڕ��̃��|�[�g������o�ł��Ȃ��������߁A��N�ڂɑ�ϋ�J������͂߂ɂȂ����B���������āA��N�ڂɏC�m�_���̎��M�ɐ�O���邽�߂ɂ����̂��Ƃ͕K�{�����ł���Ƃ�����B
�@�Љ�l��w�@���̈�N�͎v���̂ق������߂�����B�����Ƃ����ԂɏC�m�_���������ׂ���N�ڂ��}����B�C�m�_����������ŁA��ԏd�v�Ȃ��Ƃ͘_���e�[�}�̑I��ł���B�_���e�[�}�������܂��Ă��܂��A�C�m�_���͔������������Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���ꂭ�炢�d�v�Ȃ̂����A���ہA�C�m�_���ɂӂ��킵���e�[�}���݂��邱�Ƃ͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B���̏ꍇ���A��g�ł̘_���e�[�}�͓��w���ɂ͂��łɌ��߂Ă������̂́A������ǂ̂悤�Ȑ���Ō������Ă����̂��Ƃ����_�ɂ��ẮA�Ȃ��Ȃ��悢�A�C�f�B�A���������A��N�ڂɂȂ��Ă��_���e�[�}�����߂��˂Ă����B�������A�O�q�����悤�ɋߓ��[�~�́A�T�C�o�[�[�~��p�ɂɊJ�Â��Ă����̂ŁA�[�~�ł̌������\��ʂ��Đ搶��[�~�����炳�܂��܂ȃA�h�o�C�X�����Ă��������A�ŏI�I�ɂ͔[���̂����_���e�[�}���݂��邱�Ƃ��ł����B�������A�����Ƃ����͖̂{�������̗͂Ő�J���Ă������̂ł͂��邪�A�D�G�ȃ[�~���Ƃ̓��_�͎����̌��������[��������������ʂ����Ă����̂ł���B���������āA�W���[�~�ɂ���A�T�C�o�[�[�~�ɂ���A�`�����X������ΐϋɓI�Ɍ������\�����Ă������Ƃ́A��Ɏ����̌�����[�������Ă������߂ɂ͑�Ϗd�v�Ȃ̂ł���B
�@�܂��t�����Ă����A��N�ڂ̏H�ɍs�Ȃ���C�m�_���̒��Ԕ��\��ɂ́A�K���Q�����Č������\�����邱�Ƃ��]�܂����Ƃ�����B�Ȃ��Ȃ�A���̒��Ԕ��\��s�Ȃ��鎞���́A�^�C�~���O�I�ɂ͏C�m�_���̖{�i�I�Ȏ��M�Ɏ��|���钼�O�ł���A�C�m�_���̕��������O���C������ɂ̓��X�g�`�����X�ƂȂ邵�A�w�������ȊO�̐搶��A���[�~���ȂǑ����̐l�Ɏ����̌������\���Ă��炦��̂ŁA���܂��܂Ȏ�����邱�Ƃ��ł��āA����Ɏ����̌����ɐ������Ă������Ƃ��\�ƂȂ邩��ł���B���͒��Ԕ��\������Ȃ����̂����A���܂��ܒn���̖��É��Łu�I�[�v����w�@in���É��v���J�Â��ꂽ�̂ŁA�����Ō������\�������Ă��������A���̂��Ƃ����ʓI�ɏC�m�_���̎��M�ɒe�݂����邱�ƂɂȂ������̂ŁA�ƂĂ����b�L�[�ł������B
�@���āA���Ԕ��\��I���ĔN�����}����ƁA��͂Ђ�����_���������݂̂ł���B�Ƃɂ������ԂƂ̏����ł���B���Ԃ����������[�h�ɕ�܂��N���N�n�ɁA�فX�ƃp�\�R���Ɍ������Ę_�������������邱�Ƃ́A�ƂĂ��炢��Ƃł������B�������A����ɑς��邱�Ƃ��ł����̂́A���̏ꍇ�A�[�~�̓������̑��݂��傫�������B��ʓI�ɒʐM���͌ǓƂł���Ƃ����邪�A���[����C���^�[�l�b�g����𗘗p�����X�J�C�v�ʘb�ɂ���āA�[�~�����m�̘A�������ɍs�Ȃ�ꂽ�̂ŁA���ہA�ǓƂƂ͑S�������ł������B���̂��Ƃ͎����C�m�_����������ŁA�ł��傫�ȃ|�C���g�ł������Ƃ�����B
�@�ȏ�A�C�m�_������������܂ł̓�N�Ԃ�U��Ԃ��Ă������A�������͎����ЂƂ�̗͂ɂ����̂ł͂Ȃ��B�����悻�v�搫���Ȃ��A�ӂ��҂̎����C�m�_���������܂łɂ�����ƒ�o�ł����̂́A�ЂƂ��Ɏw�������̋ߓ��搶�̉��������w���ƁA�D�G�ȃ[�~���̓K�ȃA�h�o�C�X�����������炱���ł���B�ߓ��搶�ƃ[�~�̒��Ԃɂ͊��ӂ̋C�����ł����ς��ł���B�܂��A�C�m�_���̊����͂ЂƂ̂����߂ɂ͂������Ȃ����A���������͂ނ��낱�ꂩ�炪�{�Ԃł���B����̏C�m�_���̎��M�œ����o���⌤�����ʂ�y��ɂ��āA���x�͔��m����ے���ڎw���Ă���ɐ��i���d�˂Ă��������B

�u�C�_���I���āv�@�@
���ۏ���U�@�@���{�@��
�@���ꂪ�ŏ��ōŌゾ�낤���B����قǂ܂łɃL�[�{�[�h��ł����������Ƃ́A���܂����ĂȂ��B�ł��ĕϊ��A����B�ł��ĕϊ��A����B�����l���Ă���܂��łB���炭�l���Ă���Backspace�B�����Ă܂��łB�Q�N�ԁA���̌J��Ԃ��ł������B
�@ �u2�N�ԂŏC�����邽�߂ɂ��A1�N���ɕK�C�ȖځA�I���Ȗڂ�5�Ȗڂ̒P�ʏC���������ߒv���܂��v�Ƃ̏���y����̃A�h�o�C�X�ɏ]���A1�N���ɂ�5�Ȗڂ̒P�ʏC���ɓw�߂��B�������A����ꂽ���Ԃ̒��ŁA���|�[�g�ۑ�ɑ���Ӗ�����������Ɣc�����A���ނ�����o����Ƃ́A��������ςł������B�r���A�u���̂���ȂɑI��ł��܂����̂��낤���v�Ǝv���Ȃ���A�L�[�{�[�h��ł�����X�ɒx���Ȃ肪���ł������B
�@ 2�N���́A1�N���ɋ�J���Ă����Ȗڗ��C����������A�C�m�_���֖{�i�I�Ɏ��g�݂��n�߂��B�C�m�_����1�N�����炢�낢��ƍl���A�Y�݁A���x�����x���������������Ă����B�����̎��W�͎�ɐ}���ق����p���A�o�����Ȃ���������W���Ă������B
�@2�N���̖w�ǂ��C�m�_����M�̍�Ƃɔ�₷���Ƃ��o�����B�����1�N�������̏���y����́u5�ȖڒP�ʏC���v�̃A�h�o�C�X�����������炱���o�����̂��Ǝv���B
�@�C�m�_�����M�̍�Ƃɂ����āA�����̉ӏ������A�ڎ���i���ԍ��̐ݒ�A�r���Ȃǃ��[�v���̋@�\���ő���ɐ��������B�_����������ŏ͂⍀�ڂ̕t�����A���p��Q�l�����̏������Ȃǂ̃��[���͎��O�ɓ��ɒ@�����B��烏�[�v���Ƃ����ǂ��A���삷�鑤���������肻�̕ӂɂ��ė������Ȃ���Ύv���悤�ɂ͓����Ă���Ȃ��B���̂��Ƃɂ��āA�S��������著���Ē������u�_���̒��̕\�L�ɂ��āv�͔����ɗ������B
�@ �C�m�_�����M�́A���ɂ͐^�钆�܂ōs���Ă����B���ɂ�BE�Ƃ����s���j�X�g�̂悤�Ȋi�D�ŁA�L�[�{�[�h�Ɏ��u�����܂n�����邱�Ƃ��������B11������N���N�n�ɂ����Ă̒ǂ����݂ł́A�n������ɂ��Ȃ��L�[�{�[�h��ł����B���̍b��������o�������ɒ�o���邱�Ƃ��o�����B
�@ ����2�N�Ԃ�U��Ԃ�v�����Ƃ́A�u���Ԃ������ƗL���Ɏg������悩�����̂����m��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł���B�������A����ꂽ�����ɁA����ꂽ���Ƃ����Ƃ����Ӗ��ł͂悭��������ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@ ����2�N�Ԃʂɂ��Ȃ��悤�A����Ɍq���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B

�u���S�ɂ�����I�@�撣�낤�I�v �@�@
���ۏ���U�@�@�O�c�@��
�@���m����q�s�̎s�����ɒn���������Ƃ��ċΖ����Ă��܂��B�Ζ���̊�q�s�̎���Ɋ�Â��āA�n���ł̎��[�������e�[�}�ɂ��ďC�m�_���������グ�܂����B
�@�����A�n�������ꊇ�@�̐���A���\JAPAN�v��Ȃǂɂ��A�n�������͑傫�ȕϊv�����}���Ă��܂��B��q�s���ߗׂ̎s�����Ƃ̍����������E�c�_���Ă��܂��B�������ȊO�ɂ��A��X��������Ă��܂��B�܂��́A��t�œ��̌��z���A�s���^�c�̕ϊv��]�V�Ȃ������Ă��܂��B�n�������́u�Γ��E���́v����{�Ƃ��鍑�ƒn���̐V�����W���\�z���A����Ɍ��L���Ŋ��͂ɖ������n��Љ���������邽�߂����ł���͂��ł��B�Ƃ��낪�A�Γ����̏��ŁA���̖ړI��B�����A�n�������̖{�|�ł���Z���̕����̑��i��}���Ă����Ƃ������Ƃ��A�ɂ߂č���ƂȂ��Ă��܂��B�s���^�c�̌������͐^����ɐE���팸�Ƃ�����@�Ɍ���A����͍s���^�c�̍��������ł���}���p���[�̒ቺ���Ӗ����܂��B����ɁA�d�q���{�\�d�q�����̂Ƃ���IT���̔g���}���ȃX�s�[�h�ʼn��������Ă��܂��B
�@ �����̍������������ʂ��Ă���傫�ȕϊv�̒��ŁA�n�������̖̂����}��N���Ɏv���`���ɑ����͂��������Ƃ����肢�������āA���{��w��w�@�����Љ����Ȃɓ��w�����̂ł��B�n���������Ƃ��āA��q�s��ǂ��������A�n���ɉh���������Ƃ����v�����ǂ�����Ό`�ɂł���̂��BIT�ɂ��R�~���j�P�[�V�����ŁA�����W�����邱�Ƃ��ł���̂��B���낢��ȋ^�₪����܂��B�n����������������⎩�����g�̒��̗l�X�Ȗ�����������Ă������߂ɂ́A��������Ƃ�����b�m���ƐV�������̂�������Ă����_��Ȏv�l���K�v�ł���ƍl���܂��B���@�\�n�������@�Ȃǂ̖@�I�Ȓm���ƁA����̒n���s���̖���I�A�\���I�^�c��}�邽�߂�NPM�i�j���[�p�u���b�N�}�l�[�W�����g�j�̂悤�ȐV������@�Ȃǂ��w�сA���̊�b�m���̏�ɑ����I�Ȑ���`���\�͂�s���Ǘ��\�͂�g�ɂ��Ă��������Ǝv�����̂ł��B
�@ ���ɁA�������������Ƃ́AIT�V�X�e���̊��p�ł����B�����J��v���C�o�V�[�ی�A����`���Ɠ��{�ȊO�ł̏�Љ�̂������@�Ǘ��ɂ��āAIT�v���ɂ����̕ώ��Ɛ����E�Љ�̕ω��̊W�c�c�A�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ������ΏۂƂȂ�܂��B
�@ �p�\�R�������p�ł��邩�ǂ����ŁA�w�K�̔\���ɑ傫�����������鎞��ɂȂ�܂����B
�@ �����Љ����Ȃ́AIT����g����ʐM���ł��B�ʐM���͎d���Ɗw�K�𗼗������邱�Ƃ��ł��܂��B����ɁA�w�K�E��������Ɏ���̃p�\�R���ōs����_�����͂ł��B���̓p�\�R�����g���̂��D���ł����A���[����C���^�[�l�b�g�Ȃǂɂ��K�n���Ă��܂����B�����Ȃ́A��傪����ɂ킽�鋳���w��i���Ă��܂��B������A�����ȂŌ����E�w�K�����邱�Ƃɂ����̂ł��B
�@ ���ꂩ��́A�p�\�R���́A��肢���������猤�������ɉe����^���܂��B����ɂ��A�n��Ԃ̊i�����k���ł���\��������܂��B�p�\�R�������p����V��������̐��̂�肢�������̏[�������߂��Ă��܂��B�����Ȃ͍Ő�[��S���Ă��܂����A����Ȃ锭�W���]�܂�܂��B
�@ ���܂ł͉�����������ł����A�@���|�[�g�ł͋�J���܂����B�������܂����B���e��o�A�Y��A�����A�C���̉ߒ����o�A�ŏI��o�ƂȂ�̂ł����B�ŏI��o�ƂȂ�ƁA�{���Ƀz�b�Ƃ������̂ł����B
�@ �����ɉ����ł��A�����ł��Ȃ�����c���ł���悤�ɂȂ肽���A�Ƃ̖��ӎ��������āA���|�[�g�ȂǂɎ��g��ł��܂����B�d�������܂łƂ͈�������_�ŗ����ł�����悤�ɂȂ肽���Ƃ�����āA�w�K�E���������Ă��܂����B������ȏ�̂悤�Ȗ��ӎ���肢���������Ă����܂��B
�@ �ŏI�I�ɂ́A�_����ڂ́u�n���Ŏx�����s���̃}�l�[�W�����g�V�X�e���̌����v�ɂȂ�܂����B���x���A���x���A�Y�킳��܂����B�C���A�������A�ς��܂����B�������A�C�m�_�����Ƃ��Ƃ����������邱�Ƃ��ł����̂ł��B���̂��Ƃ́A����̑傫�ȗ�݂ƂȂ�܂��B�@
�@ ���S�ɂ�����I�@�撣�낤�I

�u�C�m�_�������@�v�@
���ۏ���U�@�@���q�@�ێu
�@�u�C�m�_���I�v�u���[��A�����������H�ǂ�����ď������H�v�ƍl���Ă݂͂����̂̂����A�p�\�R����O�ɂ��Ă������v�������Ȃ��B�ꉞ�A���w�������̌����v�揑�͂��邯��ǁA����x���߂Ă݂�Ɖ����F�����Ă邵�c�c����Ȃ̂��_���ɂȂ�̂��ȁc�c�w�_���̏������x�̖{���������ǂ�ŏ�����킯�ł͂Ȃ����c�c����Ȃ���ȂŁA���ǑS�R�i�܂Ȃ��B�������Ԃ����͖��Ӗ��ɉ߂��Ă����A�u����I�v��ԂɂȂ��Ă����B���̂܂܂��Ⴂ���Ȃ��B�C�����͂�����I�@����Ȏ��A�O���ƈ���č����^�ʖڂȎ����C�̓ł����āA�ǂ����̐_�l�����肪�����u���[���v�����������B�����A�C�m�_���̒����̎d�����c�c���̒��Łc�c
�@�_�l�͒����@�����������Ă��ꂽ�B�܂��A���������������u�����v�����߂�B
�@ �����ł���A��������ԐH�ׂ������́A���₷�����̂��l����B�①�ɂ��J���ĉ�����ꂻ�����l���邱�Ƃ�����B�_�����������ƁB�����������������́A�����₷�����̂��l����̂��B���̒��̗①�ɂƑ��k���Ȃ���B
�@ ���͂��̌��������ɂ͂ǂ̗l�ɒ���������悢�����ׂĂ݂�B�����u���V�s�v�ł���B��ʓI�ɂǂ̗l�ɍ���Ă���̂��A�ǂ̗l�ȍ���������̂����ׂĂ݂�B�C�m�_���ł́u��s�����v�ł���A�u���@�_�v�̕��ɂ��Ȃ�̂��B
�@ ���āA������x�A���j�����܂�����A���́u�ޗ��v�̔��o���ł���B�}���ق�{���Ŏ����A�Q�l�������W�߂�B�ޗ����ᖡ����ڂ��������̍ޗ��ɐG���A�����ƕt���Ă���B�ޗ����ڂ��ڂ��W�܂�����A���͗����̒i�����l���˂c�c�ޗ����ǂ̗l�ȁu����v�Ő邩�A�����̎d���͂ǂ����邩�B�����A�Ă��A�u�߂�c�c���t���͂ǂ����邩�H�@���������ǂ��ʼn����āA�ޗ��̎������������H�@����Ɏ������g�́u�Ǝ����v���ǂ����������B�l�܂˂���������������͏o���Ȃ����A�_�����ᙗ�ނɂȂ����Ⴄ�B�����ł��_���ł��i���͏d�v���B�_���ł́u�N���]���v���ˁB�����Ř_���̖������܂��Ă��܂��Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@ �����A�����܂ł�����A80���͊������������R���B��C�ɗ������n�߂悤�B�r���Ŏw�������A�܂��ɂ��ڂ�����A�������肵�ďł����Ă��܂����Ƃ����邯�ǁA�C�ɂ��Ȃ��C�ɂ��Ȃ��B��蒼�����o����̂�����B����ɍ��܂ŕ����Ă������ʂ��u�B�����v�Ƃ��ĉ����悤�B���ꂪ�ォ�炫���Ă���B�Ƃ肠�����A�o�������̂��u���H�v���Ă��炤�̂��厖�Ȃ��Ƃ��B�[�~�Ȃǂő��l�̈ӌ��A���z���A�����{�ʂ̖��ɏC�����ł���B
�@ �������ƈꑧ���B�����ŋC���ɂ߂Ă͂����Ȃ��B����t���ƃe�[�u���Z�b�e�C���O���B�����_���́u����@�v��Y��Ă͂����Ȃ��B����t������A��Ǔ_����p�̎d���ɋC��z�낤�B���̂���@�������ɂł���A�������I���I
�@�Ǝv������A�Ō�̓�ցA��̂������搶���ɏ����オ���Ă����˂c�c
�u���[��A�����������ɐH�ׂĂ��ꂽ�v�u�������ȕ\��v������ˁB���܂ɂނ��Ԏ��͂����Ŗڂ��o�߂��B�^������Word�̉�ʂɟ������炵�Ȃ���c�c
�@

�u�w���x���W�I�x�`���̏C�m�_������L�`�v �@�@
���ۏ���U�@�g��@�B
�P�@�͂��߂Ɂ`��w�@�Ǝ�
�@��w�@�Ƃ����A���ɂ͋ꂢ�v���o������B
�@������10�N�قǑO�̂��Ƃł���B���̂����Ђł́A�����A��w�@���C�Ƃ������x���������B2�N�ԐE��𗣂�ĕw�ɐ�O�ł�����̂ŁA�������w�Ƃ����Ă��悢���̂ł���B���͂���ɉ��債���B����܂ŁA�o�^�o�^�Ƒ����Ă��āA�����[�ċz�������Ȃ����̂ł���B�܂��A�N��A�E�ʂ��炵�čŌ�̃`�����X�ł���������ł�����B���w�����͓��ɂȂ��A��Ђł̑I�l�Ō��܂��Ă��܂��Ƃ����A������v���A�ƂĂ��g���������h���̂ł������B��i�ւ̍����I���A�S�͉@���A����A���ɏC�m�ł������B�Ƃ��낪�c�c
�@�Ƃ��낪�A�ł���B���_���猾���ƁA���͑I�l�ɗ������B�ʂ����̂́A10�߂��Ⴂ�����ł������B�ォ�畷�����Ă����Ƃ���ɂ��A�ǂ��������̎В��̑��߂������������A�В��̈ӌ���[�ǂ݂��ď����Ɍ��߂��Ƃ����B�����āA�В�����͂�u���ꂩ��͏����̎��ゾ����c�c�v�̈ꌾ�Ŋ����̌���Ă��x�������Ƃ����B�܂��A�����̈�l���A���𗎂Ƃ����߂ɁA�S�R�d���̐ړ_�̂Ȃ��A���������Ēm�荇���ł��Ȃ����ɂ��Ă̈�����I�l��c�̏�Ō������Ƃ����B�܂�Ȃ�����ł���A�܂�Ȃ��������Ȃ��A���ꂪ�킪�Ђ̌������Ǝv���ƁA�܂��o�Ȃ������B�ȗ��A�u��w�@�v�͎��̃g���E�}�ɂȂ����B����ȍ~�A���̘b�肩�炸���Ɖ��������Ă����B���{��w�ɒʐM���̑�w�@���ł����Ƃ������Ƃ́A���̕ւ�ɕ����Ă������A�g���E�}�́A�c�c��͂�A�����Ă��Ȃ������B
�@�������A10�N���o�āA����d�������������ɕw�̈ӎu���Ăы����Ȃ����B�����A�ߋ��̃g���E�}�ɂ����ʂ��A���x���W�������A�����v���悤�ɂȂ����B�����Ŏv���o�����̂ł���A�ʐM���̑�w�@�̑��݂��B�d���𑱂��Ȃ���A�����ł���B����͎��ɂ����Ă����Ǝv�����B�������A���̈���ŁA�ʐM���̑�w�@�����ɉ���^���Ă����̂��A�^��ł��������B�ϖサ�Ă���Ƃ��A�Ȃ��ۂ�ƌ������B�u��w�@�������ɉ�������邩�ł͂Ȃ��āA�����̋����������Ă��邱�Ƃ������ł��邩�ǂ������厖�Ȃ�ł���v�B����̋[���ł͂Ȃ����A�܂��Ɂu���[��v�ł������B�����Ȃ̂ł���B���̌�̏ڍׂ͏ȗ����邪�A���̌��t�����������ɁA���͂��̑�w�@�֓��w���邱�Ƃ��ł����i�ȂɊ��Ӂj�B�������Ď��̑�w�@�ւ́u���x���W�v�A�����āu�Đ��v�ւ̗����n�܂����̂ł���B
�Q�@�C�m�_���G��
�@ �Ƃ���ŁA�{�e�͏C�m�_������L�ł���B��⊴���I�ȑO���������������B�{�_�ɓ��낤�B�Ƃ͂����Ă��A�_���ł͂Ȃ��B�C�m�_���������Ă��čl�������ƁA�v�������Ƃ��C�y�ɏ����Ă������B
�i�P�j���͂����ɂ��ďC�m�_�����쐬������
�@ ���̌����e�[�}�́A��ʘ_�I�Ȃ��̂ł������B���̂��߁A���w���X�̃T�C�o�[�[�~�ŁA��y�⓯���̕��X����ٌ������Ɏ��A�h�o�C�X���A�u�e�[�}���i��I�v�ł������B���̘_����ڂ́u��@�Ǘ��v�ł���B��@�Ǘ��̒�`��T�O���͂����肵�Ȃ�������^�⎋���A����ł̑Ή��҂̗��ꂩ�猩�ėL�p�Ȋ�b���_��T��A�Ƃ����̂����̓��e�ł������B
�@ �Ȍ�A�u�e�[�}���i��v��2�N���̏t�܂Ŏ���Y�܂����B4���̏I���ɁA�N�x���߂̌��ӕ\���̂��߂̃[�~������ŊJ�Â��ꂽ�B�܂��E�W�E�W���Ă������ɁA�w�������̋ߓ������́u�N�̏����������ƁA�v����_���ɂԂ��������v�ƌ������A�h�o�C�X�����Ă����������B�v���͓������猈�܂��Ă���A�悵�A����ōs�����A�ƌ��ӂ��A�ŏI�I�ȃe�[�}�ƂȂ������̂Ɍ��߂��B
�@ ���̌�A5���̍��h�ŏ͗��Ă��قڌ��߂��B���h�ł́A���̔��\�O��A�����̑��q�����钆��2���܂Ńv���[�~�i�H�j�ɕt�������Ă��ꂽ�B���̏͗��Ăɂ��āA2�l�Ńf�B�X�J�b�V�����������̂ł���B��ό��ݓI�Ȉӌ��𑽂����Ղ��A���̃e�[�}�ɑ���v���́A��苭�łȂ��̂ɂȂ����B�܂��A���̍��h��5�����̖V�_�����_�����������߂̃p�\�R���̌����I�ȗ��p�@���u�`���Ă����������B���ꂪ��ώ��ɂ͍K�^�������B�����Ɂu���Ӂv�ł���B���āA���̌�A���h�̐��ʁi�e�[�}�A�͗��āj�������ɂ��`�����A�����������������Ƃ��ł����B�u���������n�߂�̂������ł��傤�v�Ƃ̂��ƁB�u������邼�I�v�ƌ��ӂ��V���ɘ_���������i�߂��c�c�Ƃ����킯�ɂ́A�������A�����Ȃ������B
�@ �Ă��납��A�d���̊W�ŕ����Ă�������������グ�Ɍ����ē����o���A���W���܂߂��^�c��S�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B���݂ł��p�����ł��邪�A���ꂪ��ςŁA���ɁA�H�̗����グ�����ɂ́A�_�����M���܂������i�܂Ȃ������B����ǂ��납���C�Ȗڂ̃��|�[�g���܂܂Ȃ�Ȃ���ԂɂȂ��Ă��܂����̂ł���B���Ƃ��Ԑ��𗧂Ē����ă��|�[�g���d�グ�A������̖ڏ��������̂�10�����������B���R�A���ԕ�̓��e���A�đO����傫���͐i�����Ă��Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂����B
�@���������āA�{�i�I�ɏ����n�߂邱�Ƃ��ł����̂́A11������ł���B��������͑�ςł������B�͗��Ă̒�����c��܂���ׂ��A�������X�g�b�N���Ă������B�T�C�o�[�[�~�Ȃǂŏ������߂����W�����̃t���[�Y����e���u���b�V���A�b�v���āi�����c�c���肩���j�A�W���鍀�ڂɖ{���Ƃ��ĕt���Ă������B�����ŁA�V�_���ɋ�������p�\�R���̗��p�@�K���A�����Ђ����獀�ڂƍ��ڂ̊Ԃ߂Ă������B
�@ �������A���͗e�͂Ȃ��߂��Ă����B12���̔��ɂȂ�A�����4�͍\����2�͂��炢�܂ł̖���e���ߓ������ɂ����肵���B�����Ƀ��[���ŕԎ������������A�u���̂܂܍Ō�܂ň��S���ď����グ��悤�Ɂv�Ƃ̂��ƁB�ȍ~�A1�����̕��{��o���܂ŁA�Ђ����珑���������B�K���A�����������Ƃ͌��܂��Ă���A�����Y�܂Ȃ������B�������A�ǂ��������͕ʖ��ł���A���ԓI�ɋ���������Y�ݔ������B�����āA���Ƃ������B�����Ƀ��[���ő��e�𑗂�ƂƂ��ɁA�䗹���đ�w�@�����ۂɒ�o�����B
�i�Q�j�|�C���g�͉��ł������̂��`�G���I�A�h�o�C�X
�@ ���̂悤�Ȍo�܂̒�����l�����A���ł͂��邪�A���Ȃ�̃m�E�n�E�ɑ������镔���ɂ��Ă܂Ƃ߂�Ǝ��̂Ƃ���ł���i�����܂Łu���Ȃ�́v�ł���B�O�̂��߁j�B
�A�@�_���̏�����
�@���́A�w���́i����ł͂Ȃ����j�@�w���𑲋Ƃ����B�ǂ��ł��������Ǝv�����A�@�w���ł͑��Ƙ_���͂Ȃ��B���������āA�_���̏��������킩��Ȃ��B���̘_���̏������ɂ��ẮA���ɐ_�o���ɂȂ����B�������{���ǂB�S�ʓI�ɎQ�Ƃ������̂͂Ȃ����A�����I�ɕ��@���������Ȃǂ��āA�����Ȃ�ɂǂ̂悤�ɏ����Ă����������߂��i���ʓI�ɂ����Ђ����珑�������������悤�ȋC�����邪�c�c�j�B���̎��_��22�{�����Ă������|�[�g�̍쐬�ߒ��Ŕ|�������͍쐬�͂�M���č���ŏ������Ƃ����̂������ł���B
�C�@�p�\�R���̌����I�g�p
�@ ����͏d�v�ł���B�܂��X�̃m�E�n�E�̑O�ɁA�u���C���h�^�b�`���K�����邱�Ƃ��]�܂����B���́A���w�O�ɗ��K���A�u���C���h�^�b�`�i���ǂ��H�j��g�ɂ����B�����āA�X�̃m�E�n�E�����p�����B��̓I�ɂ́A��q�̂Ƃ���V�_���̍u�`�̓��e���قڂ��̂܂ܗ��p�����̂ł���B���ꂪ���ɂƂ��đ�ϗL���ł������B���ɁA���Ԃ̂Ȃ��l�̓p�\�R�����X�g���X�Ȃ��g�p����Œ���̋Z�p�����M�O�ɏK�����Ă������Ƃ��]�܂����Ǝv���B
�E�@��ɘ_���Ƌ��ɂ��邱�Ɓ`�ʋΓr��̃����̊��p
�@���̓��ɏ������Ǝv���Ă��镔���ɂ��āA�ǂ̂悤�ȍ\���ɂ��邩�A�ʋΓd�Ԃ̒��ōl�����B�����āA��̂Ђ�T�C�Y�̗����ȃ������ɏ����Ȃ������B�������Ă����ƁA���̓��ɏ������Ƃ��ꉞ���܂��Ă���A�A��Ă��炷���Ɏ��M�ɂ������i���Ƃ����������j�B���̏ꍇ�A�ʋΎ��Ԃ��Г�10�����x�Ȃ̂ŁA�ǂ����Ă��܂Ƃ܂�Ȃ����́A�w�O�̃R�[�q�[�V���b�v�ȂǂłȂ�ƂȂ��C�ɂȂ��Ă��镔�����������Ă���i���S���āj�A�H�ɂ������Ƃ�����B����͋C�����̖��ł��邪�c�c
�G�@�[�~�̊��p
�@ �[�~�͎��Ԃ���������ϋɓI�ɎQ�����������悢�B�ߓ��[�~�̏ꍇ�A����16�N�x�͏W���[�~������1����x�J�Â��ꂽ�B17�N�x�́A�W���[�~�͂قƂ�ǂȂ��A�T�C�o�[�[�~���嗬�ł��������A�`�͂Ƃ������A�[�~�ł̔��\���ϋɓI�ɍs�������悢�B���̏ꍇ�́A�s��3�\�������A���̎��X�̍쐬�����͉��炩�̌`�Ř_���ɐ��������Ƃ��ł����B�v�l���ϋl�߂Ă������߂ɂ��[�~�͏d�v�ł���B������e�[�}�������A�قȂ�o�b�N�O���E���h�������Ԃ̈ӌ������Ƃ́A���Ƃ��ēƂ�悪��ɂȂ肪���ȒʐM���̌��_�����Ă����B���̈Ӗ��ŁA�[�~�̒��Ԃ͌����ւ̋��͎҂ł���A�ꐶ�̕ł�����B
�I�@�����̃A�h�o�C�X
�@ �ߖڐߖڂɂ�����ߓ���������̏����́A�܂��Ɂu�����v�ƚX����̂ł������B�܂��A���͎��ӎ��ߏ�ł���A����c�����I�ȂƂ��낪����̂ŁA��ʘ_�I�ȃA�h�o�C�X���u�����A����͎����ւ̃A�h�o�C�X���I�����ւ̂����肾�I�v�Ə���ɉ��߂��āA����������ւ̉��߂Ƃ��ċC���������߂��B�e�[�}�ɔY��ł��鎞�A�Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ����A����Ə���ė������\���̎��X�Ɏ������܂��悹�Ă��ꂽ�悤�ł���B
�J�@���N����
�@ ���N�͖{���ɑ�ł���B��ʘ_�ł͂Ȃ��B�C�m�_���쐬�ɓ������āA�ł���B�Љ�l��w�@���͂��̔N��Ɋӂ݁A��͂茒�N�ɂ͏\�����ӂ���K�v������B���i����A�K�x�ȉ^���Ə\���ȉh�{�A�����ċx�{��S������ׂ��ł���Ǝv���i����͔��Ȃ���ł���j�B
�L�@�J������
�@ �Ō�́A�J������ł���B�ǂ��l�߂�ꂽ�炱���l���悤�B�C�m�_���́A�w��̐��E�ւ̓�������ƐS���悤�B���S�Ȃ��̂��������ƂȂł��Ȃ��ƊJ�����낤�B���́A�C�m�ɂӂ��킵���w�͂����邱�Ƃ��̗v�Ȃ̂ł���A�ƁB
�R�@�I����
�@ �����ƈ̂����Ȃ��ƂX�Ə����Ă��Ă��܂����B���O�̘_���̏o���͂ǂ��ȂA�Ƃ̐����������Ă������ł���B���m�̏�A����͕����Ȃ����Ƃɂ��Ăق����B���ꂩ��C�m�_�����������X�ɂ����炩�ł��Q�l�ɂȂ�Ǝv���A�p�����炵�����̂ł���B
�@2�N�Ԃɂ킽��u���x���W�v�̗������A�I��낤�Ƃ��Ă���B�����āA�u�������ėǂ������v�\���ꂪ���̊��z�ł���B�����ۂ��ȃ��x���W�Ȃǂ����ǂ��ł��悭�Ȃ��Ă����B���x���W�Ƃ������������ȗ����I���A�V���ȖڕW�Ɍ����ăX�^�[�g����悤�ȋC�����Ă���B�����āc�c���̗��́A�܂��܂����������ł���B
�@�I���ɁA�ߓ��������͂��߂Ƃ����e�搶���A�����̒��Ԃ����i���ł��A�܂ɂӂꃁ�[�����ŗ�܂��������������j�A��y���Z�o�A�����āA�ȁc�c�W���邷�ׂĂ̕��X�Ɋ��ӂ̋C�������q�ׂ����Ă������������B
�u�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����v�@�@�@�@�@�@�@�@

�u�C�m�_���́A���l�H�v �@�@
���ۏ���U�@�ĎR�@���q
�͂��߂�
�@ �C�m�_���́A�u�C�m�_���쐬�v�Ƃ����s��ȗ��������Ă����̂ł͂ƁA���͎v���B
�@ �_�����o���I��������܁A������x�A���p�����Q�l�����E�_���⎑����ǂݕԂ������Ǝv���Ă���B�����ɂ͎��̋��߂�낪���邩��B�C�m�_���͂��̒�ɍ炩���Ă��������������ȉԂł�����l���B
�@ �C�m�_���͏������e��ړI�ɂ���āA�\�����@�⎑�����W�̏����̈Ⴂ������Ǝv���B���̏ꍇ�́A�_�肪���{�ƒ�������j�W���e�[�}�ɂ����u���������E�����ƒ��앐�n�̊W�ɂ��Ă̈�l�@�v�Ȃ̂ŁA�K�R�I�ɎQ�l�����𑽂���������A�ǂ肷�鎞�Ԃ��������Ȃ������B����ɁA���͕\���͂ǂ����Ă��d���Ȃ�A�ŗL�����������g��ꂽ�B
�@ ����A�u�C�m�_������L�v�ł́A���̃P�[�X�̎����I�Ȃ��Ƃ��������Ē������Ǝv���B
�P�@�C�m�_���Ƃ����A���������������l�Ƃ̏o��B
�@ �ǂ�ȗ��l�Əo����́A�����̃e�[�}�I�тɂ������Ă���B���́A�u�������v�Ɓu�R���ږ⒬�앐�n�v�Əo������B�������킹�Ă��ꂽ�̂́A�u���B�v�ŁA���̒������k���ł���B���̖��B����̈��g�҂ł��鎄�͐��n�́u���B�v���āA�_���̃e�[�}�ɂ������Ǝv���Ă����B
�@ �����ŁA���B�ɂ��ď����Ă���Ղ����{��T���ēǂB�Ղ����̂���ǂݏo�����̂́A�P�Ɏ��͓���̂��Ɨ���͂����Ă����Ȃ����炾�����B���ɖ��B�ɒ��Ԃ������{���R�̕����u�֓��R�v�ɂ��ēǂB���̌��ʁA�֓��R�Q�d�͖{����̎�Ŕ��E���ꂽ�k�����{�𑀂����匳���������ɁA�����A��������Îᏼ�s�o�g�̌R���ږ⒬�앐�n�Ƃ������R�R�l�����Ă������Ƃ�m�����B�ł́A���{�l�̌R���ږ₪���Ă��Ȃ��牽�́A�������͉͖{���ɎE���ꂽ�̂��낤���A���O�Ɏ@�m���ď����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂��낤���A�Ƃ����^����������B
�@ �����ŁA���܂ŗ]��m���Ă��Ȃ����앐�n�ɂ��Ď������W�߂����ʁA�Q�O�]�肻�����ɂ��邱�Ƃ��o�����B����ŁA�u���������E�����ƒ��앐�n�̊W�ɂ��Ă̈�l�@�v��_���̃e�[�}�ɋ^���Njy���邱�Ƃɂ����̂ł���B
�Q�@�C�m�_���쐬�́A���̗��l�Ƃ̒����������Ԃł���B
�@ �����̓}���ł������M���Ȃ��ẮA�n�b�s�[�G���h�ɂȂ�Ȃ��B���̏ꍇ�͏C�m�_�����o�ł��邱�Ƃ��n�b�s�[�G���h�ł������B
�i�P�j�@�����W��
�@ �܂��A�Q�l�������ڂ��Ă���A�����̃e�[�}�ɊW����_���⒘����ǂB�����āA�K�v�ȎQ�l���������āA�ǂ�m�F�����肵���B�Q�l�����̌�������ɂ���̂Ȃ�A�����������A�K��Ċm�F�����B
�i�Q�j�@�t�B�[���h���[�N
�@ �t�B�[���h���[�N�Ƃ����邩����Ȃ����A�Ƃ������킸���Ȏ��Ԃ𗘗p���Ď����T���������B����}���فB���E�s���}���فB�����̌��E�s���}���فB�h�q���h�q�������}���َ������B��w�}���فB�O���ȊO�������فB���l�s�̃r�f�I���C�u�����[�E�V�����C�u�����[�B��Îᏼ�s�̒��앐�n�̐��Ƃ���߃���B���앐�n�ƌ𗬂����������X�Ɩʉ�Ȃǂ������B����͑����̎��Ԃ��₷���ƂɂȂ������A���ɂƂ��Č��������Ƃ̏o���Ȃ��A�M�d�Ȑ��������Ԃł������B
�i�R�j�@�͗���
�@ ��ԁA��J�����̂��A�u�͗��āv�ł������B���̂Ȃ�A�S�̂��������߂Ȃ����ɍ��Ȃ���Ȃ�Ȃ���������B�ܘ_�A�l�����傫���A���ׂĔc���ł��Ă��ď͗��Ă��쐬����l���唼���낤���A��������ׂ����낤�B�����A���̏ꍇ�͂����܂œ��B���Ă��Ȃ������̂ŁA��x�o���オ�����u�͗��āv��_���쐬�r���ŁA���e�ɂ���Ĉꕔ�A�߂̑��ύX�����Ē������肵���B�������A���ꂪ�\�������̂́A�傫�ȋ~���ł������B
�R�@�C�m�_���쐬�̂��߂̏����ȃR�c�́A���l�ւ̉ԑ��v���[���g
�@���l�ւ̉ԑ��́A�����̎v����`���郁�b�Z�[�W�B�C�m�_���쐬�̂��߂̏����ȃR�c�́A�_���ւ̎v����`����V�N�ȃv���[���g�ł���B
�i�P�j�@�͗��đ܂̊��p�F�u�͗��āv���o������A�e�߂��Ƃɏ͗��Ă�\��t�����`�S�p��������܂�������B���̏ꍇ�͂S�͂S�߂������̂ŁA�u�͂��߂Ɂv�Ɓu�����Ɂv�𑫂��đS���łP�W�܂�������B���̑܂̒��ɂ́A���e�ɊW�̂��郁����Q�l�����̈ꗗ�\����є��������̃R�s�[����ꂽ�B�܂��A�ȒP�Ɍ����Εt�^�̑܂݂����Ȃ��̂ł���B�������A����͕֗��ő傢�Ɋ��p�����B
�@ ���Ȃ݂ɁA���|�[�g�쐬�ɓ������Ă��A���̕��@�����p���A�ۑ��܂̏�ɒ������B�P�ȖڂłS�܂����A���ɏW�߂����������Ă������B��������Ɖ����ł��A���|�[�g�쐬�Ɏ��|����₷�������B�ܘ_�A��o���|�[�g������Ă����B
�i�Q�j�@�p�\�R���@�\�̊��p (1)�F���͖��B������w�i�ɂ����̂ŁA�_�����̌��t��������Ɠ��������A�����p�����ē����ŗL�������o��B���̂��ߎ��ԒZ�k�ړI�ŌŗL�����Ȃǂ́A���j���[�o�[�́u�ҏW�v����u���{����͎����ւ̒P��o�^�v�����Ă������B�Ⴆ�A�u���앐�n�v��������u�܂��́v�Ƒł����ŁA�u���앐�n�v���o�Ă���悤�ɂ��Ă����B�u�������v�Ƃ��������u���傤�������v�Ƒł��Ă��A��x�ł͊�]�̎����o�Ă��Ȃ��̂Łu���傤�v�ƁA�ł����ŖړI�́u�������v�̖��O���o��悤�ɂ��Ă������B
�p�\�R���@�\�̊��p (2)�F���l�ɁA�u�T�l�d�p�b�h�̎菑���F���v����łȂ��Əo�Ȃ��A�������́u���Λt�v�u�k�F軁v�u�s����v�u�g�ʏˁv�Ȃǂ̓���Ȏ��́A�F���ŏo������A��͂�u���{����͎����ւ̒P��o�^�v�����Ă������B���C�̗v�邱�Ƃ����{�f�B�E�u���[�̂悤�ɁA��ɂȂ��Ď��Ԃ̒Z�k��뎚�E���̖h�~�ɂ�������������B
�p�\�R���@�\�̊��p (3)�F����ɁA�C�_�쐬���u���v�̑}���𗘗p�����B����́A���y�ɋ����Ă������������@�����A���j���[�o�[�́u�}���v����u�Q�Ɓv�A�����āu�r���v���o���āu�����r���v���o���A�Ō�Ɂu�}���v���N���b�N����ƁA�u���v�����̖͂ړI�ӏ��ƕ����ɓ����ԍ����o�Ă���B����́A���͂ƘA�����Ă����̂ŁA�D����̂ł������B
�@ �ȏ�́u�p�\�R���@�\�̊��p�v�ɂ��ẮA���w��A���߂ăp�\�R������舵�������ł̘b�ŁA���ɏd���o���Ƃ��ď������B
�i�R�j�@���M���̎����ւ̃��b�Z�[�W�F�_�������Ԃ������A�r���ő��̎d�������Ȃ���쐬���Ă���ƁA�ǂ��܂Ői�߂�������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��������B�܂��A�O��̎����͂ǂ��������Ƃ��l���Ȃ��珑���Ă����̂��A�Y��Ă��܂����Ƃ��������B�����œo�ꂳ�����̂��A����p�\�R���Ɍ����������ɑ��Ắu���b�Z�[�W�v�����Ă������Ƃ������B
�@ �쐬�r���̘_���̍Ō�̍s�ɁA���t���J���[�����ɂ��ă��b�Z�[�W���Ă����B�Ⴆ�Ύ���2005�N�U��12���̏ꍇ�A
�y6��12���A23��20���I���B����ɂ́A��1�͑�Q�߁@���{�̖��B�o�c����@�u�ɓ�����R����֓����{�̒a���܂Łv�ɂ��ď������ƁB�Q�l������ (1)���R�ȕҁw�����R���j�@���x�����[�A1979�N�A1399�|1400�ŁB(2)���c��T�w�������x�������ؓ��A1922�N�A47�ŁB(3)�X���ȁu���������Y�ƃ��[�Y�x���g�v�w���{���j�x�ʊ���295���A�g��O���فA1972�N�A62�|63�ŁB�v����̎��A�撣���āI�z
�@ �ƁA�������B�}�A�A���b�Z�[�W�Ƃ����Ă�������p�̃i�r�Ɖ����݂̂����Ȃ��́B��������ƁA����A�ǂ�Ȃɂʂ������̏�Ԃ̎��ł��A�O��̎���������̎����ɓ������Ă���āA���������ƃM�A�[���R���ɐi�ނ̂������Ȃ�̂������B
�i�S�j���O�ɏW�߂��_����Q�l�����́A�C�m�_���ɊW����Ƃ����ł��o���āA�p�\�R�����Ƀt�@�C��������Ă������B
�@�Ⴆ�A
�@ �፲�X�ؓ���w����R�l�̎��`�x���ʎЁA1963�N8��10���@�u���앐�n�v�f��119�ŁB�u�ނ͗\���V�ږ�ƌ����c�c�����̕�V�ږ�͏��䎵�v�A���앐�n�A�V�䐽���ɂāc�c�v193�Ł@�u����͓����ʼn��ԁA���`�҂̋V�䂾���͋��ɑ���āc�c�v��
�@ �ƁA�_�����e�Ɏg���������̂�A�d�v�ȓ��e��ł��o���Ă������B����ƒ����������ł͎v���o���ɂ������Ƃ��A�S��₷�������B
�S�@�s��ȗ��ɂ͑傫�Ȏ��Ԃ̗��ꂪ�������Ȃ��B�C�m�_���쐬�͂����Ǝ��Ԃ��������Ȃ��B
�@�_���쐬�����Ă��āA��Ԏ��Ԃ����������̂��p�\�R���őł��Ƃ������B���_�A�Q�N�O�̓p�\�R���Ƃ͖����̐����ł��������������邪�A���͂�ł̂ɍl���Ȃ���ł�����A�܂������肪�~�܂��Đi�܂Ȃ�������A�ꎟ�����̓ǂݍ��݂Ɏ��Ԃ����������肵���B���ɂ͓������e��ʂȃZ�N�V�����ŏd�����đł��Ă���A���̓ǂݕԂ��ƒ����ŁA�_���쐬�̃M�A�[���o�b�N�ɓ����Ă��܂��A�������i�܂Ȃ����Ƃ��āX�ł������B
�@ �������A���͗͂̂Ȃ����@���ɏo�āA����ł͂Ƙ_���ɂӂ��킵���\����T���o���n�߂�ƁA�������{�̐��E�ɂ͂��荞��ł��܂��B
�@ �܂�A�s��ȗ��Ɠ����ŁA���ɂƂ��Ă̏C�m�_���쐬�́A���ɑ����̎��Ԃ��������Ȃ������B�Ɠ����ɁA�Ō�̍Ō�܂Ŏ��Ԃɒǂ����ςȂ��ł������B
�@ �����A�Y��邱�Ƃ̏o���Ȃ��ЂƂ̌��t���A���������܂��Ă���Ă����B����́A�C�m�_���쐬�̂��߂̂���T�C�o�[�[�~�̎��A�ߓ��������[�~���̎��B�Ɂu�ꎚ�ł���s�ł������Ă��������v�ƁA����ꂽ���Ƃ������B����܂ł͊��S�łȂ���Θ_���̕��͉��͑ʖڂȂ̂ł͂ƁA���͏���Ɏv������ł����B�������A���̌��t���Ă���́u�������I�ꎚ�ł���s�ł��ǂ��̂��A����Ȃ�ŗL���������ł������Ă݂悤�v�Ǝv�����Ƃ��ł��A�_���쐬�Ɍ��������Ƃ��o�����B�]��ɂ��P���Ȏ~�ߕ��ł͂��邪�A�_�����s�����肫�������̂��B�Ƃ��ɂ��̌��t�͍s���l�������ɗL������B
������
�@���̂Q�N�Ԏ��͏C�m�_���쐬�Ƃ����A�s��ŔM�����������Ē������B�w�������ł���ߓ��������͂��߁A�����[�~�łƌʂɂ��w�����������������A��w�@�̏��搶�������ē��w������x���ĉ��������ΐ搶�A�[�~�̊F�l�����̂��w����A�h�o�C�X�����Ƃɂ���āA���̔M�����ł���C�m�_���쐬�𐬏A���邱�Ƃ��ł����B����ق��ґ�Ȏv�������Ă����Ƃ͏I���Y�ꂦ�ʂ��ƂƁA�S����S����A���ӂ��s���Ȃ��v���ł���B
�@ �����āA���̂Q�N�Ԃ����悤�A����Ɍ����ĂȂ��Ă����Ȃ���Ǝv���̂ł���B

�u���������̌��_�v
��������U�@�������G
�� �͂��߂�
�@���̂Q�N�Ԃ̏C�m�ے���U��Ԃ�A���ꂩ��C�m�_�������M���悤�Ƃ���F����ɁA�����炨�`���ł��邱�Ƃ�����Ƃ���A����́u���_�̑���v���Ǝv���܂��B���_�Ƃ́A��w�@�ł̌������u�������̏��S�ł���A�X�^�[�g�n�_�Ōf����ꂽ�����ڕW���Ӗ����܂��B�u���̂��߂ɁA����������̂��v�B����͐l���ꂼ��قȂ��ē��R�ł����A�������g�̌����ڕW�₻�̎Љ�I�Ӌ`�������ӎ��ł���قǁA���X�̌����⎷�M�������X���[�Y�ɐi�ނ悤�Ɋ����܂��B�����ł́A���ꂩ��C�m�_���̎��M��ڎw�����X�ւ̃A�h�o�C�X�Ƃ��āA�������̎������q�ׂ����Ǝv���܂��B
�� ���_�̑��
�@ �C�m�ے��Ō����������F����́A���R�Ȃ���i�����g�������ł������悤�Ɂj�C�m�_���������̂͏��߂Ă̂��Ƃł��傤�B�ŏ��́A���m�̉ۑ�Ɉ��|�����s�������邩�Ǝv���܂��B���邢�͋C�����Ɏ�����M��������Ƃ����邩������܂���B����Ȏ��́A�܂��S�𒆗��ɂ��āA�����g�̌��_�ł��鏉�S�⌤���ڕW�ɂ��āA�a�₩�ȕ��͋C�̂��ƂŎw�������Ƃ��b������邱�Ƃ������߂������Ǝv���܂��B�w�������Ƃ̉��C�Ȃ���b�̒�����A�C�m�_�����M�̂��߂̏d�v�ȃq���g�������邱�Ƃ͒���������܂���B�܂��A�C�m�_���Ƃ����u���m�̕ǁv�ɕs�����o�����ۂɂ́A�Ŋ��̑�w�}���ٓ��ŁA���ۂ̏C�m�_����I�v�_���Ɂg�L���h�G����邱�Ƃ������߂��܂��B����ɂ��A���ꂩ�玷�M���悤�Ƃ���u�����i�̊T�ϐ}�v���C���[�W�ł��A���m�Ȃ���̂ւ̕s�����a�炮�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�{�����Ȃ̊w���������A�������Ƃ��đ���w�̐}���ق�K�₷��̂́A�ƂĂ��M�d�Ȏh���ɂȂ�͂��ł��B���Ȃ݂ɁA���ɂƂ��Ắu���_�v�́A�w�A�X�^�C���X�g�i���e�t�E���e�t�j�̂��߂̃��e�B�x�[�V�����{�ʂ̎����p�ꋳ����������邱�Ƃł����B���̍���ɂ́A�������g�����ĉp��w�K�������Ă����o������A�u�p�ꌙ���Ȑl���~�������v�Ƃ����v��������܂����B�����������́u���������̌��_�v�ɂ��āA���w�������A�����ӌ������̋@���݂��Ă����������w�������ɂ́A�����S���犴�ӂ����Ă���܂��B
�� ���C�Ȗڂƌ��_�Ƃ̐ړ_
�@ ���C�ȖڂɊւ��ẮA�P�N���ɂȂ�ׂ������i�T�Ȗځj��I�����Č������L�߁A�X�̉Ȗړ��e�ƁA���g�̌��_�Ƃ́g�ړ_�h���ӎ��������邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B���|�[�g���M�̂��߂̕��������̍ۂ��A�C�m�_���̌����ڕW����ɔO���ɒu���A�����̊֘A����T��C�����ŗՂ߂A�����ӗ~�����シ�邾���łȂ��A�K�R�I�ɓƎ�������H���������|�[�g�Ɏd�オ���Ă䂭�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A�������Ċ����������|�[�g�́A�C�m�����̈�[�Ƃ��āA���炩�̌`�ŏC�m�_���ɐD�荞�ނ��Ƃ��\�ł��B�P�N���̕��L���Ȗڗ��C��ʂ��Ĕ|���������́A�C�m�_���̎��M�ɑ傫���𗧂Ǝv���܂��B
�� �v�����ĖY��Ă݂�
�@����ł��A�C�m�_�����M�̉ߒ��ɂ����ẮA�X�����v�ƌĂ�鎞�������낤���Ǝv���܂��B�ꋫ�����z������@�͐�y������̋M�d�ȏ��������Q�Ƃ��������Ƃ��āA���͂����āu����Ȏ��͂��炭���ׂĂ�Y��Ă͂ǂ����v�ƃA�h�o�C�X���������Ǝv���܂��B�Ђ�����Ɏ��g�ގ��M�������狗����u�����ƂŁA�V�N�Ȏ��_��v�l�͂��h���Ă��邱�Ƃ�����܂��B���͂Q�N���̂X���ɁA60�y�[�W�قǏ����i��ł����C�m�_���̑��e�����ׂĔj�����A�C���������S�Ƀ��Z�b�g����o�������܂����B���̗��R�́A���M���̑��e�ł͎��g�̌��_�i�����̖ړI�j�����m�ɔ��f����Ȃ����ƂɋC�t��������ł����B���ߐ肪�W���W���Ɣ��钆�A�_���\���̑S�ʓI�Ȍ��������w�������ɑ��k�����̂��A��Q�����ԁA���͎v�����Ď��M��Ƃ��痣��܂����B���v���A�����Ԃ�댯�ȓq���������̂�������܂���B��_�ȃ��t���b�V�����Ԃ��I�������́A�����ʂ�S�����ւ��āA����܂łɒ~�ς����f�[�^�╶�����g�V�N�Ȕ��f�́h�ň�C�ɐ������A�݂�����̌��_�ł���u�w�A�X�^�C���X�g�̂��߂̎����p�ꋳ��v�ɓ��������g�V�E�C�m�_���h���[�����珑���グ�邱�Ƃ��ł��܂����B���̍��A���傤�ǔN���N�n�̍Q���������ł������ɂ�������炸�A�w�������́A80�y�[�W�ȏ�ɂ킽��V���Ș_���J�ɓY�킵�Ă��������܂����B���̂��w���̂������ŁA���̏C�m�_���͌��ʓI�ɁA���w���̌����v�揑�ɋL�������_�ɉ�A���錤�����ʂɎd�オ���Ă����̂ł��B�u���������́A���������̌��_�֖߂邱�Ɓv�B���ꂩ��C�m�_�������M�������X�ɂ͂��ЁA�����g�́u���_�v����Ɉӎ�����A�g���������ɂ����������Ƃ̂ł��Ȃ��C�m�_���h�����������Ă������������Ɗ���Ă��܂��B
�� �ӎ�
�@ �Ō�ƂȂ�܂������A�Q�N�Ԃ̏C�m�ے���ʂ��A�����C���ւƓ����Ă����������ɓ��T�q�������͂��߁A�{�����Ȃ̐搶���ɉ��߂Č���\���グ�܂��B�܂��A�����̏�������ʂ��A�݂��ɗ�܂������Ă����������ɂ��A���ӂƘJ���̋C������`�������Ǝv���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�@

�u�f�����������\�\���̏C�m�_������L�\�\�v �@�@
��������U�@�O������q
�@�u�g���r�A�݂����Ș_�����ȁv���̘_����ǂ�l�̑�ꐺ�������B��l�͎d�����_�����ꂵ�Ă���B�䂦�Ɉ�Ԍ��������Ȃ����肾�����B
�@�ʐڎ���̍ہA�u���{�ꂪ���������B�N���T�ɓ��{��̃`�F�b�N�����Ă����l����H�v�ƂȂ�Ƃ��\�����ʃR�����g�������������B��l���̓��ɔ����āw�ʐڎ���̎��x�Ȃ�{���ǂ݂���Ȃ�Ɏ��^�����̏��������Ă����̂����A���܂�Ɉӕ\�����������t�Ɍ��t�ɋl�܂��Ă��܂����B
�@�u�Ȃɂ�B�g���r�A���āv������Ƃނ��Ƃ������B�u�{���ƊW�Ȃ����ʒm�����ˑR�o�Ă���v�Ǝ�l�͏��Ȃ��猾�����B����ɏ��X���Ԃ������ȕ\��������Ȃ���A�u���̘_���A�ʂ����́H�v�ƃy�����Ă���ԃy�����w��ŒT���Ȃ��猾�����B�u�������I�@�����ł�邩��B�v�ƁA���\�ɘ_�����Ђ����������B���̓��b�Ƃ��Ă͂������̂̌��nj��ĖႤ���Ɂi���Ă��炦�����j�Ȃ邾�낤�ƃ^�J���������Ă����B
�@�u���߂����Ȃ�����A�o���\�[�X�������Ƃ���������悤�ɁB�v�Ƃ����搶������̂��w�����A���̍�Ƃɐ������₵���B��x���Ă��܂����{���炻�̏o���ӏ���T���̂͌��\����c�c�E�B�ǂ�������̈��p�Ȃ̂�����K���ǂ����ɂ���͂��Ȃ̂����A���\���̎Q�l�����̒�����̐��s�͂Ȃ��Ȃ��݂�����Ȃ��B
�@ �p���ɋ����\���Ă��鎄�́A1��21���̖ʐڎ���̂��Ə��p��1�T�ԓ��{�ɑ؍݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B��o������2��13���K���B�p������̗X���������l����ƁA2��5���������^�C�����~�b�g�ł���B�܂萳���킸��1�T�Ԃł��ׂĂ��I��点�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@����2�N�ԁA���{�Ɖp���̋����ɂ����Y�܂���Ă����B�Ȃ��Ȃ��[�~�ɏo�邱�Ƃ���(�܂�)�Ȃ炸�t���X�g���[�V���������܂�B�ʏ��Ƃ̒��݂Ⓑ���؍݂̂Ȃ��2�`3�N�ŋA��邾�낤���A���{�Ɉꎞ�A��������@����������낤���A���͂��łɏZ���[���ڂ��Ă��܂��Ă���g�A�w�Z�ɒʂ��q�ǂ��̂��Ƃ��l���Ă���������Ƃ͋A��Ȃ��B���|�[�g���������邽�тɎQ�l�}������ɓ��炸�ǂ�قǁg�A�}�]���h��gOCS�h�̂����b�ɂȂ������킩��Ȃ��B���Ȃ݂ɃA�}�]���̊C�O�����Œ�n���h�����O�`���[�W�́A4,000�~�ł���B�܂�520�~�̕��ɖ{1����4,520�~�ɂȂ�̂ł���B����������������̕����������Z����A��������发��n�[�h�J�o�[�͑傫���ďd���B��������������10,000�~���z���Ă����B����ɃC���^�[�l�b�g��Ŕ����镶���̐��͏��Ȃ��B�����I�ׂ�̂͂��̋�����ނ���݂̂ŁA���������g�����đI�Ԃ̂ł͂Ȃ�����^�C�g���ɗ����邱�Ƃ������ł���B���X�]�k�b�ɂȂ邪�A�p���̓X�g���C�L���D���ȍ��ł���B���{�ł͐M�����Ȃ����낤���A���h���ł���3�����Ƃ����X�g���C�L�����s����B���̊Ԃɉ�������ΌR�����o������̂ł���قǂ̑���ɂ͂Ȃ�Ȃ��i�Ƃ͂����A���Ԓn����̌R���̓������x��A��q���ЂŏĎ��������Ƃ�����j�B�����A�X�֔z�B�ƂȂ�ƌR���Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��̂��낤�B���{�̎��ƌo�R�ő����Ă���͂��̋��ȏ����A�X�g���C�L�̂��߂ɗX�ǂ�3�T�Ԃ����~�߂�H����Ă��܂����B���ۂ�3�T�Ԃ̃X�g���C�L�̌ソ�܂����X�֕��̔z�B���n�܂�̂ŁA�茳�ɓ͂����̂�5�T�Ԍゾ�����B���ǂ��̎������|�[�g��o�ɊԂɍ���Ȃ��Ȃ�̂ŁA�܂����������{����{�̏��X�ɒ������A���{�Ɏ咣�ɍs����l�̑؍ݐ�̃z�e���ɑ���͂��Ă��炢�A���낤���Ē�o�������ɊԂɍ��킹�邱�Ƃ��ł����B���|�[�g��o�̂��тɏ������������@��g�ɂ��Ă͂����̂������x�͂ǂ����Ă��Q�l�}������ɓ��炸�A���|�[�g�����ɂ������Ԃɍ���Ȃ��B��ނ������]�o���ɔ�s�@���n���A�w�����ĉp���܂Ŏ����Ă��Ă���������Ƃ�����B
�@ ����Ȃ��Ƃ������Ă��܂��ƁA�C�̓łɁc�c�Ȃ�Ďv��ꂪ�������A��Q�������Ȃ�Α����Ȃ�قǂ���ɂ�����G�l���M�[�͑��債�R���オ����̂ł���B������Ɨ����Ɏ��Ă��邩���m��Ȃ��B��w�@�Ƃ̒����������Ɏ��ς��i��ς��A�����g���ǂ��ɂ�2�N�Ԃ𐬏A�����̂ł���B
�@ �����̒Z�C�Ȑ��i������قnj���������Ƃ͂Ȃ��B��o�Q���O�̂��Ƃł���B�\�Ȍ���o���\�[�X��T���A���e���������Ă���]�T�͂������������̂Ŗʐڎ��⎞�ɐ搶�����炢���������R�����g�ӏ��A���_���C�������Ƃ͎�l���A�������{��̂���ӂ�ȉӏ��̃`�F�b�N�����Ă��炤�����B�ƂȂ����ӂł���B�锼�ɏo����̃h�C�c�ɂ����l����d�b���������B�u���ڃo�[���[���ɍs���v�Ƃ������̂ł������B��k����Ȃ��I���͂ǂ��Ȃ�̂�A�Ɠ{�肽���Փ���}���A�����b�����B�Ƃɂ����Y�t�t�@�C���Ř_���𑗂�悤�ɁB�Ƃ������Ƃ��������A��l�̃p�\�R���͓��{��Ή��ɂȂ��Ă��Ȃ��B���������̋���A���ǎ�l�̃`�F�b�N���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����A���̎��f���Ɂg�Ԃ���h�����肢���Ă�����悩�����̂Ɂc�c�B�͂����c�c�B
�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����\���v�\Time Up
�@�y�n���A�_�����ꂵ�����{�l��w������w�҂���͂�������B�ނ�ɂ����肢�����邱�Ƃ͏\���\�ł������͂��ł��邪�A�e������ΐe�����قNjC�������Ă��܂��_���Y��Ȃǂ��肢���ł��Ȃ��B���ł����Ă������B�Ȃ�Č����Ă��Ă��A��o�Q���O�ɂȂ��āu��낵���v�Ȃ�Č�����͂����Ȃ��B�l�ԁA�f�������������邱�Ƃ�����Ə����K�V�����������Ă����c�c�B
�@ ���́w����L�x�͂��܂�Q�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ���������Ȃ��B���������Đ��ӋC�����m�ŁA�ӎ����Ȃ������ق��������Ɛ\���グ�����_��2����B
�@ �ǂ�ȏ����Ȉ��p�ł����Ă��A�o���\�[�X�͕K�����������Ă������Ƃ������߂���B�c��Ȏ�����O�ɂ��炽�߂ĒT���ƂȂ�ƁA�Ƃ�ł��Ȃ����Ԃ�������B
�@�����Ă����ЂƂ́A�������O�|���Ɋ������l���A�s���̏o�����ɋ����邱�Ƃł���B���ؓ�����ؓ��ɂ�����A�����ʂ̂��ƂɎ��ԂƑ̂��Ƃ���ƃ��J�o���[�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��i�����A12��27���ɏC�_�ׂ̈̃��T�[�`�ŃG�W�v�g�ɍs�������A�����ŕa�C�ɂ�����1�T�Ԉȏ�Q����N������ɂȂ��Ă��܂����B����Ȃ̑z��O�B���ǁA������|�[�g��2���Ȓ�o�ł����j �B
�@ �����ĉ����A�ǂ�Ȋ����ł����Ă��y����ł��܂������̂ł���B

�u�e�n�q�v�`�q�c�v�@�@
��������U�@�j�R������
�͂��߂�
�@��N�Ԃ͑��������B�C�m�_���͊y���������B��w�@�����͌����Ċy�ł͂Ȃ���������ǁB�v���Ԃ��Γ��w�����犥�����ՂƏd�Ȃ��Ă�ނȂ����ȁA�Ǝv������A���Ԕ��\���_����o���Ԃ܂ł��A�܂�ō��킹�����̂悤�ɐg���̌��������d��C�O�֏o�˂Ȃ�Ȃ������B���X�̃[�~�ɎQ���������Ă��x�r�[�V�b�^�[�������Ȃ���ΉƂ����Ȃ��B�T���Z�����Ƒ��ɖ��������ė��ݍ����Ƃ��������B����ł����X�̃[�~�̂قƂ�ǂ����Ȃ��錋�ʂɂȂ��Ă��܂����B�[�~��f�邽�тɁu����Ȃ͂�����Ȃ������v�Ɩ��͊��ɉՂ܂ꂽ�B���Ԃ��Ă���d���ɂ��g�������āA���|�[�g��o�⍇�h������Ƃ��܂��ĖZ�����Ȃ�悤�Ɋ������B�ŏ��ɔ��邪�A���͖͔͓I�@���ł͂Ȃ������B
�n���f�B
�@ �c�q��������e�͉Ƒ��̋��͂Ǝ��Ԃ̍H�v�Ȃ��Ɍ����̌p���͕s�\���B��������������ɂ���A�T��ŏ������邱�ǂ��̏Ί���������قlj��l�̂�����̂����̐��ɂ���̂��낤���B�Ƃɂ�����x���߂����Ƃ��A����͈͂Ő���t��邵���Ȃ��B���N�����ČߑO���Ɏd����Еt���A�ߌ�͂��ǂ���ڈ�t�V���i�o���邾���̗͂̏��Ղ���O�V�т��ǂ��j�A��͔����ɂ������ƐQ�������A���̌�Ɏ��̊w�K���Ԃ��m�ۂ���B�m�����������\��ł��������A�����ڈ�t���ǂ��ƗV�ԂƐ�ɖ��荞�ނ̂͂������ł������B�c�q��������e�͉��ł��\��ʂ�ɕ������i�܂Ȃ����Ƃɂ͊���Ă���B�^�钆�Ƀ{�[���ƋN���Ă��ăR���s���[�^���������͂����Ƙ_���ւ̎��O�ɂƂ���ꂽ�S��̂悤�ɕv�̖ڂɉf�������Ƃ��낤�B
�@ �������A�ʐM����w�@�֒ʂ����k�͊F�Z�����B�n���f�B�͎������������Ă��邱�Ƃ���Ȃ��B�F��������Ċ撣���Ă���̂��B�v���Ԃ��Γ�N�ԁA���͏��Ȃ����������h��[�~�Q���̂��ߒ���Ԃ̐V�����ɏ�荞�ގ����A���N�����Č������Ă��ꂽ���ǂ�������A�d�����x��Ńx�r�[�V�b�^�[���Ă��ꂽ�Ƒ���A�R���s���[�^�Ɍ������S��ɂ����ƃR�[�q�[�����Ă��ꂽ�v�̂��Ƃ��v�����сA�ނ������ɂȂ�C�������������A�ǂ��_�����������Ƃ����v�����������������Ă����B���Ԃ��͂��ꂵ���Ȃ��B���v���A�n���f�B�Ɏv�����F�X�Ȃ��Ƃ́A���ۃn���f�B�ł͂Ȃ������B
�[�~
�@ �[�~�ɖ����ɏo�Ȃł��Ȃ����Ƃ������ڂɊ����Ȃ���A����ł����h�ɂ�3��Q���ł����B����͖{���ɗǂ������B�r��y�̔��\���ŏ��ɕ������̂̓T�C�o�[�[�~�������ƋL�����Ă��邪�A�ƂĂ��ʔ��������B�����Ƌ������Ƃ��Ȃ������炾�B�������\����Ȃ�A�����Ă���l���u�������낢�v�Ƌ����������ĕ����Ă����悤�Ȕ��\���������Ȃ����B���������Q�����Ă���F�l�ɁA��������U������悤�Ȃ��̂ł͐\����Ȃ��B���\�̂��߂������ƌ��e�������A�����̌����Ă��邱�Ƃ��F�ɔ[�����Ă��炤���߂Ɏ����W�߂ɂ��͂���ꂽ���A���ۂ���ȏ�Ɏ����̌����̕����L���Ă��ꂽ�̂́A���\��ɒ������F����̎����R�����g�A�A�C�f�A�A��܂��┽���ł������B�_����������Ő���A�[�~��O�����ɏ�肭���p���邱�Ƃ������߂���B�����̋C�Â���A���ꂪ�ǂ̕ӂ�Ɉʒu�Â��̂����m�F����ǂ��`�����X�ɂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�ۑ�
�@ �C�m�_���̒��Ř_��W�J�����ŁA�傢�ɖ𗧂����̂����C�Ȗڂ̉ۑ�Ɏ��g�ނ��Ƃł������B���C�Ȗڂ̓o�^�́A�����̋����̌����܂܂ɓo�^�����B�u�Ȃ�ł���Ȃ��ȗ̈�Ȃ́H�v�Ƃ�������������̃R�����g�����������A����ŗǂ��̂��B�_���������グ�Ă݂���A�_���̃e�[�}��ʂ��đS�ẲȖڂ��Ȃ������B�����ŊJ�������̒����牽�����o�����͎�������Ȃ̂��B���ꂩ�珔��y���̏����̂Ƃ���A���C�o�^�͍ŏ��̔N�Ɋ撣���Ĉ�ł��������C���邱�Ƃ������߂��B��N�ɂȂ����Ƃ��_���ɏW���ł���B�����A���̏ꍇ�A�_���Ɠ����i�s�Ői�߂����|�[�g���A�_���������̂ɂƂĂ����ɗ������͎̂������B�ނ��듯���i�s���������珑��������������B���|�[�g�̃A�C�f�A��_���Ɏ����ꂽ��A�_�W�J�̃q���g�������邱�Ƃ��܂܂������B��ȏ�̂��Ƃ��i�s�ł���Ƃ����Z�͎�w�ɂƂ��Ă͓��ʂȂ��Ƃł͂Ȃ��B���ɂ͎O���l�������i�s���B���������Ȃ��炱�ǂ��̏h������āA�p�����Ă��Ȃ���|���Ɛ�������āA�v�̘b���Ȃ���E�g�E�g����\�\���ς�炸���͏ł��邵�A�������������܂Ő���@�ɓ����Ă��邵�A�v�̌��������Ƃ�S�R�o���ĂȂ������肷�邯��ǁA�Ƃɂ�����������Ė����b���Ă��邱�Ƃ��A�_���Ɖۑ�̓����i�s�ɖ��ɗ������̂�������Ȃ��B�_�������|�[�g�ۑ���Ǝ����d�����玙���S���Ђ�����߂āA�������ǂ�����ď�肭���������Ċ��������邩�A���ꂪ��w�Ƃ��Ă̎��̖{���̉ۑ�Ȃ̂��B
�e�[�}
�@�_���ɂ��Ă����ɂ��Ă��A�����Ƃ������Ƃ́A�S�̒��ɖ��ӎ����Ȃ��Ɠ���B��ɖ��ƌ��������ĉ������悤�A�����ł��Ȃ��Ă����߂Ď����Ȃ�̓������o�����Ɠw�͂���ߒ������̘_�W�J�ŁA���̋L�^�����ʂƂ��ďC�_�ɂȂ����B�������o�������F�X�Ȗ������������Ă���A�Ƃ����Ӗ��ł́A���͔��Ƀ��b�L�[�ł������B���Ȃ��Ƃ��q��Ă⌋��������ʂ��Ď��͖�������������ނ悤�ȐF�X�Ȗ��ɒ��ʂ�����Ȃ��B�����玟�ւƌ������ɂ͏I���Ƃ������̂��Ȃ��i���������邽�߂ɂ����ĕ⑫�����Ă��炤���A�����_���ň������̂́A�����ĕs�ς╂�C��c���s�҂◣�����ł͂Ȃ��j�B���̌����Ώۂ͎������w�����S�ɂȂ邪�A�����ɂ͎��̋��߂�e�[�}���D�荞�܂�Ă��āA�Ȃ������̒T���̓��@�ɂ��������ɂ��������̂����ċ������邩��ł���B�����̕�������ӎ��Ƌ������т��A�܂�������������悤�Ƃ����������@�ɉ��x�����ꂽ�e�[�}�͘_����������ōł���Ȃ��̂̈�ł���ƍl����B
���
�@ �Ō�Ɏ��̎w�������ɁA����Ȏ��̗���ɂ��������������Ē����A����ɐL�ѐL�тƎ��R�Ɍ����𑱂������^���ĉ�����A�h����������葱���Ē��������ƂɐS���犴�Ӑ\���グ�����B�ꐶ�k�Ƃ��āA��]�����w���������璼�ڎw�������邱�Ƃ͖{���ɍK�^�Ȃ��Ƃł���B�������Ă���e�[�}�Ɏ��g�ނ̂ɂ͂����������Ԃ�����̂ŁA�����������������炻�̎��͂܂��搶�̃h�A���m�b�N�������Ǝv���B
�@

�u���ӂ̋C������Y�ꂸ�Ɂv�@�@
��������U�@�ї��@��q
�͂��߂�
�@���������悤�ȒZ�������悤�ȂQ�N�Ԃ��A���������I��鎞������B��w�@�i�w���l���Ă�����܂߂�Ɩ�R�N�ԁA��͂�Z�������ƌ����ق�����������������Ȃ��B
�@�{���̂悤�ȏ��q�w���i�I�j�������I����ɂ�����A�����̒��ł̈���Ƃ��ďC�m�_������L�i����A�퓬�L�����H�j���L���Ă������ƂƂ����B
�P�D�w�ƂƎd���̃o�����X
�@ ���̑�w�@�ɓ��w���Ă�����������́A�قڑ唼�̕����E�Ɛl�ł���Ǝv���邪�A�������̒��̂P�l�ł���B���������Ӗ��ł́A�d�������Z�ł��邱�Ƃ��w�Ƃ̒x��̌�����ɂ͂Ȃ�Ȃ����A�����͑z���ȏ�ɉߍ��Ȃ��̂������B
�@2005�N�R������X���܂ň��m���ŊJ�Â��ꂽ�u���E�n�����v�̊��ԁA�d���ɖZ�E����邱�Ƃ͂��炩���߂킩���Ă������A�����Ď���2004�N�ɓ��w�����B�܂薜�����Ԓ��͏C�m�Q�N���ŁA�C�m�_���������Ȃ���Ȃ�Ȃ������������̂ł���B����������ł����w�����ӂ����̂́A�u�v�����������g���v�Ō��߂��ȏ�͂����ɕ����n�߂��������̂ƁA�C�_�������I����ɏW�����Ă��Ή��Ƃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����Â������݂���ł������B
�@ �����A�����͂�͂茵���������B���������łȂ����̎d�����܂߁A�u���ω����炢�肪�~�����I�@���f�D�[�T�݂����w�r�̓��ł���������]���ɗ~�����I�v�Ƃ����ɂȂ�A�w�Ƃ͑S���ƌ����Ă����قǒ���Ȃ������B�܂��d����A�y�����W�Ȃ��ɂȂ�A�P�����ԑS�����x�Ƃ������Ƃ��������肵�āA���͊ہX�����ł��Ȃ��������������X���������Ƃ������ł���B
�@�������A�����n���h�o�b�O�̒��Ɏ�����e�L�X�g�����Ď��������A�ړ����ԂɂP�y�[�W�ł���������ǂ����Ƃ����C���������͈ێ����Ă����i�Ƃ͂������̂́A���ۂ͓d�ԂŔ������Ă���Ƃ���𐏕��Ɗw���ɖڌ�����A���Ȃ�p���������v���������̂������ł���j �B
�Q�D�e�[�}����Ǝ������W
�@ �����A����Ȏ��ł��~��ꂽ�̂ɂ͗��R������B�܂��P�ɂ́A�C�_�e�[�}�͓��w������͂�����ƌ��܂��Ă����̂Ŗ������Ȃ��������ƁA�����P�̗��R�Ƃ��ẮA�e�[�}�����܂��Ă����̂łP�N�����玑�����W���n�߁A�����i�K�ł�����x�̐�s�������������Ă������Ƃł���B�����I�ȈӖ��ł̐}���فA���X���n�߁A�o�[�`�������C�u�����[�����낢��ƌ����������A�������Ȃ����ƂŔw�\����T�v�������i�K�ŁA���ꂪ�����̕K�v�Ƃ��Ă�����̂��ǂ������A�����ɔ��f�ł���悤�ɂȂ��Ă���B����͎d�����A��ɂ��낢��ȕ���̕��������Ȃ�������Ȃ��Ƃ��납��P������Ă����������Ǝv�����A���̂������Ŏ������W�����͋�J�����ɍς悤�ȋC������B
�@ �Ƃ͂����A�������W�͑����i�K����n�߂�ɉz�������Ƃ͂Ȃ��B�v�������Ȃ��������o�Ă��邱�Ƃ�����A�v�����悤�Ɍ�����Ȃ���������B�܂��}���ق�����ƂȂ�Ǝ��ԓI������l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�������W�͑��ߑ��߂��̐S�Ǝ��������B
�R�D�p�\�R���̎g����
�@ �������A�����玑�����W�܂��Ă����͂��Ď��ۂ̘_���Ɏd�グ�Ȃ���ΈӖ����Ȃ��B�����Ŏ������{�����̂́A�܂��ȒP�ɖڎ������߂ď����ݒ肷�邱�Ƃł������B���炩���ߖڎ������߂Ă����A�����C�Â������ɂ��̍��ڂɈ��p�Ȃǂ���͂��Ă����A���Ƃł�����ł��R�s�[���y�[�X�g���o���邩��ł���B�܂��ŏ�����ڎ��Ȃǂ̏����ݒ�����Ă����A�Ō�ɖڎ����쐬���鎞����J�����ɍςނ��Ƃ��킩���Ă����̂ŁA�Ƃɂ������t�ł���������A�Ɩڎ������߂ď��������͂�����Ɛݒ肵���B
�@�����P�K������Ă������Ƃ́A���������Ă��ċC�Â������ƁA�܂����p�ł������ȕ����ɂ��ẮA�����ɂ��̏�œ��͂��邱�Ƃł������B�܂����ƂŁc�c�Ȃǂƌ����Ă��ẮA��̂��ɂȂ�����o���邩�킩��Ȃ��B�u�C�Â������ɃA�N�V�������N�����I�v�Ƃ������Ƃ����͎����ɉۂ��Ă����B
�@���ہA���ꂪ���̏ꍇ�͔��ɖ��ɗ������B10���̒��Ԕ��\�܂łɈ��p����e�L�X�g�i�����j�̓��͂��ς܂������߁A���̌�͎����̘_�_��W�J���邱�ƂɎ�͂𒍂����Ƃ��o��������ł���B����Ȃ��Ƃ͓��R�c�c�Ǝv����������������邩������Ȃ����A���͓��͍�ƂƂ����͈̂ӊO�Ɏ��Ԃ̂�������̂ł���B�f�[�^�G���g���[�̃X�s�[�h�ł͍��܂Ől�ɕ��������Ƃ��Ȃ��i�l�ޔh����Ђł͂����X�s�[�h�L�^���X�V���Ă����j���ł��A�C�_�쐬�ɂ͂��Ȃ莞�Ԃ��₵���B��������ɂ͍l���鎞�Ԃ͊܂܂�Ă��Ȃ��B�P���ȍ�Ǝ��Ԃɋ��낵�����Ԃ����������̂ł���B����āA�����͓ǂ݂Ȃ���C���v�b�g���Ȃ���A�Ƃ������s��ƂŐi�߂邱�ƂƂȂ����B
�@ ���̑��p�\�R���̎g�����Ƃ��ẮA�f�[�^�ۑ��ɋC�����Ă����B�Ƃ����̂��A�n�[�h�f�B�X�N�ɓ���Ă����ăp�\�R�����g�p�ł��Ȃ��Ȃ����ꍇ�A����^���Â�����ł���B���̂��߃n�[�h�f�B�X�N�ɓ����Ƌ��ɁA�O�����f�B�A�i���̏ꍇ��USB�ƃR���p�N�g�t���b�V���̂Q��ށj���g���āA��ɕۑ����Ă����B����ə{���ʂȁi�H�jO�^�̎��́A�A�b�v�f�[�g�������̂��v�����g�A�E�g����܂ł͂��̑O�ɏo�͂������̂�ۑ����Ă������B�O�����f�B�A�ŏ\���ł͂Ȃ����Ǝv���邩������Ȃ����A�����͂�͂艽���N���邩�킩��Ȃ��B�d�q�f�[�^�͈�u�ɂ��ď�������\��������B���������ň��̃P�[�X��z�肵�āA�X�L���i�[�œǂݍ��߂�悤�Ƀn�[�h�R�s�[���K���P���͎茳�ɂ����Ă������ƂƂ����B
�@ �����P�C�����Ă������Ƃ́A�f�B�X�N�N���[���A�b�v�ƃf�t���O�ł���B�l�b�g�ł��낢�댟�������Ă���ƁA���̊Ԃɂ��f�B�X�N�ɕs�v�ȏ���܂��Ă����肷��B�܂��N�b�L�[�ɂ��s�v�Ȃ��̂����܂��Ă����肷��̂ŁA���X�f�B�X�N�N���[���A�b�v�����ăn�[�h�f�B�X�N�̂��|����S�������B�܂��f�t���O�����܂ɍs���A�}�V���������X���[�Y�ɂȂ�悤�ɂ��C�����Ă����B
�S�D���݂̋ꂵ��
�@ �ƁA�����܂łȂ�A���ɃX���[�Y�Ɏ����^�悤�Ɍ�����B����������͑傫�Ȍ���ł����āA��������悪�{���ɋꂵ�������B
�@ ���Ԕ��\�ł��낢�낲�w���E���w�E���Ă���A���悢��ǂ����݂Ƃ������ɑ�X�����v�Ɋׂ����̂ł���B���Ԕ��\���I��������ƂŋC�������Ă��܂������ƁA�܂����\���O�ɒǂ����݂����������߁A�����ň�u�o�[���A�E�g���Ă��܂����̂ł���B���ꂩ��͂Ȃ��Ȃ��_�����܂Ƃ܂炸�A�p�\�R�����J���Ă��P�s�������i�߂��Ȃ��Ƃ������X�������Ƒ������B�܂��H�̃n�C�V�[�Y���Ŏd�����Ăуs�[�N�ƂȂ������߁A���Ԃɒǂ��S���i�܂Ȃ����ԂɊׂ��Ă��܂����̂ł���B
�@�C�����͏ł邪�A�������Ă��Ȃ��c�c�B���X�A�{���ɏł���肾�������A�������͂ǂ����悤���Ȃ��A���ǁA���ł���������P���P�����ł��c�c�Ƃ����C�����ɐ�ւ��A�{���ɃJ���̕��ݏ�Ԃł��炭�߂����Ă����B
�@�Ƃ͂����A���Ԃ͊m���ɉ߂��Ă����B�ł�C�����Ƃ͗����ɁA�������ʂƂɂ�߂������Ă��Ă��Ȃ��Ȃ���ɂ͐i�܂Ȃ��B�������̎�����́A�u�R���C���͓�������c�c�H�v�Ƃ��u���N�����������������̂ł͂Ȃ����낤���c�c�H�v�ȂǁA���낢��Ǝ�C�Ȃ��Ƃ��肪�����悬�����B10���܂ł̐����͂ǂ��ւ��A�قƂقƓr���ɂ���Ă��܂����B
�@���������X�����v����E�o�ł��Ȃ��܂܁A�����Ƃ����Ԃ�12�����}�����B�X�̓N���X�}�X�C���~�l�[�V�����ʼn₢�ł������A���_�I�ɂ͂�����y���ޗ]�T�͑S���Ȃ��A���̍�����Ԉ��z�Ɋׂ��Ă��������ł��������B����ɒa������12���̎��ɂƂ��ĔN���͗�N�Ȃ�C�x���g�V�[�Y���Ȃ̂����A�C�_��ڂ̑O�ɂ��Ă�����y���ޗ]�T���Ȃ��Ȃ��Ă����B���A����Ȏ���F�l���~���Ă��ꂽ�B�u����Ȃɍ��l�߂Ă���Ă��Ă��A�s���l�܂��Ă��܂����������������ł́H�v�ƗU���o���Ă��ꂽ�̂ł���B�u�ǂ����悤�c�c�H�@�P���ł��ɂ��������Ȃ̂Ɂc�c�ł��������ʂ����߂Ă��Ă��A�������i�܂Ȃ��c�c�v�Ǝ����̒���畏����Ă������A�������̂��ƑS�Ă�Y�ꂽ��C��������ւ���āA���������܂�Ă��邩������Ȃ��A�Ǝv�����ďo�����邱�Ƃɂ����i���w�������܂����搶���A���߂�Ȃ����B�N���͂��Ȃ����ł��܂����c�c���j�B
�@ ���ǁA���ꂪ�D�]���邫�������ɂȂ����B�v���Ԃ�Ƀ��t���b�V�������������ŁA���̒��̃����������������肵���B���ꂩ��́A�H�̑�X�����v�����������̂��Ƃ������炢�A�����ɐi�߂邱�Ƃ��o�����̂ł���B
�@ �������āA���͉��Ƃ��C�_��o���ɂ������邱�Ƃ��o�����B�Ƃ͂����A����őS�Ă��I������킯�ł͂Ȃ��B��������A����ɂ͐��{��o�Ƃ܂��܂��R�͑��������A��͂蕛�{��o�܂ł���ԋꂵ�������Ɗ����Ă���B
�T�D�Ō��
�@�������āA���͏C�_����L���������߂邱�Ƃ��o������ƂȂ����B���A�����Ɏ���܂łɂ͖{���ɑ����̕��X�ɂ����b�ɂȂ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B����1�l�����̗͂Ő��������C�m�_���ł͂Ȃ��̂ł���B
�@���w���������搶���͂������̂��ƁA�Ƒ��A�F�l�A�d�����ԂȂǁA���͂̋��͂��Ȃ�����̂Q�N�Ԃ͐��藧���Ȃ������B�����̕��X�Ɏx����ꂽ�Q�N�Ԃ́A���ɂƂ��Ă͑傫�Ȏ��肠�鎞�ԂƂ��Ȃ����B�܂��A�C�m�_�����o�������Ƃ��A�����������F����ւ̎ӎ��ɂȂ邩�Ǝv���B����������ȏ�ɁA�������x���Ă��ꂽ���X�ւ̊��ӂ̋C������Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B
�@ �����ɉ��߂ĊF�l�Ɋ��ӂ�\���グ�邱�ƂŁA����L����߂����肽���B

�u���Ȃ̋����A���Ȃ̊w�k�ƂȂ�v�@�@
��������U�@�R�{���v
�^�钆�͕ʂ̊�
�@���͂ӂ����w���ɐ����������Ă���B���Ă͏����w������Љ�l�܂Ŏw�������Ă������Ƃ����邪�A���͂����ς獂�Z���ł���B���R�̂��Ƃ����Ȍn�̐l�ԂƎv���Ă��āA�����Ƙb�����Ă��đ�w�@�̂��Ƃ��b��ɂ̂ڂ����Ƃ��u�����̃e�[�}�́H�v�ƕ����ꂽ�̂Łu�m�ԂƓm��v�Ɠ�����ƁA�ނ́u�m�Ԃ͓��{�e�n������܂�������˂��v�Ƃ������B�ǂ����ނ́u�m�ԂƓk���v�Ɗ��Ⴂ�����炵���B�܂��A���̂ق��������̐搶�炵����������Ȃ��B������͂܂������̗��Ȍn�l�ԂƂ����킯�ł͂Ȃ��B��w�͋���w���̏��R�[�X�Ƃ������r���[�Ȋw�Ȃ̏o�g�ł���A�w������ȗ���Ȃ��Ȃ������̂̓p�\�R���ł͂Ȃ��w���c�����S�W�x�̕��ł���B������ɂ��撋�ԁuDNA�̓�d�点��\���v���́u���t�Ìł̂����݁v���̂��u���A�[��w�Z�{�m�ԑS�W�x��w�a���{�����W���x�����J�����X�Ƒ��Ȃ����B�V�h�j�B�E�V�F���_���̏����ł͂Ȃ����u�^�钆�͕ʂ̊�v�ł���B
�����W�߂Ƙ_������
�@ �_���̎����W�߂͊y�����B�����ǂ݂̓`�g�ꂵ���B�_�������͋�s�ł���B���̒��ɂ͋���Ȃ����͂����̂���l�����āA���Ƃ���G.K.�`�F�X�^�g���Ȃǂ͂������Ȃ��Ȃ�ƁA���C���ƃ��[���p���������Đl�C�V���[�Y�u�u���E���_�����́v�̒Z�ҏ�������C�ɏ����グ�������ł���B������ɂ���Ȍ|�����ł���킯���Ȃ��_�������ɂ͋�S�S�邵���B����ɂ���ׂĎ������������̂͊y�����B�[�~��w��o�Ȃ̂��ߏ㋞����ΕK���_�c�_�ے��̏��X�X�֑����^�B���̊E�G�̂��ꂵ���Ƃ���́A���X�݂̂Ȃ炸���H�X���̂̂܂܊撣���Ă���X�����邱�Ƃł���B�������ʂ�̗m�H���̃J�c�J���[�͊w������̂܂܂����A���R�ʂ�̋i���X�͍������C�V���c�ɒ��l�N�^�C�̃E�F�C�^�[�����d���Ă����B������܂������W�߂̊y���݂̂ЂƂł������B�������A�D���������Ƃ������A���q�ɏ���đ厸�s�B��N�̃N���X�}�X�ɓ��肵���w�G���I�b�g�S�W�x�������Ԃ����낭�A ����͂��И_���Ɏ�����˂Ǝ��s�Ɉڂ����A�d��ȉӏ��ł̌�ǂ�搶����w�E����啝�ɏ��������R�g�ɁB�_�������͋�s�ł���B�������A�����I�ɏ��������̂͂����Ƌꂵ���B�������̂��Ƃ͂��߂��珑���������Ƃ��l��������o������T�ԑO�Ƃ����Ă͂���������B���������ɂ͂��ǂ�ʘ_����K�ڂɓ��������͂����Ă����B�z�c�ɓ��邱�Ƃ��Ȃ��������Ƃ��Ă���ƁA���ꗎ���Ă����{�̉��~���ɂȂ��Ď��ʖ�������B���͂�Q�Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��ƈӂ������A����ԓO�邵�ďC�_���{��o�������̒����d�グ��B���̖͂ڂ��C�ɂ��V�����Ԓ��Ő��{��ƁB�p�\�R���̑O�ɂ����Â��ċ�̈����Ȃ����Ђ����J�N�J�N�����Ȃ��珊��̑�w�@�ɂ��ǂ蒅�����Ƃ��ɂ͓������Ă����B
����̏H�t��
�@���͈ꌩ�����Ƃ���p�\�R���D���Ɍ�����炵���B����Ȑl��������̂��^��Ɏv�����u��̓p�\�R���ł����v�ƕ����ꂽ���Ƃ���ĂȂ炸����B�u�\����ł��v�Ɠ�����Ƒ���͂Ȃ�قǂ���ł킩�����Ƃ����������B����܂��s�v�c�Ȃ͂Ȃ��ł͂���B�R���s���[�^�͑�w�̂Ƃ��ɂ͂��߂Ď�ɐG�ꂽ�B���̓������A��c�M�`�搶������\�V�F�C�N�X�s�A�O���[�v�̈���ł������̂ŁA�R���s���[�^���\�����������ɏo��������ƂɂȂ邪�A�@�B���m�͐��ɂ���Ȃ������B����䂦�H�t���ɂ������Ȃ������̂ł��邪�A�C�_�R���̓��ɂ��܂��܊�����킹�������[�~�̉@���S�l�A�w�d�Ԓj�x���Ȃ���Ƀ��C�h�E�J�t�F�őł��グ�����悤�Ƃ������ƂɂȂ�A����̂Ȃ����H�t���ւނ������B�u13�Ԃ̔ԍ��D���������̂���l�l�A���삳�܂��v�Ƃ̐��ɁA�u���̓��{�ꂨ�������Ȃ����H�v�Ǝv���u�������A�������v�ƃ^�����g�̉��t���̃��C�h�i�E���̓E�F�C�g���X�ł��낤���j���Ăъ�B�A�C�{���[�ƃs���N�̓��ނ̃��C�h��������̂��^��Ɏv�����₷��ƁA�X�^�b�t�̐��������Đ���������Ȃ��Ȃ����̂ŐV�l�̃R�ɂ̓s���N�̂��̂𒅂��Ă���Ƃ̂������B�ɐ����Ă���炵���B�X�i��Y�搶�̂����悤�Ɂu�G���o�ρv������̌����ԂƂȂ�̂ł��납�B�����Ƃ�������Ƃ��Ă͌i�C�����_���R���̃p�X�Ɉꑧ���Ă���Ƃ���ł���B�v�����̓�N�Ԃ͂Ђǂ��Z���������B�\�N��ɓ������Ƃ����Ƃ����Ă�������������Ȃ��B�������A�U��Ԃ�Ίy�������Ƃ̕������������̂��܂������ł���B�N����E������Z�n���Ⴄ�l�l���������ďW�܂��Ęb�������Ă��邱�Ƃ��s�v�c�ȉ��ł���B��w�@�ɓ���Ȃ�����肦�Ȃ������ł��낤�B�w�ŊF�Ƃ킩�ꂽ�Ƃ��͂��̏ꂩ�痧�����肪�����C���ł������B

�u�Z�J���h�o�b�O�͔������J�S!?�v �@�@
�l�ԉȊw��U�@�ΒÊ��q
�@
�@��w�@�����ŁA���̊Ԃɂ��A���̒ʋɂ́A�������J�S���������Ȃ����̂ɂȂ��Ă����B�X�[�p�[�̐H�i�����ȂǂŌ�������A��̔������J�S�̂��Ƃł���B���C�ɓ���̗m���𒅂��D�u��(�H)�W���P�b�g���͂���A�g�т���z�A���ϕi�ȂǓ��ꂽ�o�b�O�����ɂ����A�����ĕЎ�ɁA���傫�Ȕ������J�S�������ďo���Ă����̂ł���B��ʓI�ȏ����̒ʋX�^�C���Ƃ��ẮA������Ƃǂ��납�A�傫���͂���Ă���C�����邪�A���́A�����A�����Ў�ɏo�����B
�@���āA���䂦�ɒʋɔ������J�S�Ȃ̂��\�\�B���́A���A�d�����I���ƁA���̂܂ܐE��i�w�Z�j�ŁA���|�[�g�쐬��������A�������܂Ƃ߂��肷�邱�Ƃ����������B���ی�A�����Ė�̐E��i�w�Z�j�́A���낵���Â��ł���A���ɂƂ��č�Ƃ��ł��͂��ǂ�ꏊ�ł���������ł���B�����ŁA���ƂȂ����̂��A����ƐE��Ԃ̎����̎����^�тł���B���|�[�g�쐬�⌤���ɂ́A�������̏��Ђ�A�����̕������K�v�ł������B���̂��߁A�����̎��������邱�Ƃ��ł����e�ʂŎ��o���₷�����ꕨ�A�K�v�Ȃ��̂��T���₷���A�Ȃ����A�^�т₷�����ꕨ�����߂�ꂽ�B����ɁA�������J�S���œK�ł������Ƃ����킯�ł���B�`�ԏ�A���̏o�����ꂪ���₷���A�ЂƖڂʼn��������Ă��邩���킩��B���ڂ��ē���Ȃ��Ă��A�o�T�b�ƕ��荞��ŁA�T�b�Əo�����邱�Ƃ��ł���B����ɁA�ǂ�Ȃɏd���Ȃ����Ƃ��Ă��A������������d���ł���A�����̉ו��������悭�^���ł���̂ł���B
�@ �Ƃ������ƂŁA���́A�������J�S�ɁA���̓��ɕK�v�ɂȂ肻���ȏ��Ђ⎑�����A�Ƃ肠�������荞��ŏo���A��́A����Ŏg�������Ȃ��̂��l�ߍ���ŋA����B�K�v�Ȃ��̂��ᖡ���Ď��������̂ł͂Ȃ��A�K�v�ɂȂ����Ƃ��ɃX�O�g����悤�ɁA�g���\���̂�����̂����������Ă����̂ł���B���̓~���A�������J�S�́A��͂�劈��ł������B�C�m�_�����M�ɕK�v�ȕ����⎑���͎R�̂悤�ɂ������B�����̎�����S�āA�Ƃ��ɂ̓p�\�R�����������J�S�ɓ���A�����A�����������B�x����N���N�n�ɁA�����������ĐE��ɍs���A���M���������������B
�@ ���̂悤�ɁA���̑�w�@�����ɂ́A�������J�S�͕K�{�ł������B����́A�c�ɂ̐E��Ɏ��Ɨp�ԒʋA�����������������h�A����h�A���\���Ƃ����A���̒ʋΊ����琶�܂ꂽ�A�������J�S�̃Z�J���h�o�b�O���Ƃ�����B�����d�Ԓʋ�������A���邢�͒ʋŒ�������������K�v����������A�����Əo���Ȃ��������Ƃ��낤�B
�@ �C�m�_���������I�������݁A�������J�S�ɓ����Ă������Ђ͖{�I�ɖ߂��A�����⎑�����������Еt�����B����ƂƂ��ɁA���̒ʋX�^�C���́A����ƕ��ʂɖ߂����Ƃ���ł���B

�u�����t�́w�C�_��o�܂ł̉䖝�x�v �@�@
�l�ԉȊw��U�@���{�@�z�q
�@
�@ �s�s�s�s�c�c�������܂����������̖ڊo�܂����v������Ƃ̎v���Ŏ~�߂�B
�@�Ӂ[���A�����c�c���A�Ƃ肠�����N���邩�c�c�B
�@�J�[�e�����J����ƖҐ���A�z���C�g�A�E�g�ł���B�ߑO3���B
�@�܂��܂��O�͈Â��B����^�����ł���B�����ɐV���`�̋��s��̖����肪������B
�@�p�\�R���Ɍ������d��������B�p�\�R���������オ��܂ŁA���̏�ő�̎��ɂȂ�B
�@�Ȃ�����Ȃ��Ƃ��Ă���̂��낤�B
�@�Ȃɂ����悤�Ƃ��Ă���̂��B
�@��w�@�Ȃ�Ď����ɂ͖����������B
�@�ʂɏ���������Ȃ��Ă���������Ȃ����A�N�ɗ��܂ꂽ�킯�ł��Ȃ����B
�@�y�����Ȃ���B�ꂵ���Ȃ��߂�����c�c�B
�@�c�c�����ւ̌�����̌��t���c�����s�ɓ��̒����삯����B
�@�����ނ�Ɋ��ɖڂ����ƁA�p�\�R���͗����オ���Ă���B���C���B
�@���[�����`�F�b�N����B�[�~���Ԃ�����������̃��[���������Ă���B
�@�����A�������܂ł���Ă����ȁB�����Ȃ��A�݂�ȁB
�@����������邩���B
�@�\�\�\���炶��Ɩ邪������B
�@�����A�����͔R���Ȃ����݂̓����B���낻��R�[�q�[����邩�ȁB
�@���������c�c���낻��p�����Ă��Ȃ���B
�@���������c�c���̃t�@�C���搶�ɂ݂Ă����Ȃ��Ⴀ�B
�@���������c�c���킠�����I�@�t�@�C���Y�t��Y��ă��[������������������I
�@����ȓ��X�𑗂���2�N�ł������B
�@40�˒��O�A�����̍��܂ł̐l������蒼�������Ȃ����B���ꂩ��͖{���̎����̐l����T�������Ȃ����B���l�\�ɂ��Ęf�����ƁA�f�����ƁB�����Ďd�������߁A��̃e�[�}������đ�w�@�ցB���ꂩ��p�[�g�����Ȃ���@���̐������n�܂����B1�N���͂Ђ�����5�Ȗڂ̗��C�ۑ�����Ȃ����Ƃ�����t�A�C�_�̂��Ƃ͕������W�߂邱�ƂƎ����̃e�[�}���ł߂邱�Ƃ��炢�ł������B
�@�C�_��2�N�����炪�{�Ԃł������B�������A���̂Ƃ����瓯����2�̎d�����|���������邱�ƂɂȂ�B�\�肵�Ă������ƂƂ͂������ꂪ���ɑ�ς������B�V�����d������2�A�x���͓��j���̂݁A�������Ǝ�������B�ƂɎd���������A�邱�Ƃ������B�F����A�قƂ�ǂ̎Љ�l��w�@���͓����ł���Ɛ������邪�A�d���ƉƎ��Ɖ@�̎��ԓI���z�ɋ�J�����B�V�����d���̊��Ɋ��ꂸ�A�[�т�H�ׂȂ��琇���ɏP���A�H�ׂȂ��炤�Ƃ��ƐQ�邱�Ɛ��m�ꂸ�B����ł��Ȃ�Ƃ��[�H�̌�Еt�������Ċ��Ɍ������Ă�������炸�������͂��ǂ�Ȃ��B�d�����瓪���ւ��邽�߂Ɉ�x�Q�āA�钆�ɂ����Ă����������Ƃ����X�^�C���ɕύX����B�Ȃɂ��~�������āA�m�͂��~�������̗͂��~�����I�I�������Ԃ̊m�ۂ̓[�~�̒��ԓ��ł��b��ɂȂ�A�d�����g�C���ʼn������邱�Ƃ��[���B
�@�C�_�ł͂Ȃɂ������������A�������͂����邱�ƂɁB���������炫���_��������A���n�ɍs�����̂ɁA�ǂ����Ă���Ȃ��Ƃ����Ă��܂������B�ł���肽���B���ꂪ�v������莞�Ԃ�����A���͂����x����蒼�����B���̂Ƃ��N���������ł����₭�B�u�ʂɒN���M���ɉ������߂ĂȂ���v�B�����Ɍ����m�炸�̉@���̘_���̂��߂ɃA���P�[�g�ɋ��͂��Ă��ꂽ�l�����̃��b�Z�[�W�������ԁB�u���ЁA������Ă��������v�B�u�悭���������Ɍ����ނ��Ă���܂����v�B�c�c�����̃��b�Z�[�W�ʂɂ͂ł��Ȃ��B�₨��v���Ȃ����B
�@�Ƃɂ����A���Ԃ����Ȃ��B�̂����Ă����Ȃ��B�C�����������ł�B���߂̋C�����ƔS�肽���C��������������B���ɔN�������Ă���ƁA�d�����Ƃ̎G�����܂��܂������Ȃ�A����܂łɂ܂��Ď��ԂƑ̗͂Ƃ̐킢�ɂȂ�B�N���N�n�͉ŋƂɃV�t�g�B�Ƒ��Ŕ����}���\�������Ȃ���A�u����Ȃ��Ƃ��Ă���ꍇ����Ȃ����낤���v�Əł�B���Ԃ����Ȃ����Ƃɉ����āA�m�͂�����Ȃ�����B���x�����߂悤�Ǝv�������A�ʕ��ɂ��ւ�炸���߂��Ɏw���E�Y�킵�Ă�������w�������̓c���搶�A�[�~���Ԃ̐l�����̃��[���ɗ�܂��ꂽ�B�u�����Ȃ�����͋Z�ŏo���Ă��܂����v�ƃ[�~���Ԃ���N������������Ƃ�����G���W���S�J�B�C�_���ߐ�O���ɗX�ǂɂėX�������Ƃ��̋A�蓹�͂������ɃW�[���Ƌ��ɔ�����̂��������B�]�E�A���z���A���z�n�k�A�Ƃ��낢�날�����Ȃ��B
�@�C�_��o�̒���͒��r���[�Ȏd�オ��ɁA�B�����▞�����Ƃ͂قlj������̂ł��������A�������ĕ����L���������Ă��������Ă���ƁA��͂蕂���Ԍ��t�́u���Ӂv�ł���B���̔N�߂ŃA���X�g�e���X�ɐG���@��A�Ⴂ�ًƎ�̐l�����Ɛڂ���@��A�V�������Ƃ��w�ׂ�@��A�����̑̊��ł����Ȃ��������Ƃ𗝘_�ƌ��ѕt���Ă܂Ƃ߂邱�Ƃ̂ł���@��A���͂̐l�������珕�����Ă��邱�Ƃ������ł���@��A�l�X�ȋ@���^���Ă����������B�����̂��Ƃ͔����ґ�Ȃ��Ƃł���A���w�����͍l���Ă����Ȃ����n�ł������B
�@���w�����u�i��w�@�Ɂj�s���Ă��������Ƃɉe���������ȁv�Ə��ɓI�^���ŁA���h��X�N�[�����O����A��ƕs�@�����̂��̂ł������v���A�Ō�͊O�H�����������������������Ő�̂��ꂽ���r���O�_�C�j���O���������킸�ɉ䖝���Ă��ꂽ�B�����t�́u�C�_��o�܂ł̉䖝�v�B�������������͗������������߂�����B
�@�w�������̓c������Y�搶�A��w�@�����ۂ̊F�l�A�w���v�f�B�X�N�̔��コ��A�}�����̊F�l�A���C�ۖڂ̐搶���A�{���ɂ����b�ɂȂ�܂����B�d�˂����ː[�ӂ������܂��B�����āA���������̂Ȃ������Ō�܂ł��������Ă��ꂽ�[�~�̊F����Ɋ��ӂ������܂��B
�@�Ō�ɁA��y�̊F�l�ɂ͉��̎Q�l�ɂȂ�܂��A�v����Ɂu���߂Ȃ����Ɓv�ł��傤�B

�u�������z���āc�c�v �@�@
�l�ԉȊw��U�@���c�O���
���w
�@�������{��w��w�@��I���R�́A�܂��d�������Ȃ�������o����ʐM���ł��邱�ƁA���Ɂu���̂̍l�����v���w�т����ƍl���Ă����̂ŁA�u�N�w�v���w�ׂ��w�@�ł��邱�Ƃł����B�����̗v�����C���^�[�l�b�g�Ō��������Ƃ���A�S���̑�w�@�œ��{��w��w�@1�Z�����������̂ŁA�Ȃ��������ƂȂ��A���͓��{��w��w�@�����邱�Ƃ����߂܂����B
�@ �O���A���ɏZ��ł��鎄�͔�s�@�œ����������܂����B�h���͗����̖^�z�e���ł����B���͎������g�̊w�͂ł́A�܂��s���i�ɂȂ邾�낤�Ǝv���Ă����̂ŁA�L�O�Ɂu�������������ɗ����̂�����g�����h��H�ׂ悤�v�ƁA1�l�Łg�����h��H�ׂĂ��܂����B
�@���������A�M�L�������I���Ă���ʐڂ�����܂������A�ȑO����w�Z�̎����ɍڂ��Ă��鍲�X�ؐ搶�̎ʐ^�����x�����߂Ă����̂ŁA���ۂɍ��X�ؐ搶�ɏ��߂Ă�������Ƃ��A�u���킟�`�A�{���̍��X�ؐ搶���I�v�ƁA�����Ƌْ������荬�������S���ł����B
�@���̂悤�Ȏ��ł����A���̌�ɋ����̍��i�ʒm���͂��܂����B
��N��
�@ ���X�ؐ搶�̃[�~�́A��ʌ�����s�̖{�w�łQ�����Ɉ�x�A�Q���Ԃɂ킽���čs�Ȃ��܂��B�搶�͂P�l�P�l�̉@���ɑ��āA���J�ɂP���Ԉȏォ���Ďw�������ĉ�����A�[�~�I����ɂ͍��e����s�Ȃ��܂��B�܂��A�[�~���͑S���e�n����W�܂����l�����ŁA�E�Ƃ��N������܂��܂ł����A�����ɑł��������ǂ��Ȃ邱�Ƃ��o���܂����B
�@�����A���̏C�m�_���̑薼�́u��ʕa�@�ɂ����銳�ґ����ւ̉��P�ĂƗϗ�������@�v�ł������A���߂Ẵ[�~�ł͉������Ă����̂��킩�炸�A���������̌��ʔ��\�ŏI����Ă��܂��܂����B
�@�ẴX�N�[�����O���I���W���̌y��h�ł��A�܂������̕��������s�m���������̂ŁA��藯�߂̂Ȃ����\�ɏI����Ă��܂��܂����B�������A���h�̍��e��̎��A�����u�搶�A�N�w���ĉ��ł����H�v�u�N�w�����̖̂{����₤���̂��Ƃ���A�ǂ����Ĉ�w��Ō�ɂ͊T�_��ϗ��������ēN�w���Ȃ��̂ł��傤���H�v�Ǝ��₵�܂����B����Ǝ��̖₢�����ɑ��āA�搶���͂��߃[�~���F���l���Ă���܂����B
�@���ꂩ��P�Q���܂ł̊ԁA���̏C�m�_���ň�Ԗ��Ƃ��Ă��鑸���ɂ��āA�u������₤���߂ɂ́A�N�w���K�v�Ȃ̂��낤���v�Ƃ������Ƃ�Y�ݑ����܂����B�����āA�P�Q���̃[�~�ŁA����܂Ŏ����Y��ł������Ƃ�b���A�薼����e�̕ύX��搶�\���o����ƁA�搶�͉����������ĉ������܂����B�����ŁA�悤�₭�C�m�_���̕������������Ă��܂����B
�@�Q���̃[�~�ł́A�薼��V���Ɂu��Âɂ����銳�҂̑����\�V���Ȉ�ÁE�Ō�N�w���߂����ā\�v�ƕύX���A���͂��l���܂����B���̏��͂����������ƂŁA���������Ƃ��Ă��邱�ƁA���𖾂炩�ɂ������̂��Ƃ������Ƃ������Ă��܂����B
��N��
�@ ��x�ڂ̏t�������������A�C�m�_���͏��͂Ɏ����ŁA�͗��Ă��l���܂����B�͗��Ă͏��͂ɉ����čl���܂������A�܂��܂���G�c�Ȃ��̂ł����B�͗��ĂɊւ��ẮA���X�ؐ搶���牽�x���w��������A�W���Ă̌y��h���ɂ͖{���̑�Q�͂܂ŏ����Ă����̂ł����A�搶����͏͗��Ă̎w���������A�������Ɏw�����邱�Ƃ��o���܂���ł����B�͗��Ă����ɐi�ނ��Ƃ��o���Ȃ����ɁA���[�~�̗F�l��������A���낢��ȃA�h�o�C�X���܂��̌��t���A�搶�̎w����F�l�����̌��t���v���o���Ȃ���A�C�m�_���̏C����{����i�߂Ă����܂����B
�@�P�O���̃[�~�ł́A�{���̑�R�͂܂ŏ����i�߂܂����B���̍�����悤�₭�{����P�͂����R�͂܂ł̎w����搶����邱�Ƃ��ł��A�C�����s�Ȃ��Ă����܂����B�������A�c��{����S�͂ƏI�͂��l����O�ɁA�N���N�n�͏C�m�_���ɏW�����邽�߁A���C�Ȗڂ̃��|�[�g�𑁁X�ɒ��肵�A�P�Q���ɂ͑S�Ẵ��|�[�g���ŏI��o���܂����B
�@ �P�Q���̃[�~���ŏI�ƂȂ邽�߁A�[�~�܂łɎ�芸�����c��̖{����S�͂ƏI�͂������I���āA�搶����̎w��������悤�ɂ��܂����B�������A���̑�S�͂œN�w�ɐG��邽�߁A���Ȃ�̎��Ԃ�v���܂����B���낢��ȓN�w�҂̖{��ǂ݁A�w�сA�l���A�ŏI�I�ɂǂ̓N�w�҂�_���Ɏ��グ�邩�ƔY�݂܂����B�����ďI�͂������I�������ɁA������x�薼�ɂ��čl���A�u��Âɂ�����l�Ԃ̑����\��ÁE�Ō�N�w���߂����ā\�v�ƍŏI�ύX���邱�Ƃɂ��܂����B�[�~�ł͑�S�͂𒆐S�ɐ搶���w�����A���̓N�w�҂̑������ɂ��ă[�~���F���ӌ���A�h�o�C�X��^���Ă���܂������A�P���ł͘b���������A�b�͗����܂Ŏ����z����܂����B
�@�ŏI�[�~���I���A���֖߂������́A���͂����R�͂܂ł̏C���E�lj��A��S�͂ƏI�͂̏��������ƁA���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���������܂����B���̂��߁A�V�тɍs�����Ƃ�x�b�h�ł������x��ł͂����Ȃ��悤�Ɏv���A�d���ȊO�͎���ʼn߂����A����̘a���ɑ�w�@�݂��o���̃m�[�g�p�\�R����u���A���͂ɂ͖{�Ǝ����A�����Ŗ��邱�Ƃ��o����悤�ɖ��Ɩѕz��u���Ă��܂����B�������A�̒�������Ă͏C�m�_���������Ȃ��Ȃ邽�߁A���ׂ������Ȃ��悤�ɋC�����A�̒����ێ����܂����B
�@���������߂��A���̂悤�Ȑ��������Ĉꃖ���A�悤�₭�C�m�_�����������܂����B�������A�C�m�_���Ɨv�|�����������̂͂P���P�Q���ߌ�ł����B��o�������P�R���X���K���ƂȂ��Ă����̂ŁA���ʂ̗X�ւł͊Ԃɍ���Ȃ��Ǝv���A�Q�Ăċߏ��̑�z�Z���^�[�삯���݂܂����B�ŋ߂̑�}�ւ͑����A������ł��u�P�R���̌ߑO���ɂ͓͂��܂���v�ƕ����A���S���܂����B
�@ �P���Q�P�����q���ⓖ���A���ł͐�͍~���Ă��܂���ł������A�֓������̂��ߔ�s�@�͉������܂����B�܂�Ŏ�����̂悤�ȑ傫�ȐႪ�[�X�ƍ~�葱���钆�A�u����ȓ����̑��̓��Ɍ��q�������Ȃ�āA���U�Y����Ȃ����낤�Ȃ��`�v�Ǝv���Ȃ���A�����c���c���Ɗ��点���q������Ɍ������܂����B���q����ł́A���낢��Ȏ����w��������܂������A�����I���邱�Ƃ��o���܂����B
�@ �ŏI��o�͂Q���P�R���X���K���Ƃ������Ƃ������̂ŁA���q���₩�炵�炭���Ԃ�����܂����B�ȑO�ɍ��ۏ��̋ߓ��搶���A�u�C�m�_������������A���炭�_����Q�����Ă���A������x�_����ǂ�ł݂�ƁA����܂ŋC�Â��Ȃ������뎚�E�E���Ȃǂ��悭�����Ă����v�Ƌ����Ē����Ă����̂ŁA���͂��炭�C�m�_���ɖڂ�ʂ����Ƃ͂���܂���ł����B�Q���P�O���A���͋v���Ԃ�ɏC�m�_����ǂނƁA�������������C�m�_�����Ƃ����̂ɁA�V�N�ȋC�����œǂނ��Ƃ��o���܂����B����ƍ��܂ŋC���t���Ȃ������뎚�E�E���╶�͂̕s�����Ă���Ƃ��낪�킩��܂����B�ŏI�C�����I���āA�Q���P�Q���ɍĂё�z�Z���^�[����X�����܂����B�����P�R���ɂ͑�w�@�����ۂ��u���{��o�m�F�v�̃��[�����͂��܂����B
�Q�N�Ԃ�U��Ԃ�
�@���ɂƂ��đ�w�@�ł̐����́A�ƂĂ��y�����[���������̂ł����B�����Z��ł��镺�Ɍ���ˎs����{�w�̍�ʌ�����s�܂ł́A���Ȃ�u���������v������܂��B�������A���ɂ͂��́u���������v���S����ɂ͂Ȃ�܂���ł����B�ނ���A�܂�Ō�ߏ��̑�w�@�ɒʊw���邩�̂悤�Ȋ��o��������܂����B���ɂ��́u���������v���u�߂������v�ɕς��Ă��ꂽ�̂́A�u���X�[�~�v���Ǝv���Ă��܂��B�[�~�ł͎��̍l���ɑ��āA�M�S�Ɏw�����ĉ����鍲�X�ؐ搶��A�����̖��̂悤�Ɉꏏ�ɍl���Ă����F�l���������܂��B�܂��A�F�l�����̔��\�⍧�e��̌�炢�̒�����A���͑����̎����w���Ē����܂����B����ȃ[�~�ɍs�����Ƃ��A���͂ƂĂ��y���݂ł����B���͂��ꂩ����u���X�[�~�v�ň�ĂĒ������u���̂̍l�����v���ɂ��A�N�w�̌ꌹ�ł���Ñ�M���V�A��uphilosophia�i�m��������j�v�𑱂��Ă��������Ǝv���܂��B
�@�Ō�ɂȂ�܂������A�K�Ȍ�w���Ɖ���������̌��t���܂������X�ؐ搶�A�ߓ��搶���͂��ߏ��搶���A���X�[�~�̊F����A�f�r�r�b���̊F����ցA�S����[�����ӂ�\���グ�܂��B

�u�ŏI�R�[�X�͑S�͎����v �@�@
�l�ԉȊw��U�@��w�@�a�q
�@
�@ ���̏ꍇ�́A���m�O���ے���3�N�Ԃ������Ă��܂��܂����B�u�l���͌v��ʂ�ɂ͍s���Ȃ����̂ł���v�Ƃ������Ƃ��������������ł����B
�@���ꂩ��撣�낤�Ƃ���4�����w����A����̋���v�킵���Ȃ��Ȃ�A6���ɔ]�[�ǂ̍Ĕ��œ��@���܂����B2�������܂�őމ@���A���ی��̂����b�ɂȂ�܂����B�������A�a�l�̐������O���ɏ悹�Ă������Ƃ͑�ςł����B�P�A�}�l�[�W���[�A���F��̂��߂̕ی��t�A�����^���ƎҁA���z�[���̂��߂̑�H����A�Z��x���ɂ��肷��̐ݒu�ƎҁA��z�ٓ��̋ƎҁA���S�Z���^�[��ЂȂǂƂ̑ł����킹�A�\���A�_��A���{�ŁA���z�[�����ς݈�i�������̂͑�A���ł����B���̔N�A������o�ł������|�[�g��1�Ȗڂ����ł����B
�@ �ʐڃ[�~��T�C�o�[�[�~�͋x�݂����ł������A�[�~�̃����o�[�Ɏx�����Ȃ���Q�����Ă��܂����B���̂���ȂɖZ�����̂Ǝv���邱�Ƃł��傤�B����̉�������܂����A���W�҂Ƃ̒����Ɏ��Ԃ��Ƃ��Ă��܂��̂ł��B�P�A�}�l�[�W���[�͌v�揑���쐬���邾���ŁA���{����̂̓w���p�[����ł����B�w���p�[����́u���A�Ԉ֎q�������̂͏��߂Ăł��v�ƕs�����B���܂���B���̓P�A�}�l�[�W���[���w���p�[�̋����w�����s���Ǝv������ł��܂������A����͌��ł����B���͂��ꂩ�痈��w���p�[����̂��߂Ɏ��Ԃ��L�������s���ʂ̃t���[�`���[�g�Ǝ菇�����쐬���܂����B��ʎ�i�Ɋւ���菇�A�ړ��Ɋւ���菇�A�����x�����̎菇�A��f�̎菇�A�\��̎菇�A������炤�܂ł̎菇�A�U���p�̎菇�A���������s�p�̎菇�A����Ɋւ��錒�N��̒��ӎ����i�g�C���̉���@�A�����̐ێ�A�H���̂��ƁA�ً}���̘A����j���쐬���A���ւ��̃w���p�[�����S���ĉ��ł���悤�ɂ��܂����B�w���p�[�����S�ł��邱�Ƃ́A����ɂƂ��ėǂ������邱�Ƃ��ł���ɂȂ���̂ł��B�܂��A��f�̍ۂɂ�1�����̌����₻�̑��̕ω���S����p�ɋL�����A�w���p�[����Ɏ��̑�s�����Ă��炤�悤�ɂ��܂����B�����̃P�A�[�v��������쐬���A�P�A�}�l�[�W���[�ɑ����Ă��܂����B���̕����Ă�����̍��{�́A��Â�Ō�̐��ƂłȂ��l�Ԃ�����҂�a�l�̐��b�����邱�Ƃɂ͖���������Ƃ������ƂȂ̂ł��B���̊Ԍ��߂邽�߂ɁA���͎��g�̐��m���ƋZ�p�����p������Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
�@2�N�ځA�Ȃ�Ƃ��撣�蔲�������Ǝv���͂����Ă��A�d���A�Ǝ��A���A��w�@�ł́A���ׂ����Ƃ����肷���đ̂����Ă��܂���B����̓���Ђǂ��Ȃ�ӎv�̑a�ʂ�����Ȃ��Ă��܂����B�����ŁA���|���Ɠ����̎���̌���������ł��肢���邱�Ƃɂ��܂����B���̍ۂ�����������ƌ����Ă����Ȃ������̂ł��B���A�ŁA���̔N��3�Ȗڂ𗚏C���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@ �������A3�N�ڂ�7�����ꂩ�猤���̎��{�Ɏ�肩���낤�Ǝv���Ă������̂��ƁA���|���ɗ��Ă���Ă������̑̒����D�ꂸ�A�����������Ă����l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B8���A�ڂ̑O�͐^���ÂɂȂ�܂����B����2�Ȗڂ̗��C�Ǝ������s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�X��9������͊Ō�w����2�N���̗Ւn���K��1�����]��g���������Ȃ��Ȃ�B10���Ɏ����̎��{���v�悵�܂����B�����Q���҂Ƌ��͎ҁi�w���j�Ǝ����ҁi���j�̒����͓���A�������Ԃ�6�T�]����₵�Ă��܂��܂����B12���A���x�͊Ō�w��1�N���ŏ��߂Ă̗Ւn���K�ł��B�����āA���K���I�������̂�12��16���ł����B�����͍s�������̂̏C�m�_���͏����n�߂Ă��܂���B���ꂩ�炪�Ō�̏����Ǝv���Ă�����A26���ɍēx�A����̓��@�ŁA�N���N�n�͏C�m�_���ɐ�O�������Ƃ̍l���͖A�̂悤�ɏ����Ă��܂��܂����B�������A10���]��̓��@�ł����̂Ő����͑�ςł������A�ȍ~�͘A���p�\�R���Ɩ{�I�Ƃ��s�������Ȃ���A�������Ŏ���Ƃ͎v���A�S�������ɍא�_���𑗐M���w�����Ȃ���A1��13���A�_���K�����ɏ���܂Ŏ��Q���A�_�����Ē����܂����B13��17��30���ł����B
�@1��21���͌�������ł��B���̏T�ɂ͗��K�̂��߂̃T�C�o�[�[�~��2��s���܂����B15���Ԃʼn����ǂ̂悤�ɓ`���邩�B�ƂĂ����ɂȂ�܂����B�������A���\�p�̎��ŋ����쐬����K�v������i�p���[�|�C���g���g�p�ł��Ȃ��j�A�O���[��ɃR���r�j�ŃJ���[�R�s�[�����āA�����ɌЕt�������܂����B�������Ԃ�����܂���B���ŋ��̗��ʂɔ��\�p�̓��e��\��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�����������Ƃ��Ă���Ǝv�����̂ł����A�ڊo�܂����g�т����肵�߂��܂܁A�C���t���Ǝ��Ԃ��Ȃ��B�d�Ԃł͊Ԃɍ����������Ȃ��A�����^�N�V�[�����A���ƃ^�N�V�[�̒��ŁA�^�]�肳��Ɂu�ǂ����A���ɂ��\���Ȃ��v�ƌ����āA���ʂ̌Еt����Ƃ����܂����B�F�X�Ȃ��Ƃ�����܂������A���Ƃ�����������I�����邱�Ƃ��ł��܂����B��͂��w�����������e��lj��܂��͏C�����邱�Ƃł��B2��12���N���l�R���}�g��}�ւɏC�m�_���������13���K���A����Ŋ����ł��B
�@���܂��̓^���A2��14���A�o�����^�C���f�[�ł��B���͒��̖����d�Ԃ̒��ŁA�������܂܋C�������Ă��܂��܂����B�C�����Ɓu���v�ł����v�Ƃ��������̐��B�d�Ԃ̍��Ȃɍ����Ă��܂����B�u���E���E�ς݂܂���v���ꂪ����t�̎��̐��ł����B�Ō�W�҂Ȃ�Č����Ȃ��B�p�����������B
�@ ���ꂩ��C�m�_�����������ɂȂ�F�l�ցA����Ȏ��ł���������[�~�̒��ԂɎx�����Ę_�����������Ƃ��ł��܂����B�Ō�܂ł�����߂Ȃ����Ƃ��|�C���g�̂悤�ł��B

�u�Q�Ă��o�߂Ă��p�\�R���v �@�@
�l�ԉȊw��U�@�c�����ݑ�
�@
�@ �v���N�����Q�N�O�A��w�@�������n�܂����p�\�R�������B�p�\�R���ɐG�ꂽ���Ƃ��Ȃ����ł����w�o������̂��ǂ������q�˂����Ƃ���A�u���v�A80�̕��ł��C�����܂�����v�Ƃ������t�ɉ��̋^������������������w�����܂����B
�@ ���Ă��悢��{�i�I�Ɏ��ƁH�̊J�n�A�J�Z�������A�ڂ̑O�Ń[�~���s���A�ڂ��_�ɂȂ�A�g���S���ł܂��Ă��܂����B�u���͏�Ⴂ�ȂƂ���֗��Ă��܂����v�ƌ���̔O�ɋ���܂����B�܂��A�ʐM���Ȃ�N�ɐ����֍s���Ηǂ��͂��A�ƌy���l���Ă��������N�ԃX�P�W���[�������āA�傫�Ȋ��Ⴂ�������ƒm�����B�����Ď���̐l�͊F����f���炵���l����ő��X�C��ꂵ�A�s���ɂȂ��������v���o���܂��B�C��ꂵ�Ă��Ă��A��Ⴂ�ȂƂ���֗��Ă��܂����ƌ�����Ă���Ԃɂ��A��w�@�̍r�g�̒��ɂǂ�ǂ�������čs���܂����B
�@4���Ƀp�\�R�����C���A�����N���X�͓d���̌q��������A�����グ���A�}�E�X����ȂǏ����̑������狳���Ē����܂����B���̌��C�ŁA���d���ŃA�����J�ݏZ�̍��ۏ���U�̕��Ƃ��m�荇���ɂȂ�A�A�����J�ɒ����Ă���A���[���̂��������āA���݂��Ƀp�\�R���̗��K�����܂����B�u���͂悤�������܂��v�ƃ��[��������ƁA�u���ӂ́A��������͖钆�ł��v�ȂǂƁA�u���ɂ��Ԏ����͂��C���^�[�l�b�g�̑f���炵���Ɋ��S���܂����B
�@ 5�����A����ƃp�\�R�����q����A����Ŏg�p�o����悤�ɂȂ�܂����B�p�\�R�����J����ƁA��糃[�~�̊F����̂��j�����[����������������Ă��ċ����A�܂��������܂����B�܂��A���̃��[���֕ԐM���邱�Ƃ���n�܂�܂����B�ԐM����ԈႦ����A�[���A�ϊ��~�X�ŕςȕ��͂̂܂ܑ�������A�l�����Ȃ��悤�ȃ~�X���������܂����B
�@ �p�\�R�����q�����Ă���A���Ԃ�����p�\�R���Ɍ������Ă��܂����B�����ʂ�Q�Ă��o�߂Ă��p�\�R����Ԃ������Ă��܂����B���ӐQ��̂�3�����ł����B���̒��̓p�\�R���̉���Ȃ����ł����ς��A�������Ȃ��܂ܖ���̂ŁA�]���ߖ��������̂��A�s���ȐQ����p�ɂɌ����悤�ɂȂ�A��l����u�p�\�R���ɍ����l�߉߂�����Ȃ����v�ƌ����ď������߂Ƀp�\�R������ĐQ��悤�ɂ�����������܂����B�������A�搶���瑗���ė��郁�[���ɓ����čs���ɂ́A�Q�鎞�Ԃ������Ăł����Ȃ��Əo���܂���ł����B
�@ ���͖��É��Ńs�A�m�������Ă��܂����A�u�s�A�m���e����p�\�R���������o����ł���v�Ƃ悭�����܂������A������ł��Ƃ����Ȃ炻�������邩���m��܂��AExcel��ppt���s���ɂ́A�s�A�m�̂悤�Ɏw�𑬂����������Ƃł͂Ȃ��A������͋Z�p�K����L���͂������K�v���Ɛg�������đ̌����܂����B
�@���ɂ͐搶����̉ۑ�́A�s�A�m�̐��k�ɒu�������čl�������A�h���~�t�@�\������Ɗo�����Ƃ���ɁA����̓V���p���̃m�N�^�[����e���ĉ������B�ƌ���ꂽ�̂Ɠ����ʂɊ����Ă��܂����B�������X�e�b�v�A�b�v�ŁA���X�ɐi���ȂǂƐ��������������Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��Ƃ����v���ŕK���ɊK�i���삯�オ���čs���܂����B�܂��A�����s���J�ōs����[�~�ł́A�u�K�����\��������́v�Ɛ�y����f���Ă��܂����̂ŁA���炸���Ɣ��\���ė��܂����B�U��Ԃ��Ă݂�A�قڊF�Ώ܂ł����B�J�Z���ɖ��������֍s�����ɋ����Ă��܂������A�l���Ă݂�A���\�̓x��ppt�Ɗi������ςł������A���N�x�͓����̖��̉��h�ɏh�����A2�N�ڂ̓z�e���ɏh�����ă[�~�ׂ̈ɓ����֍s�������y���݂ɂȂ��Ă��܂����B
�@���������糃[�~�Ŗ����s���Ă����T�C�o�[�[�~�ł́A�Ȃ��Ȃ���肭���ꂸ�A�搶����u�ʂ��Ă��܂����A�����������܂���B������̐������������灛�������Ȃ�������~����U��ł��ĉ������v�Ƃ�����b���悭���܂����B�܂�ő�꒵�тɓ���Ȃ��l�̂悤�ł����B
�@���̂悤�ȃp�\�R���Z�p�K������ςȎ����ɂ��Ȗڗ��C�Ƃ����傫�ȓ�肪�n�܂��Ă��܂����B�P�N�Ԃ�5�Ȗڂ܂ŗ��C�ł��̂ŁA��̑�ς����l����5�Ȗڗ��C�͂����o���܂����B�P�ȖڂɎ��|�����āA�ŏI��o�܂ł̓��̂�̑�ς��ɋC�t���܂����B��������邵������܂���B�O�����|�[�g��o����������A5�Ȗږڂ�������o���Ȃ��Ɗ�Ȃ��Ƃ������ɁA���É��ɑ傫�Ȓn�k������܂����B���̒n�k�̒��ł��h��Ȃ���p�\�R����ł��Ă�����������܂����B������|�[�g�ł͂������������A���|�[�g�ɒǂ��Ă��܂����B��y���u����͒�o�������Z���̂ŁA���z�c�ŐQ���͉̂������������ȁH�v�Ƃ������b���͎f���Ă��܂������A��͂莩��������������y�Ɍ����Ă��܂��܂����B
�@���]�ԑ��Ƃ̂悤�Ɍ������e�E�Ȗڂ̕��ɒǂ��A�p�\�R���̋Z�p�K�������ė��܂������A�C���t���ΏC�m�_���̒��Ԕ��\�̎������}���Ă��܂����B����Ȃɉ����o���Ȃ��������ł������Appt���g���Ĕ��\�o����܂łȂ��Ă��܂����B�A�j���[�V�������g����悤�ɂȂ�ʔ����Ȃ��āA�������������Ă��܂��A�搶����u����͎g�������ł��v�ƌ����Ă��܂��܂����B�z���ȏ�Ƀp�\�R�����o����悤�ɂȂ������Ɋ��ӂ��Ă��܂��B
�@�����܂ŗ���܂łɂ́A��糐搶�A�[�~�̐�y�E�������A�F�B�ɂ͑�ς����b�ɂȂ�A����Ȃ����f�����|�����ė��܂����B�Ō�܂Ō��̂Ă����ؒ��J�ɂ��w�������܂��Ė{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�܂��A����ȐS�Ŏx���Ă��ꂽ�Ƒ��Ɋ��ӂ��Ă��܂��B

�u�l���̕v �@�@
�l�ԉȊw��U�@�V�c�@���}
�@
�@ ��w�@�Ŋw��2�N�Ԃ͎��ɂƂ��Đl���̂̕悤�ȋM�d�Ȋ��Ԃł����B30�N�ȏ�O�̑�w�����ォ��N�w���w�т����Ɩ]�݁A�܂��A����܂Ől�ԂɊւ��Ĕ邩�ɕ����Ă����l�X�ȋ^��ɑ��铚���́A��U�����l�ԉȊw�̒��Ō����邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�Ⴆ�A�������ӎ��ŔY��ł���20��̂���A��������̒����Ɂu�u���̌�ɂ͎��ӎ��ŋꂵ�݁A��X�Ƃ��Ė���Ȃ����Ƃ��x�X����v�Ƃ����������݂����S�������Ƃ��o���Ă��܂����A�l�ɂ͂Ȃ����ӎ�������̂��A���ӎ��Ƃ͉����Ƃ������Ƃ̓����́A��w�@�Ŋw�Ԃ܂Ō����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B
�@����ɁA�Ǐ����ő�̊y���݂ł��鎄�́A��w�@�Ŋw��2�N�ԁA���I�ȓǏ��͂��������ɂ��Ȃ��Ɣߑs�Ȍ��ӂ����A�w�������ɕK�v�ȓǏ��ɓO���܂������A�K�v�ȓǏ����܂��y�����A���ɖ����x�̍������̂ł����B�����ɂ͏�ɔ����Ɗ���������A�m�I�D��S���h������܂����B��ɂ́A���|�[�g���M�Ƃ����ꂵ�݂��҂��Ă��܂������A���̋ꂵ�݂��܂��A�����w�̒��J�Ȏw���̉��A�u�����グ���v�Ƃ����B�����錹�ƂȂ�܂����B
�@
�@�����āA���J�Ȏw�������Ă��������������w�́A30�N�O�͔��ɉ������݂ł������A�@���ɂȂ��Ă���͂ƂĂ��t�����h���[�ŁA���ɂ����J�ɓ����Ă������邽���ւ�߂������݂ł����B���[����ʂ��ē͂����t�͏�ɗD������肩���A������Ă��b��������S���ʂ������悤�ȋC�����܂����B�w�������Ƃ̃[�~��̎�Ȃ͂܂�œ����̂悤�ȕ��͋C�ŁA������܂��y���݂̂ЂƂł����B
�@���̂悤�ɕ̒��ɂ͎Љ�l�����ł͓����Ȃ��ʂ�L���ȕ��������������Ă��܂����A���̎����ɗ�܂��������w�F�����Ƃ̏o����܂��傫�Ȏ��n�ł����B�^�钆�߂��̓d�b�ƃC���^�[�l�b�g���g�������Ƃ�́A��������Ă��Ă��ړI���ЂƂɂ��Ď��g�ދ����ƗE�C�A��܂�������܂����B
�@��w�@�Ŋw���Ƃ͍���A�Љ�ɊҌ����Ă����Ȃ���Ȃ�܂��A�w�������ł�����糈�ߋ����́u�C���͌����҂Ƃ��Ă̓�����v�Ƃ������t��S�ɍ��݁A���ꂩ������Ȍ��r���d�ˁA��葽���̐l�ɖ𗧂悤�w�߂Ă��������ƍl���Ă��܂��B

�u�C�_�������I���āv �@�@
�l�ԉȊw��U�@�͌��@���_
�@
�L�q��
�@���m�O���ے��ł́A���w��ɘ_�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ԃ����ۂɂ͊ۂQ�N���Ȃ��̂ŁA���i���\�シ���Ɍ����e�[�}�i�R���v���C�A���X�ƋA���ӎ��j�Ɋ֘A���鎑���̎��W���n�߂悤�Ǝv���������B�����Ő悸�g�߂ŊȒP�ɏo���邱�Ƃ��l���A�����e�[�}�Ɋ֘A����V���L���̃X�N���b�v���s���n�߂��B
�@���ۂɂ��̎��݂��n�߂�ƁA�X�N���b�v��Ƃ͂��������P���̐����̒��ł̎��Ԃ��������A�����~�E�����x�݂ɊW�Ȃ��Q�N�ԍs���̂͐h�����ƂɂȂ����B�������A���̂Q�N�ԂŎ��W�����X�N���b�v�L���̗ʂ́A�C�����t�@�C���z���_�[�V�����ƂȂ�A���̊֘A�L�����n���ɗ]�����ڂ�ʂ��Ă������Ƃɂ���āA����I�Ɏ������g�̃��x���A�b�v�Ɍq���邱�Ƃ��ł����B
�@�܂������ł́A�_�����쐬����ɂ������Ēn���݊w���i�{�錧�ݏZ�j�Ƃ��Ă̋ꂵ�݂��������B���R�A�_�����쐬����̂ɂ͐�s����֘A������ǂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�K���ɂ��AGSSC�͓d�q�}���ً@�\�̏[���ɂ���ĉ��u�n����ł��ȒP�ɘ_�����发�̎��͂ł���B
�@�������A�����������������W����ɂ������Ă��A�P�ɘ_�����发�̑薼���z�[���y�[�W��ŗ��Ă��邾���ł́A�������]�ޓ��e�̕������ǂ����킩��Ȃ��ꍇ������B���������ꍇ�ɂ́A���ڂɐ}���قɍs���ĂP���P����ɂƂ��Ėڎ��Ȃǂ�����e���m���߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���������B����Ȏ��A��͂�n���݊w���Ƃ��āA���{��w�̊e�}���ق��W�������s���ɋ��Z���Ă��Ȃ����Ƃɑ���s�����������B
�@�����A�s�����Ƃ���v���Ă͂����Ȃ��̂ŁA�n���͒n���Ȃ�ɐg�߂ɗ��p�ł���}���ق��ő���Ɋ��p���悤�ƍl���A�����}���ق�s���}���فA�����Ă����F�̔Z�������T���ɂ͍�����w�̐}���قƕ��L����������L�߂��B���ꂪ���ƂȂ��Ă͋M�d�Ȍo���ƂȂ�A�y�����v���o�ɂ��Ȃ����B
������
�@�l�ԉȊw��U�̏ꍇ�A�T�ˏC�m�_�����쐬���邽�߂ɂ͉��炩�̃f�[�^�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A��Ɏ��炪������������s��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ������̂ł͂Ȃ����A�ł���Ύ����̎�ς����邽�߂ɂ��A�q�ϓI�ȃf�[�^�̎��W�͎����̎�ōs���������ǂ��悤�Ɏv���B���ɎЉ�l�̏ꍇ�́A�������Љ�Ŋ����Ă���^���S�������e�[�}�ɂ��Ă���ꍇ�������Ǝv����̂ŁA�l�̐���ςȂǂ�r�����邽�߂ɂ��K�v�ɂȂ��ƂƂ����邩������Ȃ��B
�@ �����Љ�l�w���͂قƂ�ǂ̏ꍇ�A�d���Ƃ̗����ŒP�ʗ��C�ƌ�����i�߂Ă���̂ŁA�������Ƃ��Ď��،������s�����Ԃ̓s��������̂�����ɂȂ�B���̏ꍇ���A����͖ʐڒ������s�������A�����Ɗ��I�Ɍ��������Ƃ����������B���Ƃ��Əo�g�͑��Ȃ̂ŁA�����Z����{������̕��������̈˗��͂��₷�������B���̂��߂ɁA���x���ʐڒ��������{���ɑ��ɍs�����ƂɂȂ����B����ł́A�ʐڋ��͎҂��瓾����f�[�^�̒n��F�����߂悤�ƍl�������߁A�����ł����l�ɖʐڒ������s�����̂ŁA�ŏI�I�ɂ͒����ɂ�����ʂ̃R�X�g���n���ɂȂ�Ȃ����̂ɂȂ�A���S���������B
�@ �������A�����C�m�_���������I���Ċ����邱�Ƃ́A�����̊��I��������z���Ē������s�������ƂŁA�t�ɒ����J�n�O�ɂ͍l�������Ȃ������p�x����f�[�^�̓��e�������錋�ʂƂȂ������Ƃ͂�����B���ꂪ�A���w�����z�肵�Ă������e��蕝�̂���_�����������ƂɌq�������Ƃ͎v���Ă���B
�[�~��
�@����Ȃ���ȂŁA���낢��ƂQ�N�Ԃ͎��s������J��Ԃ��Ȃ���C�m�_���������I���邱�ƂɂȂ������A�U��Ԃ��Ă݂��͂�[�~�ł̎w�������⓯���[�~���Ƃ̌𗬂�x�������̒��ŁA�����ɏC�_�����Ƃ����ڕW��B���ł����Ǝv���B���ɏ��������c���[�~�́A���̐��̈悪���̍L���Y�ƁE�g�D�S���w�Ƃ�������������āA�����S���ړ_�̂Ȃ�����ŐE�Ɛ����𑗂��Ă���[�~���Ƃ̌𗬂�����A�[�~�ł̊����Ȉӌ��������獡�܂łɂȂ��V�N�Ȏ��_��ʂ̊p�x����^����ꂽ�B���̂��Ƃ́A�C�_�̍쐬�ɂƂ��ď_��Ȏv�l�������炵�Ă���Ă����Ƃ��v���B���U��Ԃ��Ă݂�A�܂��������Ɍb�܂ꂽ�Ƃ��������悤���Ȃ��Q�N�Ԃ������ƒɊ����Ă���B
�@

|