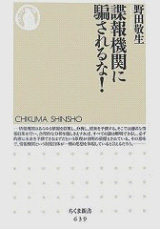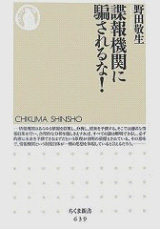|
国際政治の舞台裏では、各国インテリジェンス機関による周到な情報活動と巧妙な駆け引きが展開されている。しかし、例えば9・11をめぐる"対テロ戦争"では情報大国であるはずのアメリカ、イギリスも失敗の連続であり、テロの脅威はむしろ拡大している。
本書は元公安調査庁調査官である著者がイラク、アルカイダ、中国・ロシア、朝鮮半島についての当該地域・組織を舞台とした、諜報活動合戦を事例にひき、諜報機関の性質とその限界を検証したものである。其の中でも、とりわけ第1章「イラク」と第4章「朝鮮半島」の関係が興味深い。
第1章「イラク」では、米国政府がありもしない大量破壊兵器をあると断定した根拠となった情報、その収集と分析に焦点をあてたものである。著者は、イラク開戦に踏み切った「情報の失敗」を調査する米独立委員会の調査レポートを照らし合わせながら、CIAなどの米諜報機関の動きを検証する。
「情報の失敗」とは、諜報機関が収集・分析し、まとめた情報が、蓋をあけたら、実際とは違っていたという状況を指す。また情報の失敗は、大別して収集過程と決断時の二種類に分けられる。具体的には、フセイン政権中枢への協力者を確保しえなかったことやテクノロジーへの過度な依存など、映画や小説のイメージとは大きくかけ離れているのが実状のようだ。
一番重大な過ちは、ブッシュやその側近たちを「フセイン=悪者」とする先入観が「情報の政治化」(「情報の政治化」とは、諜報機関が政府の政策オプションに介入ないし迎合する状態を指す)を誘発し、イラク開戦の引き金を引いたという事実に尽きるだろう。
第4章「朝鮮半島」では、北朝鮮の核疑惑に焦点をあて、当該地域における日本、北朝鮮、米国の諜報活動を分析するものである。ここで著者が暗に指摘するのは、米国の対イラクでの核兵器ないし大量破壊兵器の保有についての情報判断の失敗が、北朝鮮の核保有の情報判断に、奇妙な影を落としてしまっているということである。要するに、イラクでの、「ないのにあると」言ってしまった事への後遺症から、北朝鮮が核を保有していると断言することに、米政府ならび日本政府がおよび腰になってしまったということである。換言するなら、米国のイラクにおける「情報の失敗」がわが国の安全保障に重大な支障をきたしているとも言えるだろう。
しかしながら、著者はここで対外諜報機関の創設や既存機関の強化といった論理展開をしない。なぜなら、彼は基本的に諜報機関とは、対イラク諜報活動のCIAの例にみるように、相当な予算をかけてもその性質は払拭されないとする。要するに、諜報機関に多くの予算をつけるよりも、得られた情報を柔軟に受容する政治システムが構築され、諜報機関の収集分析したインテリジェンスを活かすも殺すも政府内中枢のインテリジェンス・リテラシー次第であるというのが、著者の見解である。
諜報機関はあらゆる情報を収集、分析し将来を予測する。そこでは適切な情報収集を行い、合理的な分析を施しさえすれば、すべての謎は解明できるし、必ず的確に未来を予測できるはずだとういう幻想が存在する。昨今、諜報機関強化論が声高に叫ばれているが、情報の断片を集めれば直ちに答えが出るというような「インテリジェンス幻想」は払拭する必要があるだろう。諜報活動は将来についての完全な予言ではなく、最も深くかつ客観的に根拠付けられ、注意深く検討された見通しを与え得るものである。諜報活動の本質と限界を理解することなく、過剰な期待を寄せるのは慎むべきであろう。
|