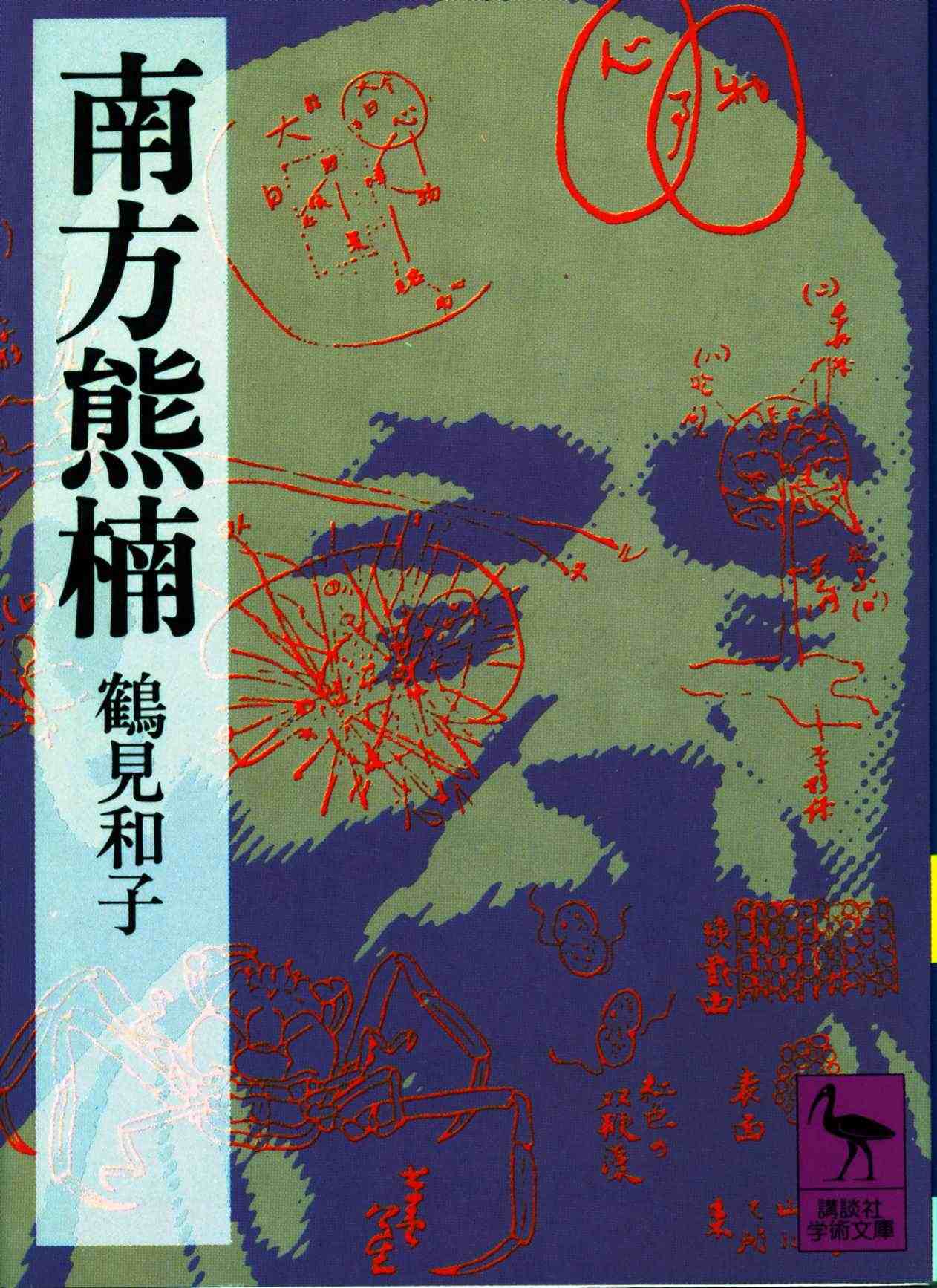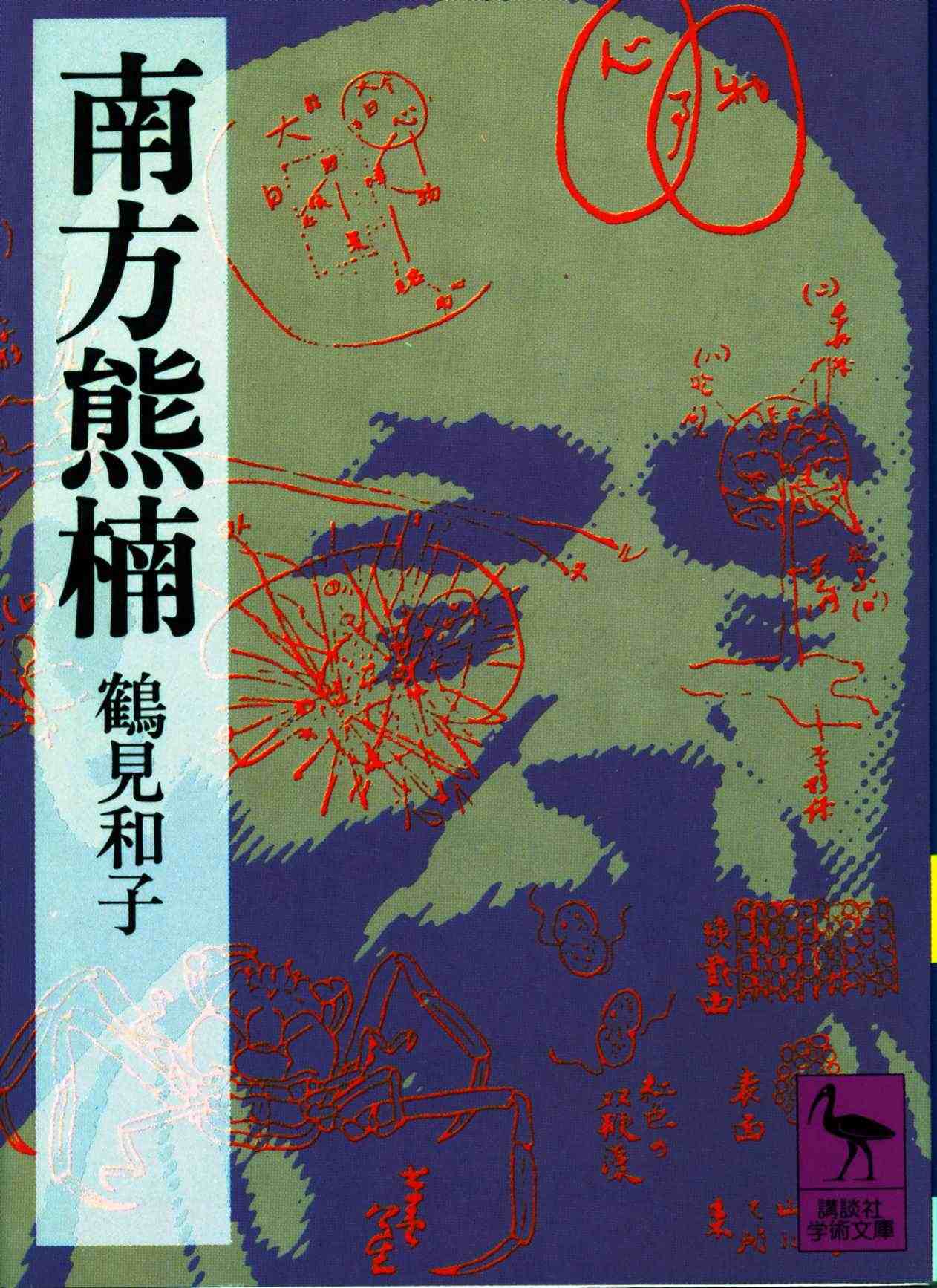|
かの夏目漱石がロンドンに留学したのが1900(明治33)年。それに先立つこと8年前、1892(明治25)年、単独イギリスに渡り、在英中、自然科学雑誌『ネイチャー』に論文を投稿、学術誌『ノーツ・エンド・クィアリーズ』においても世界の有識者・学者と対等にわたりあい、問答形式の論戦を繰り広げた人物がいる。その人こそ、南方熊楠(みなかた くまぐす)である。さらに驚くべきことに、熊楠は渡英前にはサンフランシスコ、ミシガン、フロリダ、キューバ、ハイチ、ベネズエラ、バレンシア、ジャマイカ島、ニューヨークを漂泊した。アメリカ大陸、西インド諸島を約5年間にわたって巡歴のすえ、大英博物館等を学究の拠点にして文献をあさりイギリスに約8年間滞在、そして、1900年に33歳で故郷和歌山へ帰国(注1)して後も引き続き、熊楠は、同誌に英文で寄稿し続けるのである。
南方熊楠とはいったい何者か。
実に熊楠の世界には、土俗学、民俗学、民族学、人類学、宗教学、歴史学、考古学、博物学、生物学、本草学、植物学、地学、地質学、鉱物学、岩石学、天文学、そして、微生物・地衣類・菌類・粘菌研究(注2)といった数あまたの学問領域が縦横無尽に交錯している。それゆえ、個別に機能分化し専門化されてしまった学問体系とその価値観のなかでは、ともすれば熊楠の世界には雑駁な印象がつきまとってしまう。
けれども、本書において鶴見は、南方熊楠の世界を「学際的」とは決して位置づけていない。「学際的」とは、あまりに専門化が進みすぎ、学問の縄張り意識が顕著になった20世紀後半に生み出された言葉である。あくまで鶴見は、そういった境界領域を超越する「解毒剤」として、「南方学」を捉えているのである。
今の学者(科学者および欧州の哲学者の一大部分)、ただ箇々のこの心この物に
ついて論究するばかりなり、小生は何とぞ心と物とがまじわりて生ずる事(人
界の現象と見て可なり)によりて究め、心界と物界とはいかにして相異に、い
かにして相同じきところあるかを知りたきなり。 (注3)
まさに熊楠は、ヴィクトリア王朝末期のイギリスで「科学が、未分化の状態から専門化が始まろうとする」過渡期にいた。また、当時、一世風靡していたダーウィンの進化論が熊楠にも衝撃を与えたことは想像に難くない。熊楠は、ダーウィンの進化論から派生した短絡的な進歩史観や社会進化論、単系発展論と対峙し、その脆弱な論拠を喝破する。
つまるところ、鶴見は、熊楠の世界を国際的な学問の土俵で果敢に他流試合を挑んだ「比較の学」と位置づける。
比較民俗、比較民話、比較宗教の視座。たとえば、欧米文化とアジア文化の国際比較を通して、熊楠は、生物学と民俗学の統合を図ろうとする。従来異なると考えられていた種別分類を比べ、正面から対決させる。そして、自分の体験や調べた資料と照合し、秩序立てて配列し直す。必ず原典にあたって、出所典拠を明らかにし、事物の因果律および属性の変化を厳密に把握することによって、その相互作用がいかに系統的に関連づけられるかを発見・発掘する。文献で蒐集不可能な場合は、野外観察をおこない、事物を採集する。導き出した判断に誤りを発見すれば、訂正・修正するのはやぶさかでない。要するに、熊楠は、自己に課した命題の妥当性を実証するのである。
熊楠の作品群には理論体系がない、その目的とするところが定かでない、といった批判や評価に対して、鶴見は「南方学」の構造を「生成の理論」として位置づけ、その思想の連鎖を「南方曼荼羅」(注4)と表現している。
「南方学」は、演繹法的な検証方式を採らない。まずデータの観察と蒐集から始め、蓄積したデータを分類し、振り分けたカテゴリーの属性の共通点と相違点を比較。そして、問題設定をおこない、閃き、直観、想像力を発動。異なるカテゴリーの属性とそれに関わる生成変化について新しい関係を発見する。その結果、複雑かつ多様な仮説を許容しつつも、継続して諸現象の相互作用、相乗効果を帰納法的に実証するのである。したがって、「南方学」は「事実にもとづく理論」(注5)と言い換えることができる。
そもそも「曼荼羅」とは、「宇宙の真実の姿を、自己の哲学に従って立体または平面によって表現したもの」(注6)である。すなわち、熊楠の「生成の理論」は単なるデータの羅列・分析にとどまらず、その背景には「曼陀羅」が存在すると鶴見は主張する。「南方曼陀羅」とは、事物と人間に関わる因果の結び目と道筋を辿って謎をとく科学理論のモデル、すなわち森羅万象の相関図なのである。
熊楠は決してアカデミックな学者ではない。さまざまな交流のなかで在野の研究者として真っ正直に生きた。確かに柳田国男や孫文といった当時の著名人たちとの交友は注目に値する。ところが、そういった有識者との知遇のみならず、イギリスから帰国した熊楠は「地域に深く根を下ろし、高く世界に飛翔する」(注7)という生き方であった。むしろ、後半生、熊楠は、再度世界の各地を駆け巡りたいという願望と葛藤し、ときに対立しながらも肌をふれあってさまざまな職につく人々とつきあい、学びあう。地元紀州の豊かな大自然のなかで、純粋無垢に野外観察をおこない、粘菌の新種を発見し、再び「比較の学」を通じて他流試合を挑み続けたのである。
そういう意味では、日本における民俗学の草分け柳田国男と対比すれば、熊楠の世界はより際だつ。面白いことに、両者のアプローチと価値観は全く対照的である(注8)。また、熊楠の展開した神社合祀反対運動(注9)は彼の宇宙観を全身全霊で実践した行動学そのものである。
一生、無位無官で学歴も学位ももたず、自分の信念で全人的に学問を追究し、流浪した「南方熊楠」。その生き様から、現代人が失いかけつつある野性的な知的好奇心と人間感覚が呼び覚まされる。
自由奔放、豪放磊落、天衣無縫。確かに熊楠の生活には、家庭の不幸や偏狭な社会情勢から湧き起こるさまざまな束縛があった。けれども、そういった環境により分裂する意識にさいなまれながらも、その生き方はどこまでも奇想天外、型破りで、しかも、熊楠の学風はまさに正攻法そのものであった。強靱な集中力で、文献を読み、資料を写し、野外で動植物を採取・観察し、文章や標本にまとめる。「自習自発見」(注10)。熊楠は、自分の眼で、耳で確かめ、自分の頭で思考し、あくまで独学で自分を叩きあげる。
もしかして我々が日々拘泥しているようなことは、枝葉末節ではないのか。リスクを背負って生きるか、それとも、志、夢を抱いて突き進むか。実は、条件が整わなければ実行に移せず、ついつい、ものごとの本質をみつめずに我々は日々やり過ごしてしまっているだけなのかもしれない。
熊楠のように、果たして生涯、何本の論考を発表できるだろうか。独創性をもちつつ、どれほど自己の内外にむけて情報発信が可能であろうか。
鶴見は遺された書簡を紐解いて、文通の軌跡から熊楠の思想を解明している。今日、研究活動にあたっても電子メールのやりとりが頻繁におこなわれているが、それが将来的には学究上の貴重な資料になることだってあるのかもしれない。
随分長い間、本箱の奥にしまいこんであったこの文庫本に読み返して、私はふとそう考えたのである。
注1) http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/kumagusu/lifemap/lifemap.htmを参照。
注2) http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/kumagusu/word/word.htmを参照。
注3) 本書 85ページを参照。
注4) 本書 83ページを参照。
注5) 本書 234ページを参照。
注6) 本書 82、217ページを参照。
注7) 本書 155ページを参照。
注8) 詳しくは、本書を是非ともご覧いただきたい。
注9) http://www.minakatakumagusu-kinenkan.jp/kumagusu/life/life.htmを参照。
注10) 本書 209ページを参照。
|