『映像となんだろうか、−テレビ制作者の挑戦―』
岩波新書 吉田直哉 2003年6月20日 777円
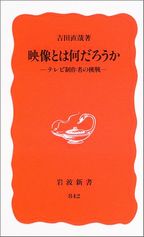
|
『映像となんだろうか、−テレビ制作者の挑戦―』 岩波新書 吉田直哉 2003年6月20日 777円
|
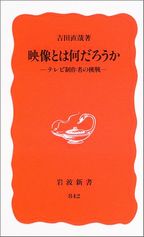 |
国際情報専攻 4期生 ・ 修了 長井 壽満
|
|
吉田直哉はテレビ放送が本格的に始まった時にNHKに入社し、ディレクターとして多くのドキュメント、ドラマの映像を世に送り出している。「日本の素顔」、「新興宗教をみる」、「日本人と次郎長」のドキュメント物から、大河ドラマ『太閤記』、『源義経』、「ミツコ―二つの世紀末」等を手がけている。同時代の日本人ならこれら番組のうちの幾つかは覚えているでしょう。 この本は映像化された文章から始まる。吉田直哉が最初に手がけた映像「新興宗教」の失敗談である。創価学会二代目会長戸田城聖の説法の撮影である。吉田直哉は、よほどこの失敗が悔しかったのか、映像に迫る迫力で戸田城聖の撮影失敗の説法を文章で描いている。 「グイッとあけな。グイィと」 「・・・いえ、これから撮影・・・。仕事中ですから」 「なにィ? それを言うなら、こっちだって仕事中だぞ」 からこの本は始まる。現場の緊迫した感覚が肌を刺す文章である。まさに映像である。 吉田直哉はドキュメントの制作から映像の世界にはいった。 最初の作品は「日本の素顔」シリーズである。ドキュメント映像を作成しながら、到達したテレビ映像の原点は「考えるカメラ」である。映像は作者の手をはなれると同時に、映像素材そのものの訴求力がひとり歩きしてしまう。視聴者は映像から派生した自己の想像力を通して作品を自分なりに受け入れていく。そして視聴者は映像に登場する者(物)に作者が全く意図していなかったフィードバックを与えてしまうのである。「<考えるカメラ>で撮れば、テレビは巷でいわれているような衆愚 製造装置にならず、考えるための道具、<考えるテレビ>になるだろう・・・・・[i]」。21世紀の今、ヴァアーチャル・リアリティーという言葉が氾濫し、刺激的かつ無責任な映像がテレビ やインターネットを通して氾濫している時代に映像の原点「考えるカメラ」という言葉は重い意味をもつ。 吉田は「一人歩きしてしまう映像」の怖さから、ドキュメンタリーからドラマ部門に移籍を希望し、ドラマを撮るようになる。大河歴史ドラマ『太閤記』である。文学には「時代小説」、『歴史小説』、「史伝」などのジャンルがある。吉田は「歴史ドラマ」というジャンルを開拓した。現代と過去の間をタイムマシンで行ったり来たりし、過去の人間の生き様を茶の間に送り届ける手法である。過去と現在の接着剤は「ナレーション」である。「ミツコ------二人の世紀末」では吉永小百合が一人二役、ミツコとリポーターになって、現在と過去をオーバーラップさせ、効果的に視聴者の想像力に働きかけている作品である。 歴史ドラマの場合、ディレクターは過去の歴史的人物のイメージを自分なりに消化し、そのイメージに合った俳優の人選をおこなう。最初に登場人物のイメージである。ストーリーは歴史から借景したドラマである。小説と言い換えてもよい。ドラマが史実と一致する必要はない。しかし、人の生活や世の姿に「歴史的変化」がある[ii]。その由来に愛情と尊敬の念をもっていなければ、歴史ドラマでないのではないか? 例えば女性の心理など、現代そのままのものを舞台設定だけを昔に置きかえただけの作品が実に多い。現代では起こりえないような荒唐無稽な葛藤やサディスティックな事件も、過去とういう辺境に場を借りて堂々と描かれる[iii]。 吉田はここでも、また悩み始めるのである。 悩みを持ちながら次にチャレンジしたのは、歴史そのものでなく、歴史に埋もれている「知らざれる風景を探し出し、ヴァーチャル・リアリティーとして映像にする仕事であった。「風景は運べないが、映像にすれば<実質的に>運んだことになる[iv]。この発想が『海外取材・明治百年』シリーズのきっかけとなっている。 吉田の映像作品の根底に流れているのは「われわれはなぜ現在かくあるのだろうか[v]」である。この言葉が何回も現れてくる。映像化とは時間を切り取り、切り取った時間(素材)を編集者の意図に基づいて再生する作業である。どうしても、歴史に目がむくことになる。この発想から始まったのが『未来への遺産』シリーズである。遺産とは「廃墟」である。吉田はヒットラーの言葉「ローマ帝国のなかで今残っているのは何か、彼らの建造物の他に何がある! どんな国民の歴史にも衰退の時期がある。しかしそうなったとき、建造物がかっての力を語りはじめるだろう。ローマがその手本だ![vi]」を引用している。映像が廃墟を伝える手段となっている。映像はタイムマシンーンの空間を我々の世界にもちこんでしまったのである。 吉田は常に歴史を意識していた映像芸術家である。同時に映像の受けてである視聴者も意識していた。そして<映像化>とは、割符をつくり、その片方を所有してひとに示す作業ではないか?それは、現実というもう片方の存在を確かに予感(想像)させるときに、始めて信頼できるものとなる。と締めくくっている[vii]。 この本はテレビ映像というメディアを通じてメッセージは発信した側の証言である。メッセージを作り送る側は、テレビ・メディアのもつ特徴を考え抜いてメッセージを発信しているのである。メッセージの受け手は無防備に口を空けてチャンネルを切り替えている存在である。テレビ・メディアの送り手と受け手の落差が大きくなっている。映像はますますイメージを伝える手段となりつつある。強力なイメージで受けての想像力を駆逐している。吉田がコマーシャル映像と撮る機会があれば、コマーシャル映像をどう扱うか、興味あるテーマである。今、メディアはどうあるべきなのか?この本は20世紀に創出された映像文化のあり方を豊富な経験と例でドキュメンタリー風に説明している。 吉田は1931年生まれ、青春時代を戦争で過ごしている。最後の戦中派知識人である。戦争体験を持っている数少ない知識人である。日本人が50年間忘れている戦争を体験し、そして消えつつある貴重な知識人の証言である。 メディアに興味ある方にはお勧めの一冊です。 以上 [i] 吉田直哉『映像とは何だろうか』岩波新書、2003年6月20日、37−38頁。 [ii] 同上、168頁。 [iii] 同上、168頁。 [iv] 同上、176頁。 [v] 同上、192頁。 [vi] 同上、203頁。 [vii] 同上、218頁。
|

|

|