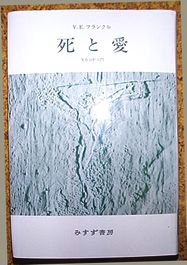

古くて新しい本を紹介します。2点ともヴィクトール・E・フランクル(オーストリアの心理学者、精神科医。1905−1997)の著書です。強制収容所体験を綴ったルポルタージュ『夜と霧』は1947年刊、フランクルの心理学的立脚点を明らかにした『死と愛』は1946年刊です。初出から半世紀を超えて、フランクルは近年、我が国でリヴァイヴァルとなっており、みすず書房版のセレクションに加えて、春秋社によるコレクションも刊行されています。ちなみに、『夜と霧』の1977年改訂版も、邦訳が昨年刊行されました。
『夜と霧』は、両親・妻・二人の子供を奪われ、彼自身も極限状態にさらされた過酷な強制収容所体験を著したもので、世界的ベストセラーとなった本ですからご存知の方は多いでしょう。『死と愛』は、この体験を踏まえて考察された論文です。前者が「心理学者の体験記」、後者が「体験的理論書」という関係になります。扱っている「臨床例」もほとんど同じですから、できればセットで読まれることをおすすめします。ただし、フランクルの思想の全体像については、近年邦訳されている講演集の方が平明に語られているので、そちらの方をおすすめします。
さて、なぜ古くて新しいのかは、後述させていただくとして、『夜と霧』の主題、『死と愛』の構成を紹介します。
1 『夜と霧』について
ユダヤ系オーストリア人であったフランクルは、被収容者を収容先にふりわける最初の選別(体力なしと判断された9割がガス室直行、労働に耐えうると判断された1割が強制労働へ。)をパスし、頭髪と体中の毛を剃られ、囚人番号「119104」として
いくつかの収容所を転々とすることになります。第1段階の収容ショック、第2段階の「感動の消滅」、理由なき懲罰の殴打と愚弄、皮下脂肪を消費して筋肉組織を滅するほどの飢餓を経て、さらに選別されてガス室へ送られる恐怖、脱走への誘惑、「死との競争のラストスパート」が解放される直前まで続きます。
この肉体的・精神的な極限状況の中で、彼は「精神の自由」に想いをはせます。これまで学んだ心理学説(人間は環境によって規定されるなど)を根本から疑い始めるのです。「人間の自由はどこにあるのだ」、「収容所にいてもなお人間として踏みとどまり、おのれの尊厳を守る人間になるかは自分自身が決めることなのだ」。そして人間の「存在」、「生きる意味」を洞察していきます。生きる意味を見出せなくなった被収容者は、その瞬間から精神的に破綻し肉体的抵抗力を喪失して斃れていき、未来を信じることができた者だけが生き延びたという「事実」から、彼の生涯を貫く学説(50年間ほとんど頑なまでに変わらなかった)が生まれました。彼自身は、自己体験に固執することが学説を歪めかねないことはよく認識していましたが、風雪に耐えうる学説とは頑なさを必要とするのかもしれません。
2 『死と愛』について
生還したフランクルは、本書で独創的な心理学説を世に問います。内容は次の3章からなります。
第1章 心理療法からロゴテラピーへ
第2章 精神分析から実存分析へ
第3章 心理的告白から医学的指導へ
第1章は、フロイト(精神分析)やアドラー(個人心理学)に対する批判にあてられています。人間の精神は無意識の産物ではなく快感原理で動いているわけでもないし、人間存在は還元主義的に決めつけられるものでもない。これらの有効性を全否定しているのではなく、心理療法を補充するものとして、一種の哲学的な療法、人間精神の立場から心理療法をとらえなおす療法(ロゴテラピー)を提起しています。「心理」だけを扱うのでは療法にはならない。「精神」を領域に引き入れる「精神的なものからの心理療法」が試みられなければならない、と説きます。
第2章では、彼が創始した分析方法である「実存分析」、人生の意味を問う分析の意義が説明されます。中心は「生命の意味」、「死の意味」、「苦悩の意味」、「労働の意味」、「愛の意味」にあてられています。
骨子をいくつか要約すると、人間が実現しうる価値は3つある。まず「創造的価値」。人間は活動を通じて創造を行うことができる。次に「体験価値」。人間は自然や芸術に触れ感動を体験することができる。ここまでは育ちや環境に影響されうる価値であるが、第3に「態度価値」。これが最も偉大な価値であり、変えることのできない運命に対して人間としての勇気と品位を維持することである。「態度価値」を示しうる限り人間の実存は無意味になりえない、と説きます。
人間の実存は、個々人で独自のもので1回しかなく(独自的かつ1回的)、死すべき有限性や過去を引き受ける(過去に拘束されるという意味ではない)ことから導かれる。独自かつ1回であることを認識することから、過去を乗り越えた未来を信じることができ、生きることの意味が見出しえます。
ここから、不安神経症に対しては、ユーモアを用いて不安から距離をおくことの有効性、また更年期の危機については積極的な再生にかえること、などの知見が導かれます。
第3章では、医学的指導は宗教の代用品ではなく、実存分析は治療者の世界観を患者に押し付けることなく、患者の決断能力の回復をめざすものであることが示されます。そして、彼が開拓していこうとする領域は「医学と哲学との境界領域である」として結ばれます。
3 フランクルの意義(私見)
その後のフランクルの業績は『夜と霧』、『死と愛』で提起したテーマの実証と補充、平明な言葉に置き換えての普及にあてられたと言っても過言ではありません。彼は、晒す必要もない無意識を暴こうとする精神分析学の傾向について「精神分析ごっこ」と呼び、また、人間を「適応型システム」とみなす還元主義的なアプローチを最後まで拒み続けます。ほぼ、同時代を生きたスキナー(行動主義心理学の大家)とは全く違う道を歩んだわけです。行動分析学や認知心理学の大いなる成果が明らかになってきた21世紀から見れば、フランクルの言説にいくつかの疑問を感じることはありうると思います。私自身、認知心理学や行動分析学の成果には、日常うなずくことが多いので、ときどきフランクルに道学的な臭いを感じることがあります。
また、彼の知性重視の傾向、患者の「世界観を論議する能力」を重視すること、人間の個性を重視するあまりの「大衆」への嫌悪(個性の意味は大衆の中では滅亡する)は、読者へ西欧的モラルの承認を要求するものでもあります。
しかしながら、私はフランクルの意義は今なお衰えていないと思います。「生きる意味」は強制収容所の中でのみ必要だったのではない。むしろ、強制収容所は単なる野蛮な装置ではなく、凝縮された異形の近現代でもあった。人生の無意味さに悩み、人生の意味に憔悴する「時代の精神病理」は、これから近現代が極まろうとしている21世紀において、ますます世界を覆っているのではないか。これは、飽食と並ぶ先進国病理ではなく、近現代の成りゆく果ての病理としてとらえるべきではないかと私は思います。「ぜいたく病」ではなく必然の摩擦ではないのかと。
さて、フランクルは1970年の講演において、彼が「実存的空虚」と呼ぶ「生きがい欠如」、その反応としての「過度の自己解釈癖」の蔓延、その原因としての、還元主義的な思考方法の行き過ぎに警鐘を鳴らしています。彼は終生、療法アプローチの哲学的意味にこだわり続けました。彼が決して手離さなかった試み、心理学・精神医学(人間を扱う科学全般と置き換えてもいい)と哲学を架橋しようとする試みは、彼が「望み多き土地」と呼んだように、意義を失っていないと考えます。この試みが近現代を解きうるかどうかは私にはわかりませんが、今日、「臨床哲学」や「臨床人間学」という新たな境界領域が試みられているのを知るにつけ、挫けそうになる学びと研究への意欲をかきたてたいと思っています。
最後に『夜と霧』、『死と愛』から、私が繰り返し読んだ一節をいくつかご紹介します。フランクルの文章は概ね美しく読みやすく、個々人の琴線にふれる箇所はいくつか見出せると思います。「他に代替できない」私にとって好ましい言葉が、「他に代替できない」あなたにとって好ましい言葉であるとは限りませんから、読まれた方はぜひ、あなた自身に響く珠玉の言葉を探してみてください。
「運命は大地のように人間に属している。人間は重力によって大地にしばりつけられるが、しかしそれなくしては歩行は不可能なのである。われわれは、われわれが立っている大地に対するのと同様に、運命に対さねばならず、われわれの自由に対する跳躍台としなければならないのである。運命なき自由は不可能である。自由はただ運命に対する自由でのみありえる。」霜山徳爾訳『死と愛』より
「およそ生きることそのものに意味があるとすれば、苦しむことにも意味があるはずだ。苦しむこともまた生きることの一部なら、運命も死ぬことも生きることの一部なのだろう。苦悩と、そして死があってこそ、人間という存在ははじめて完全なものになるのだ。」池田香代子訳『夜と霧』(新版)より

