�w���Y�t�H�x�Ɗ�g�w���E�x�̘_����������{�̌o�ϐ������l�@����
���ۏ���U�@�����c�M�F �_������F�����{�̌o�ϐ����ƎЉ�\���̕ϑJ �|�u���{�I�Ȍ̊m���v�ւ̈�l�@�| �����ȏЉ�@�����s�ŏ��@�탁�[�J�[�ɋΖ����Ă��܂��B���Ќ�ɒ��ߓ��֏o�����A�p�ݐ푈�̌��ǂ���߂ʃN�E�F�[�g�A��������Ђ����p�������o�m����ڂ̓�����ɂ��܂����B���̌�A�p�L�X�^�����ɂ��n�q���A�l�Ԃ̌Q�W�ƃo�C�^���e�B�ɐG�ꂽ��������Ȉ�ۂƂ��Ďc���Ă��܂��B�����̌o�������ւ��āA�{�e�̘_�|�ł�������{�ւ̍l�@��[�߂邱�ƂɌq�����Ă���Ǝ������Ă��܂��B

���̓x�A���ۏ��_���u�T�̃��|�[�g�ۑ肩��A�u�����{�̌o�ϐ����ƎЉ�\���̕ϑJ�|�w���{�I�Ȍ̊m���x�ւ̈�l�@�v�Ƒ肵���_������e����Ɏ������B���|�[�g�A�y�і{�e�̍�Ƃ́w���E�x�E�w���Y�t�H�x�̎�v�_���i�����̕\���Q�Ɓj�ɖڂ�ʂ����Ƃ���J�n�������A�����̘_�����r����ƁA���߂Ă��̋c�_�A�咣�̑��l���ɋ����̂ł���B
�@���̓��{�́A�č��̉���ɂ���Čo�ϓI���H�����o���A�����̔ɉh�������炵���B�������̕ϑJ�́A�����̔g���ɕx�ނ��̂Ƃ��āA���ɐ[���ȕs����p�j�b�N�Ɋׂ�A�Ǝ�ȎЉ�\���̗l�������I�悵�Ă����B�ł́A���������A�܂������Ǝ�Ȃ̂��B�č��̋@�B�I�A�v�f�I�Ȏ��{��`�͖{���ɗL���Ȃ̂��B���̓_�ł́w���E�x�y�сw���Y�t�H�x�����l�Ȋp
 ���E�@����{��`�͕ς��������s���d�l(1958.1-2)�^����{�o�ς̂䂪�ݣ���Z�����@�@�@�@�x����咣��W�J���A����N���s
���E�@����{��`�͕ς��������s���d�l(1958.1-2)�^����{�o�ς̂䂪�ݣ���Z�����@�@�@�@�x����咣��W�J���A����N���s
�g(1961.8)�^����̂т����Q�|���̐����o�ϊw��{�{����(1962.12)�^��Љ��`�Ɓ@�@�@�@���Ă����̂ł��邪�A�����_�����@�@
�s���Љ��c����(1968.2)�^����x�����̍čl�@��������p(1968.5)�^��o�ϊw�͌��@ �@�@�u��O�v�ɗ��r���A�č��̌v�ʓI��
���ɂ�������ꂤ�邩��ɓ�����(1971.7)�^��p�j�b�N�̎Љ�o�ύ\����{��`��@�@�@ �@�@�͂�����uMass�v�Ƃ������̂Ɋ�
(1974.7)�^��_�b�̎���͏I������|�o�ϊw�͗L���������߂����邩����a�����@�@�@�@�@���邱�Ƃ���A���̌o�ϐ�����
(1979.7)�^��w�y�����Ɓx�j�b�|���|�����Đ��Y�V�X�e���̈���Ɠ��h��ΐ�^���@�@�@�@�@�́A���ׂĂ�������̂ɂ��Ă���
(1983.8)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B�@�@�@
���Y�t�H�@����͂���ł͂Ȃ������D�v(1956.2)�^��Ԋ��Ɛ�����\�N�ԣ�O�c��@�@�@ �@�@�����A�uMass�v���}���ɐZ������
(1958.8)�^������{���̓������������K�V��(1961.12)�^��ɉh�̂��߂̎Z�p������K�@ �@�@�Љ�\���́A���̑�ւƂ��āA�v�z
�V��(1964.8-12)�^���Ђ͗V���n�ł͂Ȃ�����c���v(1965.11)�^����{�����̐@ �@�@�I�ȑ��ʂ╶���I�w�i�ɂ��Ă��A
�ʐ^��c���p�h(1967.2)�^��g�n�R�h�͂��������ɂȂ�Ȃ���i��d�Y(1971.9)�^��p�@�@�@�@�������u�E�F�v����������Ȃ���
�j�b�N�|���̐��Ԍn���O�~��Y(1974.2)�^��J���g���|�Â����̏I�裒�����(1979.�@ �@�@���ɒ��ʂ�������ے肵������
5)�^��������Ђ͐�́w��a�x�ɂȂ飊C�����Y(1983.4)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ����v���A�܂����̂��Ƃ��A
���{��A�W�A�̌��_�E�ɁA�����̊�@�I�ϑ��������炵�Ă����������̂ł���B
��̐i�W�ɔ����Љ�\���̎�e�́A�č��哱�ɔ��Ԃ������A�X�Ɍo�ϕ���ɂ����Ă��������ɂ��v�ʓI��͂̍��x�������i����Ă���B�v���W�c�̕č��ɂ��Z�p�{���_�̊g�剻�ɁA���{�͂ǂ��Ώ����Ă��̂��B����A���߂Đ���ȋc�_���Җ]����悤�B
�@�{�e�͂܂��A����E���̋������ɂ�������{�ƕč��̐��_�`���ɂ�����w�i����A��O�̗����E�y�ь����ւ́u���o�v�̑���_�܂��A������������{�̌o�ϐ����̊T�ςɐG��A�Љ�\���̕ϑJ�ߒ��A���тɑ�O�A�l�̈ӎ��ω�����u���{�I�Ȍ̊m���v�ւ̍l�@���s�����̂ł���B�����������ۑ�Ƃ��Ă͐��ɗ͗ʕs���̊����ۂ߂��A�ٍ삾���A�F�l�̂��ӌ�������K���ł���B
�����{�̌o�ϐ����ƎЉ�\���̕ϑJ�@�|�u���{�I�Ȍ̊m���v�ւ̈�l�@�|
�P�D�������������̎����
�o�ςƁA���̐����ɔ����Љ�\���ւ̓W�]�ɂ����āA����炪��ɑ��ݕ⊮��p���J��Ԃ��A�ϑJ���Ă����ߒ��ɂ����āA��O�́A�e�X�̎��ۂ�c������ϓ_���܂��A��Ɉڂ�ς���Ă�����������Ȃ��B��������O���A�����Ƃ��Ă̑��݁A�ϗ��Ƃ��Ă̓��ׂƂ̊Ԃ����邱�ƂȂ��A�����I�����ɂ��Љ�\��������グ�Ă������Ƃ������A���̍������́A��ɔ����ɏ���Ƃ����M��A���_�̎嗬���`�����Ă������オ�������B
���݂ɁA����E���̖u���Ɠ����ɓ��{�����z���̘T�������������A��O�͂��̗l�����ǂ��Ƃ߂��̂��낤���B���̂��Ƃɂ��āA�����̐V���L�҂���O�ɍs�����A���P�[�g���������ƂɁA�ȉ��̂悤�ȋ����[���l�@���s���Ă���B
�@�@���a16�N12��8���A�����̐l�͂�����₪���ꂽ�Ƃ��A�Ƃ��Ƃ���������A��邼�@�@�@
�Ɖ��Ƃ����ȂǂƐ����ɓ����Ă���B���ǂ̏d�傳�ɐg�̈������܂�̂��o�����Ƃ����l�������B
����ɑ��āA������m���l�Ƃ�����l�̏��Ȃ��炸���A���Ƃ����n���������Ƃ��A����œ��{�������܂����Ǝv�����Ƃ��A����܂ł̐N���푈�ɂ������Â��Ă����̂ɁA�ƌ������{����������ȂǂƁA�������푈���̎p�����т��Ă����悤�ɓ����Ă���B�������B����قǐ������̎w���I�ȗ���̐l���푈��Δ��Ȃ̂�������A���Ȃ��Ƃ����̋C�z���炢�͓��R�A���_���f�����ł���V���ɔ��f���Ă����͂��ł��낤�B
�@�����A�����̐V���͂���Ȃ�Εĉp�푈�x���ǂ��납�A���̔M���I��搉́A��ӍV�g�A�c�R���Έ�F���B��Âȕ��͕����e���`�������Ă��Ȃ��B�ǂ������{�̒m���l�͎����������o�҂炵������������B�܂�A���قł����w�������D�����x�������̂ł͂Ȃ����i��c�Y�����ҁw�]�����̐헪�U�@�������a�x�o�ϊE�A1988�N�|�T���A��c�Y���u�����̎��ォ�獂�X�x�H�ƎЉ�̎���ցv�j�B
�@�@�@�@�@
���̓��e�́A���{�l�̂���M�d�ȑ��ʂ�掦�������̂Ƃ��āA�����ɕx�ނ��̂ƌ�����
���P�B��Ђ̍Œ��A�푈����i���邱�Ƃ͐��Ɋ댯�ł���A����ł�ނ����Ȃ����Ƃł͂���ƊϔO�����A�����͂��납�A��ςȂ��ƂɂȂ����ƘT�������l�����Ȃ肢���͂��ł���B���������I�ȓ��������̂܂����V���́A�������ڂ݂��A���Ȃ̂悤�ɁA��O�Ɍ������Đ�ӂ�������w�i���_�Ԍ�����̂ł���B
�������̒��A���̐�����������A�c�����邱�Ƃ͔@���ɍ���ł������Ƃ͂����A���̋L�҂́A�V���ɂ�����咣���ߑ�Ɏ��ȕ]�����ׂ��A�����̓��{�R�̔��Ώ���`���Ɖ��������_�̑Ó����A�y�ѐ���������A�����̓��{�l�̎v�z��f�肵�A����������������o�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��l������B
�@�܂����̂悤�Ȃ��Ƃ́A�����̐V���݂̂Ȃ炸�A�����̎G���₻�̑��̕��f�B�A�S�ʂɂ��Ă������邱�Ƃł͂Ȃ����B���_�̎��R��搉̂���A���l�ȃ��f�B�A����O�ɗ��r���Ă��鍡���ł����A���O��`���͂��߂Ƃ���U�P�s�ׂɍS������A���f�B�A�͐̕^���A�^����`���邱�Ƃ���������̂�����ł���B�X�ɂ��̂��Ƃ́A��O�ɂ�������{�l�̎v�z�����ɑ���u���o�v�͂��납�A�����Љ�̖{���I�ȕ������猩�����Ă��܂��댯����s��ł���Ƃ��l������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@����ŁA���̐푈�ɂ�����A�������̕č��ł́A���̐����I�Ǘ�����̒E�p�ɐ������A���E�I�����̍\�z�ƈێ��̂��߂Ɏ���ӔC��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ�������ƁA�]������\�z����Ă������|�I�Ȍo�ϗ͂Ƃ����ւ��āA�����I���u�č��̐��I�v�ł��邱�Ƃ�錾���A�č������̑唼��������u���o�v����Ɏ������Q�B���̂��Ƃ𑣐i�������w�i�Ƃ��āA�]���̓Ɨ������I�����Ɋ�Â����R�A�y�і����`����Ƃ������z��`�I�Ȏg�����ƁA����Ɏx����ꂽ���ێ�`�I�ȕč����i�V���i���Y���́u��ȗZ���v�����݂��Ă����Ƃ���Ă���B
�h�C�c�ƁA���̐�͂𗊂�ɊJ��ɓ��ݐ������{�̑S�̎�`�ƌR����`�ɂ������ʂ̐N���A�y�юE�C�́A�č��̗��z�I�Ȏg�����Ɛ��`���A�X�ɂ̓i�V���i���Y�����h�����A�u��ȗZ���v�̌`���ɔ��Ԃ��������B�č��́A�o�ςɂ����Ċ��ɒi�Ⴂ�̐i�W�������Ă����u�č��̐��I�v�̌������A���E�����̏�ɂ����Ă��A�悤�₭�F�߂��̂ł���B
�@���̂悤�ȕč��̈��|�I�Ȑ����E�o�ϗ́A�R���͂ɁA�h�C�c�ƂƂ��Ɍ���I�Ȕs�k���i�������{�́A���W���鋕�E���̂��ƂɁA����ł͍��ׂƂ����r�p�̒��ł̉�������O�ɐZ���������B��O�́A�Ȃ��s�����ɋ����Ȃ�����A��T��ŕ��X�̓���𗊂�ɕ����o���A�₪�Ď��E����܂��Ă���ƁA�����̍ďo���𐾂��A�u�߁v�E�u�H�v�E�u�Z�v�Ɋ��H�����߂ē����o�����̂ł���B
�@���{�����ւ̓��́A�o�ςɂ������̊��H���Ȃ������B���N�푈�ɂ������́u�_���v�������N�����A�܂��A�S�ʍu�a���ۂ��̋c�_�͂��������̂́A�č��̕��j�ɑ���A�T���t�����V�X�R�u�a���𐬗������A�u�O��̐_��v�Ƃ���ꂽ�ƒ�p�d�����i�����y���A��O�̓��{�o�ςւ̊��҂͉v�X���܂邱�ƂɂȂ����B
�@���͂�u���v�ł͂Ȃ��R�B1956�N�A�u�o�ϔ����i�N���o�ϕj�v�͑O�N�x�̌o�ϕ��͂�ʂ��āA���̕���������u�ߑ㉻�v�ɂ�鐬�����ɓ����Ă��邱�Ƃ��������A�܂������ɁA�����ڕW�Ƃ��Đݒ肷�邱�Ƃɂ���āA��ƌo�c�҂ɐݔ�������V���ȋZ�p�̓��������N�����Ă������B
�����A���͂�u���v�ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ���ŁA�u��O�v�ɖ߂����Ƃ������Ƃł͂�
���A����͂܂������V�������{�̗����ł������ƌ����悤�B��O���ƌo�c�҂����M�����߂����Ƃ͂����Ă��A����͌o�ϓI�ȑ��ʂ����ŁA�܂�́u�n�R�v�ł��Ȃ��Ă��ς݂������A����A�u�n�R�v�͂ނ��댾����ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ȃ����Ƃ��������ɂ����Ȃ��B����̐j�H�͂��ׂĕč��̎蒆�ɂ���A��]����Ҋ��ƕ��s���āA�s�����⌜�O�A�Ђ��Ă͐����̎��̐��̂Ȃ�����������������Ȃ��V�������{�̎p�ł������B
��c�Y�����́A�č��̉���ɂ��u�V�����{�v�̎Љ�\���ɂ��āA���̂悤�Ɏw�E���Ă���B
�@�@�V�������{���������̂́A�A�����J��̌R�ɂ��O�ꂵ���_�n����ł���A�����
�݈ʐ���c�����̔p�����t�����A�Ǝ�E�n��̃p�[�W�A��ƍٔ����Ƃ��Ȃ��Ė����ȗ�
�̓��{�Љ�̎x�z�̐������{����j�A���E���j�ɂ�����݂Ȃ��قǂ̕����Љ����
����o�������Ƃɂ���i�u�����̎��ォ�獂�X�x�H�ƎЉ�̎���ցv�j�B
�@
�o�ϐ������B������A�����͉��ɂ����鋇�R��i���̖��͉��P���A�H�ɂ݂镽���Љ���������̂����A�x�z�ґw�̕���������炵���̂́A���{�̎������ő䓪���Ă����V���Ȑ��͂ɂ����̂ł͂Ȃ��A�č������̍������`���������Ƃɂ��B���̂��Ƃ́A���{�ɐV���Ȏ�����x�z���A�Ǘ������̓I�ȎЉ�w�����܂�Ă��Ȃ��������Ƃ������Ă���B
�@�s��Ƃ����O���I�v���ɂ���āA�č��̋��e�̂��Ƃň琬�E�}������A���̊�Ղ��\�z���������̐��A�y�ъ�Ƒg�D�́A�傫�ȉ��l�ς̓]���𔗂�ꂽ�B�`���I�Ȏx�z�ґw����V���A�u�V�c��m�v����u�Y�Ɛ�m�v�ւƔ��Ύ��Ȕے�I�ɍĐ��������̔��F��}��A���̓]�g�̉ߒ��ɂ����āA���{�͓Ǝ��̎Љ�\��������グ�Ă������̂ł���B
�Q�D���x�H�Ɖ��̐��n�ƃp�j�b�N�̎Љ�\��
�@���͂�u���v�ł͂Ȃ��A�Ƃ̐��_����ь������A���{�͋Z�p�͋����ɔ������x�ȍH�Ɖ��Љ�̎����Ɍ�����簐i���������̂����A���̓]�����̍Œ��ɂ���������Ƃ��āA���𒆐S�Ƃ����Љ��`�ւ̗��z�����܂����w�i����������B
�@�����ő����_�|�����E���邪�A�����}���N�X�E���[�j����`��W�Ԃ��A���W�𐋂����邩�̔@������Ă��������E���\�A���A�����I�Η��̗l����[�߂Ă��������ƂŁA����E���Ɍ���ꂽ�鍑��`���ƊԂ̑Η��ȏ�ɁA�댯�ȉe���𐢊E�����̉ߒ��ɐA���t���Ă������w�i�����ڂɒl������L�����ƌ����悤�B
���c�������́w���E�x1968�N2�����ɂ����Ď��̂悤�Ɏw�E���Ă���B
�@�@���X�̔̕w��ɂ���q�ϓI�Ȗ��́A���{������̎Љ��`�ւ̈ڍs�ƁA�Љ��
�`���狤�Y��`�ւ̈ڍs�̗��ߓn�����A���V�A�ƒ����̗��j�I���y�I�������ɔ}���
�Ȃ���A�������݂��Ă��邱�Ƃ̂����ɂ���i�u�Љ��`�Ǝs���Љ�v�j�B
���̂��Ƃ́A���݂̂Ȃ炸�A�m���l���܂߁A���{�ł��}���N�X�o�ϊw�v�z�ւ̋c�_�������������炵���w�i�ƌ��т��Ă���ƍl������̂ł͂Ȃ����B�����ł���Ȃ�A�č��哱�̎��{��`�I�s��o�ς̋@�B�I�A�����͗v�f�I�ȗ��_�̓������́A�L�@�̘_�I�Ȏv�l�@�ɗ���A���ꂪ���{���L�̓`���ɂ�����l�ԁA�����͎Љ���Ƃ������̂ɂ��đz����y����ꏕ�ɂȂ������ƂŁA�u��e���ꂽ�v�ƍl����̂͋����߂��邾�낤���S�B
�@���{�ɂ�������̌o�ϐ����̌����́A�č��哱�̎��{��`�I�s��o�ςɔ������R�����̎Y���ł������ɂ��S��炸�A����ł͏�q�̗��z�_���䓪���A�g���̒����A�X�ɂ͊w���^���̍��g�A�ߌ������t������Ƃ����A�V���ȎЉ�\���ɂ����閵���Ƙc�݂�I�悵���T�B
�o�ςɂ������H���Ȃ����{�́A�F���ɓ��������������E���ށE�Z�p��č��̎w���Ə��͂ɂ���Ċl�����A�����̕��y�I�����ɍ�������㵒p�S��ʎq����ؕ��@���邱�Ƃɂ���ĖҐi���čs���B�u�����A�����Ēǂ����A�ǂ��z���c�v�Ƃ����n��̂���悤�ȑ�O�̐M�O�́A���L���Ȑ����ւ̗��z���A���u�����I���O�v�Ƃ��Ē蒅���������̂悤�ȑ��ʂ��炠�����B
�o�ϐ�������Ƃ������㒪���́A����ł͐����ւ̊S���}���ɒቺ�����A�������܂��A��O�ɉ䖝�E�E�ς�����I�ɒ�Ă���\�z�͂������A���������P�E���コ����A�Ƃ����X���[�K���ł��̐����W�Ԃ��Ȃ���A��O�̎x���������邱�Ƃ��o���Ȃ������B
�@���{�����x�Ȑ�i�H�ƍ��̒��ԓ�����ʂ��������Ƃ���邩�̔@���A1964�N�ɊJ�Â��ꂽ�����I�����s�b�N�́A���W�r�㍑�𑲋Ƃ����L�O���T�Ƃ��č����Ɏ��M�Ɗ�]��^���A�X��1970�N�̖���������́u�V�����{�v�ɂƂ��ĐV���ȓ]�@�������炷���ƂɂȂ����B�@
�����A�����w��̏�̉_�x�����M���̍�ƁE�i�n�ɑ��Y���ƁA���呍���ōH�w���m�ł�����V�����Ƃ́u���{�̔ɉh�����������́v�Ƒ肵���Βk�U�́A�s�킩��Փ�o�葱���Ă�����i�H�ƍ����{�̊�H������������̂ł������ƌ����悤�B�����Ȃ邪�A�ȉ��͂��̎�v�����̈��p�ł���B
�@�@�i�n�@���{�͖����ېV�ȗ��A���m���炢���ȃp�e���g���āA���ꂱ���S�́@�@
��������珗�̌C���̂�����܂Ńp�e���g���Ă����܂ł���Ă����B�Ƃ��낪
�����ւ��āA�p�e���g���Ă��ꂽ��i����ǂ��z����������킯�ŁA�����Ȃ�Ɠ�
�{����ׂ��A�����p�e���g�͔����Ă��Ƃ������ԓx�ɏ��O�����Ȃ��Ă�����
�炵���B�i�����j����Ȃ炻��ŁA���͂ŋZ�p�v�V������Ă����͂����{�ɂ���̂��ǂ�
���B�Ȃ��Ƃ�����������܂��ˁB�u���{�͋Z�p�̎O�������v�Ƃ������͂��w���Y�t�H�x��
���a45�N3�����ɂ��̂��Ă���܂����A����͉��H�Y�ƍ��ƂƂ��ẮA�G�l���M�[�m�ۂɗ�炸�A�d��Ȗ�肾�Ǝv����ł�����ǂ��B
�@���V�@��́A���f�������Ȃ���ΈӒn��������Ȃ��ł��ނ킯�ŁA�i�����j�G�R�m�~�b�N�E�A�j�}���Ƃ�����ʂ����߂�Ƃ����邱�Ƃł��ˁB���܈�́A�Z�p�i���_�Ƃ����͓̂��{�ŋN����O�Ƀ��[���b�p�ŋN�����B�t�����X�̃}�V���E�v���Ƃ����d�q�v�Z�@���[�J�[���A�����J��IBM�ɏ������āA���ꂪ���[���b�p���Ŗ��ɂȂ�A�A�����J�Ƃ̋Z�p�i�����Ȃ�Ƃ��k�߂Ȃ��Ⴂ����ƌ������Ă݂��B
�@���ʂ͔ߊϘ_�Ȃ�ł��B�i�����j�i��ł��鍑���傫�ȓw�͂����Ă������A����
�傫���Ȃ���肾�A�Ƃ����ߊϘ_�ɗ���������ł��ˁB�Ƃ��낪���{�̏ꍇ�͏�����
���B���[���b�p�͐i��ł����̂��A�����J�ɒǂ��z���ꂽ���A���{�͏��Ȃ��Ƃ����܂�
���Ēǂ��z���ꂽ���Ƃ͂Ȃ��Ƃ������M�������āc�B
�i�n�@�ςȎ��M������ǂ��A�i�j����͑傫���ł��ȁB
���V�@�傫���ł��B�����̂Ƃ��낪���[���b�p�Ɠ��{�̋Z�p�i���_�̈Ⴄ�Ƃ���Ȃ�
�ł��ˁB���{�̋Z�p�҂͒ǂ��z�����Ǝv���Ċ撣���Ă��܂���B�i�����j�ꗬ�ɂȂ낤��
�v���Ă���Ă܂��B
�i�n�@���������l�����̎m�C����������悤�ȍ��̐��~�����ł��ˁB
���V�@�����B���ꂩ��i�������̂��߂̐헪�𗧂Ă�ׂ����Ǝv����ł��B�i���j
���C�����Ђ�����V�����ƁA���x�ɔ��B�����d���w�Y�Ƃ̔��W����̎��Ȃ�ۑ�B����́u�S�|�Ɓv�A�����n�[�h�E�E�F�A����\�t�g�E�E�F�A�J���A���тɐ����E���Y����m�����W���T�[�r�X�Y�Ƃւ̓]���ɑ��Ȃ�Ȃ������B
���������̓��̂�ɂ��ẮA�����łܑ͕��������s�\���ł���A����Ŏ��_�������Љ�Ɍ�����ƁA�u�_�v��ڎw���ēo�葱���Ă������ʂƂ��āA�����v���������炵���ƒ�p�d�����i����ɓ���A�o�ϓI��Ƃ�͊m�ۂ������̂́A���́u�_�v�́A�������s���Ƃ����u�É_�v�ւƕω����Ă������B�X�ɉ��߂�A���Q�́u�C�v�����R�Ƃ����g���Ԃ����グ�A�����ɃI�C���E�V���b�N��ϓ����ꐧ�ɂ��h���艺���́u���v�������r���B�ӂƌڂ݂�A���͂╂����Ă���͂����Ȃ��ߍ��Ȗ��ɒ��ʂ��Ă����̂ł���B
�u�s���ƃp�j�b�N�v�́A���̎����̓��{���ے������L�[�E���[�h�Ƃ��đÓ��ł��낤�B�u�É_�v�ɕ����A�u���v�Ɍ������钆�A���̔E�ςɂ����E���������B��O�͕s���������������ŐS�̉���ɂ��������������X������U���A�O���ɂ���킷�s�����ē��{�S�͖̂��h���ȏ�Ԃ̂܂܃p�j�b�N�Ɋׂ����̂ł����V�B
���x�ȍH�ƎЉ�̎����Ɍ������Љ�\���́A�J���̏W�ɔ����l���̖��W���������A��ɏW���^�̑�n�J���A�j���[�^�E���̌��݂ւƐi�������B���W�n�̌Q�O�s���́A�u�l�ԂƐl�Ԃ̘A�ѐ��̌��@�ƌ��z�\����̑��݊֘A���Ƃ̖����W�v��I�悵���`�ŁA���̐Ǝ㐫������ɂ����ƍl������B�u�W�c�v��u���W�v�ɂ����Č��ʂ�����͊w�̗l���́A�����������Ŗ��m�ł���A���̗͂�2�{�A3�{�ƂȂ��ĉ��肳��Ă������̂����A�O���ɐƂ��A��U�������A�X�ɂ͊m�M���܂őr�����Ă��܂��ƁA�X�̗͕͂��U������Ă��̌��ʂ����ނ�����B���{�́A���j�Ղ��������q�C�̂悤�ɁA���Ă��Ȃ��A�C�H�̓��a���K�ꂸ�A�����ڐ�̐j�H��ڎw���đO�i���Ă����������̏���Ⳃ͌�������Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B
�R�D��Љ�̓����Ɓu���{�I�Ȍ̊m���v�ւ̉ۑ�
�u�É_�v�ɕ����A���m�Ȑj�H��r�����Ă������{�ɁA�悤�₭���������n�߂��B����͂܂�����č�����́u�A���v�ɂ����̂ł͂��������A�h�b�i�W�ω�H�j�̊J�����͂��߂Ƃ���}�C�N���E�G���N�g���j�N�X����̔��W�ɔ����A���ٓI�ȋZ�p�v�V�������炳�ꂽ���Ƃł���B
�@����܂ł̓��{�ɂ�����A�S�|�Ƃ���ՂƂ���d���w�Y�Ƃ�ړI�Ƃ����o�ϐ����́A�Q�D�ŐG�ꂽ�i�n�E���V�����̑Βk���ɂ����ċc�_���ꂽ�Z�p�i�������̂��߂́A�X�Ȃ�v�V���Җ]���ꂽ���ɂ����āA���Q���̔����A�X�ɂ̓G�l���M�[�̑�ʏ���Ɋ�Â��I�C���E�V���b�N�̉e�����A���̌��ʁA��i�H�ƍ��Ƃ��Ă͉�蓹�����邱�ƂɂȂ����B
�@�}�C�N���E�G���N�g���j�N�X�ɂ��Z�p�v�V�̐i�W�́A��[�̍H�ƋZ�p���A�d������^����t�����l���������y���Z���^�Ɉڍs����Ƃ����Ռ��I�ȕω����\�ɂ��A�i�������̂��߂̑��|��Ƃ��ď]���̓�_���������Ă������B���̋Z�p�v�V�̔g�́A��̒�LSI�i�������x�W�ω�H�j�̊J���ɂ��R���s���[�^�̔��B�E���тɏ��^���𑣐i�����A�X�Ɍ��t�@�C�o�[�Z�p�̐i�W�ɂ��f�B�W�^���ʐM�l�b�g���[�N�iISDN)�̍\�z�́A�Y�ƍ\���̓]���ɔ��Ԃ������Ă������B
�Z�p�̐������ɔ����āA��Ƃࢌ��ʌo�c��헪�ɏ��o�����B���ɐ����Ƃ̑����̕���ɂ����āA�@�B���E���������Z�����A���Y����̏]�ƈ��̔䗦�͒ቺ�A�ς��Ĕ̔��Ǘ��⌤���J������̔䗦���㏸�����B���̂��Ƃ́A�o�ϑS�̂ɂ�����T�[�r�X�Y�Ƃ̌���A�Ђ��Ă͌o�ς̃T�[�r�X���𑣂��A�Q�D�Ŋ��q������ܑ�������́A�Z���Ԃ̂����Ɍ����Ɏ������ꂽ�̂ł����X�B
�@�}�P�́A���̌o�ϐ����ɂ�����Z�p�v�V���A�d������^����A�������ɂ��y���Z���^�Ɉڍs�����w�i�ƁA�J���́A�X�ɂ͎��{�~�ς̊�^�x��\���Ă���B�S�|�Ƃ���Ƃ��鍂�x�������܂ł́A���|�I�ȋZ�p�i���������ł��邪�A���̌�͊�Ƃ��u���ʌo�c�v�헪�ɓ]�����A������x�̋Z�p�������ێ����Ȃ�����A�J�����Y���̌���Ǝ��{�~�ς���̂Ƃ����Y�ƍ\���̓]���ɔ����A�o�ς̃T�[�r�X���ւƈڍs�������Ƃ�\�����Ă���B
�i9.7%�j �i8.7%�j �}�P ��1�j���{�̋Z�p�i�����o�ϐ����ɂǂꂾ����^���������ԓI���Y����p���Đ��v�������� ��2�j�����ł����Z�p�i���̊T�O�͐V���i�J���A�J�����Y������A�X�ɂ͒ᐶ�Y����i�_�Ɓj���獂���Y����i�H�Ɓj�֘J���͂��ړ�����Y�ƍ\���ϊv�����܂��A���L���T�O��Ώۂɂ��Ă���B �o���F�G�R�m�~�X�g�Վ��������w�����{�o�ώj�x�i���o�͎��ˎ��Y�w���{�o�ς̐����́x�_�C�������h�ЁA1979�N�j
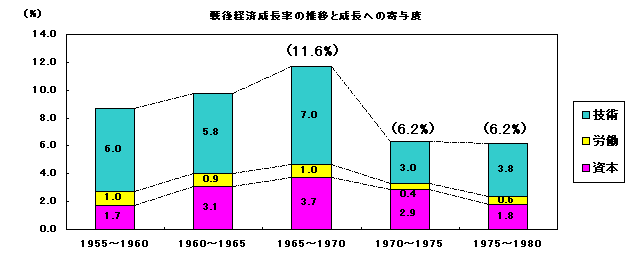
���̂悤�ɁA�o�ς̃T�[�r�X�������i���ꂽ���Ƃ́A����ł͑�O�̓��퐶���ɂ�����l�ԓI�ȐڐG�̏�̑���ȕ������A�s��I�ȊW�ŕ���ꂽ���Ƃ��Ӗ����Ă���10�B���{��`�I�s��o�ς������������v���́A���̂��Ƃ��������Ǝ��R�����𑣐i�����A�䂽������ۏႷ�邽�߂̋ɂ߂Č��ʓI�ȑ̐��ł���A����i�ł���Ƃ������ƂɋA������B�܂������̗v�f�Ɍl�̑I��I���R�������A����l�̗D��I���l�ɑ������s���ȑ̐��ł���Ƃ��l������B
�����Ⓦ���������͂��߂Ƃ���A�Љ��`���Ƃ̑��������p�ƕ���͉����Ӗ�����̂��B�䂽�����i���n�߂���O�́A���̎S���c�����A���Ẵ}���N�X��`���A���̌����������猩�āA���͂���ł������ƔF�߂���Ȃ��Ȃ����B�܂��A�g���������Ƃ����̐���ێ����Ă��邱�Ƃ���A���̂悤�ȎЉ�͍��ۋ�������E�����Ă��܂��A�g����������Ƃ��A�s�ꋣ���ɂ����Ĕs�ނ���̂ł͂Ȃ����Ƃ����F���܂ł��A���̎����̑�O�̊S���L���߂��Ă������w�i���������ׂ��ł͂Ȃ��낤�B
���������́w���Y�t�H�x1979�N5�����ɂ����āA�o�ϐ����̗��C���ƕ��s���āA�g���̌������͒����X���ɂ��邪�A����ł͘J���^���W�̎G����A�P�s�{��ǂ����肪�����Ă���Ƃ����V���ȌX�����w�E���Ă���B
�@�{���ɂ���̂͌l�ł���B�l���g�D�̃e�L�X�g���ɂ���̂ł͂Ȃ��A��
�l����l�Ŏ����̂��߂ɔ����ɂ���̂ł���i�u�J���g���|�Â����̏I��v�j�B
���̂��Ƃ́A�]���̑g���̌����������āA�J���҂͎��������̌l�����A�����A�l�I����𒆐S�Ƃ��������X�^�C�������ɒ蒅�����邱�Ƃ��������A��Ƃɂ����鋤���̈ӎ���o����]�̒ቺ���A�V���ȁu���{�I�Ȍ̊m���v�Ƃ������ʂ̈ꕔ����掦���Ă���Ƃ��l�����悤11�B
�@�}�Q�́A�Q�D�ŏڏq�������x�H�Ɖ��Љ�̐��n�������Љ�̊J�n���Ƃ��l������1973�|83�N�̑�O�̈ӎ��ω��ɂ��Ă܂Ƃ߂����̂ł���B�o�ϐ����ɔ����A�����ɂ�����x�̖��������B�����ꂽ��́A�o�ς̃T�[�r�X�����i�ނɂ�A�����ւ̊S�x���ቺ������A�E��ł̌����E�������̐Êϓx�A���тɎЉ�ɂ����镽���E��u���x�����シ��Ƃ����A�V���ȁu���{�I�Ȍ̊m���v���ֈڍs�������Ƃ�\�����Ă���B
��1) �I���̉e���x�͍���c���I���̍ہA���[�����̐����ɉe�����Ă���x�����i�L�������o�j�̋�����\���B ��2) �E��ɂ����錋�ЁA�������̐Êϓx�����܂����w�́A20�`40��̓�������̔N�w���w���B ��3) �����̎�N�w�����S�ł�����<��>����̂Ƃ��������E��u���x�́A���N�A�X�ɂ͍��N�w�܂ŐZ������ ���������A�����ł͔N�w�I�ɍł����ƂȂ钆�N�w�̐��ڂ�\�������B �o���FNHK���_�������w������{�l�̈ӎ��\���i���Łj�x�A�y�ьo�ϊ�撡�ҁw�A�W�A�o��2000�x�̓��e����쐬�B �}�Q
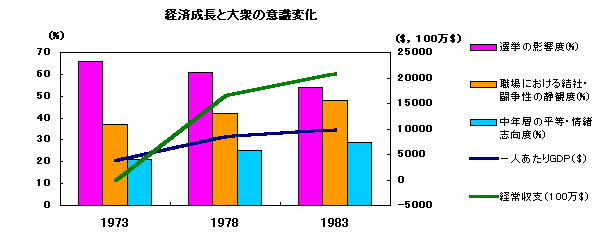
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�����A��Ƃ��u���ʌo�c�v�헪�𐄂��i�߁A�l���팸�ɂ���ĕϑ��I�Ȍo�c�헪���\�z���Ă������ƂƁA�J���҂ɐV���ȃ��`�x�[�V������~�������N����Ȃ��Ƃ������ƂƂ́A�o�������ΑĐ��I�Œ��Ԃ���̏�ԂɊׂ�댯����s��ł���B�܂����̂��Ƃ��A�J���҂̍\�z�͂��Ƃ݂̂Ȃ炸�A�Љ�S�̂̊�������j�Q���ẮA���S���ƕېg�݂̂��䓪����u���{�I�Ȍ̊m���v�𑣂��Ă��܂��B�X�ɂ́A�ӗ~���ނɔ����S�̋����ۂ܂ł���w�������Ă����̂ł���A����̌o�ϐ����ɂ����Ă��傫�ȃ}�C�i�X�v���ɂȂ肩�˂Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@��Љ�������āA�o�ς̍��ۉ��ɔ����{�[�_���X���A�O���[�o�������i�W���A���{�����ێЉ�̒����ɍ��킷�ׂ��s��J���𔗂���B�����A���ۉ��̒����ɒǐ����āA����ł͑�O�̊m�ł���A�C�f���e�B�e�B�̊m�����X�Ȃ�ۑ�Ƃ��ĕ����яオ���Ă���B�@
�Z�p�̐������̎���Ƃ͂����A�n���Ȑ��Y�����ɂ�����J����Љ�����c�ޏp���������A���@�Ǝv�������嗬�ƂȂ�A�����I�Ɏ��Ȑ��䂷��\�͂��������ƂɌq����\��������B�܂����̂��Ƃ����[�ƂȂ��āA�ڐ�̋��y�u���Ɋׂ邱�ƂɂȂ�A�m�łƂ����u���{�I�Ȍ̊m���v�Ȃǖ{���]�|�ƌ��킴��Ȃ��B�O������Ȃ��悤�ȐV���@���ɂ���p��A��_�Ƃ����v���Ȃ����_�ɁA���疜�l�Ƃ�����O���U���A���̂悤�Ȉُ�Ƃ���������Ԃ���Љ�̐i�W�ƕ��s���A�g�債�Ă���̂�����Ȃ̂ł���B
�@
�S�D�܂Ƃ�
���̓��{�́A�j��I�����p���i���A�č��̐�̂�̌������Y�Ƃ̋ߑ㉻�E�������𐄐i���A�f�ՁE���{�̎��R���ɂ�鍑�ۋ����͂̋����Ɛ����̉��P�Ɍ����ēw�͂𑱂��Ă����B���̌��ʁA���{�́u�o�ϑ卑�v�Ƃ��č��ێЉ�ɂ����ē��p�������A���̊Ԃɂ��u�㔭���^�E�s�퍑�^�Z�J���h�E�����i�[����A�t�@�[�X�g�E�����i�[12�v�ւƖ��o�Ă��܂��Ă����B
�@���������{�l�́A���������̔�����s�������ێЉ�ɑ��đ���ȉe����^����悤�ɂȂ��Ă�����A���̌��R���鎖���m�Ɂu���o�v�ł��Ă��炸�A���ʂƂ��āA���{�Ǝ��̐��E��̔��f�A�y�ѐ헪�������Ƃ̕K�v�������Y�p���Ă��܂����̂ł͂Ȃ����B�{�e�S�̘̂_�|�A�X�ɂ͂R�D�Ŋ��q�����u���{�I�Ȍ̊m���v�ւ̎��_�������ɗ��r����B
�@���߂Đ��̓��{����ڂ��Ă݂����A���{�̐���Ƃ͂����ς�č��ɒǐ����A�č��̊�F���f�����ۓI�ȍs���[�u���Ƃ��Ă����w�i����������ɂȂ��Ă���B�܂����̑��ʂ́A�o�ϓI�ɂ̓t�@�[�X�g�E�����i�[�Ƃ��đ䓪���Ă���ɂ��S��炸�A���_�I�ɂ͑��ς�炸�Z�J���h�E�����i�[�ɊÂA���{�I�ȉ��P�͂���Ă��Ȃ����ʂ��ے����Ă��邩�̂悤�ł�����B
�@���Ă̕č��ł����A�����̌o�ς����E�I�ɑ���ȉe�����y�ڂ��悤�ɂȂ����Ƃ͂����A�u�č��̐��I�v�錾���Ȃ���Ă��̏d�v����c������܂łɎ��Ԃ��₵�A�푈�ɂ���ď��߂Đ����I�哱���ƂƂ��ĐӔC��S���Ƃ����u���o�v�Ɏ��������Ƃ́A�{�e�̂P�D�ł����q�����ʂ�ł���B
�@���{�l���A���Ă̕č����l�́u���o�v�����邱�Ƃɂ����āA������x�̎��Ԃ��₷���Ƃ͂�ނ����Ȃ����ʂ�����Ƃ͂����A���ێЉ�ɂ����錻���ƁA���{�l�̏�q�̂悤�Ȉӎ��\���Ƃ̃M���b�v�����܂ł����u�����ɂ������Ȃ��B���{�l�̂��̂悤�ȍs���l��������ɂ́A�����W����`�Ɖ���`�̍����A�܂���������ɋc�_����Ă���u���{�I�o�c�v�ɂ�����W�c��`�̐��x�I�A�\���I�]���ւ̎��������߂Č������ׂ��i�ق̉ۑ�ł��낤13�B
�@�o�ϐ�����B�����邱�Ƃɂ���āA�����ېV�ȗ��A���{�������Ɏ��g��ł����Y�Ƃ̋ߑ㉻�E�������̘H���͏I�����A�܂�����́A�u�č��̐��I�v�ɒǐ����鎞��̏I��ł��������B�����A�����}�N���I�ȋߑ㉻�E�������͒B�����ꂽ���̂́A�~�N���I�ȋߑ㉻�͐��n���Ă���Ƃ͌������A�Ȃ��ۑ�Ƃ��Ďc���ꂽ�܂܂ł���B��������O�́A�m�ł���u���{�I�Ȍ̊m���v����̂Ƃ����s���I�Ȉӎ��A�y�ѐӔC�̌`���ɐs�͂��ׂ��ł��낤�B�܂����́u���o�v�����ł́A��O�̐ϋɓI�Ȑ����Q���𑣂����߂̖���I���x�Ɋ�Â��A�^�̈Ӗ��ł̑�O�����`�̊m���͊��҂ł����A�X�ɂ�21���I�̍��ێЉ�ɂ����Ă��A���{�Ǝ��̍����I���O���|�Ƃ���V���ȃi�V���i���Y���̊m���܂ō��߂��邱�Ƃ��A�����Ă��肦�Ȃ��ƍl�����邩��ł���B

